過去日記
最初の第一歩。
@=
山中教授凄いな。ノーベル賞、おめでとうございます。 ABC理論の望月教授もそうだけど、業績もさることながら、研究成果を隠すことなく広く公開する高潔な人柄が素晴しい。
@=
突然の雨。公園で1時間ばかり雨宿りした。何をするわけでもなく雨を眺める。たまにはいいものだ。
@=
NILFSに初めて救われた。定期的にバックアップをとっておくのは必須だけど、ちょっとしたミスで消えた数分前のファイルの復活には大変便利だ。忘れてたんで覚書。 chcpコマンドでcp(チェックポイント)をss(スナップショット)に変換してからマウントすること。
@=
久しぶりにJavaScriptをさわる。いやはや、ほとんど忘れてたなぁ。リファレンスさえ見ればプログラムは書けるけど、構文やライブラリの詳細は完全に忘却の彼方です。
@=
のどが痛い。風邪をひいているわけでもなく、体調に変わりはないのだが、1年に1度ほどのどだけが痛くなる。酷くなると醤油をかけない豆腐でさえ食べることもできなくなるので気をつけよう。
@=
とりあえず今日一日で大体のAtomフィードは書けるようになったけど、細かい制御がまだまだよくわからん。体系的な理解のために明日、書店にでも行こう。
@=
あら、シアヌーク国王が死んだのか。アンコール遺跡が好きでカンボジアには3度行ったけど、街中のいたるところで写真を見たなぁ。功罪色々ある人だけど、それなりに慕われてた面もあるみたいだし、インドシナの歴史に大きな役割を果した人物であることは間違いない。ご冥福をお祈りします。
@=
RSS関連はろくな書籍がないな。なんだかんだでRFCが一番丁寧だしわかりやすい。結局、既存のコードを読みながら実験して覚えていくしかないのね。
@=
nginxで遊んでみる。今さらなんだろうけど、なかなか面白い構造だな。長くウェブサーバ界隈から遠ざかっていたので新鮮だ。
@=
uwsgiの研究。これを機会に本格的にPythonにも手をだすかな。 Object指向言語としてJavaは思想があまり好きになれないし、 PL/SQLと同じで仕事で仕方なく開発していたからいい思い出がない。言語としての魅力はやはりLispやHaskellが高いけど、広く利用されているという点を考慮するとPythonは悪くないしな。
@=
喉が痛かったのは風邪であった。おかしいなぁ。今度は鼻水が止まらない。
@=
風邪がおさまってきたので、ジョギングを再開。しっかり治ってからやればいいのにと自分でも思うんだど、なんかこう一日サボると、一日分弱くなったような気がしてしまう。まぁ、なんというかこういう脅迫観念って子供のときからの性分だな。
@=
香図を用いた暗号生成ルーチンをXSLTで組んでみた。うん、雰囲気的なものだけどなんとなく優雅だ。暗号って大抵は数字の羅列で味気ないだけにいい感じ。
@=
RFC3339はISO8601をベースとしていながらも結構違うのね。機械にとってはRFC3339は処理しやすいだろうけど、人間にとってはそこまでの正確性はあまり必要ないよなぁ。日記とかだと記述した日付が重要なんであって厳密な時間とかどうでもいいもんなぁ。
@=
香図暗号をヴィジュネル暗号対応にしてみた。我ながら相変わらずくだらんことにこだわってるな。
@=
日付フォーマット再考。時間の一意性としてはUTCで記録しておいて、閲覧者の環境に応じてローカルタイムに変換するのが正しいのだろうけど、現実的には時間は場所と依存しあう関係だから、変換しないほうがいいのではないだろうか。日本で13時に「お昼ごはんおいしかった」と記録したとき、イギリスでは早朝4時にあたるわけで、同時刻という意味ではその通りなんだけど、これはやはり読み手の感覚としてはおかしいと感じるだろう。大体、読み手は書き手の心情に立って解釈するから、そのまま何の変換もせずに13時の方がいいような気もする。タイムオフセットをつければ同時性も含めて解決するけど、誰にでも時計算が瞬時にできるわけでもない。タイムゾーンを採用してゾーン名と併せて記述すれば、一番良いと思うんだけど、コンピュータ処理が難しくなるため、 ISO8601やRFC3339では考慮されていない。具体的には正にこの日記の投稿日時をどう表現しようかということなんだけど。
@=
当面、日付形式として「YYYYMMDD 'T' hhmmss ('Z' | 'P' hhmm | 'M' hhmm) ["zone abbreviation"]」を採用する。具体例では'20121114T114913Z'とか'20121116T075602P0900JST'みたいな感じ。 RFC3339から日付と時間の区切り文字を除いて、タイムオフセットの'+'の代わりに'P'、'-'の代わりに'M'で記述して、末尾にタイムゾーンの省略名を付け加えてもよい(なくともよい)としたもの。数字と英字以外の特殊な記号を使いたくないのと、おおよその場所を表すために所属する標準時を任意で追記できるようにした。あまり独自形式は使いたくないんだけど、標準が要求に合わないから仕方がない。
@=
nginx の graceful restart は HUP シグナル。 graceful shutdown は QUIT シグナル。 lighttpd の graceful shutdown は INT シグナル。
@=
dvipngは便利だな。いつ出来たんだろうか。こんな便利なコマンドがあるなんて知らなかった。 Ghostscriptでppm画像に変換して、 cropして、背景色変更して、拡大して、色深度を変えて、やっとPNGファイル作成してなんてのを個別のコマンドでやってた頃は昔になりにけりだなぁ。
@=
ついでに、dvipngを知る機会になったのが、pnmtopngのバグと思わしき挙動。
長いテキストの場合、1024バイトを越えた分が切り詰められてしまう。 pngcrushでも同じ症状がでたので、両者が共通で利用しているlibpngの問題だろうか。
@=
lighttpd をバックエンドとして UNIX Domain Socket にバインドして使いたい。でも、 setuid する前に bind がコールされるから、パーミションが root になってしまう。まぁ、 TCP へのバインドのことも考えたらこれは仕方がないことだけどなんとかしたい。あらかじめ server.username で lighttpd を起動すれば解決するけど他に影響がでる。プログラムを少し改造すれば済む話でもあるけど、バージョンアップのたびにパッチをあてるのは面倒だ。どうしたものかな。
@=
emacsで文字コードをutf-8にしてファイルを開きなおす。 'C-x RET c utf-8 RET C-x C-v RET' 短かいファイルだとよく誤認識するね。
@=
ウェブページを作る。でも、HTMLを書くのが面倒だ。ヘッダやフッタとか共通部分が多いし。よし、XMLで記述してXSLTで変換しよう。
@=
リヤカーのタイヤがパンクする。荷物が非常に重く汗だくになる。タイヤを求めてホームセンターをはしご。必要以上に疲れてヤレヤレ。
@=
沖縄県庁の前で万歳。 400Km踏破。やっと着いた〜!
@=
久しぶりに日記復活。今度は道北旅行。富良野から稚内を目指す。 7月1日スタートして4日目。当麻町という所に来た。毎日大雪連峰が綺麗だ。
@=
特に観光スポットもないので目一杯歩く。当麻のスポーツランドから剣淵まで30Kmを越えるくらいか。今日はほとほと疲れたので、もう寝る!
@=
朝から雨。剣淵でゆっくりするかと思っていたけど枝幸カニ祭に行く。自動車は偉大だ。早過ぎる。
@=
名寄で天文台に行く。七夕の今夜、夜空にはほぼ雲もなく、彦星と織姫もさぞ喜んだろう。
@=
5時半に出発したら美深アイランドに14時前に着いてしまった。 2時間近く温泉でゆっくりでき大変満足。
@=
朝から雨。昼食の後は再び温泉。 14時過ぎに晴れてきたものの、近場になにもないしやることがない。仕方がないので温泉の休憩室にてのんびり。
@=
雲一つない夜。満天の星空。夏の大三角形。
@=
本旅行3度目のキャンプ場貸し切り。静かで開放感に溢れていて大変快適。
@=
天気晴朗。北緯45度を越える。日射しは強いものの、涼風が心地良い。
@=
稚内に到着。装備も貧弱だし、今回は挫折しそうだったけど、結局、踏破してしまった。歩き旅を終えて、利尻島に渡航。残り数日は島でゆっくりしよう。
@=
利尻山に登る。綺麗な雲海ではあったものの、雲一つないとはいかず残念。雲海だと高い山ならどこでも見れるからなぁ。島の360度のパノラマが見たかった。
@=
礼文島縦走。ウエンナイの休憩所が安くてうまい。筋肉痛が治らない。島でゆっくりどころか、結構ハードな毎日だな。
@=
自転車を借りて宗谷岬まで往復。残念ながら霧の中。特に感動はなし。礼文島はきれかったなぁ。昨日のことだけど桃岩から知床の方も大変景色がよさそう。今後の楽しみにとっておこう。
@=
札幌に帰還。道北の旅はこれにて終り。特に印象深く綺麗だったのは遠望した大雪山と礼文島の西海岸。次はダートや山道にもチャレンジしてみようと思う。背負子を改造してコマを付けてみよう。ザックスタイルとカートスタイルでオールマイティだな。
@=
光る風 堀の水面の 揺れ桜 踊る心に 花びらが舞う
@=
空映す 堀にさざ波 影桜 揺れる心に 花びらが散る
@=
陽を受けて輝く水面に、気持ちのいい風が吹いてさざ波が立っている。青い空と満開の桜が鮮やかに映しだされ、そして揺らめいている。美しい景色に驚き心弾むも、この感動を伝える人がいないのは寂しくもあるわ。
@=
宵の酒 桜透かしの 街路灯 薄紅は 子らの笑顔に
@=
花見酒はいいものですな。皆が酔うから宵の口、深い青に桜色が重なると泡盛だってワイン色。大人達の話をよそに、遊んでいる子どもの頬もほのかに赤く染まってるよ。
@=
春望「春画見て ジジイ回春 望む春」そんな春は嫌だ!
@=
もっとヤダ。「春画見てババア回春して売春」春が三つも入りながら全く季節が関係ない17拍。一つぐらい季語にならんのか?
@=
「春画見た回春ジジイが即買春」なんか好色なジジババのちょっといい話に思えてきた。
@=
「春画見た回春ババアも望む春」お幸せに。
@=
やっぱり春って一番いい季節だな。てな気分で春をお題に言葉遊びをしていたら、しょうもないことばかり思い浮かんだ。書き散らしてから、ドラゴンボールの亀仙人と、源氏物語の源典侍が思い返されたんだけど、二人だと、、、あんまりうまく行かないかな。
@=
5/2から5/10にかけて、鳴門から松山まで歩いた。お遍路さんのせいか四国は歩いて旅している人が多い。野宿にも寛容な風土なのか、道行く人も親切で優しい。
@=
falseとnologinは似たようなものだけど、違いとしてnologinではエラーメッセージがでるようだ。この程度のことで/etc/passwd内のログインシェルとして使いわけるのは面倒だなあ。
@=
Subversionではファイルの実行属性のみ管理している。 rw属性は関係ないのね。いまさら知ったよ。
@=
makeで空白を含むファイル名は利用できない。
@=
Time::Pieceのstrptimeは%Zを使うとエラーがでたり、 parseできない文字列で'garbage ...'うんぬんと警告メッセージが出たり、なんかまだ洗練されていないようで大変使いにくいのでは?
@=
読経はロックだ。木魚はドラムだ。お鈴はシンバルだ。仏教はタテノリだ。
@=
ワールドワールド(AsianKanfuGeneration)を般若心経で歌えた。
@=
7月2日、留萌にて日本海と右手を繋ぐ。 7月14日、旭岳にて南面す。 7月26日、網走にてオホーツク海と左手を繋ぐ。
@=
Makefileで.DEFAULT_GOAL変数をセットしておけば、最初のrule以外のtargetから依存関係を解決できる。 ".DEFAULT_GOAL := all"としておけばallがどこにあっても大丈夫。
@=
dateコマンドで時刻指定してUNIX時間を得る。 "date --date='1999-12-31' +%s" 調べりゃすぐにわかるけど、今更ながらに知らないことが沢山あるなぁ。
@=
$ cat <<< string (here-strings) ヒアドキュメントの文字列版。どっかで見たことあるなぁと思いながらも忘れていた。こういう記号だけの構文は検索が難しいので調べるのに時間がかかる。
@=
awkやsedはパズルみたいで楽しい。 perlで簡単にできることをsedで技巧的にやる。
@=
CSSで3桁の16進数RGB値は、各桁を2度繰り返した6桁のRGB値に等しい。 "#f00"="#ff0000"
@=
PHPの$_POSTでバイナリデータを受けるのは止めたほうが良さそうだ。裏で8ビットコードの数値参照や改行コードの変換がされてるみたいだし。
@=
jQueryのajaxでリダイレクトは捕捉できない。
@=
ヒトの核ゲノムは31億塩基対。 1塩基対が2ビットの情報量を持つから62億ビットで、およそ8億バイト、即ち、800メガバイト。子供の頃、コンピュータは8ビットマシンで、RAMはあっても64キロバイト。フロッピーディスクの容量が無限に思えた時代、やはり、生物は凄いなぁと感じたものだけど、今思えばたったの800メガバイト。逆にその程度のコードで人間が作れてしまうのが驚きだ。
@=
『や〜きいも〜〜。やきいもっ!』信号待ちの交差点で隣の親子が言った。幼児「焼き芋食べたい。」ママ「あんた、すぐ食べたい食べたいゆうけど、いっつも食べへんやないの!いっつもママばっかり食べてるやないの!」幼児「・・・」ママ「今日だけ特別やで。」
@=
そう言えば先日、公園でウォーキング中のジジババがいた。ジジ「昨日病院でなぁ。大きな腫瘍ができてるらしい。」ババ「あんた、それ、えらいことちゃうの。」ジジ「ああ、大変なんやでぇ。」ババ「さすがあんたやなぁ。誰にでも出来るもんとちゃうんやろう。」ジジ「まぁなぁ。大きいのは難しいて言うてたわ。」ババ「やっぱりなぁ。あんたは、ほんま、すごいわぁ。がんばりやぁ。」ジジ「おう。まかせとき。」
@=
信号待ちの交差点で、親子がナゾナゾ遊びをしていた。幼女「ももの木ってなーんだ!」私(ムズッ。えーと、植物界被子植物綱バラ科、、、。って、こんな答でいいのか。ていうか、、、)パパ「ももの木はももの木やろ。」幼女「せーかい!」私(それでえーんかー!)
@=
前述、ナゾナゾ。幼女は桜の木を見ていた。道端の桜を見ていた娘「桃の木ってなーんだ。」私(、、、。ていうか、この子は桜の木を見ているぞ。これは、あれか。禅問答なのか。黙って右手を前に突き出したり、庭の柏樹のようなものってのが答えになるのか。)信号しか見ていない父「桃の木は桃の木やろ。」娘「正解!」私(深読みしすぎたー!)
@=
前述、父親は悟っていた。私が間違えていた。反省した私はこれからはナゾナゾキングだ。「一本足で真っ赤な顔した手紙や葉書を食べるものってなんぞや。」「それは、一本足で真っ赤な顔した手紙や葉書を食べるものである。」
@=
式の結果が自動的に暗黙変数に格納される。既にPythonに実装されてた。ちょっと残念。確かに誰でも考えつくことではあるよなぁ。
@=
と、思ったらインタラクティブモードだけなのかなぁ。 Pythonシェルから'>>> [1,2,3];print _'はOKだけど、スクリプトファイルでの実行や、Python -c '[1,2,3];print _' ではエラーになった。それとも、なんぞ、自動変数を有効にする起動オプションがあるのかしらん。
@=
長らく放置していた日記を再開。この2年、毎週のように山登りをしていたけど何も書いてない。しばらく山日記をつけるとしよう。
@=
昨日は、関バス停から、市道山、醍醐丸、陣場山、城山、大洞山、草戸山、四辻、高尾山口。今日は、楽してケーブルカー。御嶽山から、日の出山、つるつる温泉。
@=
本日、膝が痛いため、足慣らし。高尾縦走黄金コース。陣馬高原下〜陣馬山〜景信山〜城山〜高尾山〜稲荷山〜高尾山口。
@=
18切符で小旅行。岩井駅->富山->岩井駅(上り:尾根、下り:伏姫の谷)。保田駅->大仏->地獄のぞき->石切場->鋸山三角点->車力道->浜金谷駅。
@=
奥多摩駅(8:21)->鋸山->(大岳山は巻く)->馬頭刈山->瀬音の湯->五日市駅(14:30)。前から行きたかったコース。雪が無くなったのでチャレンジ。瀬音の湯までなら約5時間。結構早いほうだと思う。ちなみに先週は、つつじ新道から檜洞丸、犬越路で下山。 3日前の雪が残っていたため、非常に怖かった(こちらはU氏、N氏の三人)。
@=
ケーブルカー => 御岳山 => ロックガーデン => 日の出山 => つるつる温泉。同行は、新宿K氏、小竹向原K氏、沖縄出身K氏。
@=
デジカメに保存されていた過去の写真から1日1枚をピックアップしてみる。
@=
自転車で通りすぎる親子から聞こえてきた。「恐竜が出てきたらどうする?」後ろカゴの幼児の問いかけであった。私(なんて非現実な。いや、幼児にとっては現実も空想も違いはない。) パパ「そうだなぁ。」私( そうだ、子供にとっては現実の「もし」なのだ。決してありえない仮定で述べたのではない。となると、ここはやはり、「戦う」とか言うべきだろう。もしくは、もう少し大人の現実的対応として「一緒に逃げる」でもいいかもしれない。 ) パパ「それは、怖いなぁ。」幼児「うん。すっごく怖いよねぇ。」私(それで終りかよ!)
@=
午前は雨。午後から出発。高尾駅=>拓殖大西尾根=>草戸峠=>大戸=>(キャンプ場入り口あたりでバスに乗って相原駅)。初めてのコースと思って行ってみれば、大昔に来たことがあった。展望も開けないし面白くないコース。なんで、忘れてしまっていたのであろう。雨上がりの緑の匂いが堪能できたことは収穫であった。
@=
昨日は塔ノ岳(ヤビツ峠=>表尾根=>塔ノ岳=>大倉尾根)。定番コースで同行は宮崎出身のK君。一昨日は川苔山(川乗橋=>百尋ノ滝=>川苔山=>赤久奈山=>川井駅)。
@=
昨日は、小河内バス停=>三頭山=>笹尾根=>和田峠=>陣馬高原下バス停。これは疲れた。太股の筋肉がまだなんか変。三頭山から笹尾根のブナ林は新緑で素晴らしい。秋にまた来ようと思う。紅葉も楽しみ。
@=
先週は石老山。石老山入口バス停=>石老山=>プレジャーフォレスト前=>嵐山=>相模湖駅。石老山だけのつもりであったが、体力的にものたりなかったため嵐山を追加。今日は、高柄山。四方津駅=>千足沢=>洗足峠=>高柄山=>御前山分岐=>(御前山ピストン)=>鶴鉱泉=>上野原駅。千足沢は苔生して綺麗であった。御前山に眺望はない。総じてあまり特徴のない山道。
@=
えらく悩んだ。 ETagヘッダは「ETag: "TTT"」てな具合にクォートする必要があったようだ。 ngx+luaの症状として、「ETag: TTT」だと、text/htmlの場合はEtagがつかない。それ以外のMIME-TypeであればEtagがつく。「ETag: "TTT"」であれば、「text/html」の場合は「ETag: W/"TTT"」となる。それ以外のMIME-Typeであれば「ETag: "TTT"」がつく。
@=
emacsからのコマンド実行。「C-x h」で全バッファを選択。「M-|」で選択バッファを入力としてコマンドを実行。シェルスクリプトであればコマンドに「sh」と入力する。
@=
emacsからコマンド実行するだけなら「M-!」でよい。
@=
四方津駅=>大地峠=>矢平山=>倉岳山=>高畑山=>鳥沢駅。初夏の陽光を受けた広葉樹林が美しい。倉岳山までは岳人もまばらで静かな山行を楽しめたが、倉岳山は人気の山みたいで山頂には結構な数の登山者がいた。
@=
昨日の山行。藤野駅=>イタドリ沢の頭=>明王峠=>堂所山=>北高尾山稜=>高尾駅。イタドリ沢の頭から明王峠までは静かで良い。蝶の大群が舞い散る(舞い上がる?)花びらのようで綺麗であった。
@=
御岳山=>大岳山=>日の出山=>つるつる温泉。定番の初級コース。同行はマイ・ブラザー。山行自体は楽なのだが先週怪我したヒザ痛を再発。
@=
 関空、LCCターミナル。雨。大阪でも梅雨が始まったっぽい。実家に2泊3日でゆっくり。両親は元気。本日、まずは、沖縄に飛ぶ。5回目の沖縄。沖縄も2泊3日の予定で中部を中心に友人に案内してもらう予定。
@=
関空、LCCターミナル。雨。大阪でも梅雨が始まったっぽい。実家に2泊3日でゆっくり。両親は元気。本日、まずは、沖縄に飛ぶ。5回目の沖縄。沖縄も2泊3日の予定で中部を中心に友人に案内してもらう予定。
@=
沖縄は曇り、時々日差しあり。大変蒸し暑い。私の感覚から言えば、すでに完全に夏だ。空港でレモンジャー、ブルー隊員と合流して名護までドライブしてもらう。彼のご母堂謹製の天ぷらは大変美味しかった。衣にした味をつけているので、具もさることながら衣自身が香ばしく旨味が広がるのは絶品。晩はホテル近所の宮古そば屋さんで野菜そば。付け合せのゴーヤの漬物がいい感じであった。
@=
ブルー隊員に連れられて、6時から1時間半の宜野湾市内一周散歩。植生と町並みを眺める限り、すでにタイの片田舎を歩いているような気分になる。いい汗をかいてホテルに帰還。洗濯が終われば二度寝しよう。
@=
昨晩は、青、紫、ライムと宜野湾で飲み会。結構酔っ払ったし、失礼なこと言ってたかもしれんなぁ。まぁ、ええ、おっさんやし、少々乱れても許しておくれって感じです。うん、楽しい酒であった。明日以降海外なので、旅の勘を取り戻すまではしばらく禁酒かな。
@=
 摩文仁の丘の下。ここも最高に良いところなのだが、ほとんど人が来ない。写真中央は同行してくれたフィアンセをこよなく愛する沖縄在住のM氏。今晩の便でバンコクに飛ぶのだが、出発まで3時間弱あるので空港散策。
@=
摩文仁の丘の下。ここも最高に良いところなのだが、ほとんど人が来ない。写真中央は同行してくれたフィアンセをこよなく愛する沖縄在住のM氏。今晩の便でバンコクに飛ぶのだが、出発まで3時間弱あるので空港散策。
@=
バンコクに零時半到着。宿に移動して色々してたら2時。タイのほうが沖縄より涼しいような気がする。
@=
7時起床。8時行動開始。チケットを買いに北バスターミナルへ。 9時半頃猛烈な雨。流石雨季、滝のような雨では3秒でずぶ濡れだろう。駅で30分ばかり雨宿り。当初はチェンコーンから一気に北へと向い最短で雲南(中国)へと思っていたのだが、昨晩考えが変わり、久しぶりにタイも観光してみるかと、イサーン(東北)で一週間くらい遺跡巡りをする気になっていたものが、この雨で再度心変わりし、結局、国境を目指してルーイ(Loei)行きのバスのチケットを買う。理由は雨が嫌だったのと出来るだけマイナーな国境を超えてみようとの魔がさしたこと。サイニャブリー(ラオス)に抜けるこのルートで国境越えしたことがある人はそんなにはいないのではと思う。遅めの昼飯は何かよくわからない冷やしにゅうめんみたいなもの。まずくはないが辛かった。明日は早朝5時チェックアウトなので早めにホテルに帰還。
@=
 バンコク再考。写真は雨宿り中のモーチット駅。雨宿り中、BNK48がペイントされたバスも見たのだが、シャッターチャンスを逃した。この街はやはり好きになれない。 3時間ばかり散策したのだが、車が多い、煩い、臭い、汚いでいいことがない。ただ、バンコクに限らず、ビエンチャンやハノイなどの大都市は全て嫌いである。昔(20年前)はバンコクが好きであった。ホーチミンやプノンペンも好きであった。エネルギッシュな熱気に心が弾んだものだ。ところが今はとにかくこの喧騒から逃れたい。街は何も変わっていない。私が、そして旅のスタイルの方が変わってしまった。明日の今頃はルーイである。
@=
バンコク再考。写真は雨宿り中のモーチット駅。雨宿り中、BNK48がペイントされたバスも見たのだが、シャッターチャンスを逃した。この街はやはり好きになれない。 3時間ばかり散策したのだが、車が多い、煩い、臭い、汚いでいいことがない。ただ、バンコクに限らず、ビエンチャンやハノイなどの大都市は全て嫌いである。昔(20年前)はバンコクが好きであった。ホーチミンやプノンペンも好きであった。エネルギッシュな熱気に心が弾んだものだ。ところが今はとにかくこの喧騒から逃れたい。街は何も変わっていない。私が、そして旅のスタイルの方が変わってしまった。明日の今頃はルーイである。
@=
4時起床。5時チェックアウト。バスターミナルへと向かう。バスは8時発。ホテルが空港近くと市街からは逆に遠いため。早めの行動開始。街を超えて、平原を超えて、ジャングルを超えて、、、9時間かかってルーイに到着。バスに乗っているだけで特に何もない一日。なお、バンコクでは、BS Residenceというところに宿泊したのだが、空港までの無料送迎がついて3000円ほどだから悪くはないと思う。以前泊まったトンタリゾートよりは良かったのではないだろうか。
@=
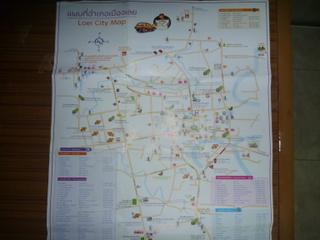 バスに乗っているだけで特に何もない一日。、、、とは行かなかった。ルーイバスターミルで地図を手に入れようとするも、誰にも英語が通じない。まぁ、半分くらいは私の貧弱な英語力(特に発音の悪さ)のせいもあると思う。 infomationの親父に'map'と書けば通じたのだが、散々探してないと言われる。街の中心がどこか不明だし、どの道をどう進めばいいのかわからず途方に暮れる。仕方ない、なんとかなるさ、と歩きだしてみると、後ろから親父が追いかけてきて、観光用の地図をくれた。私が途方に暮れている間も探してくれていたのだろう。この親切さがタイだ。やはり東南アジアは旅がしやすい。目指すGHまで30分。地図を頼りに汗だくになって到着。 The Stay Guest Houseのオーナーは親切で紳士な英国人。つたない英語でも通じてホッとする。
@=
バスに乗っているだけで特に何もない一日。、、、とは行かなかった。ルーイバスターミルで地図を手に入れようとするも、誰にも英語が通じない。まぁ、半分くらいは私の貧弱な英語力(特に発音の悪さ)のせいもあると思う。 infomationの親父に'map'と書けば通じたのだが、散々探してないと言われる。街の中心がどこか不明だし、どの道をどう進めばいいのかわからず途方に暮れる。仕方ない、なんとかなるさ、と歩きだしてみると、後ろから親父が追いかけてきて、観光用の地図をくれた。私が途方に暮れている間も探してくれていたのだろう。この親切さがタイだ。やはり東南アジアは旅がしやすい。目指すGHまで30分。地図を頼りに汗だくになって到着。 The Stay Guest Houseのオーナーは親切で紳士な英国人。つたない英語でも通じてホッとする。
@=
 たこ焼き屋を見つけた。早速食す。甘い!クレープか?タコじゃない。食感は、、、イモか?うーむ。似て非なる物、、、というか全くの別物であった。まぁ、遠い異国の片田舎で、たこ焼き鍋が見れただけで、浪速っ子としては衝動買い。
@=
たこ焼き屋を見つけた。早速食す。甘い!クレープか?タコじゃない。食感は、、、イモか?うーむ。似て非なる物、、、というか全くの別物であった。まぁ、遠い異国の片田舎で、たこ焼き鍋が見れただけで、浪速っ子としては衝動買い。
@=
 午前の散策を終える。田舎町は良い。ルーイには自転車用のレーンがあり、GHで無料の自転車を貸してくれる。一回りするのに1時間とかからない。車もゆっくりのんびり走っているのだが、それなりに交通量があるのは難点。もう一つの問題は犬。雰囲気のいい小道だなと入っていくと、誰もいない路上で野良犬に吠えられる。一匹吠えるとどこからか集まってきて数頭に囲まれる。いや、正直怖いです。逃げると追いかけられてもっと怖い目に合うので、睨みつけながら後ずさり。どうしても進みたいときは蹴っ飛ばす勢いで前進。観光客があんまりいないので、人に慣れていないのでしょう。「あっ、いい感じ」と、軽い気持ちで路地に入って行くと後悔する羽目になる。写真は朝市の周辺。店舗がない店も路上で頑張ってます。
@=
午前の散策を終える。田舎町は良い。ルーイには自転車用のレーンがあり、GHで無料の自転車を貸してくれる。一回りするのに1時間とかからない。車もゆっくりのんびり走っているのだが、それなりに交通量があるのは難点。もう一つの問題は犬。雰囲気のいい小道だなと入っていくと、誰もいない路上で野良犬に吠えられる。一匹吠えるとどこからか集まってきて数頭に囲まれる。いや、正直怖いです。逃げると追いかけられてもっと怖い目に合うので、睨みつけながら後ずさり。どうしても進みたいときは蹴っ飛ばす勢いで前進。観光客があんまりいないので、人に慣れていないのでしょう。「あっ、いい感じ」と、軽い気持ちで路地に入って行くと後悔する羽目になる。写真は朝市の周辺。店舗がない店も路上で頑張ってます。
@=
 11時、午後の行動を開始。出かけようとしたところ、宿の女将からベッドメイクの要否と明日のチェックアウト時間について尋ねられる。なんでも明日10時に所要でバンコクへと出発するらしく、遅いチェックアウトだとうんぬん(よく聞き取れない)などと言っているようだ。朝の行動は早いので、9時までにはチェックアウトするので問題ないと伝える。さて、本日のメインは南へと続く自転車レーンを行けるところまで行ってみること。昨日、ルーイに来るバスの車窓から眺めている限りだと、10kmほどはありそうだ。往復で2時間くらいだろうからちょうどいいくらいのサイクリングであると判断する。雨季でずっと曇り空、時折スコールが降るが南国のカンカン照りよりはよほどマシであろう。とはいえ、都合5回も雨宿りすることになるは、それなりにアップダウンはあるは、そもそもシティサイクル用のしょぼい自転車だわで結構大変であった。体力と耐力で強引に乗り切る。ちなみに穏やかな風土が生み出すタイ力も少なからず分けてもらっている。タイは世界一のお米の輸出国。中盤を過ぎたあたりから水田が広がるのどかな風景。大平原に続くライスガーデンが背後の山稜を借景にしている。おっ、いい景色だぞ。道中気儘に立ち止まり。一人気楽な旅の道。農家の人たちもみな忙しくしている、、、ようには見えない。の〜んびり仕事をしているのかなぁ。
@=
11時、午後の行動を開始。出かけようとしたところ、宿の女将からベッドメイクの要否と明日のチェックアウト時間について尋ねられる。なんでも明日10時に所要でバンコクへと出発するらしく、遅いチェックアウトだとうんぬん(よく聞き取れない)などと言っているようだ。朝の行動は早いので、9時までにはチェックアウトするので問題ないと伝える。さて、本日のメインは南へと続く自転車レーンを行けるところまで行ってみること。昨日、ルーイに来るバスの車窓から眺めている限りだと、10kmほどはありそうだ。往復で2時間くらいだろうからちょうどいいくらいのサイクリングであると判断する。雨季でずっと曇り空、時折スコールが降るが南国のカンカン照りよりはよほどマシであろう。とはいえ、都合5回も雨宿りすることになるは、それなりにアップダウンはあるは、そもそもシティサイクル用のしょぼい自転車だわで結構大変であった。体力と耐力で強引に乗り切る。ちなみに穏やかな風土が生み出すタイ力も少なからず分けてもらっている。タイは世界一のお米の輸出国。中盤を過ぎたあたりから水田が広がるのどかな風景。大平原に続くライスガーデンが背後の山稜を借景にしている。おっ、いい景色だぞ。道中気儘に立ち止まり。一人気楽な旅の道。農家の人たちもみな忙しくしている、、、ようには見えない。の〜んびり仕事をしているのかなぁ。
@=
 体力考。大抵の問題は体力で解決している。本当は知識と機転で解決できればスマートなんだろうけど、まぁ、ないものをねだっても仕方がない。それに体力での解決にはいいところもある。地道だが確実に解決できること。知識や機転はハマれば強いが、如何ともしがたいときがある。旅の問題を解決できる武器はやはり体力であろう。話は変わるが、仕事でも二番目に必要なのは体力だと思う。知識やスキルなんぞは三番目以降のことだ。最後の最後で踏ん張りが効かないといい仕事はできない。やはり、最後は体力が物を言う。さて、先にタイの田舎サイクリングが気儘で気楽なように書いた。この感動を誰かに伝えたい。いやむしろ共に体験したい。、、、と思うのだが、結局のところ半分は修行であって、おそらく大半の人には楽しくないかもしれない。暑いし、汗だくだし、そもそもしんどいし。なぜこれが楽しいのか自分でもよくわからないときがある。ただ、少なくともこれが楽しいと思えるのは体力のおかげだとは思う。おっと、偉そうなことを書きました。ごめんなさい。実は体力もそんなにありません。私が人並み以上に能力を発揮できるのは主に遊んでいるときだけですわ。
@=
体力考。大抵の問題は体力で解決している。本当は知識と機転で解決できればスマートなんだろうけど、まぁ、ないものをねだっても仕方がない。それに体力での解決にはいいところもある。地道だが確実に解決できること。知識や機転はハマれば強いが、如何ともしがたいときがある。旅の問題を解決できる武器はやはり体力であろう。話は変わるが、仕事でも二番目に必要なのは体力だと思う。知識やスキルなんぞは三番目以降のことだ。最後の最後で踏ん張りが効かないといい仕事はできない。やはり、最後は体力が物を言う。さて、先にタイの田舎サイクリングが気儘で気楽なように書いた。この感動を誰かに伝えたい。いやむしろ共に体験したい。、、、と思うのだが、結局のところ半分は修行であって、おそらく大半の人には楽しくないかもしれない。暑いし、汗だくだし、そもそもしんどいし。なぜこれが楽しいのか自分でもよくわからないときがある。ただ、少なくともこれが楽しいと思えるのは体力のおかげだとは思う。おっと、偉そうなことを書きました。ごめんなさい。実は体力もそんなにありません。私が人並み以上に能力を発揮できるのは主に遊んでいるときだけですわ。
@=
少し寄り道してチェンカーン(Chiang Khan)に来る。タイでは人気の観光地らしい。来るまでにも色々、着いて早々色々あるのだが、ばっさりカット。すべての出来事を書いていたらきりがないし、もともと筆無精なのでマメに書いてたら続かん。街を知るためにまずはひと歩きする。
@=
 チェンカーンの観光スポットは2つ。山と川。山は乾季だとタイでは珍しい雲海が見れるらしい。雲海は日本で何度も見ているのでパス。そもそも今は雨季。午後はGHで借りた無料の(オンボロの)チャリで、観光名所となっているらしいメコン川が大きくV字にカーブするケン・クッ・クーを目指す。、、、が、道を間違う。途中道を間違えたと気づきながらも(だって遠すぎる)、 V字の対岸まで行ってみれば思いの外いい景色であったので良しとする。帰り道すがら正しい道を発見してケン・クッ・クーも制覇。うーん。まぁ、風光明媚なところではあるんだけどねぇ。メコン川下りは2回してるし(5年前と20数年前)、もっと凄いところを見てるからこんなもんかという感じ。
@=
チェンカーンの観光スポットは2つ。山と川。山は乾季だとタイでは珍しい雲海が見れるらしい。雲海は日本で何度も見ているのでパス。そもそも今は雨季。午後はGHで借りた無料の(オンボロの)チャリで、観光名所となっているらしいメコン川が大きくV字にカーブするケン・クッ・クーを目指す。、、、が、道を間違う。途中道を間違えたと気づきながらも(だって遠すぎる)、 V字の対岸まで行ってみれば思いの外いい景色であったので良しとする。帰り道すがら正しい道を発見してケン・クッ・クーも制覇。うーん。まぁ、風光明媚なところではあるんだけどねぇ。メコン川下りは2回してるし(5年前と20数年前)、もっと凄いところを見てるからこんなもんかという感じ。
@=
 こちらは有名らしい川エビの唐揚げ。うまいっ!、、、というほどではなく味は期待通りというか予想通り。思った通りの川エビの唐揚げ。普通に美味しいんだけどね。ビールが合うだろうなぁ。一人旅中はできる限り(そもそも真っ昼間だし)アルコールは自粛中。
@=
こちらは有名らしい川エビの唐揚げ。うまいっ!、、、というほどではなく味は期待通りというか予想通り。思った通りの川エビの唐揚げ。普通に美味しいんだけどね。ビールが合うだろうなぁ。一人旅中はできる限り(そもそも真っ昼間だし)アルコールは自粛中。
@=
タイとラオスには相当な経済格差がある。チェンカーンではメコンビューのペンションが2kmくらいに渡って続いている。ケン・クッ・クー周辺も開発が進んでいて川沿いの遊歩道が整備されつつある。つながれば5km以上に渡る川沿いの散策路となるだろう。対岸のラオスは、、、うん、まぁ、ラオスだ。なお、静かな滞在を好むならばケン・クッ・クーまで行ってしまうほうが良さそうだ。
@=
 夜になるとこうやって露店街になったりするのが観光地たるゆえんだろうか。ルーイでは間もなくお祭りが始まる。仮面行列が通りを練り歩くというもの。あと、3日滞在すれば見れるのだけど、人混みが嫌なのであえて避けることにする。
@=
夜になるとこうやって露店街になったりするのが観光地たるゆえんだろうか。ルーイでは間もなくお祭りが始まる。仮面行列が通りを練り歩くというもの。あと、3日滞在すれば見れるのだけど、人混みが嫌なのであえて避けることにする。
@=
 旅の日常、日の出で起床。早朝のチェンカーン散策。小さい街だからもう主要な道は何度も通っている。それも飽きたので、再度、ケン・クッ・クーを見に行く。蒸し暑い。汗だく。宿に帰ってシャワーを浴びてチェックアウト。一旦、バスでルーイに戻り、明日、ラオスへと向かう。写真はソンテウ(乗り合いのトラックバス)の停留所。実際には道端の休憩小屋。そもそも、どこで乗ってもいいしどこで降りてもいいので停留所が必要ない。ただし、目的地に向かう車はいつ来るかわからない。なんかそれっぽい車が通るたびに「ルーイ?」と聞いてみては断られる。 30分ばかり待っていると、34バーツ(ソンテウより安い)でしかも早いから、このトゥクトゥクのおっさんについて行けと休憩小屋で一緒だったタイ人から言われた(ような気がした)。ええっ、トゥクトゥクがソンテウより安くて早いなんてことがあり得るか?と思うが、言われるままに(実際には何を言ってるのか9割方わからないが)トゥクトゥクに乗り込むと100mくらい先で降ろされた。なんとルーイ行きの定期バスのバス停であった。ソンテウではなく、エアコンも効いている路線バス。なんだ、こんなものがあったのかよ。うーむ知らなんだ。わずか100mくらいしか乗っていないが情報料だと思い20バーツ(80円弱)払ってやる。しかし、バンコクを出てから周りはタイ人ばかり。いや、タイなんだから当たり前なんだけどさ。タイってどこに行っても外国人(タイ人以外)が多いイメージだっただけに少し意外。それこそ20年前のタイであればどこにでも日本人がいたものだけど、今は全く出会わない。
@=
旅の日常、日の出で起床。早朝のチェンカーン散策。小さい街だからもう主要な道は何度も通っている。それも飽きたので、再度、ケン・クッ・クーを見に行く。蒸し暑い。汗だく。宿に帰ってシャワーを浴びてチェックアウト。一旦、バスでルーイに戻り、明日、ラオスへと向かう。写真はソンテウ(乗り合いのトラックバス)の停留所。実際には道端の休憩小屋。そもそも、どこで乗ってもいいしどこで降りてもいいので停留所が必要ない。ただし、目的地に向かう車はいつ来るかわからない。なんかそれっぽい車が通るたびに「ルーイ?」と聞いてみては断られる。 30分ばかり待っていると、34バーツ(ソンテウより安い)でしかも早いから、このトゥクトゥクのおっさんについて行けと休憩小屋で一緒だったタイ人から言われた(ような気がした)。ええっ、トゥクトゥクがソンテウより安くて早いなんてことがあり得るか?と思うが、言われるままに(実際には何を言ってるのか9割方わからないが)トゥクトゥクに乗り込むと100mくらい先で降ろされた。なんとルーイ行きの定期バスのバス停であった。ソンテウではなく、エアコンも効いている路線バス。なんだ、こんなものがあったのかよ。うーむ知らなんだ。わずか100mくらいしか乗っていないが情報料だと思い20バーツ(80円弱)払ってやる。しかし、バンコクを出てから周りはタイ人ばかり。いや、タイなんだから当たり前なんだけどさ。タイってどこに行っても外国人(タイ人以外)が多いイメージだっただけに少し意外。それこそ20年前のタイであればどこにでも日本人がいたものだけど、今は全く出会わない。
@=
5時起床。 8時5分、定刻より5分遅れてバスは出発。バスは整備された2車線路を軽快に走る 9時45分、ラオス入国。バスはゆっくりと、それでいて大きく揺れながら走る。だって、国境とつながる幹線道路でさえ穴ボコなんだもの。水田が広がる。水牛が行き交う。やはりラオスは良い。人も穏やか、時間も悠々、心なしか風景も日本と似ている。
@=
バスが市場前で謎の停車。 10分後、ニコニコした顔で運転手が市場から出てくる。手にはなにか買ったらしい商品を持っている。乗客置いてけぼりのこのルーズさがラオスらしい。なお、車内には20名ばかりの客がいるが、私以外は全員がタイ人かラオス人だ。普通、国境バスは旅行者に人気だから誰かしら外人がいるものなんだけどなぁ。なお、10名位は謎の美女集団。タイ人モデルかなにかの慰安旅行だったりするのだろうか。
@=
ラオスはとても良い国だ。そしてなんにもない国だ。国境を超えて3時間。信号一つありゃしない。だって交差点がないんだもの。そもそも一本道なんだもの。橋がなければトンネルもない。すべての峠を登り、すべての谷を降る。だから、真っ直ぐな道がない。道はクネクネと蛇行する。この先残り3時間、やはり何にもないだろう。あぁ、親愛なるラオの友人たちよ。なんで、スマホは持ってるの?
@=
昨日はタイのルーイからラオスのルアンプラバーンへ9時間のバス。今日はルアンプラバーンからルアンナムターまで9時間のミニバン。 2日連続の移動日。ここまで来たらいつでも中国・雲南省に入国できる。明日、ムアン・シンに移動し、2,3日ほどゆっくりして気息を整えようと思う。
@=
 ラオスは旅をしていて本当に楽しい。純朴で人は皆穏やかだ。そのうちじっくりともう一度この国を隅々まで旅してみたいと思う。今やラオスは旅してみたい国ナンバーワンの存在であり世界中から観光客が集まってくる。ここに来るのは4回目である。という訳で、ルアンプラバーン考。ルアンプラバーンは日本で言えば京都、タイで言えばチェンマイ。要は古都。世界遺産にも登録されているラオス随一の観光都市だ。ここは私が最も好きな街の一つであり、また、思い出も数多くある。古くからの仏教寺院、朝もやの中をゆく托鉢僧、丘から見る街の全景。人と文化と歴史と風土。ここは全てにおいて調和している稀有な街である。しかし、それ故に観光客が増えすぎた。人も車も増えすぎた。街はホテルとゲストハウスとトゥクトゥクで溢れ、看板には中国語が氾濫している。ラオスの旅は楽しい、が、個人的に言えばラオスの旬は過ぎたと言わざるを得ない。 20年以上前を知る身とすれば、特にルアンプラバーンは魅力を失ったといえる。もう、あの静かで、厳かで、それでいて優しい街の雰囲気は二度と戻っては来ないだろう。今は雨季なのでオフシーズンだがオンシーズンで春節と重なる2月ともなれば、ゲストハウス(簡易宿泊所)ですら1泊100ドルを超えるらしい。それでも泊まれればマシだそうだ。売りに出されている物件が1億6千万というのも驚きだ。東京より高いぞ。ナイトマーケットはごった返しで進むことすら出来ない状態になるとか言う話である。さて、日記に戻る。昨日、17時に南バスターミナルへと到着。この街には日本人が経営しているゲストハウスがあるらしい。そこに行けばおそらく日本人がたくさん泊まっていると予想して歩いて向かう。この先、日本語を話せる機会はほぼないと思われるので、思い切り会話を堪能しておく。前述、個人的にはこの街に魅力を感じなくなってしまったので翌朝早くには出発することにする。悪くも書いたけど、ラオスに来たことがなければやはりルアンプラバーンはおすすめだと思う。ゆっくり、のんびり、たおやかな時間の流れを堪能できるでしょう。写真は、何もかも変わったと思えるルアンプラバーンで唯一変わりないと思った朝市の風景。とはいえ、路地とそこでの営みは変わらないものの、路地脇の建物は新しくなっています。
@=
ラオスは旅をしていて本当に楽しい。純朴で人は皆穏やかだ。そのうちじっくりともう一度この国を隅々まで旅してみたいと思う。今やラオスは旅してみたい国ナンバーワンの存在であり世界中から観光客が集まってくる。ここに来るのは4回目である。という訳で、ルアンプラバーン考。ルアンプラバーンは日本で言えば京都、タイで言えばチェンマイ。要は古都。世界遺産にも登録されているラオス随一の観光都市だ。ここは私が最も好きな街の一つであり、また、思い出も数多くある。古くからの仏教寺院、朝もやの中をゆく托鉢僧、丘から見る街の全景。人と文化と歴史と風土。ここは全てにおいて調和している稀有な街である。しかし、それ故に観光客が増えすぎた。人も車も増えすぎた。街はホテルとゲストハウスとトゥクトゥクで溢れ、看板には中国語が氾濫している。ラオスの旅は楽しい、が、個人的に言えばラオスの旬は過ぎたと言わざるを得ない。 20年以上前を知る身とすれば、特にルアンプラバーンは魅力を失ったといえる。もう、あの静かで、厳かで、それでいて優しい街の雰囲気は二度と戻っては来ないだろう。今は雨季なのでオフシーズンだがオンシーズンで春節と重なる2月ともなれば、ゲストハウス(簡易宿泊所)ですら1泊100ドルを超えるらしい。それでも泊まれればマシだそうだ。売りに出されている物件が1億6千万というのも驚きだ。東京より高いぞ。ナイトマーケットはごった返しで進むことすら出来ない状態になるとか言う話である。さて、日記に戻る。昨日、17時に南バスターミナルへと到着。この街には日本人が経営しているゲストハウスがあるらしい。そこに行けばおそらく日本人がたくさん泊まっていると予想して歩いて向かう。この先、日本語を話せる機会はほぼないと思われるので、思い切り会話を堪能しておく。前述、個人的にはこの街に魅力を感じなくなってしまったので翌朝早くには出発することにする。悪くも書いたけど、ラオスに来たことがなければやはりルアンプラバーンはおすすめだと思う。ゆっくり、のんびり、たおやかな時間の流れを堪能できるでしょう。写真は、何もかも変わったと思えるルアンプラバーンで唯一変わりないと思った朝市の風景。とはいえ、路地とそこでの営みは変わらないものの、路地脇の建物は新しくなっています。
@=
 本日、7時に北バスターミナルへと向かう。ルアンナムター行きのバスは8:30発らしいのでチケットを買い待つ。バス停にはラオス人しかいない。まぁ、普通の観光客はパッケージツアーだし、個人旅行者だって現地の旅行代理店で手配してピックアップバスを利用するもんなぁ。で、待つこと一時間半、バスが来ない。トゥクトゥクが二台用意されこれに乗れと言われる。なんでも客が集まらないからミニバンになったそうだ。ミニバンの停留所までトゥクトゥクで送迎というわけだ。う〜ん。まぁ、いいけどね。旅に小さなアクシデントはスパイスみたいなものだ。 10分ばかり走ってミニバンに乗り換え。ちょっと待て、客多すぎないか?すべての座席、補助椅子は埋まり、子供はみんな膝の上。通路や助手席横の空きスペースにも座っているぞ。ちなみに再び外人は私一人。周りは全員ラオス人。誰も文句を言いませんが、なんでバスを出さなかったの?
@=
本日、7時に北バスターミナルへと向かう。ルアンナムター行きのバスは8:30発らしいのでチケットを買い待つ。バス停にはラオス人しかいない。まぁ、普通の観光客はパッケージツアーだし、個人旅行者だって現地の旅行代理店で手配してピックアップバスを利用するもんなぁ。で、待つこと一時間半、バスが来ない。トゥクトゥクが二台用意されこれに乗れと言われる。なんでも客が集まらないからミニバンになったそうだ。ミニバンの停留所までトゥクトゥクで送迎というわけだ。う〜ん。まぁ、いいけどね。旅に小さなアクシデントはスパイスみたいなものだ。 10分ばかり走ってミニバンに乗り換え。ちょっと待て、客多すぎないか?すべての座席、補助椅子は埋まり、子供はみんな膝の上。通路や助手席横の空きスペースにも座っているぞ。ちなみに再び外人は私一人。周りは全員ラオス人。誰も文句を言いませんが、なんでバスを出さなかったの?
@=
 山岳風景について。ラオスはバスでの移動が本当に楽しい。北部はほぼ山岳地帯でカルスト地形も多く、全路線が高原のスカイラインと言ってよい景色である。そして山中に点在する村も家屋もまた素朴そのもので車窓を流れる風景を眺めているだけで飽きない。
@=
山岳風景について。ラオスはバスでの移動が本当に楽しい。北部はほぼ山岳地帯でカルスト地形も多く、全路線が高原のスカイラインと言ってよい景色である。そして山中に点在する村も家屋もまた素朴そのもので車窓を流れる風景を眺めているだけで飽きない。
@=
 焼畑と中老鉄路と高速道路について。ところが山岳風景にも異変がおきている。以前来たときも山が荒れているなと思ったが、この5年で加速がかかったようだ。一つは焼畑。おそらく考えなしに焼いてはトウモロコシを植えているのだろう。熱帯雨林は土地が痩せている。作物はすぐに実らなくなり、放置され植林されることはない。そして驚いたことに中国資本で鉄道と高速道路が建設中である。山は切り崩され、谷は堰き止められ、ジャングルは伐採されてコンクリート柱が立ち並ぶ。ラテライトの地盤がむき出しになり、セメント工場がいくつも建設されている。素朴であってほしい、自然であってほしいと願うのは先進国の驕りであろう。彼らには彼らの生活があるのだから変わっていくのが当然だ。 5年前、「5年後にはもうラオスは面白くないのでは」と思っていたことは現実になりつつある。確実にラオス旅行の旬は過ぎている。鉄道と高速道路が完成したとき、ラオスに来ることはなくなるだろう。
@=
焼畑と中老鉄路と高速道路について。ところが山岳風景にも異変がおきている。以前来たときも山が荒れているなと思ったが、この5年で加速がかかったようだ。一つは焼畑。おそらく考えなしに焼いてはトウモロコシを植えているのだろう。熱帯雨林は土地が痩せている。作物はすぐに実らなくなり、放置され植林されることはない。そして驚いたことに中国資本で鉄道と高速道路が建設中である。山は切り崩され、谷は堰き止められ、ジャングルは伐採されてコンクリート柱が立ち並ぶ。ラテライトの地盤がむき出しになり、セメント工場がいくつも建設されている。素朴であってほしい、自然であってほしいと願うのは先進国の驕りであろう。彼らには彼らの生活があるのだから変わっていくのが当然だ。 5年前、「5年後にはもうラオスは面白くないのでは」と思っていたことは現実になりつつある。確実にラオス旅行の旬は過ぎている。鉄道と高速道路が完成したとき、ラオスに来ることはなくなるだろう。
@=
以前から来てみたかったムアン・シン。落ち着いた地方都市だ。山に囲まれた小さな盆地である。今回の旅で初めてのネットに繋がらない環境。電波は飛び交っているようだが、宿が提供するサービスではないらしい。ここで2泊する予定。海外に出て一週間が過ぎた。そろそろ休日を挟まないと長丁場を乗り切れない。
@=
 ナムターからの道が素晴らしかった。谷筋の一車線路。街道脇にはひなびた村が点在し、民族衣装の人々が行き交う。ジャングルを進む未舗装路は雨を吸って泥濘だ。舗装されている部分も陥没だらけである意味土路よりひどい状態。揺れること揺れること、折角のいい景色だけどカメラを構えることが不可能だ。乗客も静かなもの。と、いうより話していると舌を噛むだろう。ジャングルは深く、普通に恐竜が顔を覗かせそうな感がある。ここにはまた来そうな気がする。
@=
ナムターからの道が素晴らしかった。谷筋の一車線路。街道脇にはひなびた村が点在し、民族衣装の人々が行き交う。ジャングルを進む未舗装路は雨を吸って泥濘だ。舗装されている部分も陥没だらけである意味土路よりひどい状態。揺れること揺れること、折角のいい景色だけどカメラを構えることが不可能だ。乗客も静かなもの。と、いうより話していると舌を噛むだろう。ジャングルは深く、普通に恐竜が顔を覗かせそうな感がある。ここにはまた来そうな気がする。
@=
 ナムターからのバス。やはり車内はラオス人ばかり。いわゆるバンに22人(大人20人・膝上の子供2人)乗っていた。 8時発の時刻表であったが、定員(超過してると思うけど)になったからか、 7時40分には出発した。30分前にバス停に行っておいて良かった。
@=
ナムターからのバス。やはり車内はラオス人ばかり。いわゆるバンに22人(大人20人・膝上の子供2人)乗っていた。 8時発の時刻表であったが、定員(超過してると思うけど)になったからか、 7時40分には出発した。30分前にバス停に行っておいて良かった。
@=
街を散策。 1時間で見終わる。市場を発見したので、ぶらり覗いてみる。昼飯何を食べよっかなと思っていると、おおっ、こんなところに日本人が、、、!ビールを解禁。昼間から飲む。当然おごる。いくらおごっても1000円もしない。若い子が元気なのは嬉しい。25歳二人と27歳一人。三人とも女子でした。旅を始めて一ヶ月、昨日出会ったそうで、一年かけて世界一周をするらしい。そうだね。若い子はこのくらい元気でないといけない。安定志向と言うか、昨今、安全志向な人間ばかりが多いけど、そんな人が大半を占めるようになったのが、今の日本社会が衰退する原因のように思う。失敗を許さない社会ではなく、こういった人たちが帰国後に活躍できる社会であればいいなぁ。人間として魅力的な方ばかりでした。彼女らの話を聞くにつけ、そのバイタリティに尊敬の念をいだきつつ、私はこれから昼寝です。だって、南国のクソ暑い中で発汗と同時にかいた汗の分だけ2時間位ビールを飲んでたんだもの。 20代の体力には敵いませんわっ!
@=
 ムアン・シンから夕焼けの風景。なんにもない田舎が大好きだ。明日も一日この街である。旅の目的地はドイツのデュッセルドルフ。いつになったら着くのだろう。その前に、どうやって行ったらいいんだろう。ただ、道は繋がっている。そして終わらない道はない。一歩進めば一歩近づく。進みさえすれば必ず到着する。それは間違いがない。いい年したおっさんなのに感傷的な気分になる。そんなムアン・シンの夕暮れ。
@=
ムアン・シンから夕焼けの風景。なんにもない田舎が大好きだ。明日も一日この街である。旅の目的地はドイツのデュッセルドルフ。いつになったら着くのだろう。その前に、どうやって行ったらいいんだろう。ただ、道は繋がっている。そして終わらない道はない。一歩進めば一歩近づく。進みさえすれば必ず到着する。それは間違いがない。いい年したおっさんなのに感傷的な気分になる。そんなムアン・シンの夕暮れ。
@=
当世バックパッカー事情。旅の仕方が20年前と今では全く異なっている。 5年前と比べても大きく変ったと思う。インターネットとスマートフォンの影響は大きい。今やスマホに話しかければ自動翻訳してくれる。それを相手に見せればコミュニケーションは成立というわけだ。これで買い物や宿泊、交通といった部分での意思疎通は問題ない。コミュニケーション以上の利点は、地理と現在位置の把握だ。世界のどこにいてもスマホで地図を見ることができる。 GPS搭載だから自分がどこにいるのかがわかる。そして、地図にはホテルやレストラン、駅やバス停の場所も示される。コミュニケーションが取れず、どう進んでいいのかすらわからない、、、と途方に暮れるということがなくなるのだ。旅先で出会った旅行者は「スマホがないと旅ができない」と言う。宿の女将が言うには、「最近はバックパッカーもほとんど予約してくる」とのことであった。「ウォークイン(直接来て泊めてください)のお客さんは減ったねぇ」とも言っていた。どこにいてもどんな時間にでもネットの予約サイトでその日の宿を検索できるのだからそうなるであろう。一ヶ月くらいの旅なら全行程を事前に決定し、全宿泊施設を予約してから旅をするバックパッカーも多いそうだ。すべての情報はネット上にある。これを活用するのが今時の旅行者なのだ。
@=
振り返って、私はスマホを持っていない。不安と驚きがない旅は無味乾燥に思うからだ。コミュニケーションに四苦八苦し、初めての都市ではまず途方に暮れる。郊外のバスターミナルから市街中心にたどり着くまでが一苦労であるが、これがまた楽しい部分でもある。とはいえ、20年前の旅のスタイルを維持することは不可能だ。昔は情報は宿で得た。もしくはタクシー(バイタクやトゥクトゥクも含む)ドライバーから得た。宿には宿泊者ノートがあり、そこには訪れた旅人たちの感想が細かに書かれていた。旅の経路やおすすめの観光スポット、交通事情などがみっしりと書き込まれており、それを読むのも楽しかった。タクシードライバーはノートを持っていた。そこにもやはり、旅行者の感想が書き込まれていた。「このドライバーは信用できる」や「宿までぼったくらずに連れて行ってくれる、親切」などといろんな言語で書かれていた。当のドライバーはノートに何が書かれているのかを理解していないであろう。しかしながら、彼らに取ってはこのノートが信用の源泉であり営業活動なのだ。バスが到着すると客引きのドライバーがノートを見せながら、「俺に任せろ」とアピールする。ノートを読み利用後は私もノートにメモを書き込んだものだ。次に利用する旅行者のためを思って。今や、すべての情報はネットにある。宿ノートもドライバーノートもなくなってしまった。宿のレビューやクチコミ情報はネットで確認できるし、タクシーの標準的な金額もネットで調べることができる。情報のありかが、宿や案内所からネットに移った以上、旅人もスマホを待たざるを得ない。
@=
流石に私もPCは持ち歩いている。インターネットがつながる場所で次の目的地の地図を確認する。場合によっては簡単なメモを取る。 PDF化して読書用に持ち込んだkindleに転送することもある。あとはコンパス(方位磁石)である。もう本当に物理的、登山用のコンパスである。こんなの見ながら歩いてる人なんて他には誰もいないよ。
@=
コンパスなくなった。どっかで落としたらしい。あ〜れ〜。
@=
午前中にルアンナムターまで戻る。ラオス人は車酔いに弱い。まぁ、道が強烈だし、車に慣れていないのでしょう。運良く窓際に座れたのだが、大きな誤算が、、、。一応、車中にはビニル袋が用意されているんだけど、みんなゲーゲーした後、窓からポイするんだよねぇ。窓際の私の前をビニル袋は何度も通過していきました。
@=
午後はルアンナムターを自転車で一周。
@=
さて、明日からは中国。今までは戦う必要がなかったけど、ちょっと気を引き締めないといけないかな。
@=
 私は今驚いている。景洪の変貌に瞠目する。中国の辺境雲南省、そのさらに辺境西双版納傣族自治州。同州首府であるとはいえ6年前の景洪市には何もなかった。地図を見るまでもなく西双版納などどう考えても辺境である。街道沿いのうら寂れたホテルに泊まり、何もないメコン川を眺めていたような気がする。写真は現在メコンに浮かぶ遊覧船と向こう岸の摩天楼。
@=
私は今驚いている。景洪の変貌に瞠目する。中国の辺境雲南省、そのさらに辺境西双版納傣族自治州。同州首府であるとはいえ6年前の景洪市には何もなかった。地図を見るまでもなく西双版納などどう考えても辺境である。街道沿いのうら寂れたホテルに泊まり、何もないメコン川を眺めていたような気がする。写真は現在メコンに浮かぶ遊覧船と向こう岸の摩天楼。
@=
今日の驚きについては、時間のあるときに、まとめて書くとしてまずは日記。 5時半起床、6時半チェックアウト。7時前にはバスターミナルに到着。出発時刻は8:30と案内板には書いてあったが、8時には出発してしまった。そして、さすが中国人運転手。苦虫を噛み潰したような顔だ。愛想のかけらもない。宿泊も決めてないし、最初の目的地景洪は6年前に寄ったことがあるとはいえ、ほとんど何も覚えていない。とにかく不安だけが心を支配する。あぁ、旅のしやすい優しいラオスよさようなら。さて、中国へと続く道路は、例の中国資本による鉄道と高速道路の建設予定地でもある。その工事の規模の大きさに驚く。ダンプが何百台と往来し、削った山と埋めた谷の広さに驚く。中国が本気を出すと凄まじい。(感嘆はするが素晴らしいとは別。)那覇空港の埋め立てなんて何を小さな工事に何年もかけているのかと思ってしまう。国境に到着。中国に入国。これが面倒なんだよね。ラオスなんてノーチェックだ。パスポートはメクラで判子をついているだけだし、そもそも荷物チェックはない。これが中国だと、荷物はだいたい開けさせられるし、中国語も英語もよくわからないのに入管があれこれ言ってくる。案の定、荷物はほとんど出されて、問題ないことを確認。ところが、入管が違った。機械が日本語で話してくれるのである。「指紋のチェックをします、親指以外の4本の指をセンサーに押し当ててください。」いや、もう、自動音声の案内に従うだけで入国手続きは完了。さらに入管のカウンター前には4つのボタンがある。ボタンに書かれているのは「大満足」「満足」「やや不満」「不満」と言ったこと。もう、日本のサービス負けてるわ。「満足」を押す。本来入管なんてサービス業と違うでしょ、と思う所までサービス向上に務めるあたり侮れない。 3時間走って景洪に到着。自分が何処にいるのか全くわからないので適当に繁華街っぽい方に歩き出す。何をするにもお金がいる。道中見つけた銀行で中国元に両替。が、銀行員がなにを言っているのか全くわからない。多分中国語で「中国語が話せるか?」と聞いているらしいので「わからない」と日本語で答える。日本語は通じないだろうが、雰囲気とゼスチャーで「ああ、こいつなんもわかっとらんな」とは通じたはずだ。そこで銀行員が取り出したるは神器スマホ。やったね、スマホの翻訳機能だ。やるな、文明人。私は持っていないけどな。翻訳されたちょっとぎこちない日本語を読む。「外国人が両替するのは面倒だ」って、えぇー、どういうこと?さらに「同僚が両替したことにするけど、いいですか?」って、意味がわからんけどとりあえずOKって言ってみる。すると、顧客サポートのお姉さんが自分のIDカードを貸してくれました。要は外人が両替するには、パスポートをコピーしたり、色々書類を書いたり面倒だったらしい。色々突っ込みたいがとりあえず一言、「お姉さん、どうして日本の一万円札持ってるの?」とはならないんだろうか。さて、宿泊までにはまだ悶着あるのだが、もう、流石に長くなるのでバッサリカット。
@=
ラオスのルアンナムターから中国の景洪まで250キロ弱。 5時間ほどのバスの旅。途中国境を超えたり昼食があったりするので、実質乗車時間は4時間くらい。大陸の感覚から言うとすぐ隣と言ってもいい近さなのですが、、、。この2つの都市と両者を結ぶ国境バスはある意味今が一番興味深いと言えると思う。
@=
 ラオスで建設中の鉄道と高速道路。山も谷も全てを強引に平坦化している。幅数百メートルで何キロにも渡って雨を吸った紅土が広がる。投入されている重機とトラックの数が半端ない。少なくとも数百台ではきかないはず。自然を好む一員としてこのやり方はないのではと思いますが当事者は受け入れているでしょう。道路も橋も学校も病院も他国の援助で作ってもらっている国だしなぁ。素朴で素直なラオス人。中国は支援の先にあるものが結構露骨なんだけど大丈夫かなぁ。工期はたったの五年間。言っては何ですがラオス北部は相当な山岳地帯です。補給基地となるような街もろくすっぽないジャングルです。総延長400キロ。それをたったの5年間。
@=
ラオスで建設中の鉄道と高速道路。山も谷も全てを強引に平坦化している。幅数百メートルで何キロにも渡って雨を吸った紅土が広がる。投入されている重機とトラックの数が半端ない。少なくとも数百台ではきかないはず。自然を好む一員としてこのやり方はないのではと思いますが当事者は受け入れているでしょう。道路も橋も学校も病院も他国の援助で作ってもらっている国だしなぁ。素朴で素直なラオス人。中国は支援の先にあるものが結構露骨なんだけど大丈夫かなぁ。工期はたったの五年間。言っては何ですがラオス北部は相当な山岳地帯です。補給基地となるような街もろくすっぽないジャングルです。総延長400キロ。それをたったの5年間。
@=
 国境の町はこうなっていました。ちょっと、信じられません。鉄道と高速道路を作るということはそれに付随する施設(街すら)も作るということ。北部ラオスは中国化し、貧富の差を生み、搾取の構造が持ち込まれるのは目の前だ。一帯一路って言うのだったっけ。私に見えるのは属国化。中華王朝風に言えば藩屏化。別に批判するわけではないですし、これが文明化というものだとも思う。
@=
国境の町はこうなっていました。ちょっと、信じられません。鉄道と高速道路を作るということはそれに付随する施設(街すら)も作るということ。北部ラオスは中国化し、貧富の差を生み、搾取の構造が持ち込まれるのは目の前だ。一帯一路って言うのだったっけ。私に見えるのは属国化。中華王朝風に言えば藩屏化。別に批判するわけではないですし、これが文明化というものだとも思う。
@=
 工事現場以外はこんなもの。伝統的なバンブーハウス(竹の皮を編んで作った家)。一つ前の国境の町ボーテンも5年前はこんなもんでした。日本もラオスのためにメコン川にかかる橋を作ったり、道路を整備したり色々援助してるんですよ。ドイツやフランスなんかも学校や病院を作ったりしています。そういった援助施設には記念と友好の碑が残されていたりします。そこに中国。うん、やるならこれくらいやらないとね。かけてるお金が桁違い。高速道路に高速鉄道だからなぁ。ついでに街も作ってあげて、至るところ中国語の看板だらけ、華人も大量に送りこむ。友好の碑なんていりません。だってそこはもう中国になるんだもの。 5年前ラオスで話した海外青年協力隊の方が言ってました。「北部は中国だし、南部はタイだし。もうラオスっていらないんじゃね。」今はもう全部中国が持っていっちゃう状況だし、その頃からラオスに援助することの意味に疑問を持っていたのかもしれない。
@=
工事現場以外はこんなもの。伝統的なバンブーハウス(竹の皮を編んで作った家)。一つ前の国境の町ボーテンも5年前はこんなもんでした。日本もラオスのためにメコン川にかかる橋を作ったり、道路を整備したり色々援助してるんですよ。ドイツやフランスなんかも学校や病院を作ったりしています。そういった援助施設には記念と友好の碑が残されていたりします。そこに中国。うん、やるならこれくらいやらないとね。かけてるお金が桁違い。高速道路に高速鉄道だからなぁ。ついでに街も作ってあげて、至るところ中国語の看板だらけ、華人も大量に送りこむ。友好の碑なんていりません。だってそこはもう中国になるんだもの。 5年前ラオスで話した海外青年協力隊の方が言ってました。「北部は中国だし、南部はタイだし。もうラオスっていらないんじゃね。」今はもう全部中国が持っていっちゃう状況だし、その頃からラオスに援助することの意味に疑問を持っていたのかもしれない。
@=
景洪は物価が高い。 1.5リットルの水が約80円だから、日本とそんなに変わらない。一食するのに数百円はする。簡素なチャーハンでやっと200円くらい。宿も安いところに泊まっているけど1400円。西成のゲストハウスのほうが安いんとちゃうか?5年前と比べて換金レートが悪くなっているし(元高円安)物価も大きく上昇している。
@=
 6時起床。雨。二度寝。8時行動開始。中国は標準時が一つしかなくどこでも北京時間だから8時も実質的には7時。まずはメコン川(中国では瀾滄江)沿いの歩道の散策から始める。散策路のほぼ中央の広場を起点として右岸北西を目指す。
@=
6時起床。雨。二度寝。8時行動開始。中国は標準時が一つしかなくどこでも北京時間だから8時も実質的には7時。まずはメコン川(中国では瀾滄江)沿いの歩道の散策から始める。散策路のほぼ中央の広場を起点として右岸北西を目指す。
@=
 求人の掲示板。大体月額で3000元(6万円)から5000元(10万円)くらい。 KTV(カラオケテレビ?)ってカラオケスナックのことかなぁ。 16歳から28歳の女性限定って書かれていて、月額18000元(36万円)でした。僻地の地方都市ですらこのくらいの給与水準があるなら物価が高いのも納得。
@=
求人の掲示板。大体月額で3000元(6万円)から5000元(10万円)くらい。 KTV(カラオケテレビ?)ってカラオケスナックのことかなぁ。 16歳から28歳の女性限定って書かれていて、月額18000元(36万円)でした。僻地の地方都市ですらこのくらいの給与水準があるなら物価が高いのも納得。
@=
 新しい景洪はちょっと気に入っている。結局、今晩を含めて3泊することになった。私は強引な都市化には否定的ではあるのだけど、この街は自然となかなかうまく調和していて居心地が良い。「あれっ、中国ってこんなに旅行しやすかったっけ?」と疑問に思うほどだ。街は綺麗だし、みな朗らかで親切だ。ゲストハウスから眺めるメコン川も悪くない。スーパーでは過剰とも思える店員が常に独り言を言っている。独り言と書いたが私がわからないだけで多分「いらっしゃいませ」とか「ご用はありませんか」などだろう。実際、客にあれこれと説明している姿が散見される。 20年前の中国で見た全くやる気のない座っているだけだった店員がなんとかわったことか。街にゴミはない。車はクラクションを鳴らさない。都会だけど落ち着いている。住民たちの所得と物価を勘案するに日本の都会よりかはよっぽど住みやすいのではないだろうか?いやはや、驚くばかりである。
@=
新しい景洪はちょっと気に入っている。結局、今晩を含めて3泊することになった。私は強引な都市化には否定的ではあるのだけど、この街は自然となかなかうまく調和していて居心地が良い。「あれっ、中国ってこんなに旅行しやすかったっけ?」と疑問に思うほどだ。街は綺麗だし、みな朗らかで親切だ。ゲストハウスから眺めるメコン川も悪くない。スーパーでは過剰とも思える店員が常に独り言を言っている。独り言と書いたが私がわからないだけで多分「いらっしゃいませ」とか「ご用はありませんか」などだろう。実際、客にあれこれと説明している姿が散見される。 20年前の中国で見た全くやる気のない座っているだけだった店員がなんとかわったことか。街にゴミはない。車はクラクションを鳴らさない。都会だけど落ち着いている。住民たちの所得と物価を勘案するに日本の都会よりかはよっぽど住みやすいのではないだろうか?いやはや、驚くばかりである。
@=
 そして昔ながらの屋台街、、、と思いきや、支払(決済)はスマホである。列車やバスの予約もスマホアプリ。中国は日本以上のネット社会である。しかも管理されたネット社会。近未来を舞台にしたSF小説やマンガの世界に近いものを感じる。現金も使えるけど、むしろ不便である。
@=
そして昔ながらの屋台街、、、と思いきや、支払(決済)はスマホである。列車やバスの予約もスマホアプリ。中国は日本以上のネット社会である。しかも管理されたネット社会。近未来を舞台にしたSF小説やマンガの世界に近いものを感じる。現金も使えるけど、むしろ不便である。
@=
さて、景洪のことを色々褒めているが、これにはカラクリがあると思う。一言でいってしまえば国家による締め付けであり自由があるとは思えない。まず、スピードを出す車がなく、アジア名物爆音クラクション合戦がないこと。これは簡単で、ほぼすべての交差点を公安が監視している。監視していると言えば聞こえが悪いが、主な仕事は旗を持っての交通整理である。もちろん、交差点には信号機があるのだが、加えて公安も必ず配置されている。そして街にゴミがないこと。こちらは、300m置きくらいに清掃員を見かける。もう、拾うゴミがないと思うところでも頑張って枯れ葉や枯れ枝を拾っている。さらに、高圧洗浄車が市内を循環している。水しぶきを上げながら街のホコリを洗い流していく。最後は、想像だが国境間近の都市として政府からふんだんにお金が出ているのではないだろうか。これだけの開発が地方自治体にできるわけがない。中国はこれからラオスやミャンマーも含めて東南アジアを支配する予定であろう。ラオスへの高速道路と高速鉄道も建設中である。そんなとき中国国内の発展した国境都市の存在は他国に対する何よりのプロパガンダだ。私は景洪の発展を歓迎する。無理な都市化を感じない。間違いなく住人は幸せになっている。それでいて非常に複雑な気持ちである。ユートピアとディストピアの混在を感じる。
@=
 9時まで寝る。10時行動開始。旅の記録なんて今までは書いたことがなかったのだが、書き出すと面白くなってきて夜ふかしが過ぎてしまった。本日は川向うの探索である。メコンに架かる西双版納大橋を渡る。メコン左岸は比較的旧市街が残っている。昔の景洪の雰囲気を色濃く感じることができる。ツバを吐くおっちゃんや、落ちているペットボトルになぜかホッとする。とはいえ、マナーの悪い人も落ちているゴミも激減している。以前であればペッペッする人も町中のゴミも当たり前だったので、むしろ気にならなかったのだが、今では逆に相当目立つ存在になった。ゴミ少なくマナーも良くなっているが旧市街の雑然さは変わらずである。加えて旧市街は庶民の街、新市街に比べて飯が安い、旨い。キクラゲてんこ盛り特大チャーシュ高菜ご飯モヤシナムル入り、海藻スープ付きで150円。午後は老大橋で新市街に戻る。こちらも表通りを外れると昔の面影はまだまだ残っているようだ。整備された新市街とノスタルジックな旧市街。なんとも不思議で魅力的な街である。正直、一週間くらいは滞在したい気になっていたのだが、今回のメインは中央アジアである。景洪あたりなら来ようと思えばいつでも来れる。まだまだ行きたいエリアがあるのだが、今後の楽しみにとっておこう。涙をのんで明日は昆明に向かう。バスで10時間の道のり、チケットは5000円。やっぱ、物価は高いなぁ。
@=
9時まで寝る。10時行動開始。旅の記録なんて今までは書いたことがなかったのだが、書き出すと面白くなってきて夜ふかしが過ぎてしまった。本日は川向うの探索である。メコンに架かる西双版納大橋を渡る。メコン左岸は比較的旧市街が残っている。昔の景洪の雰囲気を色濃く感じることができる。ツバを吐くおっちゃんや、落ちているペットボトルになぜかホッとする。とはいえ、マナーの悪い人も落ちているゴミも激減している。以前であればペッペッする人も町中のゴミも当たり前だったので、むしろ気にならなかったのだが、今では逆に相当目立つ存在になった。ゴミ少なくマナーも良くなっているが旧市街の雑然さは変わらずである。加えて旧市街は庶民の街、新市街に比べて飯が安い、旨い。キクラゲてんこ盛り特大チャーシュ高菜ご飯モヤシナムル入り、海藻スープ付きで150円。午後は老大橋で新市街に戻る。こちらも表通りを外れると昔の面影はまだまだ残っているようだ。整備された新市街とノスタルジックな旧市街。なんとも不思議で魅力的な街である。正直、一週間くらいは滞在したい気になっていたのだが、今回のメインは中央アジアである。景洪あたりなら来ようと思えばいつでも来れる。まだまだ行きたいエリアがあるのだが、今後の楽しみにとっておこう。涙をのんで明日は昆明に向かう。バスで10時間の道のり、チケットは5000円。やっぱ、物価は高いなぁ。
@=
夜のリバーサイドはみんなの社交場。 10年前のコンパクトデジカメのビデオ機能では明るく映らないのが残念。
@=
仕事が終わればみんなでダンス。毎日が盆踊りみたいなものなのかな。南蛮の住人はみんな幸せそうですよ。
@=
5時半起床。7時前にはチェックアウト。さようなら尋常ホステル(Wonderlust Hostel)。 7時過ぎにはバスターミナルに到着。バスは8時30分発。何だもう来てるのかと思いバスに取り込むと「これは7時20分発だ」と怒られる。時刻表にあった始発を買ったはずなのに、それより早い時刻表にのらないバスがあったようだ。しばし待つ。目的のバスは定刻通りに出発。これから10時間、車窓の景色を楽しむことにする。ちなみにバスは寝台の夜行も座席の昼行便もあまり値段が変わらないので、以前であれば観光を優先して夜行を使っていたものだが、今は観光するより景色を眺めたり街を探索する旅のほうが好きになった。で、バスに乗ること2時間、なんと4回も検問所に停車。警察による社内のチェック、そのうち2回はパスポートの提出を求められた。私以外の地元民たちもみなIDカードを提出している。人の移動はこうやって必ず公安に把握されているようだ。こんなペースでは10時間あっても着かないのではと心配になるがこれ以降の検問はなかった。なるほどね。要は西双版納傣族自治州を抜ければ検問がなくなるわけだ。少数民族の監視機構というわけか。景洪で感じた違和感のカラクリを再確認する。さて、雲南省は基本的にラオス北部から引き続き山岳地帯である。日本もそうだが、架橋と隧道が繰り返される高速道路の建設はさぞかし大変であったろうと思う。最初の通過都市は普洱市。なだらかな山稜はこれ全て茶葉の段々畑。なかなか壮観である。日本でも少しづつ普洱茶(プーアル茶)の知名度が上がってきましたね。次は、元江市。こちらの作物は米で棚田が広がる。隣町の元陽の棚田が有名だけど、こちらもそこそこではないかな。そして着いた昆明市は雲南省の省都。人口600万。来る前から大都市なのはわかっている。わかっていたはずなのにやはり私は驚いている。街は再開発が進み高層ビル街になっている。そして、やはり街にゴミはなく、車の運転もみな穏やか。考えてみればバスも安全運転であった。乗客もシートベルトの着用を求められ発車前に確認される。大都市は普通旅行がしにくい。一歩きすれば街の構造がわかる地方都市とは違うのだ。昆明の長距離バスターミナルは街の外れにあって、中心街に行くだけで大変であった。それが今は、地下鉄が走り、主要な鉄道駅とバスターミナル、飛行場を中心街へと結びつけている。自動券売機は英語対応しているし、車内放送も中国語と英語だ。地下鉄車内で大声で話す人はおらず、7割位は黙々とスマホいじりをしている。前述、街の清潔さや平穏さと合わせ、もう、東京や大阪、横浜神戸と何も変わりません。一応、裏道に入ればちゃんと汚い店もあります。ところが裏道の汚い店で食べたチンジャオロースは500円でした。後発国にとっての文明化とは強制力を伴うもの。日本だって明治維新は強引な改革だったわけだし、国民のライフスタイルを無理やり変革する中国のやり方はうまく行ってると言える。あえて街の写真は載せません。東京駅や大阪駅で降りて写真を取れば、それは昆明の写真と同じです。
@=
7時起床。成都までの列車のチケットをネットで予約。7500円。出発は明日。予約番号がメールで通知され、この番号を駅で見せればチケットと交換されるらしい。直前でも大丈夫なんだろうけど、念の為今日のうちに引き換えておこうと思う。が、出ようとすると、雨が降り出す。仕方がないので二度寝。雨季なので日に何度か降るが、大抵の場合1時間程度で止むことが多い。 11時になって行動開始。地下鉄で昆明駅に向かう。チケット売り場で予約番号をメモした紙とパスポートを提出すればそれで終わり。(私がスマホを持ってないだけでスマホアプリがあれば画面を見せるだけのはず。)服務員がなにやらカチャカチャとキーボードを叩いているが、一分とかからずチケット入手。全く話す必要がない。何でもネットでできてしまう。もうすでに近未来都市だぜ。雲南なんて辺境なのに、、、。駅舎、駅前、表通りも綺麗なもの。やはりゴミなんて落ちていない。裏道に入れば昔ながらの古臭くて薄汚れた中国が残っているが、ここにもやはりゴミは殆ど無い。本当に変わったなぁ。劇的だよ。たった5年ほど前との比較なのに人も街も同じとは思えない。帰りはホテルまで歩く。たかが地下鉄3駅だ。駅前から伸びる北京路はどこか御堂筋に似ていた。 1時間程度午睡してから再行動。地下鉄で市中央の翠湖公園に行く。なんかみんな踊ったりしていて楽しそうである。その後向かった昆明中心街は銀座と心斎橋を合わせたようなもの。活気といい、規模といい。日本の大都市以上だぜ。雲南なんて辺境なのに、、、。色々、思うことの多い一日であった。さて、明日は23時間の列車の旅。一応、一等寝台だ。ちなみに陸路とローカルにこだわっているだけで、一等寝台だと列車も飛行機や新幹線と同じくらいの値段である。新幹線なら6時間でいけるんだけどね。まぁ、旅は浪漫あってのものですよ。
@=
昆明の写真をピックアップ。あんまり日本と変わらない。籠の鳥は幸せか。金持ち婦人の飼い犬は幸せか。
@=
 体感的に200人に1人くらいが清掃員。もう、拾うゴミなんてないってば!そのほか市民のゴミ拾いボランティアがいる模様。ハイソの衣装を着ながらも、ゴミ袋と金鋏も持っている。だから、拾うべきゴミがもうどこにもないよ!清掃は市民の義務として当番制だったりするのでしょうか?なお、同様に200人に1人くらいは公安。
@=
体感的に200人に1人くらいが清掃員。もう、拾うゴミなんてないってば!そのほか市民のゴミ拾いボランティアがいる模様。ハイソの衣装を着ながらも、ゴミ袋と金鋏も持っている。だから、拾うべきゴミがもうどこにもないよ!清掃は市民の義務として当番制だったりするのでしょうか?なお、同様に200人に1人くらいは公安。
@=
 1時間ちょっとで東風広場に帰ってきた。ビル群手前の空き地は絶賛建設中。と言うより、至るところが高層ビル街で建設現場。自転車に乗ってる人が多い理由は後述。帰る途中で買ったマンゴーを2個食べて昼寝。
@=
1時間ちょっとで東風広場に帰ってきた。ビル群手前の空き地は絶賛建設中。と言うより、至るところが高層ビル街で建設現場。自転車に乗ってる人が多い理由は後述。帰る途中で買ったマンゴーを2個食べて昼寝。
@=
昔、大阪の天王寺公園北東側の坂道では人々が歌い踊っていた。路上でカラオケを歌い、好き者が仮装したりして踊っていたのだ。あの状況を何倍も派手に大規模にしたような感じである。路上カラオケは大阪名物の一つであったが、いつしかなくなってしまった。行政指導が入ったのであろう。個人的にはああいった文化は良かったと思うので残念だ。
@=
 そして東風広場に帰ってきました。地下鉄駅と自転車ステーション。自転車ステーションは昆明の至るところにあります。 1日1元(20円)で、どこで借り出してどこで返してもいいようです。これは便利だと思います。市民も多々利用しています。自転車にはQRコードが付いているので、スマホで撮影してそれが決済なのでしょう。ホント、ネットとスマホ社会です。帰る途中で買ったマンゴーを2個食べてもう寝ます。
@=
そして東風広場に帰ってきました。地下鉄駅と自転車ステーション。自転車ステーションは昆明の至るところにあります。 1日1元(20円)で、どこで借り出してどこで返してもいいようです。これは便利だと思います。市民も多々利用しています。自転車にはQRコードが付いているので、スマホで撮影してそれが決済なのでしょう。ホント、ネットとスマホ社会です。帰る途中で買ったマンゴーを2個食べてもう寝ます。
@=
今日は一日列車の旅。車窓の景色を眺めながら、書き漏らしたことをつらつらと、、、。
@=
両替は客のIDカード。銀行にて「中国銀行の口座を持っているか?」と聞かれる。持ってるわけがない。はいはい、外人の両替は面倒だから同僚のIDカードで代行でしょ。オッケーオッケー、と思っていたら、他の客からIDカードを借りてそれで手続きしちゃったよ。おいおい、どうして、そんな貧乏そうな痩せっぽちのオッサンが、2万もの日本円を持ってることに出来るわけ?管理社会なのに妙に大雑把なのが中国である。
@=
ホテルはスマホで。昆明で泊まった2000円のホテル。ネット予約はしてたんだけど受付で全く英語が通じない。やれ、筆談かと思ったところで、芦屋雁之助扮する山下清みたいな兄ちゃんが取り出したるは神器スマホ。中国語でスマホに「アイヤー、アルヨー」と話しかければ、自動翻訳で英語になって「保証金は100元、チェックアウト時に返却します」だって。これってもう、ドラえもんの「ほんやくこんにゃく」の世界だよなぁ。秘密道具を持ってるのが、私じゃなくって山下清だけどさ。なお、大変気のいい兄ちゃんで何を頼んでも「好々(ハオハオ)」と請け負ってくれました。
@=
チケットの購買について。昆明から成都行きの列車のチケットを中国の旅行代理店trip.comでネット予約した。ページの日本語訳はほぼ完璧で指示に従うだけで簡単に予約完了。支払いはクレジットカードなので現金は必要ない。予約番号がメールで送られてくるので、その番号を窓口で伝えればチケットを発券してくれる。専用のスマホアプリもあって、そちらを使えば画面を見せるだけでいいらしい。中国語なんて全く話せなくても大丈夫です。そもそもネットで完結出来るので話す機会がない。正直、今の中国は旅行がしやすいと感じる。 20年前、一番旅行がしにくいと思った中国。 5年前、東南アジア並みに旅行がしやすくなった中国。そして今、少なくとも都市部は先進国だし近隣諸国と比べて圧倒的に旅行がしやすいです。
@=
街が変わったことは写真でわかるが、人が変わったことも書いておこう。雲南省という土地柄もあろうが中国に入ってからほぼ嫌な目にあっていない。人は優しくて食事中なども結構話しかけてきてくれる。こちらが中国語ができないことを申し訳なく思うくらいだ。ぶつかりそうになれば向こうから道を譲ってくれる。一度自転車の進路妨害をしてみたが、嫌そうな顔はされたが避けてくれた。以前であれば「どけ、こら!」みたいなことを中国語で怒鳴られていたはずだ。写真を撮っていれば一旦通るのを待ってくれる。もしくは映らないように頭を下げて通り過ぎてくれる。これも以前であればこちらのことなど全く無視してカメラの前を横切ったはずだ。そして昆明では地下鉄内でさえリュックを後ろにかける。何を当たり前なと思うかもしれないが公共交通機関ではリュックを前にかけるものだ。盗難防止を意識する必要がないと言うことである。ゴミのポイ捨て、街中での痰吐きがほぼなくなったことは何度も書いた。国家権力による強制的なモラル変革であろうが、結果としてマナーは格段に良くなっている。
@=
 5時に蚊に噛まれて起床。7時半チェックアウト。昆明駅にて1時間半前には待機。昔の鉄道駅は(そして列車内も)ゴミ箱みたいなものであった。今もピーナツの殻やりんごの芯などが落ちているが、まぁ、全然許容範囲で奇麗なものである。列車は1時間以上遅れて11時過ぎに発車。切符は新幹線でおなじみの青くて大きい磁気のやつ。自動改札機があるのに何故か駅員が切符にハサミを入れるという昔ながらの手法であった。 30分走ると大平原。中国、嫌になるほど広いぜ。農村は大変美しい。1時間走ると雲南の自然と調和した農地の風景を満喫できる。 3時間走ると山稜へと入り大絶景である。よくこんなところに鉄道を敷設したことだと嘆息する。昭通を超えると一部雲が眼下に見えることから相当な高所を走っているようだ。素晴らしい景色は他で変えられない。ローカル列車にしてよかった。日が暮れてしまうのが残念。なお、点在する田舎町は古くて汚くて、うん、変わってない。駅舎もボロボロ。ゴミもたくさん落ちている。四川との州境あたりは土道も多々残っていてラオスとどっこいどっこいですな。
@=
5時に蚊に噛まれて起床。7時半チェックアウト。昆明駅にて1時間半前には待機。昔の鉄道駅は(そして列車内も)ゴミ箱みたいなものであった。今もピーナツの殻やりんごの芯などが落ちているが、まぁ、全然許容範囲で奇麗なものである。列車は1時間以上遅れて11時過ぎに発車。切符は新幹線でおなじみの青くて大きい磁気のやつ。自動改札機があるのに何故か駅員が切符にハサミを入れるという昔ながらの手法であった。 30分走ると大平原。中国、嫌になるほど広いぜ。農村は大変美しい。1時間走ると雲南の自然と調和した農地の風景を満喫できる。 3時間走ると山稜へと入り大絶景である。よくこんなところに鉄道を敷設したことだと嘆息する。昭通を超えると一部雲が眼下に見えることから相当な高所を走っているようだ。素晴らしい景色は他で変えられない。ローカル列車にしてよかった。日が暮れてしまうのが残念。なお、点在する田舎町は古くて汚くて、うん、変わってない。駅舎もボロボロ。ゴミもたくさん落ちている。四川との州境あたりは土道も多々残っていてラオスとどっこいどっこいですな。
@=
 6時起床。四川は朝から雨。 1時間以上出発が遅れた割には、予定時刻より早く到着。やるな中国鉄道。一時期とある事故で話題になった「回復運転」だ。さて、成都は人口1000万を超える大都市。もう書くことはありませんわ。物価も高い。武侯祠見学料は60元(1200円)。京都の拝観料並み。 7年前に見てるのでパス。土産物街の錦里は商魂たくましい中華テーマパーク。京都の産寧坂並み。 7年前より広くなってるぞ。成都は都会で高層ビルばかり。面白くないので一番どうでもいい写真を一枚。「成都銅雀台整形美容医院」だと。ツッコミどころがありすぎるだろ。
@=
6時起床。四川は朝から雨。 1時間以上出発が遅れた割には、予定時刻より早く到着。やるな中国鉄道。一時期とある事故で話題になった「回復運転」だ。さて、成都は人口1000万を超える大都市。もう書くことはありませんわ。物価も高い。武侯祠見学料は60元(1200円)。京都の拝観料並み。 7年前に見てるのでパス。土産物街の錦里は商魂たくましい中華テーマパーク。京都の産寧坂並み。 7年前より広くなってるぞ。成都は都会で高層ビルばかり。面白くないので一番どうでもいい写真を一枚。「成都銅雀台整形美容医院」だと。ツッコミどころがありすぎるだろ。
@=
6時半起床。成都から南へ150キロ、8時のバスで楽山へと向かう。世界遺産でもある楽山大仏は世界最大の磨崖仏であり、遺跡好き仏像好きの私としては一度は見てみたいと思っていた。、、、と、言うのは嘘で、ビザの延長のためである。楽山ではビザが1日で取得できるらしいので今のうちにと思った次第。大仏自体は7年前にすでに見ている。という訳で、楽山に着いてすぐに宿にチェックイン。宿泊証明書(ビザの延長に必要)を書いてくれと、つたない英語で受付と話していたら、隣から「日本の方ですか?」と声がかかる。うん。大阪弁イントネーションの英語だからすぐにバレますね。「おおっ、こんなところに日本人が!」と、10日ぶりの日本語での会話に嬉しくなる。聞けば彼女もビザの延長のために楽山に来たらしい。昨日手続きをして今日が受取りとのことなので、渡りに船と同行させてもらうことにする。いやぁ、親切に「あっち行って、こっち行って、ここで写真取って」と、全て教えてもらいました。 1時間とかからずに手続きは完了。ありがとう、親切な旅人よ。お昼ご飯をごちそうする。しかし、旅先で出会う日本人は若い女性が多いなぁ。今の世相を反映してるのかな。確かに昨今、女性の方が男性に比べて活発なような気がする。とまれ、女性連続4人は6%程度の確率ですから、単なる偶然でも十分起こりうることではあります。午後からは雨が降り出す。日本の梅雨の様相。しとしと雨が続くなか、時折、雨脚が強まる。止みそうにないので傘をさして川辺を散策。降り続く雨で岷江他河川は濁流と化し河岸の一部は水没してました。
@=
7時起床。大仏は既に見ているのだが、他に見どころがないので、とりあえず大仏地区を散策。拝観料は1500円。大仏は無視。中国の観光地(特に世界遺産)は俗化しすぎてもはや見苦しい。周辺の古い町並みや河岸の風景の方がよほど趣がある。昼前にビザを取得。ビザセンターで世界一周中の若者に出会う。 25才男。いいねぇ、見るからに旅行者といった風貌。すでに日本を出てから1年半が過ぎているらしい。足掛け3年の世界旅行だそうです。「今の旅行者は、女性のほうが多いの?」と聞いたら、「一緒くらいですかねぇ。僅かに男のほうが多いかな。」と言うことでした。ストイックな旅でテントと寝袋を担いでいたのには頭が下がる。もう、私には流石にマネできない。やっぱり、お昼をごちそうする。彼の話はとても面白い。午後は一旦成都に戻る。ホテル近くの四川大学とその周辺を散策。変貌を遂げる成都の中で時間が止まったかのようだ。昔の中国もまだまだ残っていました。そらまぁ、5年や6年で全く入れ替わってしまうことはないわなぁ。さてさて、成都には日本人が多い。夕食は4名で宴会となった。ビールが1瓶120円。散々飲み食いして全額でも2000円。一人だと高いが複数での飲食であればむしろ安いね。昨日今日と出会った方達が四川アムド地方(東チベット)の風景が綺麗と言っていたので、チベットエリアに寄り道することにする。鳥葬が間近で見れるらしい。これは行かねばなるまい。そもそも私が旅をするようになったきっかけは、川喜田二郎の「鳥葬の国」を読んだからだ。
@=
成都で3回目の両替。係員がちょっと待ってろと言う。奥に引っ込んで3分後、中国元を手渡されて円と交換。もはや、なんの書類もサインも必要ない。完全に係員のポケットマネーによる両替(闇両替)だな。まぁ、その方が私としても割のいいレートで交換できて得だし、係員も両替手数料が懐に入って得だし、win-winなんだけど、それでいいのか中国。
@=
法家の思想。中国による法の思想は性悪説の荀子に始まり、韓非において完成された。法と術による人民(臣下)の統制は、規則と罰則による組織運営であり、そこでは罪人の更生や、倫理の向上と言った概念は存在しない。法を複雑にし刑を厳しくすれば良いわけではないのである(むしろ法が意義を失う)。こんなことは2200年前の秦の時代に証明されていることだ。日本で言うならば、飲酒運転と喫煙への冷視なども度を越しているように思われる。
@=
昨日の宴会で私は酔っ払いであった。私以外は若い女性3人である。まぁ、楽しくて少々酔うのも仕方がなかろう。周りが若いと言うより私がジジィだな。アジアの安宿なんて若い人しか泊まらないもんなぁ。体感的には個人の旅行者は女性の方が多いと感じる。男はもっとハードでマニアックな旅をしていてあんまり表に出てこないのかな。さて、朝食も食べたので東チベットへと向かう。
@=
(2018-06-28) 7時起床。9時のバスで康定へ。四川盆地から山岳地帯に入ってからの景色は抜群だ。高原の雨を集めた川は上流域にかかわらず相当な水量で、飛沫を上げて流れ落ち、深いV時谷を作っている。康定の町は文明と文化の折衝地。チベット文化と中国文化が混ざり合っている。これより奥に入れば完全にチベット文化圏となろう。康定は標高2500m。この町に2泊して少し高地順化することにする。次の理塘の町は標高4000m。4700mの峠を超えなくてはならない。今回の旅で初めてドミトリーを利用する。うん、えらく味のある宿である。また、宿の管理人が日本好きで、ずっと日本の歌がかかっている。
@=
 チベット人はかっこいい。男も女も老いも若きもかっこいい。特に中年男がかっこいい。男前というわけではないのである。日に焼けた精悍な風貌がかっこいいのである。苦みばしった表情もイケている。おしゃれな服に見を包んでいるわけではないのである。地味でくすんだ服ながらその着こなしがかっこいいのである。ジャケットの袖を通さず肩で風を切って歩いている姿もよく見る。伊達男の街である。
@=
チベット人はかっこいい。男も女も老いも若きもかっこいい。特に中年男がかっこいい。男前というわけではないのである。日に焼けた精悍な風貌がかっこいいのである。苦みばしった表情もイケている。おしゃれな服に見を包んでいるわけではないのである。地味でくすんだ服ながらその着こなしがかっこいいのである。ジャケットの袖を通さず肩で風を切って歩いている姿もよく見る。伊達男の街である。
@=
(2018-06-29) 康定の街でゆっくり、、、とするはずもなく歩き回る。町の入口である川沿いの遊歩道から始めて、1時間も歩けばほぼ主要部は踏破。観光地は2ヶ所。南無寺とパオ(足偏に包)馬山。南無寺はこんなもんねと言う感じ。チベット寺院はもっと大規模なものを見てるし、明日理塘に入ればもっと趣のある寺があるだろう。山の方はロープウェイがあるんだけど当然歩く。結構きつい登り。やった着いたと思えば上は風景地区かなんかで入場料を1000円取られた。中国の観光名所って実に大したことないんだよなぁ。観光地区でないところこそ美しくて見る価値がある。お金がかかることより、むしろ、観光地になっていたことを残念に思う。悪くない景色ですけど、お金を取るほどかと言うと微妙。日本でも山に登ればいい景色はただで見れる。風景地区内の寺で昼食会が開かれていてそれに参加できたのは良かった。チベット僧のお経を聞いた後に参加者全員でランチ。タダ飯にありつけてしまった。しかもうまい。 15時に宿に帰還。楽山のビザセンターで出会った世界一周中の青年と再会。まぁ、旅程が似たコースであったので再会するかなとは思っていた。一緒に夕食。彼の旅行のスタイルはエネルギッシュで大変面白い。交通機関のないところにも突っ込む(ヒッチ出来なければ詰む)なんてできないよ。
@=
 風に靡くタルチョーの下、仏教徒による昼食会が行われた。バイキング形式でなかなかにうまかった。こういうところこそ写真が取りたいんだけど、あまり人にカメラを向けるのは失礼だし難しいところ。会食の写真は自粛。お坊さんは「写真とっても良いよ。」とのことでした。
@=
風に靡くタルチョーの下、仏教徒による昼食会が行われた。バイキング形式でなかなかにうまかった。こういうところこそ写真が取りたいんだけど、あまり人にカメラを向けるのは失礼だし難しいところ。会食の写真は自粛。お坊さんは「写真とっても良いよ。」とのことでした。
@=
 (2018-06-30) チベット高原は、広い、蒼い、鮮やか。理塘までの道のりは素晴らしいの一言。どこまでも続く大草原ではヤクが群れをなしている。そして、着いた理塘の街は富士山より高い標高4000mである。うん、軽い高山病だな。宿まで30分程度の道のりながら、息は上がるし、加えて頭痛がする。 15時にはチェックインできたものの、街の探索は諦め休養にあてることにする。
@=
(2018-06-30) チベット高原は、広い、蒼い、鮮やか。理塘までの道のりは素晴らしいの一言。どこまでも続く大草原ではヤクが群れをなしている。そして、着いた理塘の街は富士山より高い標高4000mである。うん、軽い高山病だな。宿まで30分程度の道のりながら、息は上がるし、加えて頭痛がする。 15時にはチェックインできたものの、街の探索は諦め休養にあてることにする。
@=
(2018-07-01) 6時半起床。頭痛と吐き気でろくに眠れた気がしない。高山病きついな。軽い運動をしたほうが回復が早いとのことなので、中心街を1時間ちょい散策。白塔寺ではチベット人が五体投地をしていた。折角なので高山病平癒を祈願してマニ車を回す。朝食を食べて宿に帰還。祈願の効果はなし。少しの階段で息が切れるし、頭痛と目眩がする。水を飲む、数秒息が止まるのでハァハァ。爪を切る、これだけのことでゼェゼェ。服を着替える、ズボンを脱ぐだけでフゥフゥ。シャワーを浴びた後など、完全に疲労困憊である。午後は鳥葬台を下見に行く。街から歩いて30分程度、草原のタルチョーはためく丘の麓にあった。明日ここで鳥葬が行われるはずだ。丘を100mほど登ってみたが、これが信じられないほどにしんどかった。すぐに息が切れるのは当然として、貧血(酸素不足)による目眩でフラフラする。周りの牧草地にはヤクしかいないし、鳥葬台近辺には野犬が数匹、少し離れてハゲワシも二匹いる。少し怖いぞ。貧血で意識を失ったら、野犬とハゲワシに襲われて、期せずして私も鳥葬だな。
@=
(2018-07-02) 5時半起床。 6時過ぎ、薄闇の中、歩いて鳥葬台へと向かう。禿鷲の饗宴は圧巻である。ものの5分で遺体は骨格となる。骨は砕かれ、腱や皮などの食べにくい部分は切り刻まれる。後には何も残らない。見事なものである。最初の鳥葬は喪主のお爺さんで80歳での大往生。その後の二件目も見た限り老人のようであった。鳥葬が一段落した後は食事らしく、二度、葬儀後にバター茶と麦こがしをご馳走してもらうことになった。宗教行事なので写真を取ることは控える。検索すれば鳥葬の画像や動画などいくらでも存在するであろう。次第だけ簡単に纏めておく。 1.僧による読経後、聖水による大地の清め。 2.清められた地に杭を打ち、杭と遺体の首を白い布で結ぶ。 3.遺体の解体(うつ伏せで手足、尻、背中、肩の肉を開いていく)。 4.禿鷲タイム。 5.骨(頭蓋骨も含む)を砕き、骨肉ミンチにする。 6.二度目の禿鷲タイム。 7.関係者による食事(死者との饗応との意味があるのだろうか)。これは相当に手間のかかる葬儀である。山に捨てて勝手に禿鷲が食うのとは訳が違う。禿鷲が食べやすいように、きちんと解体し、骨まで砕いてやるのである。なんとしても最後まで残さず食べてもらいたいとの意思を感じる。 5mほどの至近距離で見ていたが、不思議と気色悪さは感じなかった。元々、ホラー系は苦手なので、見ていられるか不安であったが、血濡れの髑髏が転がるさまや、啄まれて跳ね飛ぶ肉片はむしろ滑稽ですらあった。死者を蔑む訳ではなく非日常が生み出すそういう空間であったとしか言えない。さて、理塘での目的は果たした。少し標高を下げることにする。本当はもっとこの街を探索したいのだが、頭痛と目眩でこれ以上の滞在は不可能だ。
@=
火葬では煙となって魂は天へと昇る。鳥葬ではハゲワシに食われて魂は天へと昇る。思想的には同じで、鳥葬のことを現地では天葬と言う。
@=
葬儀中、関係者は終始にこやかである。「もっと近くで見ろよ!」と声をかけてくれる。悲しみの場はおそらく他にあるのであろう。なお、鳥葬に参加できるのは男だけのようだ。また、遺族も参加不可で遠くから見ているだけのようだ。
@=
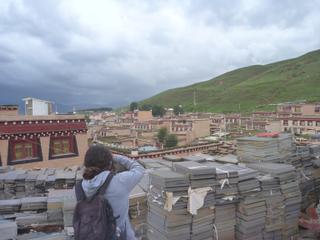 夕方、三度出会った世界一周中の青年と街の散策。理塘はチベットを身近に感じられる気持ちのいい街です。そして、男たちの伊達っぷりが半端なくかっこいいいです。「写真取らせて。」「それはやめてくれ。」伊達男は簡単にはファインダーに収まってくれないのでした。
@=
夕方、三度出会った世界一周中の青年と街の散策。理塘はチベットを身近に感じられる気持ちのいい街です。そして、男たちの伊達っぷりが半端なくかっこいいいです。「写真取らせて。」「それはやめてくれ。」伊達男は簡単にはファインダーに収まってくれないのでした。
@=
ロン毛三つ編み、小粋な帽子、洒落たアクセの、伊達男。日に焼けた肌といい、チベット男はキャプテン「ジャック・スパロウ」に似ている。
@=
 (2018-07-03) 朝から7時間半のバスの旅。道中は終始標高3000m以上。風景は申し分ないのだが、大絶景も食傷気味。道は荒れていて、スリリングで楽しい。そもそも、道を作るのに無理がある山岳地帯だと思う。着いた甘孜(ガンゼ)の標高は3300m。目眩はしないし、息切れや頭痛もほぼ解消。たった700mの差でここまで変わるのかと驚く。最近の中国では公安の取締が厳しく、定員超過やシートベルト未着用が許されないのだが、チベットではあまり守られていないようだ。バスは私以外は全員チベット人。とうとう中国人(漢人)すらいなくなった。男も女もチベット人はおしゃれです(都会的なハイセンスとは無縁ですが)。
@=
(2018-07-03) 朝から7時間半のバスの旅。道中は終始標高3000m以上。風景は申し分ないのだが、大絶景も食傷気味。道は荒れていて、スリリングで楽しい。そもそも、道を作るのに無理がある山岳地帯だと思う。着いた甘孜(ガンゼ)の標高は3300m。目眩はしないし、息切れや頭痛もほぼ解消。たった700mの差でここまで変わるのかと驚く。最近の中国では公安の取締が厳しく、定員超過やシートベルト未着用が許されないのだが、チベットではあまり守られていないようだ。バスは私以外は全員チベット人。とうとう中国人(漢人)すらいなくなった。男も女もチベット人はおしゃれです(都会的なハイセンスとは無縁ですが)。
@=
(2018-07-04) 熟睡。気持ちの良い目覚め。頭痛がないって素晴らしい。早朝、街のゴンパに参拝する。ゴンパがあるのは老街で、街全体が迷路のようである。何度も道を間違える。老街は丘の上にあり、その最上部がゴンパであるから、上りの道を選択さえしてれば着くだろうと思っていたが、むしろそれは罠で、早い段階から正しい道を選択しておかないとたどり着けない。昔はゴンパが、そして街全体が要塞だったのであろう。僧による読経は12時からであったようで、本堂には鍵がかかっていたが、「見たいなぁ」オーラを出しながら覗き込んでいると、管長らしき人が親切にも開けてくれた上に、若僧を二人つけて内部を案内してくれた。ありがとう。私一人のためにガイドまでしてくれて感謝です。本尊は釈迦牟尼仏で、龍樹くらいまではわかるけど、後は知らない仏ばかりであった。午後は宿を変えるために荷物をまとめなおして引っ越し。ここガンゼには温泉がある。しかも、日本人好みの硫黄泉である。これは温泉宿に泊まらねばなるまい。宿の女将は中国語も話せないチベタン(Tibetan)。子供は学校で習っているらしく子供と交渉。とはいえ中国語もほぼわからないので殆どが身振り手振り。小学生の「OK」の声で宿泊成立。宿帳も何もなくお金だけ払って終わり。ふっ、子供と真剣にビジネスで分かり合えたぜ。早速入浴。ほぼ一月ぶりの風呂である。気持ちいいにもほどがあるわ。風呂上がりは町外れを散策。明日は休養日に当てようと思う。
@=
(2018-07-05) 今日は休養日。外出は食事と近所の散歩くらいで済ませる。ここ数日では恨めしいくらいのいい天気なのだが、能動的な活動意欲が湧き上がらない。まぁ、こういう日はネット閲覧(停電でよく切れるけど)か読書だ。ついでに今まで書ききれなかった考察でも書こう。ちなみに本日、目覚ましに全く気づかず、6時半のバスを逃したという事情もあります、、、。
@=
老街について。老街は日本で言うならば戦前からの明治・大正エリア。旧市街は戦後に出来た昭和エリア。新市街は平成に入ってからの再開発エリアと言った感じです。大体は、老街は土壁、旧市街はレンガ造り、新市街は鉄筋コンクリートで出来ています。
@=
住宿について。中国には「住宿」と呼ばれる宿泊施設が至る所にある。ところが、これは外人には利用できない。中国では政府が許可した(ある程度)高級な宿泊施設にしか外人は泊まれないのだ。そして、チェックインのたびにパスポートの提出を求められる。ビザのコピーが控えられて、パスポート情報がPCに入力される。誰がどこに泊まったかは全て中央に把握されているのだ。この建前は結構厳密に守られているが、やはり、地方ではゆるい面があるようだ。今、宿泊している温泉宿も「住宿」であるが、パスポートの提出はおろか、宿帳の記入も必要なかった。お金を払っただけである。レシートも当然ない。公的にはこの二日間、私は無宿ということになるので、検問(やたらしょっちゅうある)などで問い詰められたら、「僕外人だから、何言ってるかわかんな〜い」と、しらばっくれなければならない。まぁ、地方では検問もいい加減なので大丈夫ではあろう。管理社会なのにいい感じに融通を効かせてくれるのが中国の田舎の旅である。
@=
チベットのゴミについて。先にチベットでは結構ゴミが落ちていると書いたが、愛嬌あるチベタンのためにいくらか擁護しておきたいと思う。もともとゴミをポイポイするのは、長江以北の漢人の文化であると思われる。チベットやウィグル、その他少数民族の村は、上海や西安といった街に比べて清潔であった。しかしながら、少数民族は漢族に支配される側である。そして、流入した漢族はよその土地でも平気でポイポイする。抗えない彼らはいつしか自分たちもポイポイするようになってしまった。一時期、勘違いした中国人(自分たちが標準だと思っている)が、日本に観光した際にも同様に行動し、そのマナーの悪さはニュースになっていた。日本人はこれを問題視できるが、被支配者であるチベット人は受け入れるしかない。今、中国は国を上げて「マナーの向上は国民の義務である」と言わんばかりに、国家権力による強制的な街の美化、国民意識の改革を行っている。そのやり方に賛同はしないが、結果としてうまく行っているのは事実であり、逆に地方(少数民族)には、その強制力が及んでいない。彼らが自然と元の文化を取り戻してくれればと思うがそれは難しいだろう。
@=
ラオスのゴミについて。実は今ラオスで同じことが起こっている。あまり触れなかったが、ラオスは結構ゴミが多いのである。 20年前、そのようなことはなかった。ラオスは今、中国による経済支配、属国化の運命にある。中国資本によって国土の開発が行われ、漢人が進出し街は中国語で溢れている。そして彼ら漢人はラオスの地で平気でポイポイする。国家権力による強制力はラオスにまでは及ばない。日本人は彼らのマナーを問題視できたが、文化力、経済力に差があるラオス人は問題視できず、彼らの行動を受け入れ、いつしか自分たちもポイポイするようになってしまった。 10年後、マナーの良くなった漢人がラオスを訪れたとき、「ラオス人はなんとマナーが悪いのだろう」と嘆息するであろう。皮肉なものである。
@=
(2018-07-05#2) 昨日は日記を書き終えてから波乱があった。午後9時20分頃、宿のねぇちゃんが、いきなりドアを開けて入ってきて、なんかよくわからないが叫んでいる。時折、「公安」との単語が聞き取れるので、あら、やっちゃったかと開き直る。直前に、「住宿について」なる題で、無許可の宿に泊まることのリスクを書いたばかりというのに、なんとまぁ、タイミングのいいことだ。「出ろ!出ろ!」と言っているようなので、とりあえず表に出ると、案の定、警察3人に取り囲まれる。面倒だなぁ、この時間に追い出されたら今からの宿探しはしんどい。「パスポートを出せ」と言っているみたいなので素直に提出。早速、笑顔で「僕外人だから、何言ってるかわかんな〜い」作戦だ。(作戦云々の前に実際に何を言ってるかわからない。)まぁ、あれだな。多分、意識高い系の誰かが警察に通報したのであろう。どこにでも権力に媚びてポイントをあげようとするヤツがいるものだし。公安はパスポートの写真を取り、何やら相談していたが、特になんの咎めも受けなかった。部屋内にまで踏み込んでこなかったし、紳士的な対応である。「部屋に戻って寝てていいぞ」みたいな感じだったので、パスポートを受取り部屋に戻る。うん。警察も面倒だから見ないフリをしてくれたのかもしれないな。もしかすると、夜遅くに追い出すのは可愛そうだと思っての見ないフリかもしれない。いずれにせよ助かった。しかし、この旅はフラグが立ちまくりだ。コンパスが役に立つと書けば、「コンパス」をなくすし、田舎じゃ規制がゆるいから住宿に泊まれると書けば、「公安に通報」される。狙ったかのようなフラグの立て方とその回収である。
@=
 (2018-07-06) 6時半のバスで康定に戻る。今日、明日の二日をかけて一旦成都に戻る。康定に戻ったのは16時半。丸10時間のバスで疲れる。宿に出向いてみると、成都で飲んだ女子二人と再会。「ええっ、なんでまだ康定にいるの?」と驚くが、聞けば二人とも足止めを食らって理塘に行けずらしい。現在、理塘周辺で軍事演習が行われているらしく外国人立入禁止になったそうだ。私が鳥葬を見れたのは結構ギリギリのタイミングであったようだ。とりあえず一緒に食事。なんかみんな同じようなコースを取るから再会が多いなぁ。世界一周中の青年とはあと2回くらいは会いそうだ。なお、バスの旅は相変わらず3000m超の絶景なのだがさすがにもう飽きた。写真はガンゼゴンパからの一枚。老街の、青空高く、鳥が飛ぶ。
@=
(2018-07-06) 6時半のバスで康定に戻る。今日、明日の二日をかけて一旦成都に戻る。康定に戻ったのは16時半。丸10時間のバスで疲れる。宿に出向いてみると、成都で飲んだ女子二人と再会。「ええっ、なんでまだ康定にいるの?」と驚くが、聞けば二人とも足止めを食らって理塘に行けずらしい。現在、理塘周辺で軍事演習が行われているらしく外国人立入禁止になったそうだ。私が鳥葬を見れたのは結構ギリギリのタイミングであったようだ。とりあえず一緒に食事。なんかみんな同じようなコースを取るから再会が多いなぁ。世界一周中の青年とはあと2回くらいは会いそうだ。なお、バスの旅は相変わらず3000m超の絶景なのだがさすがにもう飽きた。写真はガンゼゴンパからの一枚。老街の、青空高く、鳥が飛ぶ。
@=
 (2018-07-07) 今日は七夕だったんだね。残念ながら成都の天気は良くない。 7時起床。9時のバスで成都に戻る。昨日は10時間かかったのと同じ距離を今日は5時間。成都と康定の間は半分くらいまでは高速道路が完成している。来るときはこの景色でも感動したものだが、もっと凄いところに居たため同じ景色がつまらなく感じる。半分くらいは居眠りしてしまった。感動はどんどん鈍感になるな。まぁ、いいことではある。大人は子供みたいになんにでも驚くわけにはいかないのだ。なお、チベット人も車に弱い。それでいて道はカーブの連続だ。後ろの席のおばちゃんが出発10分後にはゲロっていたが、 5時間は地獄の苦しみだったであろう。ゲロゲロを聞き続ける私も地獄のとまでは言わないが、いい加減聞き苦しかった。においも漂ってくるし、、、。さて、戻ったはいいが成都に要はない。早速、明日には北へと向かう。チベット(四川省西部)への寄り道はおしまい。、、、というわけには行かない。これから北に向かうが、実は四川省北部もチベットエリアなのだ。なら、なぜ成都に戻ったかと言うとお金がなくなったから。日本円が地方では両替できないのである(ドルとユーロのみ可)。 20年前あれだけ強くてアジアならどこでも通用した円が、お隣の中国で両替に困るほどになっているとは思わなかった。というわけで、この旅3度目の成都である。写真は成都で人気のラーメン屋さん、、、ではなく、地下鉄駅。乗り換えただけですので本当にラーメン屋があるかどうかは不明。いや、成都ってただの都会だし。ネタくらいにしかカメラが向かない。
@=
(2018-07-07) 今日は七夕だったんだね。残念ながら成都の天気は良くない。 7時起床。9時のバスで成都に戻る。昨日は10時間かかったのと同じ距離を今日は5時間。成都と康定の間は半分くらいまでは高速道路が完成している。来るときはこの景色でも感動したものだが、もっと凄いところに居たため同じ景色がつまらなく感じる。半分くらいは居眠りしてしまった。感動はどんどん鈍感になるな。まぁ、いいことではある。大人は子供みたいになんにでも驚くわけにはいかないのだ。なお、チベット人も車に弱い。それでいて道はカーブの連続だ。後ろの席のおばちゃんが出発10分後にはゲロっていたが、 5時間は地獄の苦しみだったであろう。ゲロゲロを聞き続ける私も地獄のとまでは言わないが、いい加減聞き苦しかった。においも漂ってくるし、、、。さて、戻ったはいいが成都に要はない。早速、明日には北へと向かう。チベット(四川省西部)への寄り道はおしまい。、、、というわけには行かない。これから北に向かうが、実は四川省北部もチベットエリアなのだ。なら、なぜ成都に戻ったかと言うとお金がなくなったから。日本円が地方では両替できないのである(ドルとユーロのみ可)。 20年前あれだけ強くてアジアならどこでも通用した円が、お隣の中国で両替に困るほどになっているとは思わなかった。というわけで、この旅3度目の成都である。写真は成都で人気のラーメン屋さん、、、ではなく、地下鉄駅。乗り換えただけですので本当にラーメン屋があるかどうかは不明。いや、成都ってただの都会だし。ネタくらいにしかカメラが向かない。
@=
 (2018-07-08) 5時起床。北を目指す。四川省最北の若爾蓋(ゾルゲ)に向かうのだが、バスで9時間半かかるらしいので、まずは手前の松藩(バスで6時間半)まで行く。しかし、ゾルゲも松藩も聞いたこともないけど、ガイドブックには載っているのだろうか。バスは成都西北部の茶店子バスターミナル(写真)から出発。いやあ、いいなぁ。ここは昔ながらのいい感じに無知で無教養な人民が集まっている。なんだかよくわからない大量の荷物を持つ客に、ペッペッしているドライバー。大声で喧嘩してるかのような服務員たち。そうそうこれだよ中国、と呆れながらも嬉しくなる。そして、北部への道もまた険しい。岷江が削った大地は急峻な渓谷となっている。三国時代、劉焉や劉禅が引きこもったのもよくわかる。こりゃ、攻め込めませんわ。さて、着いた松藩はというと、結構観光地化されている。しかも、西洋人をたくさん見る。なんで、こんな山奥でと思ったのだが、世界遺産である「黄龍」と「九寨溝」が近く、両者の観光拠点となっているようだ。ほう、全然知らなかったよ。ってことはガイドブックにも載ってるんだろうね。ちなみに私はと言うと、折角の世界遺産だが訪れる気は全くない。行ったら後悔するに決まっている。中国の世界遺産は誠にがっかり名所だ。雲南省麗江(これも世界遺産)でのやるせなさはトラウマ級だ。日本でも、北海道や沖縄、銀座や道頓堀は中国人観光客だらけだが、中国では、その何十倍もの人間が国内旅行をしている。年間の観光客が数百万人なんてのはザラで、一日に一万人が訪れるわけだから、それはそれは俗化した醜悪な名所へと変貌してしまう。避けるのが吉です。松藩自体も中華テーマパークっぽくてあまり面白みがないので明日にはゾルゲに向かう。少し興味をひいたのは回族(ウィグル族)が思いの外多くいた事。男性のウィグル帽と、女性の頭スカーフですぐにわかる。エリア的に本来いるわけがないので、多分、文革時に強制移住で連れてこられたのでしょう。もともと、羌と呼ばれる人がいて、チベット人もいる。そこに、漢族に回族だから、まぁ、いろんな文化がモザイクになっていて、町中でも色んな料理が食べられます。
@=
(2018-07-08) 5時起床。北を目指す。四川省最北の若爾蓋(ゾルゲ)に向かうのだが、バスで9時間半かかるらしいので、まずは手前の松藩(バスで6時間半)まで行く。しかし、ゾルゲも松藩も聞いたこともないけど、ガイドブックには載っているのだろうか。バスは成都西北部の茶店子バスターミナル(写真)から出発。いやあ、いいなぁ。ここは昔ながらのいい感じに無知で無教養な人民が集まっている。なんだかよくわからない大量の荷物を持つ客に、ペッペッしているドライバー。大声で喧嘩してるかのような服務員たち。そうそうこれだよ中国、と呆れながらも嬉しくなる。そして、北部への道もまた険しい。岷江が削った大地は急峻な渓谷となっている。三国時代、劉焉や劉禅が引きこもったのもよくわかる。こりゃ、攻め込めませんわ。さて、着いた松藩はというと、結構観光地化されている。しかも、西洋人をたくさん見る。なんで、こんな山奥でと思ったのだが、世界遺産である「黄龍」と「九寨溝」が近く、両者の観光拠点となっているようだ。ほう、全然知らなかったよ。ってことはガイドブックにも載ってるんだろうね。ちなみに私はと言うと、折角の世界遺産だが訪れる気は全くない。行ったら後悔するに決まっている。中国の世界遺産は誠にがっかり名所だ。雲南省麗江(これも世界遺産)でのやるせなさはトラウマ級だ。日本でも、北海道や沖縄、銀座や道頓堀は中国人観光客だらけだが、中国では、その何十倍もの人間が国内旅行をしている。年間の観光客が数百万人なんてのはザラで、一日に一万人が訪れるわけだから、それはそれは俗化した醜悪な名所へと変貌してしまう。避けるのが吉です。松藩自体も中華テーマパークっぽくてあまり面白みがないので明日にはゾルゲに向かう。少し興味をひいたのは回族(ウィグル族)が思いの外多くいた事。男性のウィグル帽と、女性の頭スカーフですぐにわかる。エリア的に本来いるわけがないので、多分、文革時に強制移住で連れてこられたのでしょう。もともと、羌と呼ばれる人がいて、チベット人もいる。そこに、漢族に回族だから、まぁ、いろんな文化がモザイクになっていて、町中でも色んな料理が食べられます。
@=
(2018-07-09) 6時起床。西の丘に登ろうと思っていたが、天気が悪いので取りやめ。 8時半にチェックアウトし、軽く朝の街を散策した後、10時のバスでゾルゲに向かう。ゾルゲには13時半着、14時半の朗木寺行きのバスに接続している。同じバスに乗り合わせたロシア人の旅行者に、「ゾルゲには何もない。一緒に朗木寺まで行こうぜ。」と誘われたため、ゾルゲでは昼食を食べただけで再度バスに乗り込む。ゾルゲから朗木寺までの道は広大な大草原と湿地帯を横切っている。標高3500mの高原で地平線が見れるなんてちょっと信じられない光景だ。そこでは何万頭というヤクが放し飼いにされている。観光業も盛んなようで乗馬と遊牧テントの宿泊体験ができるようだ。道自体は工事中部分が多く、多くの場所で片側一車線通行となり、なんども対向車を待たされたが、おかげで自然を満喫できたのは良かった。数少ない再び来たいと思わせられる景色であった。朗木寺の町は中央を流れる川が四川省と甘粛省の省境となっている。一応、本日、四川省を脱出できました。宿は四川省側なのでまた戻ってきましたが、、、。最後に、件のロシア人と一緒に夕食に行ったのだが、「米食えねぇ。」「麺食えねぇ。」「辛いの食えねぇ。」だそうで、「ハンバーガー屋はないのか?」って、こんな田舎にねぇよ。餃子(中国はスープ餃子)なら食べられるとのことだったのだが、スープを全部捨てて(ええっ、スープ餃子なのに)、持参のバターとマヨネーズとコショウをかけて食べてました。えーと、元の味が何もなくなっていると思います。明日の朝食の約束もしたけど、いったい何を食べればいいのだろうか。
@=
 (2018-07-10) 6時前起床。目覚ましは7時。大抵目覚ましが鳴る前に起きている。今日は朝から雨。20時になってやっとやんだが、厚い雲は未だ去らず。食事以外は宿に引きこもる。今までも雨が多かったし、予報では今後一週間ずっと雨である。この季節はそうなのかと聞いてみたが、こんなことは珍しいそうだ。チベット人をしてそういうのだから、運が悪いことに今年は多雨なのであろう。宿で今後の旅程やバスの運行状況についてスタッフに質問していると、日本語を話せるチベット人が出現。詳細な交通事情を聞けてたいへん助かる。何でも彼自身、夏場はゲストハウスを経営しているらしいが、今日は暇なので私の宿泊する宿に遊びに来たらしい。聞けば、彼の奥さんは日本人で冬は5歳の子供と東京で生活しているとのこと。この3年間、日本の学校に通い、日本語を覚えて、今は宿主兼ガイドであるそうだ。うん。どういうこと?ふむふむ。奥さんは35歳(本人は29歳)で結婚当初の会話はつたない中国語であったらしい。彼が日本語を覚えてやっと最近夫婦の会話が日本語になったと言うことである。ほうほう。見えてきたぞ。何度も書いたがチベット男はなかなかに格好がいいのである。男の私が見てもそう思う。奥さんは30歳前にして、旅で知り合ったチベットの好青年を捕まえたのであろう。やるな、日本女性。イキがいいぞ。(なお、勝手な憶測です。)彼の宿には一昨日、日本人が泊まっていたそうだが、やはり女性だったらしい。今の御時世、男は保守的に、女は前衛的にならざるを得ないということだろうか。写真は夜になってやっと雨の上がった朗木寺のメインストリート。素朴な山間の村なんだけど、やっぱネオンなんだなぁ。中国化、イコール、電飾化である。最後に朝食について。なんと、ハンバーガー屋がありました。これでロシア人も満足、、、は、しなかった。フィッシュバーガーの魚が古いとのこと。魚の良し悪しが分かるとは結構グルメですな。でも、ここ、標高3400mの高地なんですけど、、、。魚を選んだ時点で間違ってます。
@=
(2018-07-10) 6時前起床。目覚ましは7時。大抵目覚ましが鳴る前に起きている。今日は朝から雨。20時になってやっとやんだが、厚い雲は未だ去らず。食事以外は宿に引きこもる。今までも雨が多かったし、予報では今後一週間ずっと雨である。この季節はそうなのかと聞いてみたが、こんなことは珍しいそうだ。チベット人をしてそういうのだから、運が悪いことに今年は多雨なのであろう。宿で今後の旅程やバスの運行状況についてスタッフに質問していると、日本語を話せるチベット人が出現。詳細な交通事情を聞けてたいへん助かる。何でも彼自身、夏場はゲストハウスを経営しているらしいが、今日は暇なので私の宿泊する宿に遊びに来たらしい。聞けば、彼の奥さんは日本人で冬は5歳の子供と東京で生活しているとのこと。この3年間、日本の学校に通い、日本語を覚えて、今は宿主兼ガイドであるそうだ。うん。どういうこと?ふむふむ。奥さんは35歳(本人は29歳)で結婚当初の会話はつたない中国語であったらしい。彼が日本語を覚えてやっと最近夫婦の会話が日本語になったと言うことである。ほうほう。見えてきたぞ。何度も書いたがチベット男はなかなかに格好がいいのである。男の私が見てもそう思う。奥さんは30歳前にして、旅で知り合ったチベットの好青年を捕まえたのであろう。やるな、日本女性。イキがいいぞ。(なお、勝手な憶測です。)彼の宿には一昨日、日本人が泊まっていたそうだが、やはり女性だったらしい。今の御時世、男は保守的に、女は前衛的にならざるを得ないということだろうか。写真は夜になってやっと雨の上がった朗木寺のメインストリート。素朴な山間の村なんだけど、やっぱネオンなんだなぁ。中国化、イコール、電飾化である。最後に朝食について。なんと、ハンバーガー屋がありました。これでロシア人も満足、、、は、しなかった。フィッシュバーガーの魚が古いとのこと。魚の良し悪しが分かるとは結構グルメですな。でも、ここ、標高3400mの高地なんですけど、、、。魚を選んだ時点で間違ってます。
@=
 (2018-07-11) 7時起床。昨日の雨を吹き飛ばす気持ちのいい晴れ。早速街を散策。山間の田舎町で気持ちのいい朝である。1時間で見終わる。街の向こうに見えるあの山に登りたい。よし向かうことにする。結構有名なゴンパのある風景地区と言うことで入場料30元を取られるが、ゴンパにも風景地区にもそれほど興味はない。行きたいのはその先の山だ。ゴンパはお座なりに見学。丘に登って街を一望した後は、風景地区の奥を目指す。カルスト地形の深い渓谷に到着。渓谷の入り口に引き馬が用意されていた。100元。ほうほう。普通の観光客はここで馬に乗って渓谷に入っていくようだ。「馬に乗れ。乗れ!」と客引きが言う。この先は危ないぞなどとも言っているようだ。引き馬ということは、馬を引くチベット人は歩いているということだ。私も歩くことにする。うん、こりゃたしかに大変だ。滝はないものの沢登りと同じである。スポーツサンダルに靴下。冷たい水に濡れながら登る。足が凍えそうである。 30分ばかりして、カルスト地形に囲まれた小さな草原に到着。いや、これは素晴らしいですわ。絶壁に囲まれた小さな草原。青い空。一日中眺めていても飽きないだろう。馬に乗ってきた観光客たちも思い思いのポーズを取って写真を取っている。引き馬サービスもここまでのようで観光客も写真を取った後は引き返していた。ただし、道自体は続いているようだ。踏み跡を追うことができる。ならば、行けるところまで行かねばなるまい。そしてこの先はさらに美しい景色であった。都合、3時間ほど山中をさまよっていたが、ここにはまた何度も来ることになると思う。夕方、宿に戻ると、世界一周青年と再会。早速明日も山に行く約束をする。今日は危険として引き返したところにも二人でなら行けるはずだ。楽しみである。写真はメインストリート。建物の間隙から見えるあの山に登りたい。そう思わせられた。
@=
(2018-07-11) 7時起床。昨日の雨を吹き飛ばす気持ちのいい晴れ。早速街を散策。山間の田舎町で気持ちのいい朝である。1時間で見終わる。街の向こうに見えるあの山に登りたい。よし向かうことにする。結構有名なゴンパのある風景地区と言うことで入場料30元を取られるが、ゴンパにも風景地区にもそれほど興味はない。行きたいのはその先の山だ。ゴンパはお座なりに見学。丘に登って街を一望した後は、風景地区の奥を目指す。カルスト地形の深い渓谷に到着。渓谷の入り口に引き馬が用意されていた。100元。ほうほう。普通の観光客はここで馬に乗って渓谷に入っていくようだ。「馬に乗れ。乗れ!」と客引きが言う。この先は危ないぞなどとも言っているようだ。引き馬ということは、馬を引くチベット人は歩いているということだ。私も歩くことにする。うん、こりゃたしかに大変だ。滝はないものの沢登りと同じである。スポーツサンダルに靴下。冷たい水に濡れながら登る。足が凍えそうである。 30分ばかりして、カルスト地形に囲まれた小さな草原に到着。いや、これは素晴らしいですわ。絶壁に囲まれた小さな草原。青い空。一日中眺めていても飽きないだろう。馬に乗ってきた観光客たちも思い思いのポーズを取って写真を取っている。引き馬サービスもここまでのようで観光客も写真を取った後は引き返していた。ただし、道自体は続いているようだ。踏み跡を追うことができる。ならば、行けるところまで行かねばなるまい。そしてこの先はさらに美しい景色であった。都合、3時間ほど山中をさまよっていたが、ここにはまた何度も来ることになると思う。夕方、宿に戻ると、世界一周青年と再会。早速明日も山に行く約束をする。今日は危険として引き返したところにも二人でなら行けるはずだ。楽しみである。写真はメインストリート。建物の間隙から見えるあの山に登りたい。そう思わせられた。
@=
 ここで谷は再び2つに別れる。正面の尾根の左右である。行きたい、が、これ以上進むのは危険と判断。道もわからないし、装備もない。誰もいないし。何か起こったときに対処のしようがない。尾根の中腹まで登って引き返そうと決意する。
@=
ここで谷は再び2つに別れる。正面の尾根の左右である。行きたい、が、これ以上進むのは危険と判断。道もわからないし、装備もない。誰もいないし。何か起こったときに対処のしようがない。尾根の中腹まで登って引き返そうと決意する。
@=
 尾根に登ってみると、谷の向こう、奥の山の手前に遊牧民のテントを発見。(写真は縮小しているので見えませんね。)これは人がいる。そこまでは行くことにする。水も切れたけどなんとかなるだろう。着いてしまえば、お茶くらいは調達できるはずだ。
@=
尾根に登ってみると、谷の向こう、奥の山の手前に遊牧民のテントを発見。(写真は縮小しているので見えませんね。)これは人がいる。そこまでは行くことにする。水も切れたけどなんとかなるだろう。着いてしまえば、お茶くらいは調達できるはずだ。
@=
 誰も中国語がわからない。チベット語しか喋れない人ばかり。唯一、このテントにいた子供とのみ筆談が可能であった。 14歳の女の子。パット見、小学生にしか見えない。 5人家族でここが彼らの夏場のマイホーム。お父さんは山に羊の放牧。お母さんとお姉さんは麓に山菜採り。お兄さんはわからない(まぁ、チベットの伊達男のことだ遊んでんだろう)とのことであった。以上、山行記録でした。帰りも色々あったけどカット。
@=
誰も中国語がわからない。チベット語しか喋れない人ばかり。唯一、このテントにいた子供とのみ筆談が可能であった。 14歳の女の子。パット見、小学生にしか見えない。 5人家族でここが彼らの夏場のマイホーム。お父さんは山に羊の放牧。お母さんとお姉さんは麓に山菜採り。お兄さんはわからない(まぁ、チベットの伊達男のことだ遊んでんだろう)とのことであった。以上、山行記録でした。帰りも色々あったけどカット。
@=
 (2018-07-12) 曇り。7時半に世界一周青年(今後、Aと呼ぶ)と待ち合わせ。朝食後、8時過ぎに山に入る。昨日より水が冷たい。足が凍りそうだ。昨日の下見があるので、さまようことなくテント村に到着。昨日、村で会話した女の子のテントに立ち寄る。昨日の帰り道に山菜採りをしていたお母さんとも顔見知りになっておいたので、テントに迎え入れてくれた。チベットの伝統的な食事を振る舞われる。バターをお湯で溶かし、きなこ(に似たもの)と砂糖を混ぜてペースト状にしたもの。悪くはない。それなりに美味しいと思える食事だ。非常にカロリーが高そうで山登りを控えた身にはありがたい。さて、この村は2つの谷の合流地点に存在する。「どっちの谷のほうが美しい?」と聞いたつもりで、「左の谷のほうがきれいだよ。」と言っているような気がした。左の谷を進むことにする。谷は家畜の通り道になっているのだろうか。獣道のようなそもそも道でもないような道が幾筋も走っている。また、あたりには動物の糞が散見される。谷の正面の岩山を目標にとりあえず高い方を目指すがすぐに息が切れる。テント村の時点で標高は3600mくらいであろう。 30分ほど登るとヤクを発見。これは遊牧をしているということだ。上には人がいる可能性が高いことから少し安堵する。ただし、軽い頭痛が始まる。私は高山病の再来を危惧するが、Aは元気なものだ。遊牧されているヤクや馬の好奇の視線を受けながら、しばらく登ると「オーイ」と人の声がする。間違いない。人はいる。しかしながら声は山で反響し、どこにいるのかはわからない。こちらも「ヤッホー」と返事をしておく。多数のヤクに囲まれて、息を切らしながら登りつづける。何度めかの「オーイ」との声。いた。谷のほぼ最上部。岩山の上に人影を発見。目標が出来た。心の中でそこをゴールとする。それから1時間ほどかかったであろうか。ようやく到着。1分間の呼吸数が半端ない。心臓はフル回転だ。AのGPSによると標高4100m。そして、ご褒美となる景色は圧巻であった。この景色を日本人で見たのはおそらく二人だけのはずだ。
@=
(2018-07-12) 曇り。7時半に世界一周青年(今後、Aと呼ぶ)と待ち合わせ。朝食後、8時過ぎに山に入る。昨日より水が冷たい。足が凍りそうだ。昨日の下見があるので、さまようことなくテント村に到着。昨日、村で会話した女の子のテントに立ち寄る。昨日の帰り道に山菜採りをしていたお母さんとも顔見知りになっておいたので、テントに迎え入れてくれた。チベットの伝統的な食事を振る舞われる。バターをお湯で溶かし、きなこ(に似たもの)と砂糖を混ぜてペースト状にしたもの。悪くはない。それなりに美味しいと思える食事だ。非常にカロリーが高そうで山登りを控えた身にはありがたい。さて、この村は2つの谷の合流地点に存在する。「どっちの谷のほうが美しい?」と聞いたつもりで、「左の谷のほうがきれいだよ。」と言っているような気がした。左の谷を進むことにする。谷は家畜の通り道になっているのだろうか。獣道のようなそもそも道でもないような道が幾筋も走っている。また、あたりには動物の糞が散見される。谷の正面の岩山を目標にとりあえず高い方を目指すがすぐに息が切れる。テント村の時点で標高は3600mくらいであろう。 30分ほど登るとヤクを発見。これは遊牧をしているということだ。上には人がいる可能性が高いことから少し安堵する。ただし、軽い頭痛が始まる。私は高山病の再来を危惧するが、Aは元気なものだ。遊牧されているヤクや馬の好奇の視線を受けながら、しばらく登ると「オーイ」と人の声がする。間違いない。人はいる。しかしながら声は山で反響し、どこにいるのかはわからない。こちらも「ヤッホー」と返事をしておく。多数のヤクに囲まれて、息を切らしながら登りつづける。何度めかの「オーイ」との声。いた。谷のほぼ最上部。岩山の上に人影を発見。目標が出来た。心の中でそこをゴールとする。それから1時間ほどかかったであろうか。ようやく到着。1分間の呼吸数が半端ない。心臓はフル回転だ。AのGPSによると標高4100m。そして、ご褒美となる景色は圧巻であった。この景色を日本人で見たのはおそらく二人だけのはずだ。
@=
 テント村にて食事をいただく。高カロリーな一品で登山前に体力をつける。なかなか可愛らしい姉妹でした。お父さんは山で遊牧。お母さんとお姉さんは午後は山菜採り。お兄さんはわからない(まぁ、チベットの伊達男のことだ今日もどこかで遊んでんだろう)とのことであった。
@=
テント村にて食事をいただく。高カロリーな一品で登山前に体力をつける。なかなか可愛らしい姉妹でした。お父さんは山で遊牧。お母さんとお姉さんは午後は山菜採り。お兄さんはわからない(まぁ、チベットの伊達男のことだ今日もどこかで遊んでんだろう)とのことであった。
@=
 (2018-07-13) 5時半起床。 6時半のバスで夏河に向かう。今日からしばらくAと同行動。ウルムチまでの旅程は大体似たようなもの。しばらくはついたり離れたりだろう。合作でバスを乗り継ぎ、13時に到着。ユースにチェックインして、午後は街の散策。夏河には20数年前に来たことがある。しかしながら、街のことは何も覚えていない。印象に残っているのは車での道が凄かったこと。夏河は標高2900mの門前町なのだが、崖にへばりつく未舗装の道を、爆走するバスでの移動で、ガードレールもなく、非常に怖かった記憶がある。また、沿道の村人たちは道の上に稲穂を敷いていた。バスが稲穂を踏むことにより、脱穀をしていたのである。ラプラン寺は荘厳な雰囲気で何人もの仏教僧が読経を上げていた。今はそんなことはない。 4車線の高速道路で快適な移動である。ラプラン寺も観光地となり、多くの中国人が訪れている。写真はラプラン寺。探せば20年前の写真(当時は写ルンです)もあるはずなので比較してみたいところである。
@=
(2018-07-13) 5時半起床。 6時半のバスで夏河に向かう。今日からしばらくAと同行動。ウルムチまでの旅程は大体似たようなもの。しばらくはついたり離れたりだろう。合作でバスを乗り継ぎ、13時に到着。ユースにチェックインして、午後は街の散策。夏河には20数年前に来たことがある。しかしながら、街のことは何も覚えていない。印象に残っているのは車での道が凄かったこと。夏河は標高2900mの門前町なのだが、崖にへばりつく未舗装の道を、爆走するバスでの移動で、ガードレールもなく、非常に怖かった記憶がある。また、沿道の村人たちは道の上に稲穂を敷いていた。バスが稲穂を踏むことにより、脱穀をしていたのである。ラプラン寺は荘厳な雰囲気で何人もの仏教僧が読経を上げていた。今はそんなことはない。 4車線の高速道路で快適な移動である。ラプラン寺も観光地となり、多くの中国人が訪れている。写真はラプラン寺。探せば20年前の写真(当時は写ルンです)もあるはずなので比較してみたいところである。
@=
 (2018-07-14) 8時のバスで同仁へ。昼前に到着。宿はツインが70元。二人で旅すると宿代が大幅に浮く。中国では(て言うか日本以外では)一部屋いくらで、基本ダブルかツインしかないため、一人旅だと常に倍額を払う必要がある。さて、同仁は観光地でも何でもない。そうなると、どうか。そう、ゴミだらけである。今まであれほどいた清掃員がこの街にはいない。子供が平気でポイポイしている。まぁ、彼らは大人の鏡だ。大人は率先して、もう、何でも町中にポイポイである。ペットボトルをポイ。リンゴの芯をポイ。スイカの皮をポイ。まぁ、これも中国です。共産党による教育と管理は都市部と観光地以外の人民には行き届いていないようだ。ちなみに昨日の食事が悪かったのか、Aも私も腹痛である。夕方頃からお座なりに観光。街のチベット寺は400年の歴史があるらしく、なかなか良かった。写真は寺院内の学院。修行僧たちによる問答合戦が行われていました。
@=
(2018-07-14) 8時のバスで同仁へ。昼前に到着。宿はツインが70元。二人で旅すると宿代が大幅に浮く。中国では(て言うか日本以外では)一部屋いくらで、基本ダブルかツインしかないため、一人旅だと常に倍額を払う必要がある。さて、同仁は観光地でも何でもない。そうなると、どうか。そう、ゴミだらけである。今まであれほどいた清掃員がこの街にはいない。子供が平気でポイポイしている。まぁ、彼らは大人の鏡だ。大人は率先して、もう、何でも町中にポイポイである。ペットボトルをポイ。リンゴの芯をポイ。スイカの皮をポイ。まぁ、これも中国です。共産党による教育と管理は都市部と観光地以外の人民には行き届いていないようだ。ちなみに昨日の食事が悪かったのか、Aも私も腹痛である。夕方頃からお座なりに観光。街のチベット寺は400年の歴史があるらしく、なかなか良かった。写真は寺院内の学院。修行僧たちによる問答合戦が行われていました。
@=
若い女性の可愛さ・美しさ比較。チベット人>>ウィグル人>>>漢人。一応、平均値的な比較。美人は民族の違いに関係なく美人です。それでもチベット人が一番可愛いかな。
@=
年配女性の美しさ比較。チベット人=ウィグル人>漢人。正直似たりよったりですな。美しいとは言い難いかも。
@=
若い男のカッコよさ・オトコマエ比較。チベット人>ウィグル人>>>漢人。チベット男も若い間はいまいち伊達っぷりが決まっていない。
@=
年配男性のカッコよさ比較。チベット人>>>(越えられない壁)>>>ウィグル人>>漢人。チベットの伊達男の圧勝です。以上、あくまで個人的な独断と偏見ですが、旅行者の誰に聞いても、全世代において「チベット人圧勝」と「漢人完敗」は共通の意見のように思います。
@=
 (2018-07-15) 午前のバスで西寧に移動。青海省の省都は200万都市。共産党の指導と監視が行き届いているようで、街は綺麗なものである。体感的に漢人5割、ウィグル人4割、チベット人1割くらい。歴史的にはチベットの領域なんだけど、草原は全て都市化されて、チベット人は駆逐された感じがする。西寧は都会ですけど、喧騒に包まれているわけでもなく落ち着いたいい街だと感じた。何より都会は集散地であるがゆえに、食べ物が安くて美味しくてよろしい。ついでに私の好物の洋菓子が手軽な値段で食べられるのが嬉しい。生クリームサンド50円。マフィン50円。抹茶ソフトクリーム35円。おやつの買食いだけでお腹が一杯になってしまった。写真は西寧の駅前。都会は日本と変わりませんな。
@=
(2018-07-15) 午前のバスで西寧に移動。青海省の省都は200万都市。共産党の指導と監視が行き届いているようで、街は綺麗なものである。体感的に漢人5割、ウィグル人4割、チベット人1割くらい。歴史的にはチベットの領域なんだけど、草原は全て都市化されて、チベット人は駆逐された感じがする。西寧は都会ですけど、喧騒に包まれているわけでもなく落ち着いたいい街だと感じた。何より都会は集散地であるがゆえに、食べ物が安くて美味しくてよろしい。ついでに私の好物の洋菓子が手軽な値段で食べられるのが嬉しい。生クリームサンド50円。マフィン50円。抹茶ソフトクリーム35円。おやつの買食いだけでお腹が一杯になってしまった。写真は西寧の駅前。都会は日本と変わりませんな。
@=
 街にはイスラム寺院があります。体感的に住人の4割くらいはウィグル人(ムスリム)。イスラム教は結構厳格で礼拝の写真を取るのははばかられるんだけど、中国人観光客が多数パチパチやっているので、気にせず写真を取ることができる。
@=
街にはイスラム寺院があります。体感的に住人の4割くらいはウィグル人(ムスリム)。イスラム教は結構厳格で礼拝の写真を取るのははばかられるんだけど、中国人観光客が多数パチパチやっているので、気にせず写真を取ることができる。
@=
 信号が赤になるとロープを張って交通整理。こうやってマナー向上を人民に体得させているわけですな。まぁ、大人がマナーを守らないもんなぁ。子供は教育できても、大人には強制的な手段を取るしかないよな。バカみたいな光景に見えるけど、実際にマナーは良くなっているんだから効果は絶大なのか。
@=
信号が赤になるとロープを張って交通整理。こうやってマナー向上を人民に体得させているわけですな。まぁ、大人がマナーを守らないもんなぁ。子供は教育できても、大人には強制的な手段を取るしかないよな。バカみたいな光景に見えるけど、実際にマナーは良くなっているんだから効果は絶大なのか。
@=
 おしゃれなケーキ屋さんやソフトクリーム屋さんと並んで、こんなものも売っている。左下「ザリガニ」。その右「ナマズ」。その上「亀」。その右の右「ドジョウ」。ほかは不明。ペットじゃありませんよ。食材です。
@=
おしゃれなケーキ屋さんやソフトクリーム屋さんと並んで、こんなものも売っている。左下「ザリガニ」。その右「ナマズ」。その上「亀」。その右の右「ドジョウ」。ほかは不明。ペットじゃありませんよ。食材です。
@=
(2018-07-16) 8時まで寝て10時行動開始。今日は20:47発の列車でハミに向かう。夜までやることがないので宿でノンビリ。思い立ったら、2時間ほど買食いに出る。ヨーグルトが安くて美味しい。路上で買っては食う。ソフトクリームが安くてうまい。路上で見つけては食う。その他、目に着いたよくわからないイスラムっぽいパンや肉まんを食う。どれも50円から100円くらい。この一月半で体重が相当落ちているのだが(腹の肉の厚みが半分以下になった)、ちょっとは持ち直したかと思う。
@=
 路上店舗のムスリム家族。今日一日観察したのだが、年配女性の美しさ比較を訂正。ウィグル人>チベット人>漢人。おばちゃんに可愛いも美しいもないから、実際には上品さランキングと言ったところです。ムスリム女性はスカーフを巻いているので、日に焼けておらず物静かなことから貴婦人ぽくあります。
@=
路上店舗のムスリム家族。今日一日観察したのだが、年配女性の美しさ比較を訂正。ウィグル人>チベット人>漢人。おばちゃんに可愛いも美しいもないから、実際には上品さランキングと言ったところです。ムスリム女性はスカーフを巻いているので、日に焼けておらず物静かなことから貴婦人ぽくあります。
@=
(2018-07-17) 昨夕20:47発(ただし、37分遅れる)のハミ行きの硬座(二等座席)で西寧を出発。人民は、通路に寝る。人の席を奪う。車内にゴミを捨てるの古き悪しき中国を体現している。さすが、最貧民層の交通手段である。いやぁ、なかなか大変な10時間であった。着いたハミは完全に政府に管理されたウィグル人社会。列車から降りるだけで荷物検査とパスポートチェックをされる。列車のチケットを買うためにも二度荷物のチェックをされ、液体(水)は実際に飲んで見せることを強要される。ウィグル人も中国人も個別に悪い人ではないのだが、この過剰な管理には嫌気が差す。荷物チェックが多すぎて旅行しにくいにもほどがある。また、管理が厳しすぎるためか中国であれほど感じる活気といったものがない。また、チベットエリアでは政府未認可の宿でも外国人が泊まれた(黙認されていた)のだが、ウィグルエリアでは無理だ。安そうなホテルは全て「外国人は泊まれない」と断られる。街に魅力がない。宿は非常に高額とくれば滞在する意味を見いだせず、さらに列車で3時間トルファンに向かう。トルファンには20数年前に来たことがある。色あせた記憶に残る街の面影はなく、何もかもが新しくなった漢人の街である。この街でも公安が異常に多く、ウィグル人は虐げられている。街からウィグル文化を感じない。砂漠の荒野のオアシス都市。用水路が流れ果樹園が広がるイスラムの街が見つからない。砂漠の荒野にいきなり現れる高層建築。乾いた大地に広がる漢人都市があるばかり。新疆の都市部において、ウィグルは早晩(文化として)滅びそうである。すでにほぼ滅んでいるのかもしれない。
@=
(2018-07-18) 遅めの起床。8時。中国は北京時間しかないので実質6時である。郊外を散策。昔のトルファンが残っていて嬉しくなる。ブドウ畑と水路とレンガ作りの家。ウィグルの人たちはとても朗らかだ。昼食夕食ともにゲストハウスのまかない飯。コックの腕がいいのか大変おいしい。夕食後は皆でウノをして遊ぶ。罰ゲームカードがあり、勝者以外は一人一枚づつカードを引くのだが、「隣の人とキスすること」や、「誰かの尻を叩くこと」などがあるので、むしろ罰ゲームが嬉しかったりする。 Aは喜んで罰ゲームに甘んじて隣の女性にキスしていた。よきかな、よきかな。
@=
(2018-07-19) 午前と夕方に街の散策。日中は熱くて(誤字ではない。もはや暑いは越えている)動けない。トルファンは歴史的には「火州」と呼ばれていた場所である。西遊記で有名な火焔山があるのもここである。芭蕉扇を持たない身としては歩くだけでも大変である。夜は再びウノ。罰ゲームで「異性に抱きつくこと」を引き当てる。これ罰ゲームなのか?
@=
ウィグル人自体は温厚で善良そのものに見える。一部、過激な組織もあるのかもしれないが、テロリストの恐怖は多民族支配・統制のための虚構に思える。
@=
ゲストハウスは客もスタッフもフレンドリーで大変楽しかった。さよなら、白駱駝ユースホステル。今日でお別れ、これからウルムチに向かう。
@=
 老若男女、スタッフ・客を含めて結構みんなと仲良くなったので記念撮影。ユースホステルは中国でも教養のある人が泊まっているので楽しいですよ。今の所、トルファン、朗木寺のユースが面白かったけど、結局はスタッフと同宿の客次第。中国(と言うか日本以外)は入れ替わりが激しいので、来年(どころか来月)行ってもスタッフですら同じ人はいないでしょう。
@=
老若男女、スタッフ・客を含めて結構みんなと仲良くなったので記念撮影。ユースホステルは中国でも教養のある人が泊まっているので楽しいですよ。今の所、トルファン、朗木寺のユースが面白かったけど、結局はスタッフと同宿の客次第。中国(と言うか日本以外)は入れ替わりが激しいので、来年(どころか来月)行ってもスタッフですら同じ人はいないでしょう。
@=
(2018-07-20) バスで4時間。ウルムチへ。はい。都会です。書くことはありません。ただの経由地。明日の夜行で伊寧に向かう予定。
@=
(2018-07-21) 朝イチで列車のチケットを買いにウルムチ駅へ。市街に近いのはウルムチ南駅で、ウルムチ駅は郊外の再開発地区にある。再開発地区なだけあって駅前には綺麗な高層ビルが立ち並んでいる。街の中心からはバスで1時間弱で、車窓から街を眺めていたがやはり魅力を感じない。民族性を失った平坦な文化の街である。顔は違えど、同じような衣装で同じような行動をしている。ウルムチも20数年前に来ている。郊外に風光明媚な観光地があり、天池などは良かった記憶がある。昨今行ったところで、観光コースが整備され自由な散策は楽しめないであろう。天池は透明度の高い湖で、友人と泳いだ記憶がある。内陸の人たちは泳げないので注目の的であった。今、そんなことをしたらすぐに警察に捕まるだろうな。さて、これから夜行で伊寧へ。伊寧で気息を整えた後はカザフスタンへ。今後の予定は、キルギス、ウズベキスタンくらいまで行って飛行機に乗ってしまう予定。そろそろ、もういいかなと言った感じ。ただ、サマルカンドは歴史好きとしては外したくない。でも、サマルカンドは超有名だからなぁ。行けば観光地化されていてがっかりしそうな気もする。
@=
(2018-07-22) モンゴルに行くAとは昨日でお別れ。 6時30分、夜行列車は伊寧に到着。北京とは経度的に2時間以上の時差があるが、中国は全土で北京時間が適用されるので夜明け前である。バスは運行前、タクシーなんぞに乗る気はない、、、ということで、予定の宿まで歩く。 1時間半で到着。相変わらず体力での解決である。伊寧の街だが、一気にイスラム色が濃くなった。街角で聞こえる会話の多くがウィグル語である。人々の顔つきもいかにもトルコ系で彫りが深い。ハッとするほどの美女がいるのだが、正直日本人とかけ離れているので、美人・男前の区別がよくわからない。警察の数は相変わらずだが、辺境のためかチェックは結構いい加減である。午前と午後に街を散策。この三日間お腹に爆弾を抱えているため遠出は控えておく。掃除が行き届いており街は綺麗である。また、イリ河畔は遊歩道になっている。国境都市として景洪と同じく、行政による資本投下と管理統制が行き届いているのであろう。
@=
 昔ながらの商店街。雑然とした店内は、もはや店主ですら何がどこにあるのかわからないのでは?昔の中国はどこもこんな感じの店だったんだけど、いつの間にやらなくなったなぁと思っていたら、地方には残っていました。
@=
昔ながらの商店街。雑然とした店内は、もはや店主ですら何がどこにあるのかわからないのでは?昔の中国はどこもこんな感じの店だったんだけど、いつの間にやらなくなったなぁと思っていたら、地方には残っていました。
@=
 どこの街にもある人民公園。全ての公園は柵で覆われ、入り口では荷物とIDカードのチェック。入るのに、パスポートを取り上げられ、10分ほど待たされました。なんでも電話をかけて確認しているらしい。(何の確認かは全く不明です。)
@=
どこの街にもある人民公園。全ての公園は柵で覆われ、入り口では荷物とIDカードのチェック。入るのに、パスポートを取り上げられ、10分ほど待たされました。なんでも電話をかけて確認しているらしい。(何の確認かは全く不明です。)
@=
(2018-07-23) 明日の国境越えに備えて今日は休養。同宿の中国人(優しい青年であった)から一緒にサリム湖に行かないかと誘われたのだが断る。サリム湖はグルジャで一番有名な観光地で車で片道およそ4時間。日程に余裕があれば行きたかったが、延長したビザも後3日で切れてしまう。明日にはコルガスに移動して、国境バスに間に合えばカザフスタンに行ってしまう予定。間に合わなければ明日はコルガス泊で明後日に国境越えである。サリム湖と大草原も魅力的ではあるが、大自然という意味合いではチベットで堪能したのでまたの機会のために取っておく。さて、カザフスタン始め中央アジアはロシア語圏らしい。ロシア語なんて全くわからない。加えてキリル文字は全く読めない。中国語は旅行に必要な50ほどの単語を知っている。加えて漢字を読めば(書けば)なんとか意思疎通はできるのだが、ロシア語なんて「スパシーバ(ありがとう)」しかわかる単語がない。一語でどこまで旅ができるか不安であるが、楽観主義と体力で解決することにする。
@=
国境越えに備えて休養、、、とは書いたものの。実際にはどのようにして国境を越えるかの調査がいる。グルジャまでくればアルマティ(カザフ)行きの国際バスがあるだろうと高をくくっていたのだが、バスターミナルの受付で聞いてみるとそんなバスはないとのことであった。「国境の街コルガスに行け。そこに行けばカザフに行くバスがある。」「カザフ行きのバスの出発時間?そんなもん知らん。コルガスで聞け。」宿のスタッフにも聞いてみたが同様の回答。これはアテが外れたなぁ。ネットで検索してみると、中国側のコルガスからカザフのジャルケントまではバスがある模様。また、ジャルケントからはアルマティ行きの定期バスがあるようだ。そうなると、旅の経路はこうだ。 1.グルジャからコルガスまではローカルバス。 2.コルガスからジャルケントまで国際バス。 3.ジャルケントからアルマティまでローカルバス。バスの発車時間が全くわからないので、あとは行ってから調べるしかない。もし、目的のバスに間に合わないようなら、コルガスなりジャルケントなりに泊まればいいや。
@=
(2018-07-24) 早めに行動開始。8時半にチェックアウト。何度か書いているが中国は全土で北京時間なので実質6時半である。実際、カザフに入国した途端、時計を2時間遅らす必要がある。 9時前にグルジャのバスターミナルに到着、、、する前に入口前にたむろする乗り合いタクシーから声がかかる。「コルガスに行くなら俺の車に乗れ、すぐに出発する。23元だ。」 OK乗る。昨日調べておいた正規の料金と変わらない。客集めにこの後10分ほどかかっていたが、正規のバスは9時半発。30分ほど早い。 11時前にコルガスバスターミナルに到着。ジャルケント行きのチケットを買う。順調順調。「いつ出るの?」「客が集まったら出発だ。」さいですか、いつ出発かわからないってことね。とはいえ、この時間にするべきことがある。カザフスタンの通貨テンゲを手に入れなければならない。体力で解決するとかカッコイイことを書いていたが、すまない、ありゃ嘘だ、、、というわけでもないけれど、最も力を発揮するのはやはりお金である。逆にお金がないと何も出来ない事態に陥る。適当なバスドライバーに声をかける。「両替したい。」「○×△ロシア×△。」ロシア語が話せるかと聞いているのであろう。「スパシーバ(ありがとう)」しか言えない。しかし、両替は簡単である。お金を見せながら、「ユアン(中国の通貨)-テンゲ(カザフの通貨)。OK?」これで十分。「OK。OK。」交渉成立。割といいレートで交換してくれる。いまこそ使うときだ「スパシーバ(ありがとう)。」お互いニッコリ握手。意外と早く客は集まったようで11時半にバスは出発。中国は出国もめんどくさい。荷物を全部開けられる。カザフスタンは入国から簡単だ。パスポートにはメクラスタンプ、荷物はノーチェックである。中国を出国したあたりで乗っていたバスとは違うバスのドライバーから声がかかる。「アルマティに行くなら俺のミニバンに乗れ。2500テンゲだ(800円)。」 70元(1200円)も払ったジャルケント行きのバスは国境までの2kmほどしか乗っていないが即答でOK。ジャルケントまで行っていつ出発するかわからないバスを待つよりよほど効率的だ。客の移動はドライバー同士で話をつけてくれたようだ。カザフの道をミニバンは疾走する。しかし、カザフには何もない。中国では道沿いには家屋や商店があったものだが、カザフには本当に何もない。ただただ、草原、荒野、砂漠である。この道はまたいつかもう一度通りたいと思う。着いたアルマティは、スラブ系美女、トルコ系美女、何やらよくわからない美女で溢れている。「ここは天国ですか?えっ、アルマティ。あぁ、天国の別名ですか。」という感じで惜しげもなく露出度の高い服装である。おそらく女性視点からは美男子が多いように見えると思う。人種が違うのであまり美醜がわからないというのもありますが、、、。さて、この街は英語が全く通じません。バス停から街の中心部に出るまで、そして、宿探しは大変であったがカット。
@=
 休憩所。サービスエリアみたいなもの?トイレがあるだけで何もない。道路沿いにも家一軒建ってない。中国であれば食堂や露天商が並び、ついでに言えばニーハオトイレでも1元取られる。なお、ミニバンに日本人は私だけであるが、韓国からの4人組が乗っていた。テグ出身。(注)ニーハオトイレとは、壁もドアもなく隣の人と会話しながら用をたせるコミュニケーションを重視したトイレである。
@=
休憩所。サービスエリアみたいなもの?トイレがあるだけで何もない。道路沿いにも家一軒建ってない。中国であれば食堂や露天商が並び、ついでに言えばニーハオトイレでも1元取られる。なお、ミニバンに日本人は私だけであるが、韓国からの4人組が乗っていた。テグ出身。(注)ニーハオトイレとは、壁もドアもなく隣の人と会話しながら用をたせるコミュニケーションを重視したトイレである。
@=
(2018-07-25) ここアルマティで今回の旅は終了。明日の夜、飛行機で帰国(日本到着は明後日)。予定を10日ほど早めに切り上げる。キルギスタンを経由してウズベキスタンまで行ってから、ドイツに寄り道して帰ろうと、昨日までは考えていたのだが、今後の楽しみとして残しておくことにする。さて、アルマティ2日目。午前中に飛行機の手配を終え、宿のスタッフにチケットの印刷を依頼する。空港までの経路を確認後、アルマティ散策を開始。昨日は行かなかった南の方に行ってみる。日差しはきついものの通りには街路樹が繁り、山裾に立地するため水路も豊富である。街から見える山の頂きには雪が残っており、雪解け水がこの街を潤しているのであろう。午後は暑くなるものの、乾燥しているため木陰に入ると涼しいし、朝夕は肌寒いくらいである。アタリマエのことなんだけど、誰もツバを吐かないし、腹出ししていないし(「中国 腹出し」で検索のこと)、公園には自由に入れるし、食事の友のハエはいないし、もっと早く中央アジアに来ていればよかったと後悔するが、どの国に行っても「うわっ、楽しい!」なのでこれは仕方がないところ。次の旅は中央アジアから再開しようと思う。食事は二ヶ月ぶりの洋食。豪勢に500円(普段は200円もしない)も使って暴食。一ヶ月以上、ほぼ中華オンリーであったため、涙が出るほど美味しい。何より生野菜が食べられるのは最高だ。もう、バスでの長距離移動はないので安心してお腹を壊すことができる。そうそう、これもアタリマエであるがニーハオトイレと違い、トイレは洋式でちゃんと紙が常備してある。腹痛になっても安心である。(注)ニーハオトイレとは、建物に入ると一本の溝が掘られているだけである。一列に並んで前の人の排便を見ながら自分も用をたせるコミュニケーションを重視したトイレである。裸の付き合い(ただし下半身だけ)を通して人民としての連帯感を深めることが出来ます。
@=
えー、茶化してますが、中国は今旅をして一番楽しい国だと思います。その偉大さと愚かさが極端で笑えますし、勢いがあるだけのことはあります。大抵の人はとても親切で色々と世話を焼いてくれます。みな助け合いの精神で生きてます。一部、客引きなどは鬱陶しいし、不快ですけどこれはどこの国でも同じですしね。
@=
旅の飽きについて。結局の所、先の読めない不安や、なんとか切り抜ける方法を考えるのが楽しいのであって、ドキドキがなくなったときに旅は飽きるのかもしれない。中国は一月以上滞在して、如何様にでもしようがわかってしまったため飽きたのだろう。そして、なぜアルマティが楽しかったのか?もう、何をするにも手探りで常に不安がつきまとう。宿を探す、空港まで移動する。食事を取る。物を買う。そんな簡単なことでも容易には実現できない。言葉もまるで通じない。それでいて人々は優しい。「ヤポン(日本)」と言うと、「オーッ!ベリーグッド」と返してくれる。
@=
アタリマエのことなんだけど、いちいち荷物チェックやパスポートチェックがないのでそれだけでも旅の楽しさが復活。
@=
アルマティはカザフスタン第一の都市だけど、街の発展で言ったら中国の辺境にも及ばない。高層ビルも少ないし、人も全然少ない。それゆえ逆に綺麗で落ち着いておりゆっくり滞在するには向いていると感じる。食事もバラエティ豊かで美味しいです。洋食と洋菓子が好きなんで、毎食デザートにケーキをつけています。
@=
(2018-07-26) 帰国の準備。、、、と言うほどやることもない。朝起きて公園に行き、ベンチに座って鳩を眺める。時間を潰しているだけである。一応、帰国後に配る為の土産物なんぞを買う。乾燥地帯はフルーツが美味しい。味が濃縮されるのだろう。土産物はフルーツ、、、が最適だが、流石に生ものを持ち歩けないので、ドライフルーツを買うことにする。ブドウみたいなものを指差して「これちょうだい」。なぜか裏から秘蔵の箱みたいなものを取りだして、「こっちのほうがグッドだ。こっちにしな。」みたいなことを言っている(ように感じる)。そうか、「じゃあ、それ」。よくわからないが販売の単位は500gのようだ。袋にどっさり。アンズみたいなものを指差して「これもちょうだい」。何故か隣の店の山積みダンボールから箱を一つ取りだして、「こっちのほうがグッドだ。こっちにしな。」みたいなことを言っている(ように感じる)。そうか、「じゃあ、それ」。再び、袋にどっさり。「これはタジキスタン産だ。最高にグッドだ」みたいなことを言っている(ように感じる、タジキスタンとグッドだけ聞き取れる)。そうか、「じゃあ、それ」。三度、袋にどっさり。「俺はタジキスタン生まれだが。これなんかも最高にグッドだ」みたいなことを言っている(ように感じる、自分を指差してのタジキスタンとグッドだけ聞き取れる)。そうか、「じゃあ、それ」。重い、袋は2キロになった。会計は8000テンゲ。高い!って、実際には大したことないんだけど、4日分の宿泊費と同額だ。物価感覚が途上国思考になっているため、とんでもなく高価に感じる。しかしまぁ、もうテンゲが必要ないため使い切るためにも購入。きっと、最高級品を取り揃えてくれたに違いないと思うことにする。なお、この後、空港に向かったのだが、15キロ先の空港までのバス代は150テンゲであった。 1時間半のフライト。ウズベキスタン航空はタシケント経由。一度、西に向かうため遠回りになる。追加料金で窓際の席を確保。赤茶けた大地に切れ込むキャニオン。パミール高原と冠雪の山脈。山を越えて歩いて旅行したいなぁと思うけど、ナイフリッジの連続だし絶対に死ぬな。空から見るタシケントは大都市で高層ビルはあまりないものの都市圏は広く、町と農地がモザイクになっており20年前のバンコクに似ている印象を受けた。トランジットのため今回入国はしないけれども、ここにも近いうちに来たいと思う。さて、後は夜のフライトで帰るだけ。書くほどのこともない。最後に、アルマティ発タシケント経由成田行だが、どういうわけか、タシケント発成田行きより安かった。同じ日の同じ便での比較。タシケント・成田間は同じ飛行機なのだが、アルマティ・タシケント間のフライトを追加したほうが安くなる。謎である。
@=
(2018-07-26) 日本がやはり一番綺麗だと思う。空からは北アルプスや中禅寺湖などがよく見えた。山は緑に包まれ、川は青く澄んでいる。「大和は国のまほろば。大和しうるわし。」がよくわかる。そして降り立った日本はスーパー先進国だ。あまりの発展ぶりに今更ながら驚く。魔法の国に来たかのように錯覚しそうである。さて、旅日記はこれで終わり。後は思い立ったときに、時々、旅行の振り返り感想を書くにとどめよう。
@=
旅を振り返って追記。
@=
旅の予算。 6/8から7/26までの49日間で、およそ24万円。両替を含む現金使用が14万円と100ドル。クレジット利用が3万円程度。往復の飛行機代が6万円程度。最初の3日は沖縄で、ほぼ3万円使っているので、純粋な海外滞在は46日間で15万円。一ヶ月10万円ですね。バックパッカーとしては結構リッチに旅行していた方だと思います。一時同行していたAの中国滞在一ヶ月の旅費は6万円だったとのことでした。
@=
西寧での両替にて。 30分以上待たされる。真面目に両替手続きを進めて、必要書類を用意しようとしているようだ。「税金はどこの省で払っている?」って聞かれても、「日本に払っている。」に決まってるじゃないか。なんで私が中国に税金を収める必要があるんだよ。とにかく処理が煩雑らしく、係員3人がかりで大混乱している。「えーと、今までは行員のIDカードを使って、両替の代行をしてもらってましたよ。」と伝えると、「おーっ、そんな方法があったのか。」と驚かれました。そして、無事両替完了。今後は西寧でも現金からの両替がスムーズになるだろう。
@=
旅の両替について。既にTC(Travelers's Check)は全滅だ。現金でさえ両替できるところが少ないし、さらにレートが悪い上に手数料が高い。クレジットカードで現地ATMから引き出すのが、一番効率よく現地通貨を手に入れられる。時代は変わったなぁ。帰国後すぐにクレジットカードの海外利用制限を解除し、外貨を預金できる(かつ、現地通貨で引き出せる)デビットカードを作りました。今までは「いつもニコニコ現金払い」だったけど、海外で両替及び決済に困るとは、、、。ついでに、今まで頑なに拒んでいたスマホも買ってしまいました。昔ながらの旅行スタイルは、苦労多く(そしてまたそれが楽しい面もあるけど)大変でしたわ。
@=
交通事情と「事故」。チベットエリアでは、山道は絶景ですが、相当事故が多いです。急峻な地形に曲がりくねった道。それを爆走ですから、そりゃ事故りますわな。 3時間おきくらいに事故現場といった感じです。大抵はトラックですけど、乗用車の比率もそれなりに高い(2、3割)。バスの運転手は比較的安全運転ですけど、夜行はちょっと乗るのが怖いかなぁ。
@=
旅と仕事について。 20代前半。旅は今しか出来ないと思っていた。 20代後半。仕事は今しか出来ないと思っていた。 30代。旅も仕事もいつでも出来ると思っていた。そして、40代。旅も仕事も今しか出来ないと思っている。
@=
今回の旅についての総括終わり。
@=
(2018-08-10) 塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉尾根のいつものコース。二ヶ月ぶりだし、まずは足慣らし、、、のつもりであったが、ひどい筋肉痛になる。また、痛めていた右足膝がまだ治っていなかったことを知る。日常生活での支障がないので、治ったと思いこんでいたが、未だ完治していなかったようだ。あまりに痛くて下りは半歩づつしか歩けず、普段の倍の時間がかかってしまった。 60過ぎの年配の方にも抜かされるばかりで悲しくなる。帰国後にはジムにも行ったが、体重が5キロ以上減ったにもかかわらず、10回の懸垂が限界。筋肉が相当落ちているようだ。
@=
 (2018-08-13) 会津駒ヶ岳。駒ヶ岳登山口->駒の小屋->駒ヶ岳->中門岳->(往復)。同行はW氏。駒の小屋まではキツイが、そこからは比較的なだらか。湿原が広がり、晴れなら綺麗であろうと思われるが、残念ながら曇りアンド小雨。駒ヶ岳から中門岳までは完全に霧の中。なんにも見えない。下りは結構な雨。リベンジ必須だな。
@=
(2018-08-13) 会津駒ヶ岳。駒ヶ岳登山口->駒の小屋->駒ヶ岳->中門岳->(往復)。同行はW氏。駒の小屋まではキツイが、そこからは比較的なだらか。湿原が広がり、晴れなら綺麗であろうと思われるが、残念ながら曇りアンド小雨。駒ヶ岳から中門岳までは完全に霧の中。なんにも見えない。下りは結構な雨。リベンジ必須だな。
@=
 陣馬山登山口=>(一の尾根)=>陣馬山=>景信山=>城山=>(高尾山)=稲荷山=>高尾山口。右膝が痛いため、足慣らしを継続。天気が良くて涼しいので遠出したいが自重。体力的には楽勝。体重が減っているので登りは軽いものだ。が、やはり下山で膝が痛い。写真は景信山から関東平野。
@=
陣馬山登山口=>(一の尾根)=>陣馬山=>景信山=>城山=>(高尾山)=稲荷山=>高尾山口。右膝が痛いため、足慣らしを継続。天気が良くて涼しいので遠出したいが自重。体力的には楽勝。体重が減っているので登りは軽いものだ。が、やはり下山で膝が痛い。写真は景信山から関東平野。
@=
塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉尾根のいつものコース。最初から右足をかばいながらであれば、膝が痛くなる前に15kmは歩ききれる。
@=
三度、塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉まで3時間55分。走ってはないけどこれは結構早い方だと思う。ずっと小雨で視界は30メートル。雨でぬかるんで走るのは危ないけど、何も見えないので景色を堪能するわけでもなく、ただただ、飛ばして歩いた。で、やっぱり右足が痛い。膝と言うより腱を痛めているような気がする。
@=
高尾駅から草戸山、城山湖、三沢峠から梅ノ木平。足も痛いし天気も不安なので近場で、、、が、低山はまだまだ暑すぎる。歩き始めてすぐ嫌になったので、2時間で切り上げ高尾山口で温泉に入って帰る。
@=
高尾駅=>八王子城址=>(北高尾縦走路)=>堂所山=>(高尾縦走路)=>(金毘羅台)=>高尾駅。折角の三連休だが天気は悪い。昨日は雨。今日も明日も曇の予報。街は曇でも山では雨が降るかもしれない。というわけで近場でトレーニング。楽しい部分は、、、、うん、殆どないな。北高尾は上り下りが激しいのだが、展望はほとんど開けない。それでも人が少ないだけまだまし。トレーニングと割り切ることもできる。が、この時期、すでに高尾(縦走路)はだめだ。人が多すぎる。雨後の道は多数の登山者に踏まれて泥濘状態。 1号路は舗装されているにもかかわらず、激混みで山道よりもゆっくりとしか進めない。
@=
古里駅=>鉄五郎新道=>御岳山=>日の出山=>つるつる温泉。鉄五郎新道はあまり人気がないのか誰とも会わない。静かないい道なんだけど、誰も通らないので蜘蛛の巣が半端ない。また、尾根に入るまではヤブが多く、儚いとは全く言えない朝露滴り、ズボンも靴も濡れてしまった。御岳山以降は人がたくさん。さっさと温泉に抜ける。午後になる前に下山。
@=
鴨沢バス停=>堂所=>七ツ石小屋=>七ッ石山=>雲取山(往復)。以前より行ってみたかった東京都の最高峰2017m。エスケープできないロングトレイルであることと、膝の調子の悪さからのびのびになっていたが連休の晴れ間を狙って決行。 3時起床。西国分寺駅まで自転車。4時35分の始発で奥多摩駅に6時着。現地は曇り。予報は晴れでもそれは平野部の話。山では雨が降るかもしれない。道中、小雨に会うものの天気はなんとか持ってくれたが、 1500mより上はずっとガスの中でなんにも見えない。高所の尾根道は展望が開ければさぞかしいい眺めだと思うのだが、残念ながら視界は20mである。 3時間半で頂上に到着。長丁場に備えて水分を2.5リットル持ち込んだが、思っていたほど大したことはなかった。山頂で30分ばかり待ってみたが、天候は回復の兆しなく、やむなく下山する。下山中、霧が少し晴れてきて、バス停に着く頃には晴天。よくある話。また来ないとダメだな。
@=
 (2018-10-06) 塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉のいつものコース。同行は大森のW氏。表尾根はずっと雲の中。なんにも見えず。ときおり雲が薄くなり、風景がフェイドイン。すぐさまフェイドアウト。 CGを見ているかのよう。大風のなせる不思議な光景。しかし、週末ごとに台風が来るのは(昨年もそうだったが)やめてほしい。写真は大倉尾根の花立小屋から一枚。
@=
(2018-10-06) 塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉のいつものコース。同行は大森のW氏。表尾根はずっと雲の中。なんにも見えず。ときおり雲が薄くなり、風景がフェイドイン。すぐさまフェイドアウト。 CGを見ているかのよう。大風のなせる不思議な光景。しかし、週末ごとに台風が来るのは(昨年もそうだったが)やめてほしい。写真は大倉尾根の花立小屋から一枚。
@=
 (2018-10-07) 河又名栗湖入口バス停=>白谷沢=>棒ノ嶺=>黒山=>岩茸石山=>惣岳山=>御嶽駅。西武沿線も行ってみようと思い棒ノ嶺を選ぶ。大変人気の山。人が多い。軽装備の人も目立つ。半分沢登りみたいな道で、先週の台風で橋は全て流されている。危険はあまりないけど、濡れないようにしようと思うと余計危ないかもしれない。子供やいかにもハイキングといった出で立ちの若い男女も多かったけど大丈夫かなぁ。棒の嶺からは北側の展望が広がる。遠く、男体山や日光白根山まで見通せる。往復するのは嫌なので南下して奥多摩線側に下山する。写真は棒ノ嶺からの関東平野。
@=
(2018-10-07) 河又名栗湖入口バス停=>白谷沢=>棒ノ嶺=>黒山=>岩茸石山=>惣岳山=>御嶽駅。西武沿線も行ってみようと思い棒ノ嶺を選ぶ。大変人気の山。人が多い。軽装備の人も目立つ。半分沢登りみたいな道で、先週の台風で橋は全て流されている。危険はあまりないけど、濡れないようにしようと思うと余計危ないかもしれない。子供やいかにもハイキングといった出で立ちの若い男女も多かったけど大丈夫かなぁ。棒の嶺からは北側の展望が広がる。遠く、男体山や日光白根山まで見通せる。往復するのは嫌なので南下して奥多摩線側に下山する。写真は棒ノ嶺からの関東平野。
@=
 (2018-10-08) 奥多摩駅=>石尾根=>六ツ石山=>水根山=>鷹ノ巣山=>水根沢林道=>奥多摩湖バス停。 3時起き。6時奥多摩駅着。駅から雲取山(20km)を目指し行けるところまで行く計画。最低でも鷹ノ巣山(12km)、多分七ッ石山(16km)くらいまでは行けるだろうと考える。が、標高1000mで霧が出て、すぐに雨が降り始める。水根山で心が折れるも、なんとか鷹ノ巣山までは登る。 1700mの展望の広がるはずの山頂も雨と霧ではなんにも見えない。エスケープルートで奥多摩湖へと抜ける。奥多摩はホント天気に恵まれない。関東一円の晴天くらいでないと霧か雨ではないだろうか。景色は間違いなく良い。ブナ林も非常に美しい。広葉樹はすでに色づいている。 10月中にもう一度、(好天を狙って)来たいところである。
@=
(2018-10-08) 奥多摩駅=>石尾根=>六ツ石山=>水根山=>鷹ノ巣山=>水根沢林道=>奥多摩湖バス停。 3時起き。6時奥多摩駅着。駅から雲取山(20km)を目指し行けるところまで行く計画。最低でも鷹ノ巣山(12km)、多分七ッ石山(16km)くらいまでは行けるだろうと考える。が、標高1000mで霧が出て、すぐに雨が降り始める。水根山で心が折れるも、なんとか鷹ノ巣山までは登る。 1700mの展望の広がるはずの山頂も雨と霧ではなんにも見えない。エスケープルートで奥多摩湖へと抜ける。奥多摩はホント天気に恵まれない。関東一円の晴天くらいでないと霧か雨ではないだろうか。景色は間違いなく良い。ブナ林も非常に美しい。広葉樹はすでに色づいている。 10月中にもう一度、(好天を狙って)来たいところである。
@=
 (2018-10-13) 焼山登山口=>焼山=>姫次=>蛭ヶ岳=>丹沢山=>塔ノ岳=>大倉バス停。予報は曇。丹沢なら雨にはならないだろうと思い主脈縦走。距離25km。累積高度上昇2000m。これがこなせると関東の山はほぼ日帰りが可能になる。 8時間かかってなんとかゴール。ヒザ痛への試金石であったが、なんとか暗くなる前に下山。足は相当痛い。帰りの電車で足が完全に固まってしまって座席から立つのに一苦労。蛭ヶ岳はお約束どおり霧の中。誰もいない。
@=
(2018-10-13) 焼山登山口=>焼山=>姫次=>蛭ヶ岳=>丹沢山=>塔ノ岳=>大倉バス停。予報は曇。丹沢なら雨にはならないだろうと思い主脈縦走。距離25km。累積高度上昇2000m。これがこなせると関東の山はほぼ日帰りが可能になる。 8時間かかってなんとかゴール。ヒザ痛への試金石であったが、なんとか暗くなる前に下山。足は相当痛い。帰りの電車で足が完全に固まってしまって座席から立つのに一苦労。蛭ヶ岳はお約束どおり霧の中。誰もいない。
@=
(2018-10-20) 三峯神社バス停=>霧藻ケ峰=>白岩山=>雲取山=>鴨沢バス停。関東は晴れ。奥多摩に向かう。再度の雲取山。バスの始発が8:30で登山口に着くのが10時前。 20kmの道程を暗くなる前に着けるかどうか不安であったが、雲取山まで登り3時間30分、降り2時間の5時間半でなんとかなった。 1500m以上の高所では広葉樹林が色づいている。気持ちのいい山道であったが、雲取山はやはり雲の中。 1500mなら雲の下で晴れ。2500mなら雲の上で晴れ。 2000mはちょうど雲の中なのか雲取山(2017m)は天気に恵まれない。日記が写真だらけになってきたので、写真は別ページに分離する。というわけで、写真はこちらをクリック。
@=
(2018-10-21) 上日川峠=>唐松尾根=>大菩薩嶺=>大菩薩峠=>ノーメダワ=>藤タワ=>貝沢=>丹波バス停。待ち望んだ関東一円の秋晴れ。しかしながら、昨日の雲取山縦走で体力切れ、及び、ヒザ痛し。流石にもう一度雲取山は登れない。よって、お気軽2000mの大菩薩嶺にする。バスで1600mまで行けるので、実質登る高さは高尾山と変わらないんじゃないかな。それにもかかわらず富士山が間近で甲府盆地も一望できる、遥か南アルプスや八ヶ岳まで見渡せる贅沢な山である。雲ひとつない晴天。当然大人気。未就学児も登っている。唐松尾根は渋滞気味。雷岩で景色を堪能した後、大菩薩嶺はおまけで登頂(景色がない)。右手、前方に富士、中部に甲府盆地、後方に南アルプスを眺めながら尾根筋を通って大菩薩峠へ。大菩薩峠では雲取山から続く石尾根が全て見渡せた。昨日もこの天気だったらなぁ。ここから、北を目指して多摩川水系へと抜ける。来るときは中央線だったけど、帰りは奥多摩線だ。大菩薩嶺とは打って変わってほとんど人の通らない寂しい山域である。危険はないけど結構山は荒れていて倒木が道や橋を塞いでいるので時折アスレチックだ。思ったより時間がかかったものの3時間ちょいで下山。バスの到着まで35分という中途半端な時間で残念ながら温泉に入ることが出来なかった。本日山行の写真はこちら。
@=
(2018-10-28) 鴨沢バス停=>堂所=>ブナ坂=>雲取山=>飛竜山=>前飛竜=>熊倉山=>サオラ峠=>丹波バス停。 3時起き。奥多摩へ。晴れの予報。3度目の雲取山。ただし、今回雲取山はおまけ。奥多摩から更に奥秩父へと向かう。奥秩父主脈の玄関、飛竜山が目的だ。なんとも名前がかっこいいぞ。鴨沢は慣れたもの、3時間ちょいで雲取山に到着。 1500m前後が関東では紅葉の見頃。山全体が赤く染まっている。石尾根に出るまでも綺麗なものだ。基本晴れてはいるものの雲は全天の7割といったところ。雲取山に近づくにつれガスが出てくる。やっぱり雲の中なのかと嫌な予感。ところが、山頂の北西側には雲がなく、来た道を振り返ることは出来なかったものの、遠く奥秩父の展望は開けていた。休憩もそこそこに飛竜山に進路を取る。15分ほど下ると峠になっており三条の湯への下山路と奥秩父縦走路に別れる。景色もよく二組食事をしていたが、ゆっくりする間もなく先を急ぐ。なんせまだ15km以上ある。奥秩父縦走路に入ってからは誰にも合わなかった。あまり人気がないようだ。道はしばらく笹薮で露に濡れているため、靴も靴下もズクズク。大変気持ちが悪い。結構怖いところもあったし、正直に言って不安であった。危険かどうかよりも誰も通らない山中に一人っきりというのが不安である。不測の事態が起こっても誰も助けてくれないし、下手すれば死ぬ可能性も十分にある状況は、気力も体力も想像以上に消耗する。着いた飛竜山はガスの中、ついでに林の中。なんも見えないしこれでは人気もないわけだ。急いで下山開始。縦走路を外れて下山路に入ってからが素晴らしかった。誰も通らないのがもったいなく思える紅葉の別天地。姿は見えないものの動物たちが落ち葉を踏む音もよく聞こえる。宝石箱の中を歩いていたような2時間であった。バス停には3時半に到着。 28.5km、8時間40分。久しぶりに本格的な登山をした気分。本日山行の写真はこちら。
@=
(2018-11-03) 東日原バス停=>稲村尾根=>鷹ノ巣山=>日陰名栗山=>高丸山=>七ツ石山=>雲取山=>三条の湯=>後山林道=>お祭りバス停。予報では午前晴れ午後曇り。午前中の勝負になるので3時起き。前回、雨で何も見えなかった奥多摩の鷹ノ巣山を選択する。バス停で降りたのは10人前後。7時過ぎに出発。集落から見える稲村岩の存在感が抜群だ。朝日を受けた稲村尾根はそれなりに綺麗だった。ただ先週の前飛竜からサオラ峠までが素晴らしすぎたので感動は少し霞む。紅葉の見頃は1000m上と言ったところ、1500mではもう終わっている。写真を取りながらノンビリ登ったので頂上に着いたのは9時半。残念ながら山では9時前には曇りになってしまったため、好展望とはいかず。分厚い雲が天を覆い、雲取山や飛竜山は雲の向うで見えない。石尾根を西進し七ッ石山を次の目的とする。鷹ノ巣山から七ツ石山までの4つの峰は全て1700m台。登って降りての繰り返しだが次の山がすぐ目の前に見えているので達成感がある。視界も開けているので気分も高揚する。これで青空が広がっていたらなぁ。 11時頃、弟から電話。「もしもし、近くまで来てるんやけど昼飯一緒に食べへん?」「いいねぇ。今奥多摩の山奥で標高1700mやけど。」「ムリ。」そりゃそうだ。七ツ石山の手前でマウンテンバイクと出会う。やるなぁ。自電車を押して鴨沢から登ってきたらしい。普通に歩いて登山するより何倍もキツイしキケンなはずだ。さすがに奥多摩のこんな山奥でダウンヒルしようとする人がいるとは思わなかった。世の中色んなスゴイ人がいて勇気を貰うこと然りだ。 11時半に七ッ石山着。曇りだし下山しようと思っていたのだが、10km程度では全然物足りない。展望は期待できないものの、おまけで雲取山にも行ってしまうことにする。雲取山山頂で懐かしい顔に出会う。昨年丹沢でタクシーをシェアした人である。関東3000万以上の人がいてこんなことがあるんだなぁ。いやぁ、奇遇だねぇということで記念撮影。さて、下山であるが鴨沢方面は人が多くて行きたくない。よって、三条の湯経由でお祭りに向かう。途中三条ダルミで休憩していると飛竜山方面からトレイルランナーが現れる。先週誰にも出会わなかった道から来たことに驚き、「丹波バス停からですか?」と聞くと、「鴨沢からです。」との答え。ええっ、これから鴨沢に行くんでしょ。どういうこと?反対方向じゃない。なんと、鴨沢7時発で飛竜山まで往復らしい。その復路とのことである。普通は雲取山往復(25km)が日帰り出来れば健脚レベルですよ。フルマラソン距離を山ん中で達成してしまうトレイルランナー恐るべし。さて、三条の湯への道は人が少なく、落ち着いた紅葉谷で想像以上に良かった。やはり雲取山よりも奥(西)がよい。深山幽谷という言葉が似合う風情だ。最後、バスの時間がギリギリだったため林道をジョギング。 30km、8時間半。私にはこの辺が限界ですわ。これでも早い方だと思うんだけどなぁ。世にはすごい人が多すぎる。本日山行の写真はこちら。
@=
(2018-11-11) 田元バス停=>モロクボ平=>牛の寝通り(途中)=>大マテイ山=>山沢入りのヌタ=>鶴寝山=>松姫峠=>奈良倉山=>山沢入りのヌタ=>小菅の湯バス停。奥多摩の本気が見れるという牛の寝通りに行く。奥多摩エリアで一番美しい紅葉が見れる尾根として『山と渓谷』にも載ったらしい。、、、が、すでに本気を出し切った後でお疲れのようであった。冬枯れの尾根道。陽光が降り注いで悪くはないんだけど、これじゃあなぁという感想。このまま大菩薩峠を越えて甲府盆地の方へ行ってしまおうかとも考えたが流石に遠いので断念。引返して大マテイ山、鶴寝山、奈良倉山と今まで行ってなかった奥多摩南部の山々を片付けることにする。奈良倉山からは再び引返して15時半に小菅の湯に到着。 14:45の次のバスは17:45。2時間近く温泉でノンビリして本日の山行終了。写真はこちら。
@=
(2018-11-17) 深山橋バス停=>ムロクボ尾根=>三頭山=>笹尾根=>(数々の山)=>和田峠=>陣馬高原下。晴のち曇の予報。午後は雲が出るらしいので1500mまでの低山にしておく。奥多摩の三頭山から笹尾根を縦走し和田峠(高尾)の方に抜けるコースを選択。奥多摩は抜群の天気。登山中、多摩川向こうの石尾根がよく見える。また、雲取山や飛竜山の向こうには甲武信ヶ岳と思われる山まで見えていた。三頭山まではとにかく急坂が多い。山頂で15分ばかり休憩。抜群の富士山を眺めながら早めの昼ご飯。 11時前、笹尾根に取り付き和田峠へと向かう。この笹尾根、とにかく長い。バス停までは20km以上あるので体力勝負。深山の路は美しいブナの森が続くのだがすでに散った後。まぁ、おかげで温かい日差しを浴びながらの時折富士を遠望できるスピードハイク。しかし、登っては降りての繰り返し、半端なく疲れる。和田峠に着いたときにはすでに午後4時。山は相当暗い。トレランをやる人ならここから高尾山(さらに15km先)まで行ってしまうらしいが、時間的にも体力的にも無理。今回のコースは30kmだけど、40kmはとても歩けるとは思えない。隔絶を感じる。写真日記はこちら。
@=
(2018-11-23) 都民の森バス停=>大滝の路=>石山の路=>大沢ノ頭=>三頭山=>鞘口峠=>山のふるさと村。先週に引き続き三頭山。同行は新宿のK氏。奥多摩三山縦走という遠望を持って登ったのだが、結果は一座目の三頭山のみで終わり。日の短い季節だとやはり無理のあるコースであったし、スタートが10時と遅れてしまったので早々に縦走は諦め、ハイキングとして楽しむことにする。天気は抜群で今日も富士と奥多摩の山並みがよく見えた。下山路は通ったことのないサイグチ沢(鞘口沢)へ。バス停まで遠いなと思っていたのだけど、麓の山のふるさと村からは奥多摩駅への無料の送迎バス(15:40発)があった。
@=
(2018-11-25) 陣馬山登山口バス停=>陣馬山=>高尾縦走路=>高尾山(まき)=>高尾駅。同行は上野のA氏。一ノ尾根を重機関車のごとく突き進むA氏。地図ではコースタイム110分であるが、80分で山頂に到着。本日は快晴。陣馬山からは360度の展望が見渡せた。ショートコースの予定であったが、予想以上のハイペースで進んだため、高尾縦走に切り替える。高尾は危ないところなど皆無のおしゃべりしながらの散歩道。4時前には高尾駅に着いたので2時間ばかり居酒屋で飲んで帰宅。汗かいて飲むビールはまわるのが早くて経済的。
@=
(2018-12-01) 笹平バス停=>払沢ノ峰=>松生山=>浅間嶺=>浅間尾根=>数馬上コース=>温泉センターバス停。寒いので1000m程度の低山がよかろうとのことで浅間嶺に行く。三頭山から続く笹尾根と大岳山を盟主とする山塊に挟まれたエリア。なだらかな山容から甲州街道の一部ともなっていたらしい。 7時に笹平出発。払沢ノ峰から浅間嶺までは照葉樹林で景色もよく楽しい。特に浅間嶺からは多摩三山を見渡すことが出来て素晴らしい。富士もそうだけど名山は実際に登るのもいいが、遠くから眺めるのもまた格別である。ただ、そこ以外の登山道は杉の植林であり景色も開けずあまり大したことはない。 10km程度の短い尾根なので12時には目的地に到着。昼間から温泉に浸かってご飯を食べると、帰りのバスと電車は爆睡。なお、本日は4時半起き。
@=
(2018-12-09) 高尾山口駅=>四辻=>草戸山=>大洞山=>大垂水峠=>稲荷山=>高尾山口駅。低山でショートコースということで高尾へ。人が多いのは嫌だということで南高尾へ。南高尾は比較的人が少なくのんびり散歩するにはいいコース。昨日くらいから冬本番。1000mを超える山はしばらくおあずけだな。寒いの嫌い。
@=
(2018-12-15) 陣場高原下バス停=>陣場山=>明王峠=>相模湖駅。 10時過ぎからノコノコ登り始め。寒くて早朝は行動する気がしない。人混みが嫌だったので縦走せずに明王峠から下山する。途中、30人以上の若いパーティーに出会う。神奈川の高校のワンゲル部らしい。すごいなぁ。もしかして今高校生にも登山人気ですかと聞くと、「ウチの高校は特別かなぁ。」とのことであった。顧問の先生と一時間ほどおしゃべりしながら下山。なお、あまり体力のなさそうな顧問の先生は、ITから教職に転職したらしい。「顧問やりませんか?」と誘われたけど、流石に今から教職免許は取ってられないわ。
@=
 (2018-12-22) 個人的には日本で一番の未開地「群馬」に行く。高崎は都会。県庁所在地の前橋は落ち着いた地方都市。臨江閣のボランティアガイドが郷土愛にあふれるご老公で、一時間近くにわたって群馬の歴史、文化、人物について語ってくれた。そこらの前橋市民より群馬について詳しくなったかもしれん。散策して初めて知ったのだが、詩人の萩原朔太郎の出生地でもある。写真の人物である。
@=
(2018-12-22) 個人的には日本で一番の未開地「群馬」に行く。高崎は都会。県庁所在地の前橋は落ち着いた地方都市。臨江閣のボランティアガイドが郷土愛にあふれるご老公で、一時間近くにわたって群馬の歴史、文化、人物について語ってくれた。そこらの前橋市民より群馬について詳しくなったかもしれん。散策して初めて知ったのだが、詩人の萩原朔太郎の出生地でもある。写真の人物である。
@=
(2018-12-24) 鳥沢駅=>扇山=>百蔵山=>猿橋駅。相変わらず10時過ぎからノコノコ登山開始。天気が良く暖かかったので、もう少し早起きして高山に行っても良かったかなぁ。扇山は360度、百蔵山も南の展望は広がる。低くて距離も短く冬の寒い日に散歩がてらに登るにはいいコースである。
@=
(2019-01-02) 春日野道駅=>青谷道=>摩耶山=>天狗道=>林間学校道=>旧摩耶道=>三宮駅。同行は家族4名+大正のシバジィ。予定の登山口が尾根側面からの直登で、トラロープの崩れやすい急坂であったため断念。整備された青谷道にコース変更。子供は元気。ジジィが10m進む間に、20m進んで10m引き返す。敢えてうさぎ跳びで登ってみる、、、などなど、およそ3倍のハンデをつけているようなものだ。掬星台での昼食後、子どもたちはロープウェー、ジジィ連は徒歩で下山。午前は晴天であったが、午後は曇天。下山途中ではあられに見舞われた。
@=
(2019-01-14) 小仏バス停=>景信山=>城山=>大垂水峠=>大洞山=>草戸山=>高尾駅。 6時の目覚まし。暗くて寒くて起きれず。 8時になってから出発。出発が遅くなったので高尾。高尾駅で降りてロシアンバスルーレットに賭けたら小仏行を引いたため、景信山から大垂水峠を越えて南高尾を巡るコースにする。登山口から20分で景信山終了。あれっ、こんなに近かったっけ?山頂でなめこうどん。朝を食べていなかったので胃に滲みる。城山に向かう途中で、地下足袋姿の西洋人と出会う。うーむ、彼はもしかして加藤文太郎をリスペクトしているのであろうか?混雑が予想される高尾山は無視して、大垂水峠に下ってから南高尾へ。歩き慣れたコースだし、特筆するほどのことはなし。(注)ロシアンバスルーレットとは、行き先を限定せず、取り敢えず来たバスに乗ることである。海外旅行などで時々やる。思わぬ収穫も多いが、ひどい目に遭うことも多い。
@=
 (2019-01-20) 鎌沢バス停=>三国山=>浅間峠=>(笹尾根)=>数馬峠=>温泉センターバス停。藤野駅9時15分発のバス。増便が出るほどの人気。陣馬山と生藤山の両睨みであったが(和田で降りるか鎌沢で降りるか)、陣馬山は却下。高尾山系は今日も人混みであろう。鎌沢で降りたのは三人。登山口までの舗装路は急であったが、山道に入ると逆に緩やか。登山口手前にトイレ付きの休憩所があり、御年76歳の御老公に話しかけられる。生藤山には50回以上登っているとのこと。山頂に至るまでの道からの景色は陣馬山よりこちらのほうが良いらしい。折角悠々自適なんですから平日に登ればと問いかければ、休日ならば「行き倒れても誰かに見つけてもらえるから」との答え。また、「崖際の道などは避けて登るように」と家族からも言われているそうな。「優しい家族ですね。」と感心すれば、「平日に崖から転落したら遺体未発見で保険金がおりない」と注意されたらしい。「現金な家族ですね。」さて、1時間程度で三国山に到着。 10人位のおばちゃんパーティーと3人の若い女性のパーティーがいた。景色を眺めながらおにぎりを食べていると、皆揃って生藤山方向へと出発していく。これは生藤山方面も混んでそうだということで、進路を逆の笹尾根にとる。こちらは大変静か。冬の日のポカポカ陽気で実にハイキング日和。2時間歩いて数組すれ違う程度であった。11月には人だかりであった数馬峠も今日は一人きり。 15時には数馬の湯に到着。温泉で疲れを癒やして帰宅。写真は鎌沢休憩所からの一枚。気の早い梅が咲いていた。向こうに見えるは陣馬山。
@=
(2019-01-20) 鎌沢バス停=>三国山=>浅間峠=>(笹尾根)=>数馬峠=>温泉センターバス停。藤野駅9時15分発のバス。増便が出るほどの人気。陣馬山と生藤山の両睨みであったが(和田で降りるか鎌沢で降りるか)、陣馬山は却下。高尾山系は今日も人混みであろう。鎌沢で降りたのは三人。登山口までの舗装路は急であったが、山道に入ると逆に緩やか。登山口手前にトイレ付きの休憩所があり、御年76歳の御老公に話しかけられる。生藤山には50回以上登っているとのこと。山頂に至るまでの道からの景色は陣馬山よりこちらのほうが良いらしい。折角悠々自適なんですから平日に登ればと問いかければ、休日ならば「行き倒れても誰かに見つけてもらえるから」との答え。また、「崖際の道などは避けて登るように」と家族からも言われているそうな。「優しい家族ですね。」と感心すれば、「平日に崖から転落したら遺体未発見で保険金がおりない」と注意されたらしい。「現金な家族ですね。」さて、1時間程度で三国山に到着。 10人位のおばちゃんパーティーと3人の若い女性のパーティーがいた。景色を眺めながらおにぎりを食べていると、皆揃って生藤山方向へと出発していく。これは生藤山方面も混んでそうだということで、進路を逆の笹尾根にとる。こちらは大変静か。冬の日のポカポカ陽気で実にハイキング日和。2時間歩いて数組すれ違う程度であった。11月には人だかりであった数馬峠も今日は一人きり。 15時には数馬の湯に到着。温泉で疲れを癒やして帰宅。写真は鎌沢休憩所からの一枚。気の早い梅が咲いていた。向こうに見えるは陣馬山。
@=
(2019-01-27) 用竹バス停=>権現山=>扇山=>鳥沢駅。登山口9時出発。バス停で降りたのは3人。 15kmちょいの気楽なハイキングコース。寒い。登っていると体は熱いが末端は冷える。今年は降水量が少ないので標高2000mくらいまでは雪がない。踏み跡に乾いた土煙が舞い、枯れ木を鳴らしたからっ風が身に刺さる。 1000mを越えたところで、マウンテンバイクに乗った若者3人と出会う。和見峠から権現山に登っての帰路で用竹まで行くそうな。今回のコースは危険のないハイキングコースとはいえそれは徒歩での話。権現山直下は相当な急登だし木の根や段差も多かった。まだ、高校生くらいに見えたけど将来は立派な冒険野郎になってくれることだろう。ロープの貼られた急坂を息を切らせながら登る道すがら、しっかりとタイヤ跡が頂上まで続いておりなんだか嬉しい気持ちとなった。権現山からの景色はまぁまぁ。富士は悪くないけど扇山からのほうが綺麗に思う。三頭山や遠く雲取山に飛龍山、石尾根、笹尾根、それに続く陣馬山、と多摩の山並みをほぼ見渡すことができ、さらにそれらが制覇済みとなればなんとなく気分は良い。
@=
(2019-02-24) 須磨浦公園駅=>旗振山=>横尾山=>高取山=>菊水山=>摩耶山=>阪急六甲駅。チチジィと大正のシバジィが須磨アルプスに行くという話なので私も行くことにする。須磨アルプスは250mから300mと低いのでわざわざ行こうとまでは思わなかったのだが、行ってみると須磨の海を見渡せるし、一部岩稜地帯もあるしでなかなかに面白かった。須磨アルプスだけだと物足りないので摩耶山まで足を伸ばす。鵯越駅以降は勝手知ったる歩き慣れた道。西六甲は目の前が海と神戸の町並み、かつ遠望が利き景色はいいのだがとにかくしんどい。摩耶山でやっと700mと標高はさほどでもないのだが、 200mくらいを登っては降りての繰り返しなので、累積標高は相当になるのではないだろうか。 8時間半かけてやっと下山。六甲駅に着いたときにはクタクタで帰りの電車は爆睡。
@=
(2019-03-05) 芦屋川駅=>荒地山=>東お多福山=>蛇谷北山=>石ノ宝殿=>船越峠=>宝塚駅。夜明け前に出発して6時過ぎ登山開始。平日だし早朝の山には誰もいない。尾根筋から枯れ木をシルエットに朝日を拝む。荒地山は岩が多く楽しいが、それ以外は至って平凡な道。後半は東六甲縦走路を宝塚まで歩くが昼前には到着してしまった。あれっ、こんなに近かったっけ?
@=
(2019-03-08) 三宮駅=>新神戸駅=>市ケ原=>摩耶山=>記念碑台=>六甲山上駅(ケーブルカー)。同行はチチジィとシバジィ。終始ゆっくりしたペースで約8時間のコース。一人だと倍速とは言わずとも5時間あれば余裕で歩けそうかな。新神戸から市ケ原までは初めて歩いたけど、舗装された登山道そのものに趣はないものの、布引の滝を始め沢道の景色としては上出来。気楽な自然散策には最適に思う。
@=
(2019-03-09) 8時30分の飛行機でバンコクへ。目的はミャンマーのパガン。なんの用意もなし。今夜の宿も着いてからの交通手段も全くの未確定。普通だとこんなことはしないのだけど、今回の旅にはスマホがある。そう。神器スマホである。さぁ、その力とやらを見せてもらおうではないか。空港内に通信会社があるので、街に出る前にはインターネットにつながる環境が出来上がり。ちょっと簡単すぎないか。スマホとパスポートと150バーツ(約500円)を渡したら、店員がほぼ全てやってくれた。私がしたのはログインのためにPINコードを入力するのと、SIMロック解除のためのパスワードを入力しただけ。後は全部店員がやってしまったからどんな操作をしていたのかさっぱりわからん。スマホは日本語のままなのにすごいなぁ。多分どんな言語でも読まずともわかるんでしょうね。さて、空港からバスターミナルに向かえば、ミャンマーとの国境の町までのバスは20時出発とのこと。あー、これは着くのは深夜の3時とかだな。時間的になんの交通手段もないだろう。国境まで歩けと言うことか。仕方がない。予定は決まった。今日このままメーソートまで夜行バス。深夜について国境まで徒歩。夜明けとともに国境を越えて、一気にヤンゴンまで行く交通手段を探す。バスの出発まで5時間ばかり時間がある。今日は土曜日なので、モーチットのウィークエンド・マーケットへ。半端ない人だかり、外人いっぱい。ガイドブック片手の日本人もいっぱい。日本からの旅行者はみな若いし春休みだから学生だろうな。旅の初日で日本語に飢えているわけでもないので、特に話しかけることもない。大体、犬もあるけば外人に当たるみたいな状況では旅行者同士での情報交換もなにもないしなぁ。 20:30発の夜行バスは定刻通り出発。やることもないし寝る。
@=
(2019-03-10) 移動ばかりで一日が終わった。バンコク発の夜行バスは翌朝4時過ぎにメーソートに到着。 24時の時点ですでに3分の2ほどの距離は進んでいたので、早く着きすぎるなと思っていたのだが、国境の町のせいか到着間近で検問が2回もあったためにいい具合に遅れてくれた。まだ、真っ暗であるが国境までの3キロを歩く。治安については心配していないのだが、野犬が怖い。案の定途中で3匹に取り囲まれた。睨みつけながら通り過ぎる。国境が開くのは5時30分。イミグレはすでに地元民の長蛇の列。外人は優先して別窓口で対応してくれるとのことで、本日(外人では)一番のりで国境を通過。まっさらなリストの一番上に記帳するのはなんだか気持ちが良い。出国して10mほどの川にかかる橋を渡るとそこはミャンマー。普通は国境緩衝地帯が何キロかあってそこをバスで移動するのだが、ここは歩いて渡れるので(国境)線を越えたという感覚を強く意識することが出来る。ミャンマーに着くと早速客引きから声がかかる。ヤンゴンまで15000チャットの声。即OK。ネットで調べた事前の情報通りの値段。8時30分に出発予定。丹念に交渉すればもう少し安い交通手段が見つかるかもしれないが、どのみち数十円の範囲。客引きの兄ちゃん(Mr.HTOO)がなかなか面白い男で彼から旅に必要な最低限のミャンマー語を習う。バスの出発まで2時間あるので8時に帰ると言い残して街を散策。町外れの朝市が活気があり結構良かった。 8時前に戻ればHTOOが待っていて客が集まったからすぐに出発だとのこと。バス乗り場までの移動はHTOOのバイクの後部座席。ノーヘル二人乗りで飛ばす飛ばす。「危ないって」というと、「ノープロブレム」と言いながら手放し運転まで披露してくれる始末。いや、だから普通に怖いって、、、。長い。あとはカット。結局ヤンゴンまで11時間かかった。
@=
(2019-03-11) ヤンゴン市内散策。二日後のパガン行きのバスのチケットを買う。4列シートは19000チャット。3列シートなら25000チャットらしい。定価なのかボラれているのかわからないが、3列シートを20000チャットなら買うと言ってみると、「そんな値段で売れるか!帰れ!」らしいので、じゃ帰ろうと「バイバイ」すると、「OK!20000チャット。」になった。適正価格がいくらかわからないが、9時間も乗って1500円だし、少々ボラれていても良しとする。宿にはミャンマーを動画で紹介するサイトを運営する23歳の若者がいた。「もう、我々は日本ではやっていけない。英語がITのどちらかで海外でも通用するようでないと先はない。」ガッツあふれる進歩的な考えで聞いていて気持ちが良い。まぁ、まだまだ日本がすぐに倒れることはないと思うけど、20年後には貧民国化するとの予測もあるし、ミャンマーもしかりだけど経済発展の只中にある国で活路を見出しておこうとする姿勢には感銘すら覚える。ミャンマーは驚くほど物価が安い。散々飲み食いしてもしれている。南国で三人で宴会。ちなみに23歳の若者(ボブと呼ぶ)は大正区在住。久しぶりに酔っ払ってしまった。
@=
(2019-03-13) 宿で朝食を取り、出かるまえにフロントにいた日本人らしき青年と話す。大学を卒業してミャンマーで配送システムのビジネスを起ち上げ中だそうな。こちらに来て思うのだが、若い人間はみんな優秀だなぁ。私なんかよりよっぽど英語ができるし、敬語と言うか話し方もしっかりしていて、考え方も合理的だ。日本の最近の若い人間ってあんまり元気がないのかなと思っていたけど、そんなことは全然なくて、優秀な人間はいち早く海外に目を向けているのだろうか?会社でも出来る人から辞めていくことが多いことを考えると、優秀な人間は(若い間の)給料の安い国内に見切りをつけているのかもしれない。昔みたいに年功序列で我慢して長年勤めていれば高給が約束されるご時世でないのは事実である。ただ、前日のボブは「大人が夢を見せてくれないから、俺達だけで夢を実現してやる」と自信家であるのに対し、今日の彼は「ミャンマーは難しい。フロンティアと言えば聞こえはいいが、要は辺境な訳で、辺境には辺境なりの人と仕事しかない」と非常に冷静である。さて、午前の涼しい間に昨日入れなかったシュエダゴン・パゴダに行く。期待していなかった割にはそれなりに良かった。ミャンマー人の信仰心と言うか信仰のスタイルが観察できる。遺跡自体はどうかな、正直すごいとも思えない。日本でも世界遺産(特に文化遺産)で価値があると思えるのは法隆寺くらい。かろうじて次点の姫路城までが見に行くに足る建造物だろうか。さて、夜行バスでバガンに向かう。世界三大仏教遺跡の一つである。そうそう、バスのチケットはボラれていなかったようだ。同乗していた方に聞く限り15ドルだったらしいので、どちらかと言えば少々安く買えていたようだ。
@=
 人だかりのヤンゴン商店街。おばちゃんの露店何処まで道を占拠してるんですか?ちょっとちょっとこの人だかりで何処を歩けばいいんですか?おいおい、こんなところになんで車が入ってくるんですか?いやぁ、いいなぁ。文句じゃないよ楽しいんだよ。昔のバンコクがこんな感じだったわぁ。
@=
人だかりのヤンゴン商店街。おばちゃんの露店何処まで道を占拠してるんですか?ちょっとちょっとこの人だかりで何処を歩けばいいんですか?おいおい、こんなところになんで車が入ってくるんですか?いやぁ、いいなぁ。文句じゃないよ楽しいんだよ。昔のバンコクがこんな感じだったわぁ。
@=
 6階建てのユートピアタワーからはヤンゴン市街が見渡せる。外人は誰も来ないし、隠れた名所と言えよう。首都とは言えまだまだ緑が多く、高層ビルも殆ど無い。そう考えるとバンコクのこの20年の発展はすごいものである。
@=
6階建てのユートピアタワーからはヤンゴン市街が見渡せる。外人は誰も来ないし、隠れた名所と言えよう。首都とは言えまだまだ緑が多く、高層ビルも殆ど無い。そう考えるとバンコクのこの20年の発展はすごいものである。
@=
(2019-03-14) バスは予定より少し遅れて6時30分頃バガンに到着。タクシーは宿のある街(たかが5キロ)まで20000チャットなどと言う。ヤンゴンだと10000チャットで20キロ以上走れるぞ。さすが観光地価格だ。大体郊外の長距離バス乗り場はたちの悪い奴らのたまり場なんだけど、柄が悪くない分だけまだマシな方か。しつこく交渉したわけではないが、14000チャットまでは値切ることが出来た。予約していた宿は朝食付き。荷物だけ先に預けた所、朝食を食べてもいいよと嬉しい申し出。しかも食べ放題で美味しい。観光は午前中が勝負なので自転車を借りて早速遺跡観光。バガンの仏教遺跡群は広大なエリアに林立している。炎天下の遺跡巡りは体力を消耗する。道がありやなしやの荒野に散在する誰も来ないような小さな遺跡を回るのは、スマホ(GPS付き地図)がないと不可能だ。樹海と同じですぐに自分がどこに居てどこに向かっているのかわからなくなる。12時に宿に戻ってチェックイン。ホコリだらけの体を洗い、服を洗濯すると昼寝。日中は人間が活動できる時間ではない。夕方ごろサンセットを見に行くと、小高い丘の上にはたくさんの観光客が集まっていた。バガンはいいところだ。まだまだ観光客は少ないし、カンボジアやラオスで失われた素朴と未開が残っている。物売りの子どもたちも擦れていないししつこくもない。観光という意味合いでもミャンマーは東南アジア最後のフロンティアに思う。ヤンゴンは20年前のタイ(バンコク)。バガンは20年前のカンボジア(シェムリアップ)に似ている。ラオスのルアンプラバーンも6、7年前までは良かったが、今はもう大挙して押し寄せる観光客に潰されてしまった。
@=
 この日は自転車だったのだが、人が通ればそこが道になっている感じ。スマホ(GPS付き地図)がないと絶対に行けない。灼熱地獄で死んじゃう。こんな踏み跡は地図にものってないし、スマホがあっても道には迷いまくり。
@=
この日は自転車だったのだが、人が通ればそこが道になっている感じ。スマホ(GPS付き地図)がないと絶対に行けない。灼熱地獄で死んじゃう。こんな踏み跡は地図にものってないし、スマホがあっても道には迷いまくり。
@=
(2019-03-15) 早朝、e-bike(電動バイク)を借りて、遺跡からの日の出を見に行く。昨日、目星をつけておいた登れる遺跡だったのだが、着いてみれば結構な数の先客あり。しかも、地元民が監視していて「登るな」とのことであった。残念。(無視して登ってるやつも居たけど。)朝食後、本格的に遺跡巡り。観光可能なのは11時くらいまで。それ以降は暑すぎて活動できない。 e-bikeは機動力が桁違い。どんな悪路だろうが気にせずに突き進む。バガンは広い。灌木の他何もない荒野をバイクで疾走するのは気持ちがいい。交通量も少ないし。馬車や牛車も行き交うのどかな道が多い。東南アジアの観光遺跡としては今ミャンマーが一番面白い。観光客はそれなりにいるけど個人旅行の西洋人中心で、中国人が何台ものバスで大挙して押し寄せるという俗化した観光地にはなっていない。土産物の売り子も主に女性や子供が手に持って「買って買って」と寄ってくるくらいの素朴なものだ。中国も昔は似たようなもので、25年前は東南アジア以下の最貧国と言っていい状況だったけど、今や周辺を中華化(属国化)すべく恐ろしい数の観光客を東南アジアにばらまいているから変わったものだ。さて、4時間走りまわったものの切りがない遺跡の多さである。大物もまだまだ残している。当初は2泊3日の予定であったが二日延泊することにする。見残しが多すぎるし、なによりこの街は楽しい。遺跡(廃墟)好きにはたまらない魅力。遺跡の中の村々も自然と調和していてなんとも私好み。涼しくなってきた頃合いで川辺に行ってみる。本日も素晴らしい夕日であった。
@=
 日の出は見れなかったけど、朝日を背景に気球群が見えた。これ、乗る予定だったんだけどなぁ。ここ数年でインフレしてるらしく、 500ドルとか言われると流石に敬遠。そこまで払うだけの価値は感じられないよ。
@=
日の出は見れなかったけど、朝日を背景に気球群が見えた。これ、乗る予定だったんだけどなぁ。ここ数年でインフレしてるらしく、 500ドルとか言われると流石に敬遠。そこまで払うだけの価値は感じられないよ。
@=
(2018-03-16) 夜明けとともに相棒(電動バイク)と遺跡巡り。誰も居ないとアテをつけていた日の出ポイントに向かえば先客が居た。しかもカップル。なんか悪いことしたかなぁ。きっと二人だけの朝日を期待していたに違いない。でも、こっちだってご来光独り占めだと思っていたんだから許しておくれ。さて、お前は何をしにバガンに行ったんだと問われたら困るので、大物遺跡(定番遺跡)を片付けてしまうことにする。まずは、シュエズィーゴン・パゴダ。ビルマでは一般的な金色のストゥーパ。金ピカで趣味が悪い。境内に続く参道にはお土産物屋さんがいっぱい。続いて、ティローミィンロー寺院。大きくて立派だけど装飾はほとんど残されていない。そして誰もが訪れるアーナンダ寺院。必見とか、ミャンマー観光で外せないとか書いてるけどそれほどのものかなぁ。四方に向かって四体の金色に輝く仏弟子の立像がある。最後にタビニュ寺院。高台の白亜に輝く大寺院。でも、装飾はないし、構造的な美しさもないため、芸術的な感動がない。結論、バガンは遺跡群。及び、遺跡を擁する風景区として優れているのである。個々の遺跡に魂を震わせるほどのものはない。なお、人のほとんどこない中小規模の遺跡に見どころがあるものが多い印象である。誰しもが自分だけのお気に入りの小さな仏塔を見つけることが出来るのではないだろうか。昼寝後、ほとんど廃墟とかしているエリアを探索。夕暮れの誰も居ない荒野に一人は少し怖いものがある。屋根に草の生える崩れかけた寺院にも仏像は安置してあり、仏様の眼差しには心の奥まで見透かされているような錯覚を覚える。寄り道しすぎて夕暮れ間近。走れメロス(相棒の名前)。本日の夕日ポイントまで疾走するんだ(安全運転やけどな)。ギリギリで本日も夕日を拝んで一日の終わり。
@=
 実はこの寺院は鍵がかかっていて、管理人に頼むと入れてもらえる。この像も昔からのもので管理人によるとブッダのママとの説明であった。「摩耶夫人のことだろ」って言うと、「おおっ、知ってるのか?」と驚かれた。「当然だ。俺は仏教徒だ。」と言って般若心経を唱えたらなんか知らんが高感度がアップしたようだ。
@=
実はこの寺院は鍵がかかっていて、管理人に頼むと入れてもらえる。この像も昔からのもので管理人によるとブッダのママとの説明であった。「摩耶夫人のことだろ」って言うと、「おおっ、知ってるのか?」と驚かれた。「当然だ。俺は仏教徒だ。」と言って般若心経を唱えたらなんか知らんが高感度がアップしたようだ。
@=
(2019-03-17) 4時半起床、、、できない。朝日は諦める。出国して一週間が経ちそろそろ疲れてくる頃。 6時過ぎに起きて朝食の後、本日の遺跡巡り開始。今日は相棒が変わって青い電動バイク。サンプラザと名付ける。取り残していた中物を狙うがこのクラスはありすぎてとても回りきれない。そもそも、遺跡巡りも少々飽きてきた。とりあえず遠方まで行ってしまって、少しづつ宿に向かうことにする。最初の半分崩れかけた遺跡が自由に登れて景色も素晴らしく、午前の涼しい風を受けて気持ち良かったためパゴダで朝寝(二度寝)と思っていたら腹痛に襲われる。ミャンマーの食事は辛くなくて概して美味しく(衛生面は相当悪そうだが)、お腹の調子も良かったので安心していたらここに来てやばいのが来た。選択肢は3つ。 (1)宿まで帰る。 (2)トイレを探す。 (3)野糞。道を少し外れれば荒野だし、(3)も十分な選択なのだが、安心していたため紙を持っていない。よって、(3)はない。なら、(1)だ。ただし、宿までは30分はかかる距離。運よくトイレが見つかれば(2)だ。神様、お願い、後30分は持ってください。走る走るサンプラザと俺。が、神は無慈悲だ。お腹はとても持ちそうにない。10分で限界。助けてアーナンダ。アーナンダ寺院に飛び込む。オフィス(寺務所?)のトイレを利用させてもらって事なきを得る。神は試練を与える。仏は慈愛に満ちて寛容だ。無意涅槃。阿難尊者ありがとうございました。などと、どうでもいいことを書いていたら長くなってしまった。この後、村のお祭り(七五三みたいなものかなぁ)を見たり、廃墟を彷徨ったり、パゴダに登ったり、夕日に照らされたりしてたら本日も終わり。
@=
(2019-03-18) 午前中に近場を散歩。宿に戻って休憩していると外から爆音が轟く。昨日の稚児行列っぽいのもそうなんだろうけど、どうやら今は何らかのお祭りであるようだ。とりあえず表に出てみると、今度は象まで行列に参加していた。 30cmの至近距離で見る象は相当な迫力。午後はマンダレーに移動。ミャンマー第二の都市。着いたのは夕方で晩飯以外に特に出かけることもなし。それそろ帰りのことを考えないといけない。調べてみると3月は飛行機代が高い。おそらく学生がこぞって帰国するんだろう。4月になると半額以下にまで下がるのだが、流石に3月末4月初めの日本が一番綺麗な桜の季節を国外で過ごそうとは思わない。 2週間では少し物足りないが23日のチケットを手配して帰国することにする。
@=
(2019-03-19) マンダレー観光。王宮とパゴダを何個か、それとマンダレーヒルを訪れる。感想としてはどれもいまいち。まぁ、所詮観光地。大したことないものがほとんどだ。バガンのほうが何倍も素晴らしい。マンダレーにはもう一つウーベイン橋という名所があるんだけど、これはパスしてしまった。ミャンマーにはまた来ることがあるだろうし、辺境を旅するにはマンダレーにも寄らざるを得ないだろう。その時のついででいいやと思う。私にはやはり田舎の旅のほうが性に合っているようだ。ただ、都会にもいいところがあって、それは食事が美味しいことと、洋菓子が手に入ること。特に後者は大きい。今の間にとドーナツやプディングを堪能しておく。明日はインレー湖に向かう。
@=
(2019-03-20) 朝食後すぐにバス。7時20分。揺られること9時間。16時30分にインレー湖北部のニャウンシェに到着。約7時間と聞いていたが大幅に遅れたようだ。この街はいい雰囲気だ。田舎すぎず都会すぎない。まぁ、普通に考えれば田舎であろうが、ど田舎と言うほどではない。夕暮れの町並みがなんともいい感じである。私は大変後悔している。なぜもっと早くここに来なかったのであろう。マンダレーなど行ってる場合ではなかった。23日帰国のためには2泊しか出来ない。痛恨である。街を散策後、夕食に贅沢をする。普段は一食1000チャットから1500チャット。ちょっと贅沢して3000チャットくらいなのだが、今日は10000チャットのミャンマー御膳。うまー。やっぱ、お金を払うとうまいな。10000チャットとかミャンマー人の月給の1/10だよ。物価感覚が現地化してきてるからとんでもなく高価に感じる。本日の9時間乗ったバス(ホテルまでの送迎付きで300キロ走破)でも15000チャットなので、今日の夕食は感覚的には10000円。でも、日本で10000円を出したらもっとうまいものが食えるかなぁ。まぁ、10000チャットって言っても700円ちょいなんだけどさ。
@=
(2019-03-21) 夜明け前の散歩で朝日を浴びた後、インレー湖へのボートトリップに出発。うん、まぁまぁ面白いんじゃないかな。風を切って走るボートは爽快で気持ちが良いし、湖上生活者の伝統的な生活を見ることができる。水上は涼しいし衛生的。丘よりもよほど生活しやすそうに見える。生産は漁労と水耕栽培、洗濯炊事風呂と水回りはこれ全て家の前(というか家の下?)。パゴダも水上(中洲?)で宗教活動も陸に上がる必要がない。学校や警察・郵便局も当然ある。実際に湖上で全て完結しているため、大人になるまで陸に上がったことのないやつもいるんじゃないかと思ってしまう。水路は迷路のようで水路の間はこれまた迷路のように橋で繋がっている。ただ、湖上生活者はベトナムでもカンボジアでも見てるからなぁ。驚きはさほどないもののインレー湖自体はいいところだ。本当にマンダレーなんかに行かず、もっと早くここに来ていればよかった。周囲は魅力的な山に囲まれているので、サイクリングとトレッキングをやり残している。明後日帰国の関係上、明日の朝にはヤンゴンに向かわなければならない。ミャンマー東部の山岳地帯はラオス・タイ北部・雲南省と接続している。これら山岳文化圏は概して同質で人は寛容・親切、気候も大変マイルドである。インレー湖周辺も標高1000mはあり、南国とはいえ言ってみれば夏の軽井沢状態である。次は水量の多い時期に来て、やり残したことをするとしよう。夕方街東部の丘まで夕日を見に行く。が、こちらは大したことがなかった。残念。
@=
 おぉ、広い、開放感抜群。来てよかった。かの後漢王朝の建国者偽劉秀も言っている。「仕官するなら執金吾、妻と行くならインレー湖。」(就職するならやっぱ警察官がいいし、たまの休みには妻とインレー湖に行きたいな。)
@=
おぉ、広い、開放感抜群。来てよかった。かの後漢王朝の建国者偽劉秀も言っている。「仕官するなら執金吾、妻と行くならインレー湖。」(就職するならやっぱ警察官がいいし、たまの休みには妻とインレー湖に行きたいな。)
@=
(2019-03-22) 一日中乗り物。 7:30に宿送迎の軽トラ。 8:15に長距離VIPバスに乗り換え。 VIPだけど車内に蚊はいっぱいいる。まぁ、それでもスタンダードよりマシ。少々の虫は平気になっているので快適である。山岳地帯はくねくね道。ラオスと同じで隧道なんぞ一つもない。大陸は広い。平原に降りれば荒野とジャングルがどこまでも続いている。開発し放題である。橋も隧道もいらないし、建設コストは安いはずなんだけどほとんど手付かず。富は偏在して格差はそう簡単には埋まらないものである。道路工事は至るところでやっていて、土道を舗装路に置き換えようとしているようだ。全体的にはラオスよりわずかに発展している感じだけど、ラオス北部は中国資本による大規模、かつ、強引すぎる開発(高速道路と新幹線工事)で、すっかり様変わりしているので局所的にはミャンマーのほうが牧歌的に感じる。なお、ラオス内のメコン川にはやはり中国資本でダムを作るそうなので、観光の目玉であったメコン川下りも出来なくなってしまった模様。 20:00になってヤンゴンのバスターミナル着。タクシーで渋滞の中1時間。 21:00にやっと本日の宿に到着。空港まで徒歩10分の距離。隣が池らしく半端ない蚊がいる。久しぶりに蚊帳のある宿であった。そういえば、昔はどこの宿でも蚊帳があったよなぁ。
@=
 サービスエリア(単なる道脇のレストランだけど)で昼食。ミャンマー飯は私の口に合う。辛くないのがいい。結局腹痛もバガンでの一時的なものだけで、至って快食快便である。冷たいジュースも移動前や移動中の食事も控える必要がなかった。
@=
サービスエリア(単なる道脇のレストランだけど)で昼食。ミャンマー飯は私の口に合う。辛くないのがいい。結局腹痛もバガンでの一時的なものだけで、至って快食快便である。冷たいジュースも移動前や移動中の食事も控える必要がなかった。
@=
(2019-03-23) 早朝、歩いて空港に向かう。空港って国の表玄関なのに、道端は投げ捨てられたゴミだらけ。まぁ、ミャンマー標準ではある。昔は中国がひどかったけど、今はすっかり綺麗になったから、アジアのゴミ王国はラオスとミャンマーだな。空港についてびっくり。こちらは驚くほどモダンで綺麗な建物であった。空港内の店舗もおしゃれそのもの。客はほとんどいないけど、、、。飛行時間は1時間とかからずにバンコク着。行きは陸路で8+12=20時間、二日がかりで旅費も変わらずだから、陸路のメリットはロマン以外には何もない。トランジットで4時間の時間つぶし、バンコクの街に出る気はない。思えば日本を出国した時もバンコク午後着、その日の夜行バスで国境へ行ってしまったので、タイには18時間いなかったことになる。まぁ、タイなんてそれこそいつでも来れるしうるさいバンコクは嫌いである。空港内は、、、半分は中国人か?案内板も離発着の電光掲示板もタイ語と英語と中国語。 20年前、日本語であった部分はすべて中国語に入れ替わっていますな。かって旅の東洋人の9割は日本人であったが今は9割は中国人かな。 20年というのはすっかり社会を変えるに足る時間である。 2週間と短い時間であったが第一次ミャンマー旅行は一旦おしまい。桜咲く日本に帰還する。
@=
旅の総括。ミャンマーは旅のしやすい国であった。有名所しか周っていないというのもあるが、それを差し引いてもイージーな国ではないだろうか。旅の不安や緊張といったものを感じることはほとんどなく、ミャンマー人も大半は心穏やかで親切な南国の民であった。事前情報何もなしでの出国であったが、不自由することがなかったことは驚きである。それには、やはり今回の旅で初めて持参したスマホの力も大きい。正直、スマホがあればいつどこでどうにだって出来るのではないかと思うほどの威力である。様々なシーンで活躍してくれたが個人的に役に立ったと思うアプリを3つあげたいと思う。第三位、タクシー配車アプリ。未知の国での移動は大変である。どこでもタクシーを呼べるのはともかく、適正価格を事前に知れるというのが大きかった。第二位、宿泊予約アプリ。翌日や当日であっても、空きのある宿をその場で検索・予約できてしかも割引がある。夜中にバス停に放り出されて、今晩の宿をどうしようと不安になることがない。第一位、地図アプリ。ダントツの一位である。自分が今どこにいてどちらに向かえばいいのか?これがわかることは旅の不安と難易度を8割削減してくれる。正直、GPS機能付き地図さえあれば他はなくても一向に構わないくらいである。今や私はスマホの便利さを知ってしまった。旅の幅は広がりもしたし、そして、同時に狭まりもしたと思う。もう、以前の旅のスタイルに戻ることは出来ないだろう。間違いなく旅はより深く、よりチャレンジングになったが、失ったものも大きかったかもしれない。
@=
(2019-04-10) アモイ航空ナメてました。ごめんなさいです。さて、本日出国である。今回は800キロの歩き、イベリア半島を横断する。空路でパリに入り、スペインとの国境まではバスで移動、そこからが徒歩。最安値のアモイ航空を利用。アモイ経由で3時間+12時間(アモイで4時間待機)。関空からパリまで5万円もしない安チケットだし、期待はしていなかった。関空にてチェックイン。荷物はアモイで載せ替えるが、人間は一度入国してくれと言われる。飛行機の乗り換えで人間だけ経由地に入国して出国するとか聞いたことないぞ。正しく荷物がパリまで届くのかいきなり不安である。しかも出発時間が50分遅れる。出入国には結構時間がかかるだけに少し嫌な予感がする。大体中国は入国も出国も面倒くさい。が、乗ってびっくり、機体は綺麗だし、機内食は美味しいし、各座席は液晶付きでゲームまでできるし、クラスの高い新型期でした。客室乗務員も親切丁寧。うん、アモイ航空、なかなか乗る機会はないけどおすすめです。再びパリに行く機会があるなら是非ともアモイ航空を重ねて利用してみたいと思う。 LCCばかり乗っていたから普通の飛行機が(エコノミーでも)こんなに快適だとは忘れていました。アモイ->パリなんて機内食は夕食、朝食(夕食並みにがっつり)と2回でるし、飲み物はアルコールも含めて飲み放題だし、LCC並に安い非LCCとして大変お得です。
@=
(2019-04-11) パリのことナメてました。ごめんなさいです。所詮大都市でしょ。あんまり興味ないなぁ。まぁ一泊くらいはするか、、、くらいの気持ちだったんだけど、、、。いやぁ、町並みの美しいこと、何かにつけてかっこつけている。しかも、それがスベっていない、普通にキマっているのである。あれだけゴテゴテ彫像やらレリーフやら装飾すれば悪趣味になりかねないのに、もう全く調和しているから不思議である。さすがは観光客世界一、花の都パリである。残念ながら日本でパリに勝てる魅力のある都市は思いつかない。京都なんて全然である。東山の方など一部はいいが、京都駅周辺は普通の住宅街だし、街全体の統一感が全く違う。高さの揃った建物、建材は全て大理石(見た目は凝灰岩だけど)で街が白銀に輝いている。所詮世界遺産でしょ。大抵は大したことないんだよなぁ。ノートルダム大聖堂。まぁ名前だけは有名だよね。どれどれ、、、。あぁ、コレ凄いわ。よう、こんなもん作ったなぁ。、、、と人類の偉大さを感じることができました。この感動は20年ぶり。法隆寺と在りし日のアンコールワット以来である。ノートルダム、ルーブル美術館、凱旋門、モンマルトル、、、とりあえず歩けるだけ歩いてみたけれど、小道も含めて全ての通りが魅惑的なので全く堪能しきれない。おフランス。いいところです。ナメてました。ごめんなさい。最後に、フランス人は信号を守らない。東南アジア並。フランス人は結構ゴミを投げ捨てる。なんで、それなりにゴミが落ちている。東南アジア並。
@=
(2019-04-12) 地下鉄一日券を買って、メジャーどころを回る。残してるのは、オペラ座とエッフェル塔とモンパルナス周辺。ベルサイユ宮殿は遠いため残念ながらまたの機会とする。相変わらず建物は一々カッコいい。フランス人は何か作れば芸術的にしないと気がすまないようだ。エッフェル塔もただの鉄塔ではなく、装飾性もあるし見ていて美しい。東京タワーとは受ける雰囲気が全く違う。美しい町並みも見飽きたところでブローニュの森へ。あぁ、いいなぁ。市内のすぐ近くにこれだけの森があるなんて素晴らしい。正直しばらくパリっ子になりたくなってしまった。しかし、なんせ物価が高い。ランチだって最低でも15ユーロはする。とはいえ、全くフレンチを食べないというのももったいないので、ネットで検索した「安い うまい 食堂」に行ってみる。前菜とメインとデザートのセットで20ユーロ。安いかぁ?さて味は、、、うーん、微妙、、、。まずくはないがうまいほどでもない。日本で2500円出せばコレよりうまいフレンチが食べられる。フレンチに限定しなければ、大阪で1000円出せばもっとうまいものは食える。やっぱ、本当に美味しいものを食べるにはお金を払わないとダメなんだろうな。でも、先は長いので一食に2000円も3000円もかけてられないしなぁ。日が暮れるまでパリを堪能して、夜行バスでバイヨンヌへ向かう。
@=
(2019-04-13) パリ発の夜行バスは朝6時にサン・セバスティアン(スペイン)で乗り換え、 2時間待機して9時にバイヨンヌ着。もちろんバイヨンヌはフランス。フランスで乗ってスペインで乗り換えてフランスに着く。国境を超えているという感覚は全くない。ECは一つだというのがよくわかる。 3時間ほどあるのでバイヨンヌを軽く観光。週末マーケットであったのか旧市街は人手が多く活況であった。フランスの片田舎なのにバイヨンヌの聖堂も立派なもので、ヨーロッパ文明の底の深さを感じる。鉄道でサン=ジャン=ピエド=ポルへ。季節も穏やかで気持ちのいい景色を見ながらの一時間。しかし、ヨーロッパはいいところいあるなぁ。空気も水も綺麗で四季があり花にあふれている。ちょっと、アフリカや東南アジアに謝れ!と言う感じである。彼らには夏しかないんやぞ。そら、こんないいところにあれば文明も発達するわと思う。日本も風景という意味では美しい国だと思うけど、ヨーロッパには負けずとも勝てないかもしれん。フランス。好きになりました。もちろん人もみんな親切で困っていれば助けてくれる。旅人に優しいです。物価は高いけど、、、。さぁ、明日からカミーノだ。
@=
(2019-04-14) カミーノ1日目。昨日晴天から打って変わって、曇り空に時折小雨の天気。大雨でないだけ良しとする。初日が一番きついと言われる1250mの上りなのだが、普段山登りしているので楽勝であった。荷物は平均より多め。多分11キロぐらい。ものすごい荷物を担いでいる人もいるし、本当に小さなリュックだけの人もいる。スタートが7時30分と予定より30分ばかり遅れたが、朝食が7時からのため平均的なスタート時間。しかし男も女もでかいなぁ。小人になった気分である。身長が1割増な分、歩くスピードも私より1割増。大丈夫かいなと少し不安になる。景色は抜群。これで晴れていたら最高だったろうけど、天気だけは仕方がない。カミーノ。少しばかりのお金と時間があるならやらないと人生の損だと思うくらいの風景である。今までヨーロッパを敬遠していたのはもったいなかった。景色、文化、建築物、やはり洗練されている。カミーノの季節は7月がピークらしいけど4月も結構歩いてます。200人くらいはいそう。はじめは談笑しながら元気だった人たちも10時をすぎる頃には無口になる。いつの間にやら私のほうがペースが早くなり、12時になるころのは先頭近くを歩いていたようで、前も後ろも誰もいない森を歩く。本日のアルベルゲも5人目くらいの到着であった。
@=
(2019-04-15) カミーノ2日目。晴れのち曇り。朝食はパン・ハム数切れ・チーズ数切れ・コーヒーで5ユーロ。高いなぁ。昨日の夕食も12ユーロで豚肉3切れとパスタ。ヨーロッパ物価が高いよ。さて、7時30分に行動開始。高原の朝は太陽も優しく歩くのが苦にならない。多分私は歩くのが相当早いほうだと思う。10時過ぎには先頭に立ったのか、前後誰もいなくなった。ヨーロッパの森を一人スピードハイクをしていると気分は馳夫である。二日目の一般的な行程は25キロなのだが、13時過ぎには到着してしまったのでもうしばらく歩くことにする。 14時過ぎ、流石に疲れてきたので、近くのアルベルゲにチェックイン。 4万歩。おそらく30キロちょいといったところ。アップダウンの山道で疲れた。 Zabaldikaのアルベルゲは教会そのものというか教会の一部。宿泊費は無料。心ばかりの寄付をするルールなので20ユーロを募金箱に投入。朝食夕食つきだしこのくらいは寄付しないとバチが当たるような気がする。食事の前に教会でお祈り。カトリックの儀式を垣間見ることができて興味深かった。
@=
(2019-04-16) カミーノ3日目。快晴。昨夕の雷鳴から始まった雨は7時になる頃には止んでいた。山歩きは終わって、基本、舗装路かか牧場の畦道といた感じ。いかにもヨーロッパってな感じの風景が続く。「わぁ、北海道みたい。」ヨーロッパを見る前に北海道を3度も歩き旅しているので普通の感想とは逆である。いい天気で暑いくらい。12時を過ぎる頃から巡礼者がぐっと増える。先行グループの末尾に追いついてしまったようだ。風景が綺麗とか同じことを書いても仕方がないので書くことは特になし。一日歩いているだけである。そんなにイベントばかりがあるわけではない。昨日に続き14時過ぎにはチェックイン。大体一日6-7時間30キロ前後を目安にする。歩くだけならもっと歩けるが、洗濯することを考えると、3時か4時には宿にチェックインしている必要がある。また、人気の宿は3時を過ぎる頃には満室になるため2時過ぎのチェックインがベスト。本当は予約をしているといいんだけどね。歩けるだけ歩くでやっている以上予約は不可能ですわ。夕食は14ユーロでバイキング形式であった。最高。歩き旅はとにかく腹が減る。みるみるお腹の肉が減っていくのがわかる。このままではゴールに着く頃には干からびかねない。大皿に野菜山盛り。大皿に煮込みスープ(具ばかりでスープ少なめ)大量。メインのチキンロースト。よそってから欲張りすぎたかなと反省する。普段の2食分はある。が、程なく完食。お替りを二回しておやつも二皿食べた。余裕であった。
@=
(2019-04-17) カミーノ4日目。曇。7時過ぎに行動開始。景色を堪能するには晴れがいいけど、こと歩くという意味では曇りのほうがありがたい。いつ降り出してもおかしくなさそうな厚い雲のためずっと不安であったがなんとか天気は持ってくれる。本日は山道は少なく(アップダウンは結構あるけど)街道歩きがメインである。北海道を歩いていた時を思い出す。道東の風景と本当に似ている。ただ、北海道では道路を歩くことが多かったけど、こちらは巡礼路なので土道か石畳である分恵まれている。 Villamayor de Monjardinのアルベルゲに宿泊。
@=
(2019-04-18) カミーノ5日目。曇のち雨のち曇。どす黒い雲。見るからに降りそうな天気。予報でも今日は雨。普段であれば早々に連泊を決め込んで休養日にするところだが、巡礼者に「雨だから行かない」はない。そもそもアルベルゲ(巡礼宿)は8時には追い出される。朝食後、7時過ぎ、ザックにカバーをかけて出発。最初の街Los Arcosまでは12キロ。10時に着くがここで雨。 30分程度雨宿りをして小雨になったところで出発。 7キロ歩いてSansolにつく。雨がひどいようならLos Arcos、ひどくなくとも雨ならSansolまでと考えていたのだが、なんとも中途半端な小雨。こう言うのが一番困る。次の街まで11キロ。雨なら諦めも尽くし、晴れなら頑張れるのだが、小雨。今日は修行だと割り切って行ってしまうことにする。女神は決断するものに微笑む。というわけでもないだろうが、程なく雨は止み天気は回復傾向。雨のため短めで切り上げる人が多かったのだろう。前後誰もいない広い広い丘陵を一人歩く。最高。本日はViana泊。イースター(日本のGWみたいな連休らしい)のため店がどこもしまっている。食料の調達に困る。少々値は張るがレストランで巡礼者セットを食べる(パスタとポーク)。
@=
(2019-04-19) カミーノ6日目。午前雨、午後晴。 7時出発。雨である。風が強い。本日は修行モード。心の鍛錬が5割、体の鍛錬が4割、観光1割と言ったところである。雨がひどいようなら10キロ先のLogrono、予定ではそこからさらに13キロ先のNavarreteまで行くことにする。 Vianaを出て1時間、ザックが水を吸ってどんどん肩に食い込む。何が悲しゅうて遠いスペインくんだりまで来て雨の中行軍しているのか?楽しいと思える時間など1秒たりともない。観光1割ないですな。 Logronoのカフェで遅めの朝ごはん。カロリーは偉大だ。折れそうになっていた心に活が入る。雨も上がったようだ。よし、予定通りNavarreteまで行くことにする。昼前に到着。が、アルベルゲ満室。近場(ヨーロッパ)の人間はカミーノを一度にやらずに分割してやる人も多いらしい。イースターは予約しておかないと宿がないかもしれないよ、、、との情報は得ていた。只今カミーノは局時的に超ハイシーズンである。 4キロ先のSotes。アルベルゲ満室。2キロ先のVentosa。アルベルゲ満室。 10キロ先のNajeraまでは流石に遠くて行く気がしない。そもそも行っても満室の可能性高し。野宿やむなし。教会は8時に閉まるため、屋根のある玄関付近にて寝袋を広げる。「Hey! Go my home. 今夜のお家は教会だ!」今回の旅で初めての野宿。46のオッサンがする旅じゃないな。願わくば野宿はコレが最初にして最後であってほしい。
@=
(2019-04-20) カミーノ7日目。晴れ。一睡もできないかと思いきや、意外と快適で深く眠れた。時を知らせる教会の鐘が大音響で鳴るのだが、11時から2時までは記憶にない。 3時以降は寒くて眠れず。寝袋の中で夜明けまで耐えるのみ。 6時に起きて6時30分には出発。13時までに30キロ先のSo Domingoに着くようハイペースで歩く。 So Domingoのアルベルゲは220人が泊まれる大規模な宿泊施設。かつ、13時までに着けばさすがに泊まれるだろうとの見込み。2日連続野宿とか嫌である。風景は北海道と同じ。山の頂には雪。菜の花畑に小麦畑の青と綺麗である。、、、が、心が不安でいっぱいなので純粋に楽しめない。ハイペースに悲鳴を上げる足の要望を無視して今日は酷使する。最悪の場合(今日も野宿)のリカバリプランも考えておく必要がある。杞憂であった。急いだかいあって宿は満室ではなかった。安堵する。相当無理したため、靴下が一足ダメになってしまった。足も今更ながらに靴擦れ。
@=
(2019-04-21) カミーノ8日目。曇時々雨。 2日に1度は雨が降るようだ。 7、8月は晴天率7割以上らしいが、ハイシーズンで混むことを考えると今の時期のほうがいい気がする。とはいえ、例年なら終わっているはずのイースターが今年は4月であるため、今日も人がいっぱい。 20キロ歩いただけで目的地のBeloradoに着く。まだ午前中だが、今日はここまで。 13時に開くアルベルゲで並ぶ。私は7番目。19人まで泊まれるらしいので本日の寝床は確保できた。もう少し歩きたいが控える。野宿を避けるためには仕方がない。次の街で泊まれる保証がない。アルベルゲにて70歳の(見た目は55歳の)ご老人に出会う。今日で10日目というから標準ペースより速い。聞けばお遍路を6周やっており、カミーノなんて全く楽勝とのお発言である。確かにカミーノは楽である。宿は適度な間隔であるし、アップダウンもゴルフ場程度。山登りほどではない。それでも普通の人からしたら結構ハードなはずである。足を引きずっている人も多いし、宿に着く頃には疲れ切っている人が半数だ。そんなカミーノを800キロで終えるかと思えば、その後別のカミーノをするそうである。今回私が歩いているのはフランス人の道と呼ばれるもの。ご老公はサンチアゴに着いたあとリスボンに移動して、リスボンからポルトガル人の道を歩いて再びサンチアゴまでカミーノ。その後、フランスを再訪してトゥールーズの道で三度カミーノ。一度日本に帰って夏にはイギリス人の道で4度カミーノだそうである。 70歳にしてこの体力。大いに見習うべきである。
@=
(2019-04-22) カミーノ9日目。曇時々晴。 6時30分出発。スペインは明日まで休みらしいので、本日は30キロ弱、13時にはアルベルゲに着くようにする。体力的には楽勝でAtapuercaに到着。
@=
(2019-04-23) カミーノ10日目。雨。夜更けに降っていた雨は明け方には止んでいた。ただし、いつまた降り出してもおかしくはない天気。予報でも雨。 6時40分。暗いうちから歩き始める。 1時間弱で峠を越える。峠と言ってもなだらかなもの。ピレネーやアルプスは急峻だが、スペインの山々は丘の連続と言った感じで穏やかである。峠越えとほぼ同時に夜明け。視界に入った広大なメセタに圧倒される。自分の目を疑うほどの広さ。北海道、、、小さいですわ。そりゃ、メセタの面積だけで日本より広いんだから当たり前だけどさ。延々と広がる小麦畑と牧場、丘陵に連なる風力発電のための風車、風車、風車。広いだけならウィグルの砂漠やチベットの草原も広かったけど、点在する街と風にそよぐ小麦畑という人の手が入った自然(ある意味公園的)でここまで広いのは感動的。晴れてりゃなぁ、、、と思いながら歩いていたらとうとう雨が降り出した。林も建物もない荒野のど真ん中。最悪のタイミング。横殴りの風に大粒の雨。ズボンも靴もずぶ濡れ。本日の気温は予報では最低1度から最高8度。9時前の段階では5度くらいか。濡れたズボンが脚に張り付き、強風に煽られてどんどん体温が奪われる。凍りそうだ。楽しくない、、、というより身の危険すら感じる。やむを得ない。走る。走れば少しは温まるし街までは30分程度だ。走れば10分だろう。街に着く頃、雨が上がる。Burgosはこの地方では一番の大都市。世界遺産の大聖堂も立派なものだ。折れた心をカロリー補給で立て直して次の街へ。町外れ、雨宿りができなくなった時点で再び雨。嫌がらせのような天気である。 10キロ歩いて気力が萎えた。Tardajosで14時にチェックイン。手はかじかんで動かないし、足も凍って感覚がない。予報では今週中は最低気温1度。日本だと真冬並。しかも毎日雨。寒すぎるぞ。
@=
(2019-04-24) カミーノ11日目。雨。今日の同室はねぼすけが多いのか6時30分になっても誰も起きず。 7時前薄明るくなる頃にパッキング開始。出発は7時10分。雨は降っていないが、予報では雨。ザックカバーにレインコートを上下ともに着込む。昨日までは下半身は濡れてもいいやと思っていたが、気温数度に強風が重なれば耐えられるものではない。街を過ぎ荒野に入る頃雨が降り始める。逃げ場がない状態での仕打ち。神様はやはり意地悪だ。湿った冷たい風が吹くと雨が降り始める。即ち、雨、風、寒さはセットでやってくる。 10キロ歩いて谷間の街Hornillos del Caminoに到着。朝食を取っていないため、とにかくカロリーが足りない。懐のカステラを取り出す。が、雨に濡れた手がかじかんで動かない。補給を諦めて進む。この天気で先を目指していいものかと不安になっていたのだが、とりあえず進むと町外れで引き返してくる人がいる。どうやら私と目的地が同じらしい。一人なら無理でも二人なら行けるだろうということで連れ立って進む。イングランド人のリチャード、銀行を退職したと言っていたから60歳過ぎだろう。私とペースが変わらない驚きの体力の持ち主である。上り坂も一向にスピードダウンしない。さて、進む決断をしたものの本当の試練はここからであった。とにかく風が強い。遮るものの何もない丘は見渡す限り小麦畑である。どうも雨が白く見える。雪が混じってんじゃないかと思っていると案の定ミゾレになり、 30分ばかり進んだ頃には本格的な吹雪となった。雪が水平に飛んでいく。風上となる左腕には雪が張り付き、あまりの冷たさに上腕がしびれてくる。気温は、、、氷点下、、、じゃないか?リチャードのザックにも雪が積もっている。やっとのことで10キロ2時間を耐え忍び、少し下ってHontanasの街に到着。ようやく雪は雨に変わった。街の気温計は3度。やはり道中は0度近かったようだ。この先も泥田のようなぬかるみ道、続く強風と災難はやまなかったが、雪の中を進んだ2時間に比べればなんでもない。13時に目的地のCastrojerizに到着。熱いシャワーを浴びてようやく手が動かせるようになった。写真?撮ってねーよ。てか、そんな余裕なかったわ。今日の私は昨日の私よりも幾分強くなった気がする。リチャードは今日をして「チャレンジングな一日」と称していた。正にそのとおり。さて、本日宿泊したアルベルゲは韓国人に人気があるのか同室8名のうち私以外は全員韓国人。ちなみにカミーノをしている韓国人は多い。10人のうち2、3人はアジア人。そのうち9割は韓国人。残り1割が台湾人で、日本人や中国人、香港、シンガポール出身者と出会うのは稀である。 1週間に1人会うかどうか。年間30万人がカミーノをやるそうだから韓国人だけで5、6万人はいそうである。
@=
(2019-04-25) カミーノ12日目。雨後晴後急変する天気。 6時起床、7時出発。出発時点から雨。当たらないと言われるスペインの天気予報だが、嬉しくないことに当たっている。町外れで一度止んだのだが、丘を超え小麦畑の平原に入った頃から雨。「かかってこいやぁ。神様のバカヤロー。」と心の中の呪詛が届いたのか、猛烈な向かい風。台風並。顔に当たる雨が痛い。「これ雨じゃなくてアラレじゃないのか?」と思っていたら、レインコートの前面が溶けかけたかき氷が張り付いたかのような状態に。少なくともミゾレではあるようだ。エライ目に会いながら次の丘を越えると教会があり温かいコーヒーをサービスしてくれた。バカみたいに砂糖を入れて飲む。生き返るわぁ。小銭を寄付して雨が止んだ頃に出発。みるみるうちに天気は回復。風が強いからなぁ。本当に台風並。雲が猛烈な勢いで流されていくので天気の移り変わりが予測不可能。 9時頃から11時頃までの2時間ばかりは比較的晴れが続いていたのだが、その後は曇、痛いと思えばアラレ、もちろん雨もと言った具合に15分おきに大きく天気が変わる。 14時半。程よく疲れてきたのでのVillarmentero de Camposのアルベルゲにチェックイン。スペインの天気。慣れましたわ。とりあえずレインコートは常に着ておいたほうが良い。 4月はまだまだ寒いしウィンドブレーカー代わりにもなる。
@=
(2019-04-26) カミーノ13日目。晴。三日間の修行は終わった。待望の晴である。7時出発。靴が濡れていないだけで快適度倍増。荷物も心なしか軽く感じる。実際に濡れたザックが乾いた分軽いはずだ。しかしながら道が単調。道路沿いの道が多く、ハイキングとも言い難い。景色は北海道と変わらず。歩けるだけ歩こうと考えていたが、左足首の古傷(捻挫)が痛みだして、30キロ時点でギブアップ。 15時にTerradilos de Los Templariosにてアルベルゲにチェックイン。足首がまわらない。明日までに治るといいんだけど。
@=
(2019-04-27) カミーノ14日目。晴。昨日まで続いていた強い向かい風もやみ、思い描いていたスペインの気候。日中は暑いくらいである。左足首は継続して痛かったものの無視して歩いていたら痛くなくなった。治ったのか、麻痺しただけなのか?最初は感動したメセタの広さも5日も続くと退屈なだけ。延々と続く小麦畑に嫌気が指す。 35キロ歩いて15時頃、El Burgo Raneroのアルベルゲに到着。この3日で100キロ以上歩いた。「早くメセタを抜けたい!」それだけである。
@=
(2019-04-28) カミーノ15日目。霧後晴。 10時まで霧。視界は100m程度。50mを越えると影しかわからない。見るほどの景色もないし特に惜しいとも思わない。涼しくてよろしい。霧が晴れると案の定見飽きた小麦畑。代わり映えのしない風景にはうんざりする。 7時から歩き始めて9時間。レオンの街に到着。長かったメセタもここで終わり。明日からはまた山岳地帯だと思うと嬉しい。正直ブルゴスからレオンまではつまらなかった。以前カミーノをしないと人生の損などと書いたような気もするが、美しい風景に心躍るのは最初の一週間だけである。全部歩くというのは意地以外の何物でもない。
@=
(2019-04-29) カミーノ16日目。晴。 7時起床。下痢。ずっと便秘気味だったのだが昨日牛乳を1l飲んだらお腹に来たようだ。リットル単位でしか売ってないんだよなぁ。しかも100円しない。料理は高いが素材は安い。 8時にアルベルゲは追い出されるのだが、レオン大聖堂が9時半にならないと開かないので、9時過ぎまでアルベルゲの中庭で待機。普段だと7時には出発している。手持ち無沙汰の2時間半がもったいなくてよっぽど無視して行ってしまおうかとも思ったが、世界一とも言われるステンドグラスが素晴らしいらしいので、これはやはりはずせない。開館即入場。うん、こりゃ凄いですわ。見る価値ありの世界遺産です。ノートルダムに続き「ようこんなモノ作ったなぁ」である。個人的には、ヨーロッパはやっぱりチョット退屈なんで、正直、旅行としてはアジアの途上国の方が面白いと思うけど、洗練された文化・芸術と言った面ではやはり群を抜いていますね。結局、1時間半も滞在して、11時頃出発。しばらくは退屈な街歩きである。 7キロ進んで北の道と南の道への分岐。 20キロ先で再び合流するので本質的な差はないが、迷わず南の道を選択。本道は北の道だが国道沿いである。巡礼者用の側道はあるであろうが気が乗らない。それに引き換え少し遠回りになるが代替ルートである南の道はどう見ても田舎道である。分岐に入ってすぐに左足小指に激痛。水ぶくれが潰れてしまった。直径1.5センチ。指の腹側は全て水ぶくれと言っていいくらいのひどい状態だったのだがとうとう破れたようだ。ティッシュと絆創膏でテーピングする。足の小指なんて歩くのになんの役にも立っていないように思うのに、痛むとわかる重要さ。一歩一歩が痛いが痛みなんて結構すぐに慣れる(麻痺する)。 13キロ歩いてVilar Mazarifeのアルベルゲにチェックイン。 7ユーロの公営アルベルゲにしては大変綺麗で居心地がよく嬉しい。本日、朝5度であった気温は12時には27度。夏日である。暑い暑い。つい数日前雪の中を歩いていただけに変な気候である。
@=
(2019-04-30) カミーノ17日目。晴。今日は辛かった。景色はつまらないし。足は痛いし。いかにもスペインな風景はもう飽きてしまった。明日は山越えなので期待。 Astorgaが着いた頃には疲れ切っていたのだが、都市は嫌いなのでスルー。アストルガ大聖堂もスルー。パリ、ブルゴス、レオンで立派なのは見たし、旅の目的もサンチアゴの大聖堂だし、中途半端なものを見ても仕方がない。頑張ってもう一つ先の町まで行く。 Murias de Rechivaldoのアルベルゲは5ユーロ。足が動かない。久しぶりの経験。ベットで2時間ばかり横になってようやく動けるようになった。町にはなんにもなく食料の調達に困っていたら、同宿のスロベニア人夫婦がたくさん作りすぎたとかで、食事をごちそうしてくれる。大感謝である。
@=
(2019-05-01) カミーノ18日目。晴。スロベニア人夫婦は超早起き。 5時に起きて6時過ぎには出発してしまった。私も5時30分には出発の用意をして6時20分出発。本日は待望の山越えである。とうとうメセタとも本当にお別れである。名残惜しく、、、はない。やはり山の風景は綺麗である。なだらかなで赤紫色の丘が連なり遠くには冠雪の山脈が見える。赤紫色?そう、丘陵全体にラベンダーが自生しているようだ。山道は花にあふれて素晴らしかった。マゼンタの山なんてこの季節じゃないと見れないだろう。寒の戻りというかむちゃくちゃ寒い日もあったけど、花咲き誇るは春の良さである。日本では平成から令和に元号が変わったらしい。スペインの山も綺麗だけど、やはり山国、日本のほうが山は綺麗だと思う。そうなるとやっぱり日本が風景も一番綺麗なのかなぁと思う。北海道に行けばヨーロッパと似たような風景はあるし。沖縄に行けば南国もあるしね。
@=
(2019-05-02) カミーノ19日目。快晴。水ぶくれが潰れた左足小指が超絶痛い。白と紫が混じったなんか凄い色になってるし、、、。黄色くはないので化膿はしていないと信じる。普段なら5分も歩けば痛みに慣れるのだが、今回は回復がまるで追いついていないのか30分経ってもまだ痛い。いつまでもビッコを引いたままではとてもじゃないが歩けない。山を下ったPonferradaまでの15キロを目標とする。天気がいいだけに悔しくはある。足の小指が痛くて歩けないなんてホント我ながら情けない。しばらく補給ができていないので8キロ歩いたBarで朝食。レストランの利用は高く付くが良いものを食べないと体も治らない。 12時前にPonferradaに到着。が、アルベルゲが開くのは14時から。くっそう痛いなぁという足を引きずって更に8キロ歩いてCamponarayaで14時前にチェックイン。この時間だとまだ誰もいない。20キロちょいしか歩いていないが限界、もう歩けない。足の小指大事です。
@=
(2019-05-03) カミーノ20日目。快晴。今日もどうせ足が痛くてろくに歩けないだろうと思い7時過ぎまで寝る。出発は7時40分。昨日は盆地の横断であったが、今日は次なる山越えのために丘陵に分け入ると言った感じである。相変わらず足は痛いが「もう少しだけ」と思いながら歩いていれば45000歩。 30キロくらいは歩いていたようだ。 15時、Ambasmestasまで歩いてアルベルゲにチェックイン。大体15時くらいまでにチェックインすると一番乗りである。おかしいなぁ。巡礼者は7時30分には歩きはじめてるし、25キロくらいしか歩いていないはずなのに、なんでチェックインが17時とかなんだろう。巡礼者もスペインの習慣に合わせてシエスタしてるのだろうか。
@=
(2019-05-04) カミーノ21日目。快晴。久しぶりにアルベルゲ提供の夕食と朝食をつけた。朝からしっかり食べて山越えの体力をつけておく。 7時40分遅めのスタート。アルベルゲの朝食が7時からなのでこんなもの。足指の痛みがやっとマシになった。見た目は白くてブヨブヨで酷いものだが、確実に皮膚は再生されてきているようだ。小指をかばいながら歩いていたので親指とかかとも痛めているのだが、こんなものは軽症だ。普通の歩き方さえできれば自然と良くなるはずである。さて、故障から回復しての山である。速い男が帰ってきた。ガンガン抜かしながら山道を登る。1200mの峠越え。あっさり制覇。日本の山に比べれば傾斜がなんせゆるい。六甲山や高尾山ですらもう少ししんどい気がする。景色は良いです。感覚的には高原のハイキングかな。 13時過ぎには25キロ歩いてFonfriaのアルベルゲの到着。足に痛みがないのであと10キロは余裕で歩けそうだが今日はここまで。昨晩泊まったアルベルゲの主人が「Fonfriaで宿泊するのが良いよ」と言っていたのでそれに従う。たしかに9ユーロとは思えない綺麗で設備の整った最上級のアルベルゲである。 15時には洗濯も終わり。やることがない。やっぱもう少し歩くべきだったかなぁと思ったが、ここに泊まったことには二つの幸運と一つの不幸があった。一つ目の幸運は夕食が食べ放題であったこと。ここぞとばかりに野菜と肉を補給する。二つ目の幸運は翌朝の景色が素晴らしかったこと。そして不幸とは調子に乗って夕食を食べすぎたため、膨満感で夜眠れなかったことである。
@=
(2019-05-05) カミーノ22日目。晴。 6時45分に出発。未だ山は薄暗い。明後日から雨の予報なので今日明日は思いっきり歩く予定。足指の痛みはほぼなくなった。しかも今日もほぼ一日山中。最高のパフォーマンスを発揮できる体調である。出発して30分。空が白々と明るくなってきた頃、谷間に雲海が見えた。雲海は悪くはないが大したこともない。山国の日本のほうがよほど凄いものが見れる。と、思いながらさらに10分。視界が大きく広がって目を奪われた。雲の滝である。高地から低地へと朝日に受けた橙の雲が流れていくのである。那智の滝じゃない。ナイアガラの如き雲の大瀑布である。しばし呆然。言葉も行動も失う。摩周湖でも夏の時期に霧の滝が見れるらしいが、これほど大規模なものではないだろう。麓の村なんて雲の洪水に押し流されそうに見える。昨日、Fonfriaに宿泊した人は幸運だね。この光景が見れただけでカミーノやってよかったと思えるのではないだろうか(メセタは要らないけど)。早起きして出発してよかったオレンジの滝を見れたのはほんの5人くらいではなかろうか。さて、本日も抜かしまくり。急いでいるわけではないけど、登りでペースが落ちないから圧倒的に私が速い。ガリシア地方は風景が美しい。カミーノのダイジェストは最初の3日と最後の7日かな。 15時30分。45000歩。流石に疲れたのでFerreirosのアルベルゲにチェックイン。いやぁ、今日はよく歩いた。
@=
 ちょこっと望遠で。まもなく村は水没。、、、は、しないかな。物理の法則。高原の空気は冷たいので飽和水蒸気圧が低い。よって雲(霧)になる。冷たい空気は重いので斜面を駆け下りる。高度が下がると気圧が上がり温度も上昇するので雲は消える。気体の状態方程式。
@=
ちょこっと望遠で。まもなく村は水没。、、、は、しないかな。物理の法則。高原の空気は冷たいので飽和水蒸気圧が低い。よって雲(霧)になる。冷たい空気は重いので斜面を駆け下りる。高度が下がると気圧が上がり温度も上昇するので雲は消える。気体の状態方程式。
@=
(2019-05-06) カミーノ23日目。曇(霧)後晴。時々にわか雨。 6時45分出発。以前であった朝早いスロベニア人夫妻と同じアルベルゲであった。少し故障していたとはいえ私相当早いはずなんだけど4日ぶりに同宿になるとは彼らも相当早い。さて、残り100キロ。3日といったところか。予報では明日以降天候が崩れるらしいがそれでも4日あれば十分だろう。本日はロード歩きが多くつまらない一日。風景も昨日とは比較にならない。消化試合ですね。淡々と歩いて15時過ぎにCasanovaでチェックイン。昨日楽しいのは最初の3日と最後の7日と書いたが、最後の最後の3日はダメそうだ。風景も大したことない上になんせ人が多い。Sarriaくらいから始める人が多いのだろうか。小さなリュックに運動靴で歩いている人が多い。100キロ歩けば巡礼として認められるからなぁ。メセタでは少なかった巡礼者が、レオンを過ぎたあたりから増えだし、ここに来て行列と言った感じである。細い道で大集団に巻き込まれると追い越すのも面倒だ。
@=
(2019-05-07) カミーノ24日目。曇時々晴時々雨。目が覚めれば6時30分であった。7時過ぎに出発。昨日とは異なりロードは少なめ。丘陵をつなぐ整備された登山道と言った感じ。「うわぁ、ヨーロッパみたい!」な美しい風景は続くが、もっと綺麗なところを見てきたので感動もない。そもそもここはヨーロッパだ。当たり前の感想でしかない。やはり消化試合である。 40キロ歩いてSanta Irene。明日は最後の一日。残り20キロと少し。昼過ぎにはゴールだろう。もう終わりかという気持ちと、やっと終わりかという気持ちが半分半分。
@=
(2019-05-08) カミーノ25日目。曇時々雨時々晴れ。最終日にふさわしい大荒れの天候。黒い雲が空を覆っている。吹雪の日以来の強風も戻ってきた。時々雨と書いたが、降れば驚きの土砂降りである。運良くBarの近くであったため緊急避難。仕方がないのでクソ高いピザを食べる。15分ばかり降るだけ降れば青空が見える派手な天気である。そしてすぐに強風に乗って次の黒い雲がやってくる。神はそう簡単にはゴールさせたくないらしい。とはいえ、たかが20キロ。予定より少し早く昼前にはサンチアゴのアルベルゲに到着。 800キロ。25日間。一切の乗り物にならずに歩き切りましたよ。感動もひとしお、、、というほどでもない。あぁ、終わったかという感じである。言ってしまえば徒歩旅行としても海外旅行としても簡単であった。歩くことさえできれば誰でもできる旅である。吹雪いたりマメが痛いのを我慢して歩いたりもあったけど、今までの徒歩旅行や海外旅行と比べるとやはり楽であった。さて、帰り支度をしないといけない。航空券とバスの手配である。調べた結果パリからの航空券が破格であったためパリ経由で帰ることにする。一通りの雑務を済ませたのち本来の目的地であるサンチアゴ大聖堂に行く。うん。これは凄い。3度目、圧巻の建築物である。でかいなぁ。見る価値あるよ。ただし、内部は残念ながら修復中。そして巡礼手帳に最後のスタンプを押してもらい、巡礼証明書を手に入れる。このときばかりは流石に何かこみ上げてくるものがありました。長かったなぁ。いろいろあったよ。景色も素晴らしかったし、出会った人たちも掛け替えのない思い出だ。そうそう日本人も7人(2組夫婦なんで5度)出会いました。新婚旅行だとかいう人もいて、それはまぁベリーハードなハネムーンですな。本日にてカミーノは無事終了である。
@=
カミーノは実はもう少しだけ続く。在りし日の巡礼者たちは、サンチアゴへの巡礼を済ませたあと、大西洋を望むフィステラ(Fisterra)まで歩き、そこで服や靴など巡礼に不要になったものを燃やしたらしいのである。また、当時Fisterraは世界の西の果てでもあった。新大陸が発見されていない時代である。ならば、私も行かねばなるまい。ここまで800キロも歩いたわけだし、Fisterraまでの90キロなんて誤差みたいなものだ。それに私は未だ大西洋を見たことがない。旅のゴールはFisterraとする。
@=
(2019-05-09) カミーノ25+1日目。雨。 7時発。曇り空は1時間で雨。午後からは土砂降りである。風は昨日ほど強くはないものの、降り続く雨に靴もズボンもパンツまでもびしょ濡れである。スペインの雨はさっと降ってさっと止むものかと思っていたが、台風上陸前のような小雨になったり大雨になったり、突風が吹いたりである。はっきりいって、1ミリも楽しくない。歩いている間はずっと苦痛である。思えばなぁ。サンチアゴからFisterraとMuxia、さらにその他観光地を回るガイド付きのバスツアーが35ユーロである。最低3日かかって宿泊日と食費で100ユーロすることを考えるとただの物好きですな。いい点は一つだけあって、巡礼者がほとんどいないこと。うん、道もすいてますね。苦痛が続くと連帯感というかある種共感は生まれる。アイルランドからのクリスと仲良くなった。 14時30分。Vilaserioにてアルベルゲに飛び込む。ホットシャワーを浴びてやっと生き返る。
@=
(2019-05-10) カミーノ25+2日目。雨。昨夜は胃が痛くて眠れなかった。胃潰瘍かと思う痛さである。 2週間前には胸が苦しくて眠れない日があったし疲れが内蔵に来ているのだろうか。さて、朝から酷い雨。流石に出発する気になれないので様子を見る。 8時30分、少し小雨になったところでスタート。昨日の雨で水を吸った荷物が重い。湿度が高い上に気温が低いから濡れた荷物が全く乾いていない。昨日もらった巡礼証明証も水を吸ってゴワゴワになってしまった。一時の小雨を狙って出発しても意味がないですね。すぐにまた本降りになるし濡れた靴も気持ち悪い。海外まで来てお金を使って時間をかけて辛い目にあってるだけの一日である。信仰心のない者にとっては巡礼なんてホント自己満足でしかない。まぁ、自分を鍛えるのに役に立ってるさと無理やり考えてもこれもホント自己満足。雨と風に打たれながら山道を登る私はまさにレッドモンク(赤いレインコート着てます)。遠景から写真を撮ったらキマってるだろうなだなんて悟りとは程遠いことを考えているレッドモンク。一向にやまない雨がイヤになって今日は25キロで14時にチェックイン。荷物もほとんど濡れているし(寝袋が濡れるとホントに萎える)、寒いから全く乾かない。そんな何もいいことがない歩き旅の一日でも夕食の時間だけは幸せです。美味しいしいろんな人に出会えるしね。ずっと雨だったので写真は取らず。
@=
(2019-05-11) カミーノ25+3日目。晴。待望の晴れである。今まで辛かったよ。 7時30分行動開始。濡れた服に濡れた靴での出発となるが歩いている間に乾くだろう。朝は丘陵歩き。いい具合に霧がかっており幽玄な雰囲気である。気持ちの問題は実に大きい。全く疲れることなく15キロを歩いてCEEの町に。昨日は10キロ歩くのがしんどかっただけに天気が良ければ気分も良く体調まで良くなるものだ。 2時間半、丘が切れて海が顔を出す。一ヶ月ぶりの海である。そして紛うことなき初めて見る大西洋である。潮風を私は懐かしく感じる。思えば日本に住んでれば山も海も身近だしなぁ。 12時30分、Fisterraに到着。アルベルゲにチェックインしてまずは洗濯。二日間の雨で全く乾いていない洗濯物の洗い直しである。一通り雑務が片付いた15時。旅の最終目的地、岬の灯台へと向かう。灯台へと続く丘陵を滑るように登っていく。荷物がないって素晴らしい。思えば今までずっと10キロを越えるリュックを背負ってきたわけで、常に肩が痛かった。少々の坂道など全て下りに思える楽さである。灯台に到着。目的地までの一里塚も遂に0kmとなった。中世西洋の世界観における大地の果てである。あー、大西洋、広いなぁ。岬は観光地にもなっているらしく、巡礼者のほか観光客も多くいた。岬の灯台ですからね。岸壁の上にあります。降りたいなぁ。地の果てで是非大西洋を触っておきたい。急だとはいえ下れなくはなさそうだ。道のような踏み跡のようなものが一応岬の突端に向けて続いている。よく見ると赤い人影が見える。よし、行ってみよう。 10m置きに後ろを振り返り、帰り道を確認しながら降りていく。上から見下ろせば明確なルートも登り返すとなると絶対にわからなくなる。誤った道を登れば滑落しかねない。見返しながら丸い岩を右、岩の裂け目を辿るなどとランドマークを頭に叩き込む。遂に崖下の磯まで到着。赤い人影は地元の漁師であった。笑いながら「危ないよ。巡礼者は灯台までだよ。」みたいなことを言われた。そして、なぜだか漁で取った貝を何個かくれた。記念品として持って変えることにする。一人降りれば誰か着いてくるものである。気がつけばもう一人巡礼者が来たので記念写真を取ってもらう。帰りは丘の最高地点に向かう。ここもいい景色。最高の一日であった。
@=
(2019-05-12) 晴。サンチアゴに戻るバスは9時40分に出発。 11時には到着。途中どこにも寄らない直行便であった。徒歩で3日かけた距離がバスで1時間20分。たった10ユーロである。早い、安い、快適。文明の利器はかくも偉大なり。雨で見逃した景色を見ようと窓側に座ったのだが、心地よい振動に抗し得ず眠ってしまった。パリ行きのバスが12時発なので、翌日のバスにしたのだが、当日のバスにしておけば一日早く帰れたな。今更だけどもう一度大聖堂へ。やることがないので町ブラして、それでも時間が余るので三度大聖堂へ。大聖堂前の広場では至るところで喜びの声が上がっている。みんなあんたを見るために遠い旅路を超えてきた人たちだよ。明日は20時間のバス。その後は20時間の飛行機。今日は早く寝よう。
@=
(2019-05-13) ギリギリまでアルベルゲでのんびり。観光する気力がない。バスは35分遅れて12時40分出発。スペイン北海岸のハイウェイを走る。カミーノにはこちらを通る道もあり、美しい海にいつか歩いてみたいとは思うが、おそらく3日で飽きるであろう。北海道歩き旅でよくわかったのだが、海岸沿いの道は風景の変化に乏しく嫌になってくるのである。スペインを通過するのにはバスでも12時間かかった。やはり25日かけて歩いた距離は結構なものである。
@=
(2019-05-14) 10時までは車中。トゥールを過ぎた頃明るくなってくる。フランスはひたすら平原の小麦畑である。高原であるメセタより地形の起伏はさらに少ない。当初はフランスの中部くらいから歩こうとの考えもあったがこれは無理ですわ。 3週間以上小麦畑のほか何もない同じ景色が続けば旅を続ける気力が持たないであろう。スペイン国境のサン=ジャンからにしておいてよかった。さて、一ヶ月ぶりのパリであるが、以前の感動が嘘のように全くわかない。どの通りも魅力的に思えたのに、今見れば「なんだ、こんなものか」以上の感想が出てこない。二回目になるだけでここまで心象が変わるとは不思議なものである。焼けちまったノートルダムを見に行く。無残な状況ですな。美しかったバラ窓のステンドグラスも今はない。近場のルーブル美術館、オペラ座と再訪するがやはり「大したことないなぁ」である。飛行機は夜発なので時間はあるのだが、観光する意欲が不足しているため空港でゆっくりすることにする。 2019年スペインカミーノをゆく旅はこれにて終わり。
@=
(2019-06-12) 金剛山ロープウェイ前バス=>細尾谷=>葛城神社=>伏見峠=>久留野峠=>千早峠=>金剛山ロープウェイ前バス。同行は上野のわ氏、シバジィ、パパジィ。雨後のハイキング。雨上がりの風はなんとも優しい感じがする。無理やり言葉にするなら、しっとりとした潤いのある爽やかさとでも言おうか。曇り空に時々陽光が射す。暑くなくてちょうどよろしい。 11キロのコースで所要6時間。休憩多めの非常にゆっくりとしたペースであった。
@=
(2019-06-15) 2週間のラオス旅行。同行は上野わ氏。関空からバンコクに飛ぶ。9600円なり。 4000km以上の距離があってこの値段は不思議である。 1kmの移動に2円ちょいとか、こんなに安い交通手段は他に思いつかない。 12時過ぎにバンコクに到着。タイの入管なんて所詮見ずに判子を押すだけだろうと甘く見て、入国カードでタイの滞在場所を空白のまま提出したらあれこれと突っ込まれた。着いたその日(今日)の夜行バスでラオスに行くからタイでの滞在場所はバスだ答えると、滞在期間が2週間(適当に書いていた)はおかしいじゃないかとか更に突っ込まれる。すまん本当は一日しか滞在しない。 2週間はラオスに行ってからタイに帰ってくるまでの期間だと誤魔化す。すると夜行バスの出発時間は何時だとかさらに突っ込まれる。適当に午後9時だと答える(そんなもん本当はバス停に行ってみないとわからんわい)。うーむ。仕事熱心なおネェさんであった。ごめんね。後ろに並んでいた人。他の人の数倍の時間がかかったよ。実際バス停に行って調べてみるとラオス・パークセー行きの夜行バスは8時発であった。大きな嘘にはならなかったようだ。到着予定は翌9時。13時間900バーツ。 4列シートながらも足元は広めで空調もよく効いており快適である。睡眠不足気味であったため心地よい揺れに1時間とせずに寝てしまった。
@=
(2019-06-16) 8時に国境到着。今回もタイ滞在は20時間である。しかもほとんど寝てた。 6度目のラオス。やはり良い。のんびり落ち着いた時間が流れる。パークセーは2度目。10年近く前に1泊しただけなのでほとんど記憶はない。首都ヴィエンチャンに次ぐラオス第二の都市であるがまだまだ閑散としたものである。ホテルにチェックインしたあと中心部を散策。この小さな町に何故というくらいに広い市場があり賑わっている。夕食はちょっとリッチに1200円。はじめは不安だったわ氏もだいぶと慣れてきたようだ。しかしパークセーは何もないなぁ。ラオスで観光資源に恵まれているのは古都ルアンパバーンとジャール平原のあるシェンクワーンくらい。ただ、観光地はかなり俗化してしまった。マイナーな町で人の穏やかさと優しさを感じる旅のほうが面白い。
@=
(2019-06-17) 午前中、町ブラ。パークセーの人口は10万と少し。少し歩けば町の大凡の構造は把握できる。橋を越えたセドン川向こうは外国人向けの店もなく、英語はほぼ通じない完全に地元民の町であった。時々子供たちに奇異の目で見られるが、町の風景を楽しみながら歩く分にはこちらの方が楽しい。ラオ人と話すと(正直意味は全然わからないのだが)猫と話しているみたいである。「にゃぁ〜、みゃぁ〜。くぁ〜ん。」この言語で喧嘩をするほうが難しいように思われる。実際、ラオスの町中で言い争いをしている人を見たことがない。昼食、昼寝して、夕食を同じ店で食べる。一人一食700円とラオスにしては相当高めだけどお金を払うとやはり美味しい。ついでに言うと店員がみんなニコニコしていて可愛い。愛想もいい。お腹いっぱい、ビールがうまい、マンゴーシェイクも安い。今回の旅は修行少なめのまったり旅行である。
@=
(2019-06-18) ラオス第二の都市サワンナケートに向かう。なにやら第二の都市が多い国である(ルアンパバーンも第二の都市と言われることが多い)。 8時ホテルピックアップで南バスターミナルを9時に出発。雨季は涼しくて良い。チリやホコリが流されて空気も澄んでいる。オフシーズンではあるがむしろ旅はしやすいのではないかと思う。日に数回強烈なスコールが降るが普段は晴れか曇りである。日本の梅雨にようにずっとしとしと雨が続くというようなことはない。比較的涼しいとはいえ、それは午前中だけの話で、午後になるとやはり暑い。公共バスなので冷房はない。天井の扇風機は暖かい空気をかき回しているだけだ。オンボロバスと言ってよいのだろうが、個人的にはラオスにしてはマシな方かと思う。ラオス南部は北部に比べてずっと豊かであるように感じる。北部は山ばかりだが南部は平原が続き水田が多い。必然的に水牛などの家畜も多いようだ。バスは途中で謎の停車を繰り返し2時間遅れの14時30分にサワンナケートに到着。サワンナケートはずいぶんと発展していて驚いた。メコン川を挟んですぐにタイだし橋もかかっている。さかんな交易でタイ経済圏に含まれているのかもしれない。
@=
(2019-06-19) サワンナケート二日目。昨日出会ったラオス支援事業で訪老中のT氏が車をチャーターしているとのことだったので、お言葉に甘えて同乗させていただき郊外のクメール遺跡に連れて行ってもらう。規模としては小さいが、場所的にはアンコール遺跡につながるクメール芸術の初期のものかと思う。また、道中T氏も関わったと言うサワンナパークなる経済特区も見たのだが、なかなかのものであった。すでに日本企業が何社か入っており工場が立ち並んでいる様子が伺える。なお、同様の経済特区はパークセーにも建築中であり西松建設が請け負っているようだ。町に戻ってみればカンカン照りである。日中は出歩く気がしないのでホテルで昼寝。夕方から行動再開。昨日立ち寄ったサンドイッチ屋さん(屋台)の子が可愛かったと言うだけの理由で、夕食前にもかかわらず買い食い。外人は目立つからね。向こうも覚えているのでなんとなく愛想が良い。メコン川沿いのあばら家食堂で沈む夕日を見ながらの夕食。西日、暑い。うどん、熱い。男二人で汗たらたらである。ロマンチックのかけらもないが幸せではある。
@=
(2019-06-20) 7時のバスでセポンに向かう。ラオスは意外と日本人が多い。毎日のように会っている。道路や橋、学校や病院などの記念碑に日本の国旗をよく見るので、相当な人員と金銭が国際協力の名の元援助されているように思われる。さて、セポンて何処だよという感じであるが、サワンナケートからルート9を東に進みベトナム国境まで残り40キロ地点になる。こんなマイナーな町だと日本人はおろか外人はいないだろうとの読みである。ルート9自体はよく整備された舗装路であった。ラオスにこんな綺麗な道があったのかと驚くくらいだが、聞けば日本の援助で日本が作った道路だということでまぁ納得。沿道には工場も多々あり、なにより新しくてモダンな家が多い。貧相なバンブーハウスをあまり見かけないのはむしろ寂しい感じがするが、ラオスは素朴な田舎であってほしいと思うのは一方的な押し付けの感情でしかない。さて、セポンへのバスであるが、エアコン付きであったもののやはりオンボロである。バックパックをバス底部の荷台に入れようとしたら、中に持って入れと言われる。うーん、空いてるのかなぁ。まぁ、中に持ち込んでいいならありがたいと思いながら乗車すると、座席の後ろ二列が物置状態であった。そして荷台に何を入れるのかと思えばなんとヤギである。抵抗するヤギをむりやりバス底の貨物スペースに押し込む。途中の村でもヤギは補充され、最終的には50頭以上のヤギがすし詰め状態で積み込まれてしまった。半分くらいは熱中症で死ぬんじゃないかと心配になる。それでも乗り切らないので20頭くらいは天井に放り投げられ、ルーフキャリアに括り付けられていた。結果、上からも下からもメェーメェーとうるさい旅であった(1時間くらいで静かになったけど)。さて、セポンは思ったとおり何もない田舎町である。そうそうラオスってこうだよねという何もなさである。あるのはジャングルと僅かばかりの水田とそして水牛である。満足である。
@=
(2019-06-21) 一足先にサワンナケートに戻るわ氏をバス停まで見送ったあと国境に行くことにする。今日明日と、わ氏とは別行動である。町に一つしかないバス停では「国境行きのバスなんてない」とにべもなく断られたのだが、しばらくバス停前の幹線を眺めていると国境の方へと走るソンテウ(乗り合い軽トラ?)を発見。声をかけて行き先を尋ねると国境の町まで行くとのこと。一も二もなく慌てて乗り込む。1時間ばかりして国境の町Davasanに到着。以前、国境に行ったはいいもののそこからの交通手段がなく難儀したことがあるのだが、 Davasanにはバスステーションがありセポンまでの定期バス(ソンテウ)も出ているようだ。うるさいバイタクの客引きを無視してバス停から国境まで歩く。「ベトナムに行くんじゃない。ラオスを出国するわけでもない。国境を見るだけ。」と入管で説明して、国境緩衝地帯に入らせてもらう。このあたりの緩さがラオスである。出国の判子を押さずにラオス国境を通過。ベトナムまでの国境地帯を散策。とはいえ山の中である。入管のオフィスと国境ゲート以外には何もない。お約束の国境をまたいで(北に向かって左足ラオス、右足ベトナム)、Davasanの町に戻る。食事後、高台にあるワットの木陰で雲をみていたらウトウトしてしまった。日差しはものすごく暑いのだが陰に入ると風も涼しく結構快適である。 12時のバスでセポンに帰還。12時から16時までは暑すぎて動けない。宿で休憩である。 17時過ぎ、昨日は行かなかった町の北側を探索。夕食として惣菜屋通りでおかずとチャーハンを買う。一品10000キップ(130円くらい)と高めだなぁと思いながら惣菜を二品頼めば強烈な量であった。一品で豚バラに味付け煮卵6個とかそれだけでお腹が一杯になりそうだ。宿で大皿を二つ貸してもらって盛り付ければ、本日は一人にもかかわらずエラく豪勢な食事となった。
@=
(2019-06-22) 8時のバスでサワンナケートに戻る。 24日バンコク発に向けての帰り支度である。予定より1時間遅れて9時にセポンを発車。客が集まらなければ待つ。客が集まれば時間前でも出発はラオのルール。結局、7時半から1時間半も暑い中バス停で待機するはめになってしまった。汗だく。 12時過ぎにサワンナケート着。わ氏をピックアップして14時半の国境バスでメコンを渡る。正直この時間の荷物を担いでの行動は堪える。汗だく。タイ側の町ムクダハンに16時前に到着。 18時30分のバンコク行き夜行バスの出発まで時間があるので町の散策。この時間でもまだまだ暑いよ。汗だく。運良く夜市を発見。冷たいジュースで水分を補給すればそれはそのまま汗の補給。汗だく。夜行バスは冷房キンキン。汗は強制的に乾くが何だがねっとりしてる気がする。、、、が気のせいだろう。
@=
(2019-06-23) バンコク5時過ぎに到着。今日明日とバンコクになる。久しぶりのバンコクである。煩い汚い臭いの三重苦で個人的には大嫌いなバンコクであるが、良い悪いはさておきバンコク(特にカオサンロード付近)は旅行者のメッカである。犬も歩けば外人(タイ人以外)に当たる、そんな町である。王宮周辺の観光エリアも20年振りに歩いてみたが、日本語もそこかしこから聞こえてくる。暑い午後は二日分の洗濯。昼寝している間に乾いて合理的。と、思えば15時にスコール。すぐに気づいたので被害は軽微だがまだ生乾き。残念。さて、私は安ゲストハウスに泊まっているのだが、わ氏は落ち着きたいとのことで別のホテル。明日の5時にわ氏を迎えに行くため、4時45分にはチェックアウトをする必要がある。当然ながらそんな早くには門もしまっているしフロントも無人である。出るなら鍵をフロントの上においてシャッターを勝手に開けて出て行けと言われる。今晩、このゲストハウスに泊まっているのは私一人だけのようだ。オーナーも使用人も19時には自宅に帰るそうなので、ゲストハウス貸し切り状態である。 5時前だとまだ真っ暗なので電気を付けておいてくれと頼むと、「You don't fear おばけ!」などと片言の日本語を交えながら、「Easy.大丈夫!」と何が心配なのかわからない様子。いや、まぁ、そりゃそうだろね。シャッターを開けて出ていくだけのことなんだから、、、。とはいえ、昔、早朝に出ようとしたら薄暗い中ドアに南京錠がかかっていて出れなかった経験があるんだよ。何度もシャッターに鍵をかけないことを確認して、さらに、一度シャッターを締めてもらって開ける練習をする。少なくとも錆びついてシャッターが開かないという可能性はなさそうだ。こちとらここまでしてんだ。もし、出れなくて迎えに行くことができなくても、わ氏よ、俺を恨まないでくれ。ついでいうと宿のネットワークの調子が悪い。シャッターの件もネットワークの件も私は困らないのだが、連絡が取れないとわ氏が不安かもしれない。
@=
(2019-06-24) 4時起床。無事5時にわ氏をピックアップ。空港に向かう。わ氏は11時のフライト。私は23時のフライトである。わ氏のチェックインを確認して出国ゲートまで見送ったあとバンコク市街に戻る。戻っても特にやりたいことはない。見たい場所もない。困ったときの時間つぶしとしてタイマッサージを受ける。おー、痛い痛い。相当コッていたようだ。特にふくらはぎがイタくて終わったあとしばらくはなんか歩き方が変であった。喫茶店で思いっきり時間を潰して、空港の展望台で思いっきり時間を潰して、この日記を書いて、、、まだ時間が余る。暇なのでラオスの地図を一時間ばかり眺める。ラオスは5年前に一ヶ月ばかり周遊している。それなりに難度の高いコースであった。当時、ボートとソンテウを乗り継ぎラオス最北部のポーンサーリーに向かったのだが、今はダムができてしまい、このコースは不可能になったようだ。面白いルートはどんどん消滅する。公共交通機関で手頃に行けて目ぼしいところはあまり残っていそうにない。今後は簡易テントと寝袋を担いで結構な奥地に行かねば満足できないかもしれない。さておき、今回はわ氏同行の8日間と短い旅であった。
@=
更衣室にて小耳に挟んだジジィ連の会話。ジジィA「この前、伊勢に行きましてなぁ。」ジジィB「伊勢ですかぁ。ええですなぁ。」 A「それで、アレですわ。名物のうどん食べたんですわ。なんやったかなぁ。」 B「伊勢でうどんですかぁ。ありましたかなぁ。」 A「ツユが入ってのうて、醤油で食べるやつなんですわ。」 B「ほぅ。伊勢うどんのことですかなぁ。」 A「あぁ、それやそれ。伊勢うどんですわ。よう知ってますなぁ。」 B「むかぁ〜し、食べたことあるような気ぃしますわ。」私(今日も平和やなぁ。)
@=
(2019-09-02) 蓬莱駅=>小女郎峠=>蓬莱山=>比良岳=>烏谷山=>荒川峠=>志賀駅。大阪の予報は晴れ。始発で比良の武奈ヶ岳を目指す、、、が、滋賀は曇り。山は厚い雲の中。こりゃ、雨かもしれんなぁと思うが2時間もかけて来た以上このまま帰れない。琵琶湖湖畔から一気に1000mを登る。相当キツイ。比良ってこんなにしんどかったっけ?途中、沢を渡っての急登を終えたところで手ぬぐいを落としていることに気づく。渡渉前の地点までバック。半端ない汗。手ぬぐいなしにはこの先の登りは乗り切れない。コースタイムより少し遅れて小女郎峠。体力が落ちているようだ。なお、景色は霧で何も見えない。本来なら右手に琵琶湖、左手に京都北山を望みながら歩く絶好の高原路が台無し。蓬莱山手前でカメラを落としていることに気づく。45000円を見捨てることは出来ない。 10分ほどバック。諦めかけた頃にようやく発見。見つかってよかった。気を取り直して蓬莱山山頂。360度の大パノラマ、、、は、望むべくもなし。びわ湖バレイを過ぎた頃、再び手ぬぐいを落としていることに気づく。流石にもう戻る気がしない。なにもない比良岳山頂。そしてとうとう雨。しかもシトシトならぬザァザァの結構な大降り。カッパを着るが汗だくで不快なだけ。カッパ無しで濡れることにする。雨に合わせてか羽虫も大量に発生。服の上からでも刺してきて痛い。武奈ヶ岳まで行く気力が失せる。もういいや。荒川峠からショートカット。楽しい要素ゼロ。修行だけで終わった山行であった。この天気が予測できていれば絶対に行かなかったな。大阪は晴れでも福井は雨。滋賀北部はむしろ日本海側の天気である。
@=
(2019-09-07) 坊村バス停=>御殿山=>武奈ヶ岳=>イブルキノコバ=>比良ロッジ跡=>釈迦岳=>ヤケ山=>楊梅滝=>北小松駅。先日辛いだけだった比良へもう一度。武奈ヶ岳に再チャレンジ。予報は晴れ、列車が京都に着くと曇り、バスが大原を通過したあたりで雨。バス停でしばし雨宿り。雨は上がったものの曇り空、少し登ると霧の中。景色は全く見えない。どうも比良とは相性が良くないのだろうか。御殿山コースは30年前に一度通った道のはずなのだが全く記憶にない。2時間で武奈ヶ岳登頂。大人が飛ばされそうなほどのものすごい風。台風が近いだけはある。週末で他の登山者もいるから安心できるが、一人だと登頂を諦めてコースを変更してたかもしれない。雲と霧がえらい勢いで飛んでいくため、時折霧の晴れ間から部分的に朽木谷を望むことが出来た。前回の蓬莱山といい武奈ヶ岳も360度の大展望が広がるはずなだけにこの天候は残念。下山は比良山系を横断して琵琶湖側へと向かう。午後からは晴れてきて眼下に広がる琵琶湖を堪能できた。対岸には安土山も見えていた。南西からの強風は相変わらずだが下山路に危ない所はないしむしろ涼しくてよろしい。
@=
(2019-09-12) 芦屋川駅=>風吹岩=>石切道=>有馬三山=>有馬温泉。六甲は近いので6時過ぎには登り始めることができるのが魅力。平日の早朝だし誰もいないだろうと思えば、なぜか登山口に向かう(もしくは帰る)人たちが多い。なぜだろうと思っていたのだが、登山口である高座の滝ではご老人主体で集団ラジオ体操が行われていた。すでに駅前で準備運動は済ませているのでラジオ体操には参加せず先を行くことにする。風吹岩への尾根道で、イノシシに進路を阻まれる。狭い登山路で悠々と食事をされると大変邪魔。人には慣れてるんだろうけど、2m位の至近距離だと結構怖いよ。刺激しないように後ろから回り込む。風吹岩は人気なのでシーズンともなればごった返すのだが、平日の7時とあれば当然誰もいない。、、、が、猫とイノシシはいた。猫はいいとしてイノシシが全く人間を怖がらず逃げてくれないのでこちらが困る。このまま真っ直ぐ有馬を目指すと早く着きすぎるので、一度隣の谷に降りてから石切道で六甲を超える。途中、谷を降りる前に七兵衛山に寄るがここは休憩所が広く景色もなかなかでいい所であった。この時期、早朝一番の登山者を悩ますのは大量の蜘蛛の巣。 100件位の巣に引っかかったかもしれない。折角の立派なマイホームを壊しまくってごめんねぇ。でもこっちだって本当は壊したくないんだよ。ネバネバして気持ち悪いし。 10時前に六甲山上に到着。おしゃれなガーデンテラスで無粋なコンビニおにぎりを食う。六甲はロープウェイが何本もある。頂上まで二車線の立派な車道もある。路線バス停まである。よって山頂で出会うのは瀟洒な建物におしゃれな人たちばかり。登山者としては少し悔しい。下りは有馬三山を越えて温泉へ。三山はどこも展望は良くないが、風が心地よくいい山歩きであった。温泉に着けばまだ昼前。汗と蜘蛛の巣にまみれた身体を洗う。三年ぶりの金泉をのんびり堪能して、ついでに食事までつければ帰りのバスでうつらうつらもやむなし。
@=
(2019-09-14) 紀見峠駅=>ダイヤモンドトレイル=>二上山駅。体力強化第四弾。33kmのロングコース。およそ25kmが歩けると大抵の山は日帰りで行けるようになる。急登コース。ロングコース。(意図していないけど)雨の中の行軍。これで秋山に向けて憂いはなくなった。さて、本日、天気晴朗なれど、まだまだ残暑で熱い。ダイヤモンドトレイルはその名に反して特に見どころはない。植林の森ばっかりで歩いていてもちっとも楽しくない。今日は修行オンリーですね。いい汗はかいたかな。しかしトレランで50km、100kmやってる人いるけどすごいなぁ。絶対真似できない。30kmでも足が棒だよ。我が家から紀見峠駅まで約35km。二上山駅までなら約25km。そう考えたら30kmでも、相当なもんだし一日山ん中歩き通しだったんだけどなぁ。ほぼ休みも無しで9時間半。
@=
紀伊清水駅=>黒河道(高野表参道)=>雪池山=>楊柳山=>摩尼山=>奥の院=>転軸山=>女人堂=>高野古道(京大阪道)=>学文路駅。古道で高野山へ。古道で高野山から。午前は天候が芳しくなかったが、午後からは晴天。平日なんで登山者は誰にも合わず。帰りの古道では大きなザックを担いだ三人の西洋人に出会った。ヨーロッパの人たちはこういう旅が好きだよね。ケーブルカーとか乗らないで自分で歩く。体験型の旅行が好みなのであろう。高野山も3割くらいは外国からの観光客。ただしアジア系はいなかった。インド系はいたかな。高野山、外人には結構エキゾチックで面白いと思う。関空からも行きやすいしもっと人気が出てもいいと思う。しかし、よくこんなところに大伽藍を作ったもんだ。黒河道は登っては降りての繰り返し。山超え川超えで本当に山奥。本日も30キロ、8時間半の山歩き。
@=
(2019-09-25) 御影駅=>西山谷=>六甲山上駅=>油コブシ=>六甲ケーブル下駅。同行はパパじぃとシバじぃ。西山谷は熟練者向けコース。二人は一年前に行ったことがあるそうだが道も判りづらく難しかったとのこと。ジジィ二人が行けるんだから大したことないだろうと思っていたが、予想よりは難度も高く、まぁそれなりという感じ、渓谷自体は近郊にも拘わらず奥深くていい感じ。命の危険までは感じなかったが、気を抜くと普通に死ねる(もしくは重症)ところも多々あるので緊張する。昨年よくジジィ二人で行ったものだと感心する。ペースは非常にゆっくり。11キロを10時間と汗もあまりかかないくらいであった。
@=
Kotlin短評。 Javaに型推論とスクリプト言語の便利機能を加えて、多数の構文糖(シンタックスシュガー)をまぶした感じ。便利かもしれないけど言語自身に思想がないから数年後には廃れていても不思議ではないような気がする。エルビス演算子なんて初めて聞いたけど、C言語(GNU拡張)の三項演算子で第二項省略するのとおんなじじゃん。
@=
今までな〜んとなく使っていたJavaScriptだが、最低限言語仕様くらいは確認しておこうと思い『開眼!JavaScript』を読む。スコープとかthisとかよくわからないままえぇ加減に使ってた。 (他からの類推と豊富なライブラリでなんとなくでも使えるのがJSのいい所だな。) 関数が1st-classっぽいのは気づいてたけど、継承の仕組みとか構文の思想がLuaとよく似ている。比べるとLuaの方が設計思想に忠実で、構文はシンプルかつ汎用性が高い。対してJSは色んな便利機能が詰め込まれているのでさくっと素早く実装を終えることができる。 Luaの文法は本当に基本的なものばかりだから、JSやるなら先にLuaをやっておいた方が教育上いいように思う。 Luaの1st-class-functionとmetatableだけ抑えておけば、JavaScriptはなんとなくでも十分に使える。ただ、残念ながら、Lua、最近は人気ないみたいなんだよなぁ。
@=
(2017-10-06) 岡本駅=>七兵衛山=>住吉道=>西お多福山=>紅葉谷=>魚屋道=>六甲最高峰=>東お多福山=>風吹岩=>岡本駅。岡本から有馬に抜け、、、ずに登り返してスタート地点に戻るというストイックなコース。温泉を横目に、、、。汗は汗で流せ。当初の予定では五助尾根を登る計画だったのだが、一人では危険と判断して安全な住吉道を選択。ハイシーズンにもかかわらず風吹岩から魚屋道に抜ける黄金ルート以外は空いたもの。特に紅葉谷は有馬までの最後の30分区間が現在通行止のため全く人がいない。おすすめである。登り返しての六甲最高峰は流石に人だかりであった。下山途中でまだ登り足りない気がしたので東お多福山に寄り道。 14時過ぎ、芦屋カンツリー倶楽部周辺で親子連れに道を聞かれる。最高峰まで行くとのこと。子供はどう見ても低学年だし(弟君は未就学児かもしれない)、奥さんは運動不足っぽいし他人事ながら心配になる。私にとって14時から16時は下山の目安。16時をこえて山中にいることはまずない(あったらそれは想定外)。ここから山頂までのコースタイムは約二時間。暗くなる前に着けばいいんだけど、、、。まぁ黄金ルートだし、親子連れの後に、遅い時間にかかわらず登る人には何人かすれ違ったから大丈夫だと信じたい。
@=
紀見峠駅=>岩湧山=>天見駅。あんまり天気がいいので午後から散歩。岩湧山はこの時期人気。季節限定のすすき野原が広がる。平日の遅い時間にもかかわらず結構な人数のハイカーとすれ違う。 5人連れの中国語おばちゃん集団。「どこからですか?」「ハルビンからよ。」「うぉ〜、遠いなぁ〜。」「しかもものすごく寒いのよ。」そりゃそうだろうなぁ。世界三大雪祭りの一つ「ハルビン氷祭り」はいつか行ってみたいと思う。下山途中ですれ違った上半身裸の人。「寒くないですか?」「大丈夫です。後どのくらいで着きますか?」「もうすぐですよ。10分もあれば山頂です。」「はぁ、よかったぁ〜。」う〜ん。私の足なら10分だけど、20分って言っておいたほうが良かったかなぁ。それなりに保温効果の良さそうな恰幅のいい方でしたし、、、。
@=
スマホからテスト投稿。
@=
紀見峠駅=>南葛城山=>蔵王峠=>滝畑ダム=>三日市駅。天気が良かったので南葛城へ。9時30分と遅めのスタート。以前、南葛城では道に迷いまくってよくわからない谷に出てしまったため引き返した覚えがある。さて、今回。南葛城山までは順調。むしろ、林道がおおくてつまらないくらい。途中、修験者に会う。装備は金剛杖に法螺貝、法衣に身を包み経塚の前で一心不乱に真言を唱えていた。うーん。こりゃ、話しかけられんわ。でも、立派な登山靴と登山用の高そうなザック。まっ、そりゃそうだよね。現代装備がないと山に何日も篭もれないよ。荷物の多さから見て里に帰らず山に駆け巡っているようだ。邪魔をしないよう通り過ぎて5分ほど経った頃、法螺貝の音が聞こえてきた。南葛城山は展望がない。おにぎりを一つだけ食べてさっさと蔵王峠へ、、、行こうとするが道に迷う。決して難しい山ではないのである。軽トラなら走れそうな林道もある、むしろ、歩きやすい道なのである。、、、が、これが曲者で広狭様々な林業用の作業道があり登山道がわかりにくいのである。結局、予定のルートでは蔵王峠にはたどり着けず、大きく遠回りする舗装路を選択してようやく到着。悔しいので蔵王峠から登山道を探しながら迷った地点まで戻ろう(正しいルートを探そう)とするも再び道迷い。やっと見つけたおそらく正しい最短のルートは古ぼけたテープだけが便りのおよそ登山道とは思えないルート。これじゃあ、結果的に遠回りしたほうが早いかな。道迷いで時間を大きく超過したため予定の三国山と和泉葛城山は断念。長いロードを3時間歩いて三日市駅に到着。
@=
(2019-10-20) 犬鳴山バス停=>行者の滝=>五本松=>和泉葛城山=>鍋谷峠=>大石ヶ峰=>和泉葛城山=>牛滝温泉バス停。葛城山は4つある。大和葛城山、和泉葛城山、南葛城山、中葛城山のうち唯一登っていなかった和泉葛城山へ。入山口とした犬鳴山七宝瀧寺は役小角開基の修験道場。早朝の薄暗い山はただでさえ不気味なものだが、社や石仏が並ぶ苔むした沢道はなんだか異界へと続くかのようである。、、、が、標高が上がるに連れ霊気は薄れてよくある植林の山になって残念。山頂近くは紀泉高原スカイラインが通っているためもはや山登りですらない状態。山頂の展望台からの眺めはそれなりに良い。関空までよく見える。牛滝温泉へと降りる予定であるが時間が早いので少し先まで歩いて鍋谷峠へ。蜘蛛の巣が多くて歩きにくい。葛城山に引き返す道すがらバイク(自動二輪)で登ってくる二人組に出会う。おいおい、本気かよ。すごいなぁ。たまに出会う自転車で登る人だって歩いて登るより何倍もしんどいはず。さらに重い二輪で登るとは、、、気が知れませんわ。、、、と、思えばその10分後、20台くらいのバイク集団と行き違う。どうやら、和泉葛城山から大石ヶ峰まではオフロードバイク界隈での名所のようだ。登山道には「自動二輪の進入禁止」なる看板があった。でも、個人的にはいいと思うんだけどなぁ。山は誰のものでもないわけで(誰かに大きな迷惑をかけない限り)好きな人が好きな方法で登ればいいと思う。牛滝温泉で汗を流して帰宅。
@=
(2019-10-23) 岡本駅=>東おたふく山=>ゴロゴロ岳=>観音山=>甲山=>甲陽園駅。明日から雨予報。今のうちにというわけで午後からハイキング。今の時期、少し遅めのスタートのほうが蜘蛛の巣がなくてよろしい。気持ちいいのは朝イチだけど、最初の登山者になると蜘蛛の巣まみれになる。関西の低山は紅葉にはまだ早い。人の多い最高峰には行く気にならないので、行きそびれていた(低すぎてこれまた行く気にならなかった)東部の有名所を巡る。観音山は結構いいところであった。500mと低い(近い)ので大阪平野が非常に大きく見える。観音山、甲山周辺は文化の香りも芳しい。甲山麓の神呪寺は神仏習合。ついでにチベット仏教も混じってるなぁ、、、と思っていたら真言宗ね。なんでもないところに創建1000年を超える寺院があるのは近畿のいい所。観音山の鷲林寺とともに空海ゆかりであった。
@=
(2019-10-26) 裏道登山道=>御在所岳=>中道登山道。ジジィ二人(ぱぱジィ・しばジィ)に同行して御在所岳。週末の紅葉の名所であるため登山客多数。御在所岳は山頂までのロープウェイもあるため観光客も多数。御在所岳は岩だらけ。奇岩珍岩。ザイルを担いだロッククライマーの姿も多い。登りに使った裏道は比較的なだらかな沢道。ただし、なだらかは斜度の話で岩だらけであることは違いない。沢の右岸には切り立った岩壁が連なる。高所が怖い私には絶対に登れないですな。 1000mを超えると雲の中。御在所岳山頂部は、伊吹山、琵琶湖に伊勢湾と、四方に展望が広がる大パノラマのはずなのだが100m先は何も見えないホワイトアウト。残念である。何年か前に一度来たことがあり、その時は快晴であった、、、のだが、ほとんど記憶にはない。下りの中道は非常に急坂。岩や枝を掴みながら降りるという結構スリリングな道で面白い。途中3度もすれ違ったトレイルランナーに声をかける。なんと本日4往復目とのこと。えーと、中道は標高差700m(累積だと800mくらい)だから掛ける4でおよそ3000m。ありえん。これだからトレイルランナーはおかしい。岩だらけの急坂を3000m昇り降りしてるんじゃねーよ。私も2往復ならできると思うけど3回めは足が上がらないと思う。なお、今回の我々はたった9kmを9時間。戦闘力5の我々ではこんなもんです。
@=
(2019-10-28) 紀見峠駅=>岩湧山=>滝畑=>三国山=>鍋谷峠=>和泉葛城山=>牛滝温泉。本日はトレーニングモード。先週の和泉葛城山と先々週の岩湧山を繋げたルートである。 25kmを7時間で踏破する計画。遅くとも8時間以内にゴールする必要がある。 6時45分に紀見峠駅を出発。駅を降りたのは二人。もう一人は金剛山の方に行ったようだ。和泉山脈に向かうのは私だけである。、、、が、道に踏み跡がある。始発に乗れば6時7分に着けるので先行者がいるのであろう。ありがたい。これで蜘蛛の巣に悩まされなくて済む。道中で二人抜かして1時間半で岩湧山。そこから滝畑までの下山は1時間。相当飛ばしているが急がないと時間制限に間に合わない。滝畑までは600mの下り。三国山へは550mの登り返し。きっついなぁ、もぉ〜。とはいえ、岩湧山から三国山までは広葉樹林が広がっており、日差しも明るく歩いていて楽しい道である。三国山は展望ゼロ。しかもここからはロード。全く面白くない。少しでも時間を稼ぐために走る。いい具合にダラダラしたゆるい下り。鍋谷峠からは先々週に歩いている。ここも眺望のない杉の植林で面白くない。スピードハイクでガンガン行きたいが体力が切れ気味。わずかな上りでもやけにしんどいわ。なんとか7時間、13時45分に牛滝温泉到着。累積上昇は1500mくらいか。 2000mくらいまでは頑張れそうだが3000mとかやっぱ無理やね。温泉に入って送迎バスで岸和田駅へ。温泉の送迎バスの最終時刻が15時30分なのである。今回の制限時間はこれが原因。牛滝温泉から路線バスだと岸和田駅まで680円。温泉に入れば入浴料750円で無料の送迎バスが利用可能。むちゃくちゃお得! いや、我ながら貧乏人根性と言うか、よく言えば経済的と言うか、普通に言えばセコいですな。
@=
(2019-11-06) 紀見峠=>(ダイトレ)=>竹内峠=>太子温泉。ダラっとしていたのでトレーニング。8時間、30キロ。前回は葛城山への登り返しがキツく感じたのだが、今日はさほどの疲労もなくすんなり。体力がついたとも思わないので、季節柄涼しくなり汗をかかなくなったのが大きいのだろう。二上山は敬遠して竹内峠から太子温泉へ。送迎バスのある温泉は下山路に最適である。
@=
使用人の障害児が言った。「僕には夢があります。将来、猿回し師になること。そして、自分のことは自分で出来るようになることです。」主人は怒鳴った。「馬鹿野郎!生意気なこと言ってんじゃねぇ!」物陰にいた少女は少年の手を引き心配した。「謝ったほうがいいよ。ひどい目にあわされるよ。」少年はニコリと笑い、少女に背中を押されるまま、もう一度主人の前に立ち、言った。「僕には夢があります。将来、自分のことは自分で出来るようになること。そして、自分以外の誰かを幸せにすることです。」目が覚めたとき、私の心は晴れており、少しばかり感動していた。
@=
山歩きでいい景色なんて全体のほんの一部でしかない。大半は黙々と歩いているだけ。時間だけは腐るほどあるのであれこれ思索しながら歩く。山道はすべて哲学の道である。昨日、ダイトレを歩きながら考えていたことは、「意識がある」とは何かと言うこと。犬に意識はあるのか?細菌や草木には?狗子仏性。趙州和尚は「無」と言う。釈迦は衆生皆仏性有りとする。自己認識とは何か?人とその他を分けるのは何か?意識の有無を識別する分離軸を色々と捻り出してみるものの、次第に「意識」の定義すらがあやふやになり、果ては意識を生み出すに至った生命の進化に踏み込まざるを得なくなった時点で時間切れ。疲れた体で温泉に入り、全筋肉を弛緩させ、全神経を開放して、仏の境地に達した(あ〜、気持ちええなぁ)時点で、そんなことを考えていたことすら忘れてしまった。
@=
さて、なんとも心地よい目覚めを迎えたのだが、なぜ、そんな夢を見たのかがわからない。障害児の使用人は、私とは境遇も時代も全く違う。半日、気になっていたのだが、ジムで腹筋運動に苦しむ中、やっとわかった。人とその他を分けるもの、意識の本質が問題だったのだ。夢の中の主人は「人間ではない」存在である。使用人の少女は「不完全な人間」であり、障害児の少年は「完成された人間」であったのだ。そしてそれは意識を持つものと持たないものを分ける最良の分離軸となる「未然に対する想像性」の有無にほかならない。大変アホらしい自分の夢を夢判断する行為となったが、個人的には納得できたので(すぐ忘れるだろうから)書いておく。完全に私見である。
@=
(2019-11-10) 岡本駅=>(往:魚屋道,復:有馬三山)=>有馬温泉。 6時スタート。森はまだ暗い。六甲山、登って降りて、温泉を横目に、また登って、、、。復路の番匠屋畑尾根は起伏が大きいため、少し不安であったが案外楽であった。有馬からの六甲山登り返しよりは、ダイトレの葛城山登り返しのほうがキツく感じる。そもそも、六甲は有馬まで往復しても25キロしかない。絶対的な距離が短いので疲労度は小さい。両親、及び、シバジィと極楽茶屋で昼食。その後、私は岡本に戻り。三人は有馬へと向かった。
@=
(2019-11-13) 御幸辻駅=>三石山=>岩湧寺=>紀見峠駅。昨日、思い立って標高のグラフ化を実装した(左地図の右上クリップアイコン)ので、その適用データとなるGPSログを増やすべく山へ。目的と手段を取り違えているような動機の山行であるが、まぁ、いいだろう。かの道元禅師も言っている。修証一等。迷悟一如。悟るために修行をするのではない。悟りは修行の基盤であり、修行そのものが即ち悟りの実践なのだ。そこには目的も手段もないのである。、、、と、誤解した正法眼蔵で自己正当化して、 8時まで寝ていた怠惰も横っちょにおいて遅めの出発。三石山は初めてであるが、麓の杉村公園は整備されているものの、山道に入るとしばらく人が通っていないのか道中蜘蛛の巣まみれとなる。山頂は展望もなく、登る価値は低い。あまり人気がないのも納得だ。ただ、広葉樹林が多いように感じたのでもう少し秋が深まればいい感じの山道になるかもしれない。岩湧山方面に進むも何度も登っているのであまり気が乗らない。よって、未見の岩湧寺に向かうことにする。 400m下ってまた戻ってくるという大変無駄なコースであるが、修行と思えば丁度よい。修証一等である。岩湧寺開基はまた役小角。和泉山脈では弘法大師以上にメジャーな存在。多宝塔は室町時代建立。こんな山中にも歴史があるのが近畿の山のいい所。登り返して紀見峠に帰還。
@=
(2019-11-16) 岡本駅=>横池=>荒地山=>高座ノ滝=>風吹岩=>保久良神社=>岡本駅。午後から散歩。急に寒くなり朝から活動する気がしなかった。軟弱だなぁ。短い散歩なので特筆するほどのことはなし。
@=
「名探偵は嘘をつかない」 2/5点。アンチヒーローっぽい位置付けの探偵。おやっ、銘探偵か?っと、思えばそういうわけではなかった。結果としては助手に簡単に殺られる探偵である。(阿久津透最後の事件、、、か?)ライトノベル的な読みやすさ(とセリフ回し)の割にはコインのくだりなど理解しにくい記述も多い。 SFやファンタジーをガジェットとして使ったミステリは嫌いじゃないのだが、謎解きの核心に転生(死んでも生き返る)を使ったら何でもありなのでもっと奇想天外な驚きが欲しかった所。少々荒唐無稽くらいでもかまわない。読みながら「逆転裁判」に似てるなぁと感じていたが、オマージュ止まりで本家逆転裁判のほうが面白いかな。読後、著者欄を見たら「若い!」弱冠二十歳でこれを書いたというのはすごい。
@=
「隠蔽人類」 3/5点。冒頭から惹きつけられる魅力的な展開。未知の民族の探索。そして人類の新種発見へ。全五章の連作短編は予想を裏切り続け、全く想像出来ない結末へと突き進む。こう書けばさぞかし驚きの連続なのか、、、と思われるが(そしてその通りなのだが)、驚きのベクトルは普通のミステリの読者を置いてけぼりにすること必定である。結末どころか、次章がどう始まるのかもわからんわ!各章ごとの殺人者は、次章では被害者である。犯人も探偵(役)も次から次へと死んでいく。それなりに人物描写をしておいて性格付もされているのに、惜しみなく死んでいく。え〜と、今回は登場人物が7名で冒頭で4人死んだけど、、、「どうすんのこれ?!」てなもんである。行き着く先は、、、。そして誰もいなくなった。それどころか、人類ほぼ絶滅?この力技は個人的には大好きである。
@=
(2019-11-30) 大台ケ原(ビジターセンター=>日出ヶ岳=>尾鷲辻=>ビジターセンター)。ぱぱジィ、しばジィが大台ケ原に行くと言うので同行。整備された道を歩く散歩みたいなものとの甘い思いで行けばすでに雪山であった。身を切る寒さの強風に雪が混じり、これ吹雪じゃねぇかと心配になるが1時間ほどで雲は晴れた。とはいえ、引き続きの強風で日出ヶ岳の山頂にあった気温計ではマイナス7度。露出している顔や手袋をしていても指先は、冷てぇを通り越して痛ぇが正直な感覚。痛みに耐えて写真を取る。大台ケ原はもともと景色の良いところだが、霧氷の回廊は銀枝を揺らせて幻想的である。朝の太陽を浴びてほのかに赤みを帯びた枯並木は満開の桜の通り抜けのようであった。平らな道でさえ滑って危ないので予定を切り上げ3時間で下山。温泉で体を温めてから帰宅。
@=
(2019-12-04) 紀見峠駅=>一本松=>蔵王峠=>燈明岳=>鍋谷峠=>和泉葛城山=>牛滝温泉。曇、ほんの時々晴。以前(2019-10-28)と同じスタートとゴール。ただし、面白みはないが楽な蔵王峠を通るコース。朝は黒くて厚い雲。薄暗い森を駈ける冷たい風がサワサワと草木を揺らし不気味なことこの上ない。修験のみちは霊気にあふれている。笹薮のガサゴソにいちいちドキッとする。多分鳥などの小動物だろうけど、夕闇のごとく森では怖さを感じる。誰にも合わないまま25キロを歩いて和泉葛城山に到着。流石に登山者がちらほらいる。生者に会ってホッとする。やっと人間界に帰ってきた。さて、牛滝温泉は紅葉の名所らしい。一応、狙ってきたのだが、感想は「大したことないなぁ」である。見頃は少し過ぎているようだが、最盛期でもそれなりなんじゃないかな。温泉に入って、「泉ヶ丘」までの送迎バスを利用して帰宅。
@=
(2019-12-12) 新神戸駅=>市ケ原=>再度公園=>森林植物園=>高雄山=>市ケ原=>布引ハーブ園=>三宮駅。体を動かしたい。、、、が、朝は寒い。と言うわけで昼からノコノコと活動。今まで行く機会がなかった西六甲北部の丘陵地帯を散策してみることにする。再度公園から植物園方面は、縦走コースから外れる上、高度もないので敬遠していたのだが、これが山深くてなかなかに良いところであった。紅葉も残っているし、落葉樹林帯のため散ってしまった後の森も明るい落ち葉道である。今の時期、再度公園周辺の森はいずれも日差しがよくのんびり歩くには最適である。
@=
(2019-12-16) 高座ノ滝=>風吹岩=>雨ケ峠=>最高峰=>有馬温泉。同行は上野のI氏。有馬温泉に行ったことがないとのことなので六甲へ。当然山越えだ。ロックガーデンから魚屋道を通るメジャーなコース。平日でもそれなりに人はいた。相変わらずI氏は重機関車のごとく力強く(そして全く軽やかならず)急坂を登ってゆく。山頂から南面は海、薄霧の向こうに四国山地。北面は盆地、青々とした空に北播磨の山嶺が見渡せる絶好の天気であった。 5時間で下山。金泉で汗を流して帰阪。
@=
山田正紀『火神を盗め』2/5点。高度経済成長期、スパイとは無縁のサラリーマン達が、中印国境の原発に仕掛けられた爆弾を撤去するためCIAを相手に奮闘する。感想としてはあまり面白くはなかったかな。時代が今とは違うし、作戦がどう考えても実現不可能っぽい。とはいえ、これらは瑕疵とは思わない。時代は読み替えて当時を想像しながら楽しむことができるし、不可能に見える困難な任務を果たすからこそカタルシスが大きいのだ。人物描写は浅くないし、冒険のスケールも大きい。が、やはり、合わない。単に私の人生経験では登場人物たちの境遇に共感できないのであろう。山田正紀の傑作の一つらしいので面白い人には面白いはずである。
@=
山田風太郎『風来忍法帖』3/5点。風太郎の忍法帖であるから面白いに決まっている。時は戦国後期、麻也姫と七人の香具師。石田治部相手の籠城戦。人間離れした風摩忍者との戦い。登場人物のキャラがとにかく立っている。悪源太助平とか七郎義経とか昼寝睾丸斎とか名前だけで笑うぞ。各人変な特技はあれど、絶対的な強者に立ち向かうには、力押しで敵うわけもなく、知恵を絞り犠牲を厭わぬ覚悟が必要。香具師忍法は鶏鳴狗盗、ならず者の一芸も大活躍。巨根(でかすぎて入らないため童貞)とか何の役に立つんだと思っていたら役に立ったよ。やはり、時代錯誤や荒唐無稽は低評価にはつながらない。娯楽小説なのだから面白ければ良いのである。体がバラバラになっても、つなぎ合わせて生き返ったり、身長も性別も異なる他人に変身できるなど、 SFやファンタジーでも禁じ手扱いの技も忍者だからいいのである。麻也姫は嬋娟可憐でかつ気丈な姫武者と来たもんだ。どれだけ時代を先取りしてんだと思うが、太田道灌と北条早雲の血を引く姫君とあらばそれも良し。色々と力技で納得させられる筆使いである。ただ、『甲賀忍法帖』には及ばない。『柳生忍法帖』にも僅かに劣る。よって、3点。
@=
(2019-12-31) 芦屋川駅=>高座の滝=>風吹き岩=>横池=>七兵衛山=>岡本駅。 2019年登り納め。ぱぱジィ、しばジィ、弟君、姪姫、甥太郎、私の6名。小学二年の体力に合わせて安全で楽なハイキングコース。ただし、子供は元気で、じじぃの方がしんどかったようだ。まぁ、よくあること。曇りがちであったが雨は振らずに済んで良かった。子どもたちにはロックガーデンのアスレチックが面白かったようで良かった。
@=
(2020-01-10) 芦屋川駅=>荒地山=>黒五谷=>打越峠周遊=>岡本駅。運動不足で膝が痛かったため六甲散歩。年末コースの大周りバージョン。普段運動をしない人が山に登ると膝を痛めるものだが、普段膝を良く使っていると逆に動かさないことによって膝を痛める(膝が固まる?)ようだ。大した距離ではないのだが、やけにしんどいし息が上がる。やはり定期的に体を動かしてないとだめだな。コースに特筆することはなし。
@=
(2020-02-05) 奄美大島最高峰、湯湾岳。 9合目まで車で行くと15分で山頂。展望は全く無く駐車場からの景色が一番キレイ。ただし、風景だけなら奄美南部に多々ある各種展望台のほう断然が良い。もちろん、車で行けるしね。
@=
(2020-03-01) 表六甲ハイキング。久しぶりの晴れ、かつ、温暖。 2月は寒くて引き篭もっていた。八幡谷から黒五谷、荒地山、風吹岩を経て魚屋道で帰還。石でやけに滑るなぁと思っていたら、靴底がすり減って真平になっていた。岩場はちょっと危ないかもと思い、荒地山からの下りで巻き道を選択したら、そのまま登山道から外れてしまい、適当な谷に降りて気がつけばキャッスルウォールに着いていた。ロッククライミングはしないので始めて見たけど、クライマーの皆さんすごいなぁ。私は無理です。風吹岩に登り返して、道標に「難路」と書かれた魚屋道を進めば、難路と言うより悪路。難路はアスレチックで楽しい面もあるけど、泥濘の悪路はちょっとも面白くないので次からは避けよう。山手甲南駅(JR)に着いてみれば大阪まで400円。阪急なら280円。当然阪急芦屋川駅まで歩く。
@=
Python2覚書。「Python2の値はだいたい全順序」である。数値と関数や、リストと辞書など型が異なっても関係演算子で比較ができる。関数どうしも比較可能。ただし、「(lambda n:n) < (lambda n:n)」は不定のようだ。「1 < (lambda n:n)」や「1+1j < (lambda n:n)」は有効だが、「1+1j < 1+1j」は無効である。
@=
Python2で関数の比較が不定になる話についての考察。手元の環境(Python 2.7.16 の対話モード)では真偽が交代で入れ替わる。最初の「(lambda n:n) < (lambda n:n)」の実行は真で、次の実行では偽、更に次の実行では真と繰り返される。思うに関数についてはオブジェクトのアドレスで比較をしており、 GCによるオブジェクト回収と再利用のタイミングから規則性が生まれているのであろう。
@=
Python3では異なるタイプの値に対する不等号による比較は出来ない。ただし、ソースを読む限りタイプ違いでの比較を禁止しているわけではない。タイプごとに比較のためのコールバック処理がある。(richcompare周りを読むこと。)
@=
(2020-03-09) 表六甲ハイキング、再び。最高気温20度、Tシャツで歩ける。今まで寒かっただけに最高だ。見知ったコースなんで風景に特筆することはなし。先週迷った荒地山を再訪。正しい下り道を確認する。すれ違いの中学生くらいの男子三人組が岩場と格闘していた。「この道下るんですか?」「うん、そうだよ。」「すごいですね。」「まぁ、何度か来てるからなぁ。」初めてだと結構怖いのかもしれないね。大人ほどの身長がないから大きな岩の急坂は難しいのかもしれない。そういえば上りの住吉道でも中高くらいの女子四人組とすれ違った。コロナ休校で行くとこがないからみなさんハイキングしてるのかな。山はウィルスもないし、中国の工場が止まってPM2.5が少ないのか、えらく先まで遠望できる。いい機会だからみんな山に行けばいいと思うな。花粉症の人は大変だろうけど、、、。
@=
(2020-03-13) 阪急岡本から六甲最高峰周遊。曇り時々晴れ。健康のための散歩。特段記すべきこともなし。平日であるが人が多い。なんせ、中高生によく出会う。まっ、急に休みになって、レジャー施設も休園ばかりじゃ暇するよね。もちろんファミリーや若夫婦の頻度も高い。いつもは年配者ばかりとすれ違うのになぁ。最高峰から少し下ったところで、足元を確認しながら歩いていると、前方から声がする。「あの人に聞いてみよう!」顔を上げると高校生くらいの女子二人組だ。「後どのくらいあります?」「あぁ、もうすぐだよ。(GPS時計を確認しながら)ここが850mで山頂が930mだからもう100mもないよ。」「もう、そんなに登ってたんだ。ありがとうございます。」「いえいえ、気をつけてね。」そんなやりとりがあって、50mほど進むと、先ほどと同年代っぽいバテ気味の四人組。山で女子高生とか普段ならありえんよなぁと思いつつ挨拶してすれ違うと、後ろから大きな声が聞こえる。「もう後、100mやってー。もうちょっとやでー。」どうやら、同じグループだったようだ。うんうん、頑張ってねー、だけど、その言い方はヌカ喜びさせるんじゃないかなぁ。距離100mと勘違いさせそう。標高差100mは15分位はかかるよ。古来、山登りで言われる「もうちょっと」とか「あとほんの少し」ほど当てにならない言葉はないので注意しましょう。
@=
(2020-03-19) 六甲最高峰往復。近郊の山は若人で賑わっている。特に学生とファミリーが多いように思う。世間では給金や単位がもらえて休みなんだから、折角の機会と捉えて楽しんでいるんだろうなぁ。無職無給の私にはあまり関係ないのが残念な所。保久良神社から金鳥山経由を予定していたのだが、小さな子連れのハイキング客が多かったため八幡谷に変更。雌池を目指していたら道迷い。踏み跡のような獣道(猪の足跡があった)のような山中をしばし彷徨う。こういう時スマホの地図とGPSは助かる。正しい道の存在さえ確認できれば少々怪しい状況であろうと突破できる。二時間ちょいで六甲最高峰に到着。1クラス分ほどの学生がいて驚く。平日なんて通常なら誰もいないのに、、、。手洗い、うがい、(できれば都会から離れて)適度な運動。自然はコロナとは無縁の世界。感染症対策としてはこれが一番良いように思う。
@=
(2020-03-21) 岡本有馬往復。晴れ。シーズンに向けてのトレーニング。 10時40分、遅めのスタート。もう少し暖かくなれば早朝から行くのだが、まだ朝夕は寒い。 3時間以内に有馬に着ければ往復も可能だろうと、13時30分有馬到着を目標にハイペースで飛ばす。今日は本当にハイカーが多かった。特に若いカップルが多かった印象。年配のグループを追い越すときに聞こえてきた会話。「40回以上来てるけど、こんなに多いんは初めてや。」うんうん、私も40回以上来てると思うけど、確かにこんなに人が多いのは初めてかもしれない。山頂広場は混んでいると予想。最高峰は帰りに寄ることにしてまずは有馬を目指す。閑散とした温泉街かと思えば意外と観光客が多かった。減った外国人の分を補うだけの日本人が訪れているようだ。中国語や韓国語に溢れていた数ヶ月前に比べれば半分ほどの人手であろうが、数年前に比べれば何倍も多い。 13時20分。有馬温泉のバス亭に到着。風呂どころか汗を乾かす間もなくすぐさま引き返す。汗臭い登山スタイル。時間に余裕があるため最高峰にも寄り道、遅めの時間にかかわらずそこそこの登山客がいた。すぐに下山。ここからは流石に空いている。有馬までは1時間もあれば行けるが、神戸側に戻るには普通の人なら3時間はかかる。茜さす静かな道すがらウグイスの鳴き声なんかも聞こえて来るのは風情があってよろしい。 16時20分駅到着。24キロを5時間40分は山ではなかなかいいペース。時速4キロを越えている。ただ、トレランする奴は最低でも時速6キロで走ってるんだよなぁ。奴らは化物だ。あと、今回最大心拍数が188であった。46歳のオッサンが出していい数字じゃない。むしろ体に悪そうである。
@=
麻耶雄嵩『友達以上探偵未満』3/5点。 JK探偵の「伊賀もも」と「上野あお」の桃青コンビ。ライトノベル風味で読みやすい。作中の小ネタ元ネタもベタだったり意表を突かれたりと面白い。ただし、事件は殺人でがっつり推理力を要求される。問題編の最後に「推理しましょう、もしくは一句」とあり、解決編が別立てで用意される犯人当てになっているのだが、二戦二敗。残ったのは汚いメモに的外れの推理と、下手な俳句が二つ。話の展開は素直。当たらないのも騙されるのもむしろ快感なのだが、麻耶雄嵩にはどうしても毒を求めてしまうため、少々物足りなく感じる。とはいえ、最後まで読むと桃青コンビの見方(特にあお)がガラリと変わるのは見事。一読と再読では垣間見える探偵の心の内が正反対になる仕掛けはうまいなぁ。麻耶雄嵩の作る探偵はいつも魅力的である。道徳心の欠片もない銘探偵。ワトソンにプロデュースされる(踊らされる)名探偵。使用人任せで自分では推理しない探偵。全知全能(ていうか神様)で推理しなくとも犯人がわかる探偵。独断と偏見で犯人を当てるものの、ワトソンにダメ出しされポンコツ扱いされる探偵。そして、今回は二人で一人の名探偵(候補)。次はどのような探偵が来るのか、、、麻耶雄嵩のミステリーはいつも楽しみである。
@=
(2020-03-26) ロックガーデン周遊。晴れ。トレーニング、、、のつもりが、寝坊して12時スタート。加えて、やけにしんどい。どうやら先週25キロの疲れがまだ取れていないようだ。いつもの散歩コースにする。以前迷った八幡谷から横池の北を抜けるコースを進む。どこで迷ったのか確認しておこうと思ったのだが、怪しげな分岐すら見つからないままメインルートに合流。不思議だ。以前はよほどボォーっと歩いていたのだろうか?幅広の登山道は明瞭で、迷うほうが難しいくらいであった。本日、風吹岩周辺はどういうわけか無人(中央嶺はそれなりに人多し)。どうしたものか思えば、岩の上からいちゃつくカップルの声。あぁ、なるほどね。こりゃなんか居心地悪いわ。座ってるならまだしも寝転がってベタベタしているのは流石に見ていられませんわ。私も早々に退散。
@=
fuse2fsでマウントしたext2fsではgitが使えない。 gitは一時ファイルを作成するとき(sha1-files.c:create_tmpfile -> wrapper.c:git_mkstemp_mode)、「flags=O_RDWR|O_CREAT,mode=0444」でオープンしようとするが、 fuse側では書き込み可能モードで書き込み権限がないオープンをアクセス違反(fuse2fs.c:check_inum_access)としている。 gitのバグと言ってもいいと思うけど、mode=0644にできない理由が何かあるのだろうか?そもそも、通常のファイルシステムで「flags=O_RDWR|O_CREAT,mode=0444」を許しているのはなぜだろうか?歴史的な経緯ってやつなのか。
@=
gitの謎実装だけど、ファイルを作成した自プロセスのみ書き込み可能だが、他プロセスは読み込みのみ可能にしたい、、、ということだろうか。ファイルを作成してからmodeを変更するのではアトミックじゃないし、アドバイザリロックじゃ強制できない。しかし、一時ファイルを他者がリアルタイムに読み込みたいなんて言う状況がそもそもないだろうからやっぱ謎だ。
@=
(2020-04-10) 紀見峠から金剛山。 20キロ弱の健康維持。三疎(疎開、疎散、疎外)を求めて山へ。午前中は曇りがちで風が強く肌寒い。 1Lのお茶は全く飲まず、汗もほぼかかなかった。杉の針葉樹林はとにかく暗い。誰一人いない修験の道は霊験あらたかで怖いくらい。いつもは巻く神福山に初めて登る。視界のない山頂に祠が2つ。道中の無事をお祈り。今日は金剛山までのショートコースなのでゆっくり目に歩く。 12時半に山頂着。流石に人が多い。大半は千早本道の利用であろう。別ルートで登っていたパパじぃたちと合流して、タカハタ谷コースで下山。金剛山は大抵の道が急だけどここも相当なもの。何箇所かロープの岩場もあり面白いが、基本的には植林が多くて視界も開けないため退屈。腰折滝はまぁまぁ。金剛山で名瀑を期待するわけにもいかないしこんなものかという感じである。
@=
(2020-04-15) ロックガーデン周遊。いつものコース、プラス、アルファ。岡本駅から八幡谷を経て七兵衛山、荒地山、風吹岩、打越山、十文字山と巡って岡本駅に帰還。荒地山の下りにテーブルロックに寄る。今まで存在は知っていたものの何処にあるのかわからなかった為、初めての訪問である。さぞや足のすくむ絶壁か?、、、と思いきやそんなに高度感もなく特に怖くはなかった。場所は新七右衛門嵓とその上部の鎖場の間で西へ向かう(登りに見て左手)踏み跡を辿れば良い。それっぽい踏み跡は複数あるが多分どれでも大丈夫なはず。私が今回通ったのは鎖場の下10mくらいのところから西に続く小道である。風吹岩周辺はそれなりの人手。とっとと通過。帰り道の十文字山も初めてであったのだが、山頂が何処かわからずしばし迷う。もしかすると柵に囲まれた私有地内なのかもしれない。特に展望が良いわけではなさそうなので、わざわざ山頂付近に足を踏み入れる価値はなさそうである。
@=
TeXによる数式表示をLaTeX+dvipngからKaTeXに変更した。今どきスマホですら十分な性能があるのだから、サーバは必要最小限の処理しかしないほうが賢明だ。大昔はシンクライアントとか言ってた時代もあったなぁ。さて、折角なので\KaTeXを利用して電磁界方程式とか書いてみる。
相対論形式での記述はとても綺麗である。美しい方程式は覚えるのが簡単だ。アインシュタイン方程式 G^{\mu\nu} - \lambda g^{\mu\nu} = \kappa T^{\mu\nu} はもっと綺麗だと思うのだが、残念ながら半分も理解できない。
@=
\displaystyle
\begin{aligned}
& \partial_\nu f^{\lambda\nu} = \mu_o j^\lambda
\\ & \partial_\nu *\bm{f}^{\lambda\nu} = 0
\end{aligned}
(2020-04-25) 尼ヶ岳、大洞山。快晴。ジジィ連に同行。毎度々々、ジジィ連と呼ぶのも何なので「いぶし銀登山クラブ」と命名。そのまま訳して英名称を`Smoke Silver Climbing Club'とする。この英名称を日本語に逆翻訳すると「煙たい年寄り山歩き愛好会」でこちらのほうが実情に近い。まぁ、とりあえず俺達SSCCとか言ってみたいだけである。さて、登山口の倉骨峠で標高800mなので、尼ヶ岳、大洞山ともに比高は200m程度と楽なもの。 SSCCの体力に合わせたゆっくりペースなのでなおさら。尼ヶ岳は北東から南西にかけて、大洞山は東西と南への展望が広がる。日本は山ばかり。滋賀、奈良、三重、和歌山にかけて山容が見渡せて素晴らしい。惜しむらくは霞がかっていること。黄砂であろうか。帰路に利用した山麓の道も苔むした岩が転がる落ち着いた雰囲気が良い。時折聞こえるヒバリやウグイスの鳴き声も風流だ。外人さん御一行と出会ったので「どこから?」と聞いてみるとスイスからであった。アルプスの本場から来てるとは驚き(名古屋住まいだそう)。大洞山からは「関西のマッターホルン」との異名を持つ高見山が綺麗に見えるのだが、本物のマッターホルンとは比較にならない(と思う)。
@=
bashの変数置換は遅い。たかが改行削除に外部コマンド呼ぶのもなぁ、、、と思い、
- BAR=$(tr -d '\n' <<< "$FOO") ==> BAR=${FOO//$'\n'/}
 800kmの徒歩旅行を終えて破顔一笑の私@フィニステレ岬(一年前)。誰も存在を知らないネットの片隅ながら公開はされているので、プライバシーを考え意図的に人物の写真は控えていたのだが、風景だけでも詰まらないので顔認識AIによる自動モザイク機能をプログラムしてみた。 AIについては素人だけどライブラリを使えば僅か数行で実装できてしまうのだから簡単だ。 GPGPUによる開発環境を整えるほうが手間であった。
@=
800kmの徒歩旅行を終えて破顔一笑の私@フィニステレ岬(一年前)。誰も存在を知らないネットの片隅ながら公開はされているので、プライバシーを考え意図的に人物の写真は控えていたのだが、風景だけでも詰まらないので顔認識AIによる自動モザイク機能をプログラムしてみた。 AIについては素人だけどライブラリを使えば僅か数行で実装できてしまうのだから簡単だ。 GPGPUによる開発環境を整えるほうが手間であった。
@=
Debian10でCUDA開発環境を構築する際の覚書。
- # apt install nvidia-driver nvidia-cuda-toolkit
- NVIDIA DEVELOPPERからcudnn(v7.6.5 for CUDA 10.1)をダウンロードして/usr/local/cudaにインストール。
- $ pip install face_recognition
- $ python -c "import dlib; print(dlib.DLIB_USE_CUDA)"
- False
- $ git clone https://github.com/davisking/dlib.git
- $ cd dlib
- $ mkdir build
- $ cd build
- $ export CC=gcc-7
- $ export CMAKE_PREFIX_PATH=/usr/local/cuda
- $ cmake .. -DDLIB_USE_CUDA=1
- $ cmake --build .
- $ cd ..
- $ python setup.py install
(2020-05-08) 岩湧山。晴れ。 9時過ぎ、電車がすく時間になって出発。普段は紀見峠駅からすぐに西へ向かう林道に入るのだが、今回は、一旦、紀見峠まで上がってそこからダイトレに入る。少々遠回りとなるが見飽きた林道歩きよりはよろしい。山頂付近でマウンティングバイクを何台か見る。皆、バラバラに行動していたのでグループというわけではなさそうだ。その他、食事する者、読書する者、寝ているものと思い思いのレジャーを楽しんでいるようだ。ススキは刈り取られているが、新緑の候、暖かい日差しに、冷たい薫風を浴びて気持ちが良い。山腹の里ではツツジも満開であった。
@=
熊野川を下る。そう考えた時、どこから始めるべきであろうか。本宮からと言うのが一つの答えであろう。そもそも熊野川なる名称は、下流域である和歌山県内でのものであり、奈良県側の中流域では十津川と呼ばれ、上流域では天ノ川と称される。しかしながら、下流の比較的平坦な流路に沿って歩くだけで、熊野川を歩いて下ったとするのではなんとも寂しい。やはり、上流部から、出来れば源流から辿ってこそ熊野川を制したと言えよう。地図を追う。天ノ川は天川村の川合よりやや東、山上川と川迫川が合流する所から始まる。おそらく最遠の源流はいずれかの先にあろう。河口からの直線距離であれば山上川、流路に沿って測るなら川迫川になるだろうか。どちらを選べば良いのか。悩ましい、と思いきや実は簡単な解がある。山上川は山上ヶ岳西北の谷、川迫川は南麓の谷に端を発する。よって、両者の分水嶺たる山上ヶ岳に登ってしまえば、そこが紛うこと無き熊野川の濫觴と言ってよかろう。
@=
(2020-05-12) 熊野川紀行(源流編1)。阿部野橋まで歩く。普段なら絶対に乗らない特急で下市口へ。乗客は車輌に二人。洞川温泉行きのバスは私一人。温泉街から1キロほど離れたキャンプ場を拠点とする。テントを張り終え、未だ二時前。近場の大天井ヶ岳へと向かうが、登山道が閉鎖されていた。仕方がないので下見として山上ヶ岳入口、女人結界まで行ってみる。山上川沿いの自然散策路では子供たちが川遊びをしていた。水は透き通り、木の葉を反射してか、青にやや緑がかかったように見える。この辺りの清流は大峰ブルーと呼ばれるらしい。登山口の清浄大橋には駐車場があり、観光客も幾名かいたが、格別見るべき程のものはない。珍しいと言えるのは女人結界くらいか。キャンプ場に戻り、汗を拭いて洗濯物を干し、袋麺で食事にすると半径2メートルのエリアだけ一気に生活感がただよう。なお、キャンプ場は貸切状態である。半径100メートルは杉の木立である。日の入とともに就寝。寒くてほとんど眠れた気がしないのだが、何度も夢を見ていたのでまどろんではいたのだろう。以下、どうでもいい夢の一話。突然の大雨に驚いて目覚めると、テントが何者かに押されている。どうせ鹿だろうと寝なおそうとするも、テントを押し倒されてしまう。テントも寝袋も水浸し。冷たい雨の中、エライ苦労をしてテントを立て直し、搾った寝袋に震えながら潜り込んだところで再度目が醒めた。うぅー、さむー。夢で良かった、、、とは思うものの、どうせなら最初の雨に驚いた時点で本当に目覚めてほしかった。
@=
(2020-05-13) 熊野川紀行(源流編2)。山上ヶ岳から大普賢岳。先の考察の通り、熊野川の起点と言えるのは山上ヶ岳である。山頂の大峯山寺は役小角以来1300年の歴史を持ち、修験道の根本道場として行者達の信仰の地であり第一の霊場でもある。今回の旅の最初の目的地として誠に相応しい。 5時起床。実際には寒くて3時くらいから寝袋で震えていた。朝食はクリームスパゲティ。茹でてレトルトのクリームシチューを混ぜるだけ。 6時半出発、7時半に清浄大橋。ここから800メートルの高度上昇。途中一度休憩を挟んで二時間の登り。道中茶屋が多く、普段なら賑わう参詣路であろうが時節柄誰もいない。おそらく周囲数キロは誰もいない山中である。なんでもない鎖場であるが、絶対に事故れないと思うとやはり緊張する。大峯山寺も参詣停止中。無人の伽藍に石碑が立ち並び、不動明王は虚空を睨む。初夏の眩しい光の中、境内は異様な霊気を孕んでいる。白昼であるがゆえに怖さが引き立つ。三度視界の端に人影を感じ、目を向けると石灯籠に隠れた。非日常が心象に投影する幻影であろう、、、が、単に寝不足による錯覚かもしれない。山頂に立つ。西北に伸びる谷は山上川となり、南からJの字を書く谷は川迫川となる。この2つの大渓谷が熊野川の源流である。広潤な谷も素晴らしいが、見渡す大峰山脈は別格だ。南西に荒々しい稲村ヶ岳の山嶺、その向こうには台地状でどっしりとした弥山が控える。 10時前、大普賢岳を目指し奥駈道を進む。往復のコースタイムは5時間半。4時間で達成できれば夕暮れ前に下山可能だ。とりあえず12時までに行けるところまで行って、時間切れなら引き返すことにする。大普賢岳には行かねばならぬ訳がある。地図で確認する限り、川迫川の一部支流が大普賢岳と稲村ヶ岳の方に伸びており、熊野川最長の源流がこの2つの山に発している可能性がある。片手落ちとならぬようこれら二峰もしっかりと踏みしめておきたい。予定通り二時間弱で大普賢岳に到着。東方にも広く視界が開けているため大台ケ原までがよく見渡せる。道標によると弥山まで10キロ。キャンプ地の洞川までは15キロ。引き返すのがなんだか惜しいが仕方がない。疲れも大分と足に来ている。山上ヶ岳に戻ってレンゲ辻からレンゲ坂谷を下る。山上川はこの谷から始まるため、ここでの水源を見ておけば、熊野川を源流から辿ったと言ってもよいだろう。ガレた沢筋は岩壁に挟まれ落石が怖い。細心の注意を払って急いで通過する。涸れ谷が湿ってきた頃、大きな岩の下から雫が落ちているのを発見。うむ、満足。熊野川の始まりを確認できた。後は川沿いにキャンプ地まで戻るだけ。まぁ、季節や雨の状況によっては水源は移動するでしょう。本当は川迫川の水源も辿りたいが登山道がついていないのではやむなし。キャンプ地に戻ると管理人が豆ごはんに佃煮、牛肉と山菜の煮付けをごちそうしてくれた。あぁー、めちゃくちゃうまいわぁ。本日は30キロを歩いてクタクタ。風呂を沸かしてもらい、毛布の貸出を受けて、日の入り前には寝袋へ。
@=
(2020-05-14) 熊野川紀行(源流編3)。稲村ヶ岳。 6時起床。稲村ヶ岳は近いので8時まではのんびり過ごす。朝食はカレースパゲティ。茹でてレトルトのカレーを混ぜるだけ。 8時半から登山開始。稲村ヶ岳には20年以上前に両親と来たことがあり、母親でも登っていたのだから簡単なハイキングコース、、、との思い込みがあったのだが、どうしてどうして、「落ちたらやばいな」と思える箇所も多々あり、なかなかの緊張感であった。道中出会った人の話では大日山のトラバースでは何年かに一度滑落事故が起こっているらしい。だよなぁ。危ないよここ。さて、稲村ヶ岳はJの字の川迫川の中央に位置し、山頂の展望台からは川迫川を大きく取り囲む大峰山系を四方に見渡せるため、景観は山上ヶ岳や大普賢岳より優れている。雲一つない晴天で、金剛山や葛城山までが綺麗に見えたのには驚いた。稲村ヶ岳を中心に東北の一部を除く10キロ四方はほぼ熊野川の源流と言って良いエリアである。見渡す渓谷の無数の沢は全て熊野川の源流なのだ。うむ、満足。目的達成、さぁ、帰ろ。来た道を引き返す。途中、岩峰の大日山にもチャレンジする。鎖を登り梯子を越え怖いなぁと思いながら進むものの、途中の鉄階段で挫折。 30歳を過ぎてから高いところが怖くなってしまった。法力峠まで引き返して、観音峰からみたらい渓谷の方に下る。観音峰には長慶天皇の碑がある。南北朝の戦争に敗れ、吉野から追われたらしいが、よくもまぁ、こんなとんでもない山奥までと同情する。なんだかんだで20キロを歩いてキャンプ場に帰還。風呂を沸かしてもらい、食事も用意してもらうことにする。鍋うどん。うまぁ。さて、しばらく管理人と話していたのだが、若い頃は娘を担いで稲村ヶ岳に登ったそうだ。また、学校行事でたくさんの中高生が登るみたいだけど、過去、滑落して死んだ先生もいたんだとか。うん、普通に怖いところがたくさんあったよ。
@=
(2020-05-15) 今晩からしばらく雨。テントをたたみ、家に戻ることにする。人混みを避けるため昼前のバスに乗る。乗客は一人。電車は来たときと同じく特急。まぁ、高いけどね。今の御時世、そのくらいはした方がいいだろうし、政府が10万円を配ってくれるという話もあるから、ある程度は消費して地域経済に貢献するべきだろう。さて、次回は、熊野川紀行、上流編。、、、に行く前に今一度源流編パート2としようと思う。弥山川や舟ノ川、大峰山脈東の北山川も十分に熊野川の源流と言っていい資格を持つ。ならば、八経ヶ岳や釈迦ヶ岳にも登っておく必要がある。また、将来、大峰奥駈道を縦走するための下見でもある。
@=
(2020-05-28) ロックガーデン周遊。天気がいいので六甲散歩。いつものコースで先行く爺さんを追い越そうとしたら声がかかる。話すところでは、「100名山、200名山、全都道府県最高所」を制覇したそうだ。やるな、矍鑠ジジィ。話はいつしか海外となり、シルクロードから中国の名山、ネパールでのヒマラヤトレッキング、チベットの話題からは自然と河口慧海に続くなど、なかなかに切り上がらない長話となってしまった。月牙泉、峨眉山、スークーニャン、ポカラ、ダウラギリ、、、。なんでこんなジィさんからこんな言葉が出るんだと思っていたが、向こうもなんでこんなオッサンからこんな言葉がと思っていただろう。ジジィになってからキナバル山に登ったとかは普通に凄いと思う。 4000m越えてるからなぁ。私だと高地順化なしでは高山病になりそうだ。なお、語学が達者というわけではなく翻訳アプリを使ってるらしい。「次は、ミャンマーの遺跡に行きたい」と言っていたので、「パガンのことですね、是非行くべきです」と答えておいた。やるな、老黄忠。「子供達も親が施設にいるより、海外ほっつき歩いてる方が気楽やろう。カッカッカッ。」は名言かもしれない。さて、いつものごとく七兵衛山から荒地山に向かい、テーブルロックで巻き寿司を食べる。日差しは暑いが風は冷たく気持ちが良い。いろんな鳥の鳴き声がBGM。ただし、ウグイス以外はわからない。鳥と花の知識はもう少しあったほうが楽しいと思うので勉強するかな。
@=
(2020-05-29) 天見からダイトレ経由水越峠。 SSCCが金剛山に行くと言うので、彼らとは別コースのロングルートで金剛山へ。出発地の天見は「ザ・日本の農村」と言った風情。大阪にもそれなりに立派な棚田があるものだ。しばらく田舎道を歩いて登山口へ。道は整備された区間と放置された区間の落差が大きい。所々、シダが登山道まで進出していて足元が見えない。何だがジェラ期の森を歩いているような気分になる。いや、ジェラ期行ったことないけどさ。ジェラシックパークみたいな感じではある。歩くと時々ゴソゴソと音がするが、流石に恐竜はいないのでヘビかトカゲであろう。恐竜たちの生き残り、、、ではない。本当の末裔は木々に隠れて狂騒中である。マイナールートで誰もいないのは嬉しいのだが、蜘蛛の巣にまみれるのは少し気が滅入る。新味に欠けるとは言えダイトレに入ればやはり快適である。道中、大峰の山が綺麗に見えていてちょっと嬉しい。山頂に着けば結構な人だかり。登山道ですれ違うことはあまりなかったので大半は千早本道の往復なのであろう。昼食後のSSCCと合流。どうせSSCCは遅いだろうと思っていたら私よりも1時間も早く着いていた。やるな。SSCCも老人にしちゃあ結構元気だ。下山はダイトレを通れば水越峠まで簡単な道のり。車に同乗させてもらい、風呂に入ってから帰宅。
@=
(2019-06-08) 和泉山脈散トレ(散歩&トレーニング)。梅雨入り前の晴れ間に岩湧山散歩。往復するだけじゃ簡単すぎるので、山頂を目の前にして一旦下山。岩湧寺の登山口まで降りる。が、高々300mの下降であった。あら、案外大したことないのね。登り返しは健脚コースと書かれた標識に従う。階段多め、坂キツめ。とは言え、やはり大したことはない。道標では下り向きとの説明があったけど、むしろ下りこそ怪我しないために緩い坂を選択すべきだと思う。岩湧山山頂に着けば大阪平野は雲ひとつない快晴。ただし、モヤが出ているので遠望がきかないのは残念。大峰の方を振り返ればこちらは結構な雲がかかっていた。紀伊半島南部は日本有数の多雨地帯。熊野川紀行は行くタイミングが難しい。さて、6月ともなるとハードではなくとも汗だく。本日は早めの帰還。
@=
(2020-06-16) 表六甲中周りコース(いつものコース)+東お多福山。いろいろやりたいことはあるけれど、折角の梅雨の晴れ間に外出しないのはもったいないしで、すぐ行けるいつもの散歩コースへ。先日まで長く雨が続いたため結構ぬかるみが多い。登山道も一部小川状態になっている。久しぶりに立ち寄った東お多福山は、草の背丈が私の身長を越え道が見えない部分もちらほら。遠目には美しい草原という感じだけど歩きにくいし視界も制限されるので今の時期は避けたほうが良さそう。緊急事態宣言も終了し、会社や学校が始まったからか一時期より人は少なくなってきた。個人的にはこの方がのんびり落ち着けてよろしい。ただし、季節柄かもしれないが空気は淀んできたように思う。高々10キロちょいの散歩コースながら、6月ともなると暑くて汗だく。そろそろ低山は厳しい季節となってきた。本日、1Lは汗をかいたな。
@=
(2020-07-08) 北海道ロカビリー道中1日目。同行はSSCCのジジィ連二人。パパじぃとシバじぃ。当初は母親も同行して北海道一ヶ月(基本キャンプ)を考えていたのだが、足が痛くてハードな旅は無理とのことで断念。ここ数年のうちに連れ出さないと年齢的に無理かなぁとは思っていたが、足腰が衰えるまでの体力残存期間に間に合わなかったことは残念である。さて、北海道は四度目である。釧路から根室、知床、網走と海岸沿いに歩いて、屈斜路湖、釧路湿原を縦断する道東千里(400km)周遊が2012年。翌2013年は、富良野から旭川、天塩川を下って道北を稚内まで歩き、さらに勢い余って利尻、礼文まで行ってしまった。さらに翌2014年には、留萌から暑寒別岳を越えて石狩川を遡上、旭川から大雪山に登り層雲峡に抜け、糠平、足寄、阿寒を経由して網走まで、北海道を日本海からオホーツク海まで(やっぱり歩いて)横断している。それぞれ三週間くらいだから計60日程度は北海道をほっつき歩いていたことになる。まぁ、(相当マニアックかもしれないが)それなりに良いところは知っているつもりなので、冥土の土産になるくらいの旅は提供できるはずだ。しかも今回は車がある(72歳越えのジジィに歩けとは流石に言えない)(ただし山には登ってもらう予定)。楽勝やろとは思うが、さてさてどうなるかな。なお、本日は大阪を17時に出て舞鶴まで4時間半。大阪を抜けるまでは大渋滞であった。船は予定通り23:50出港。明日の夜には小樽である。
@=
(2020-07-09) 北海道ロカビリー道中2日目。船に乗ってるだけの一日。なんにもない。梅雨のシーズン、各地で豪雨みたいだが、日本海は晴れ。 20:45、定刻で小樽港着。本日は2000円のドミトリー。寝るだけなんで十分である。小樽は時節柄、静まり返っている。何度も来ているので見たいところもない。ジジィ連は居酒屋へ。キッチンに冷蔵庫と電子レンジがあったので、私は近所のドラッグストアに買い出しへ。大盛り冷凍パスタをレンジでチンすればお腹いっぱいである。
@=
(2020-07-10) 北海道ロカビリー道中3日目。一座目、ニセコアンヌプリ。晴れ。小樽の近場からということでニセコへ。最初に目指したキャンプ場が7月中は閉鎖ということで、いきなりアテが外れる。町営なんで大事を取っての休業との説明であったが、(コロナには変なクレーマーや変な警察も多いだろうし)、いくら休んでも給与がもらえる町営ならではという気もする。慌てて近隣のキャンプ場に営業中かの確認の電話をする。民営は普通に開いてるし、公営もだいたいは営業していた。一安心。ついでに言うと本日キャンプ場の管理人はマスクをしていなかった。施設によって相当温度差があるようだ。テント設営して13時半。明日はニセコアンヌプリ登山なのだが、聞けば往復3時間とのことだし、ジジィ連のビールタイムも始まったので、明日の下見として一足先にニセコアンヌプリに登る。手軽に登れて眺望抜群。いい山である。「富士は遠くから眺めるもの」との言葉もあるが、羊蹄山も少し離れて眺める方がいいのかもしれない。 15時半には下山。17時から焼肉。個人的には色々と口出ししたくなるのだが(そして実際口出ししているが)、出来るだけ我慢するようにする。本人たちは楽しそうだし良しとしよう。私は食後温泉へ(ジジィ連は食前に温泉済)。キャンプ場隣の五色温泉は湯治の宿という感じで趣がある。ただ、800円は少し高いかなと思う。 21時には宴会も終わり就寝。
@=
(2020-07-11) 北海道ロカビリー道中4日目。二座目、イワオヌプリ。曇り時々晴れ一時雨。夏の北海道は半白夜と言うか、4時から20時くらいまでは明るい。標高800mのキャンプ場はそれなりに冷え込むがセーターを着込めば我慢できないほどではない。日も高くなった7時。SSCCとともにニセコアンヌプリ登山開始。シバじぃ、バテまくり。でもまぁ、頑張って登るだけの価値はある山である。山頂でノンビリしていたとは言え下山したのは12時過ぎ。昼食に食パンを一枚食べて、一人、イワオヌプリへ。こちらも悪くはない山である。硫黄の散らばる噴火口跡があり、生を拒絶する風景が広がる。ただ、別名硫黄山という通り、ありきたりとも言える。噴気孔の上がらない大涌谷や、屈斜路湖の硫黄山、栃木の殺生石周辺なんかをイメージすれば、それはイワオヌプリである。なぜか西洋人がたくさん登っていた。外国のガイドブックに載っているのだろうか。 15時にはキャンプ場に戻る。早めに食事を済ませ、温泉にゆっくりつかることにする。 SSCCは多分宴会してるやろ。
@=
(2020-07-12) 北海道ロカビリー道中5日目。曇りのち晴れ。標高800mのキャンプ場は結構寒い。ついでに道央以南は天候が崩れがちということで道北へ。海岸沿いの道は単調で面白みにかける。増毛に着いたのが午後3時半。この時間から買い出しやテントの設営などが面倒なので暑寒荘(無料)へ。先客が二名いた。71歳のおば(あ)ちゃんズ。明日、暑寒別岳に登るそうである。私達もここまで来た以上は登山である。暑寒荘は設備充実、生水が飲めない(要煮沸)こと以外は快適である。布団やマットまである。
@=
(2020-07-13) 北海道ロカビリー道中6日目。曇りのち晴れ。三座目、暑寒別岳。山頂付近は霧、一時雨。 4時起床。5時発。暑寒別岳の標高は1492m。山荘付近で300mくらいはあるので比高は1200m。大倉から塔ノ岳に登ることを考えたら大体同じ感覚である。 SSCCに合わせてゆっくり登る。パパじぃは登頂成功。シバじぃは9.5合目までは来ながら無念の断念である。暑寒別岳は花の100名山に選定されているだけあり、山頂付近の高原は高山植物のお花畑となっており一見の価値はある。晴れてたら良かったのになぁ。 6年前にも登ったことがあり、その時も霧で景色は何も見えなかった。虫の多い山(特に蚊)なのだが、6年前よりは激減している(それでも多いけど)。 7月も遅めになれば蚊の発生も落ち着くのかもしれない。 11時間(20km)に及ぶ登山後となれば、さらなる活動をする元気はなし。暑寒荘にもう一泊である。
@=
(2020-07-14) 北海道ロカビリー道中7日目。梅雨の影響が少ない北部を目指して一気に美深へ。留萌から美深までの100kmは本当に何もない。自動販売機すらない。なかなかの僻地っぷりであった。やっと到着した美深の町で遅めの昼食。美深アイランドキャンプ場は道の駅の隣で大変整備されている。入浴施設やコインランドリーまで併設されており、溜まった垢と汚れた下着を処理するには最適である。テントを張って洗濯をして風呂に入ればなんだか疲れてしまって夕食もそこそこに寝てしまった。
@=
(2020-07-15) 北海道ロカビリー道中8日目。美深町巡り。名所は函岳と松山湿原。函岳は標高1129mで360度の視界が開ける。が、曇り空に霧多めで、見えるはずの日本海、オホーツク海、利尻山に旭岳と、、、どれも見えず。まぁ、それでも一部の霧が晴れたら美深町くらいまでの高原は見渡せて十分に綺麗。四座目に数えたいところだが、山頂まで車で行けるので山登りは出来ない。そもそも山登りしようにも登山道がない。残念。松山湿原は標高900mの高層湿原。駐車場からは30分、200mくらいの上りで登山で疲れた足の整理運動にはちょうどよい。が、やはり霧。残念ではあるが幽玄な雰囲気があるのでこれはこれで有りである。晴れてたらきっとこんな感じなんでしょう。
@=
(2020-07-16) 北海道ロカビリー道中9日目。曇り後晴れ。本日は休養日。キャンプ場でまったり。温泉施設でまったり。空いた時間に日記をまとめて書く。食事は昨日の余り物。プラス外食。明日以降また移動が続くかもしれないので洗濯を済ましておく。キャンプ場に無料のwifiスポットがあるので棋聖戦を観戦。聡太勝利。最年少戴冠。すげぇ。
@=
北海道ロカビリー道中10日目。一路北へ。北緯45度を超える。サロベツ原野に寄り道して稚内へ。 7年前、5日かけて歩いた距離が車だとたった5時間。速いなぁ。当時は自動車専用道路は通れないし、交通量の多い国道や、トンネルは避けていたので、かなりの遠回り。片道10キロのサロベツ原野への寄道にはエラく気合がいったものだが、車だと「ちょっと寄ろか。」くらいの非常に軽い感覚である。前回、600メートル(往復1.2キロ)の距離が歩けず、涙をのんで見送った北海道命名の地にも立ち寄る。 150年前、探検家松浦武四郎がこの地のアイヌの長老の話を受けて北海道なる名称が誕生した。天塩川が作る渓谷の今となっては寂しい河川敷である。道も地図もない時代に蝦夷地内陸部の地誌文化を書き留めた先人の偉大さには只々敬服する。旅から帰ったら松浦の「天塩日誌」を読んでみよう。
@=
(2020-07-18) 北海道ロカビリー道中11日目。快晴。そろそろ山登りがしたいということで道東へ。宗谷岬を経由して網走まで、、、は行けずに湧別まで。それでも300キロ近い距離があるんじゃないかな。文明の利器は偉大だ。歩いたら二週間はかかるよ。湧別ではオートキャンプに泊まる。やっぱ快適。フリーサイトとは整備のされ方が違う。お値段は少し高め。まぁ、疲れてきてるし、たまにはいいかな。 SSCCのキャンパーレベルも随分と上がって私も楽になってきた。明後日から天気が崩れるみたいなのが懸念事項。空の様子と相談しながら、摩周岳と雌阿寒岳を攻める予定。
@=
(2020-07-19) 北海道ロカビリー道中12日目。摩周岳に登るために屈斜路湖畔のキャンプ場へ。途中、網走で昼食。ウニ・イクラのコンビ丼とステーキのセット。大ボリュームで満腹。小清水原生花園に寄り道。 8年前と変わらない風景。地方は時が止まったかのようだ。中国は然り、ラオスでも5年も経つと町は様変わりするだけに嬉しいような残念なような気分で複雑。屈斜路湖はエラい人出であった。砂湯キャンプ場はファミリーのレジャーが多く落ち着かないのでパス。和琴キャンプ場は加えて高い(一人2000円)ので泊まる気が失せる。摩周周辺は観光客も多く何かと強気の価格設定だ。諦めて阿寒湖に行くことにする。キャンプ場は、、、管理棟無人で施設閉鎖。、、、が、無料で勝手に泊まって良いとの張り紙がある。ラッキー。本来なら630円だけど、諸事情?により無料開放してるらしい。ここを根城にして明日は雌阿寒岳だ。
@=
(2020-07-20) 北海道ロカビリー道中13日目。四座目。雌阿寒岳。 6時キャンプ場発。野中温泉登山口に6時40分。雌阿寒岳は樹林帯、ハイマツ帯、岩稜帯、山頂部は蒸気の上がる噴気孔を持つ火口と活火山を存分に楽しめる贅沢な山。 100名山の一つでもある。天気も絶好。大雪山の山映まで見渡すことができた。当初は往復を考えていたのだが、ジジぃ連曰く「別の道があるならそっちのほうがいい」とのことでオンネトー側に下山する。 8年前に私が辿ったのとは逆のコースである。当時はついでに阿寒富士にも登ったのだが、今回はSSCCの体力的にパス。まぁ、雌阿寒岳の方が景色はいいらしいので良しだろう。なお、8年前は霧と小雨で何にも見えなかったので、阿寒富士からの眺望は不明である。あんまりにも悔しかったので、翌日再度雌阿寒岳だけ往復したのを覚えている。よって、雌阿寒岳は実に3度目の登頂である。下山後、野中温泉で汗を流す。源泉掛け流しの硫黄泉。風情が良くて大好きな温泉。ただし、あまりに熱くて内湯は入れない。充実した山行。SSCCも大満足な一日であった。
@=
(2020-07-21) 北海道ロカビリー道中14日目。五座目、西別岳。六座目、摩周岳。本日の午後から北海道全域でしばらく天気が崩れる模様。勝負の午前中に摩周岳を登ることにする。摩周湖第一展望台が登山口。外輪山を巡る登山道はよく整備されていて、広い北海道を満喫出来る最高のハイキングコースでもある。見渡す限りの平原、振り返れば阿寒の山々、緑のアーチに涼しい風が吹き抜ける。摩周岳と西別岳の分岐点から独り西別岳を往復して、直接摩周岳に向かったSSCCを追いかけることにする。摩周岳には以前登っているが、西別岳は未踏であり、 SSCCのスピードであれば十分に追いつけるとの読みである。あまり有名ではない西別岳であるがこちらも素晴らしい山であった。羊蹄山を望むならニセコアンヌプリがいいように、摩周を望むと言う意味でなら西別岳の方が優れている。西別岳の先の道も笹原が広がり樹木はなく、眺望の良い尾根歩きが楽しめそうなのでいつかは再訪したいものである。急ぎ引き返して摩周岳山頂にてSSCCと落ち合う。 SSCCは30分前にはついていたそうだ。摩周岳は切り立った崖なだけあり、四方遮るものなく、北海道の広さと美しさ堪能できる。また、最鋭角で最青の摩周湖を見下ろすならここしかない。水の青さに空の青さを重ねる摩周ブルーは、摩周岳からの眺めで極まると言っていいだろう。花咲く登山道をノンビリ下山すれば14時過ぎ。摩周温泉につかってキャンプ場に戻る。
@=
(2020-07-22) 北海道ロカビリー道中15日目。未明からの雨は朝方止んだものの、しばらく天気は崩れる予報。休養日としてなんにもしない一日にあてる。午後からホテルの日帰り入浴を利用。それなりに格式のありそうなホテル。流石にwifiも速い。溜まっていた日記を更新する。
@=
(2020-07-23) 北海道ロカビリー道中16日目。一日中雨。雨の切れ間を利用してテントを撤収。根室方面へと向かう。厚岸の漁港直売店が破格で牡蠣を売っている。昼食後であったことから二個食べただけ。また来なければ。とにかく雨。霧多布に着いた頃には霧雨。風と合わさり、もはや雨が何処から降ってるのかわからない。運よくバンガロー(一棟1760円)を借りれて良かった。暗くなれば視界は5メートル。ヘッドライトも周囲を薄ぼんやりと照らすのみで、目的地が見えないまま進めばいつの間にやらぐっしょりである。雨に濡れるというより、細かな水滴が服に吸い込まれていくようだ。テントであれば相当に大変であったろう。本日、浜焼き、牡蠣、寿司屋(頼んだのは豚丼とそばだけど)と食事に結構お金を使った一日となった。観光?雨と霧でなんにも見えませんわ。
@=
(2020-07-24) 北海道ロカビリー道中17日目。雨のち曇り。ドライブしながら観光。しばらくは山登りできそうな天気じゃないので道東巡り。しかし、雨だとだめだな。霧とセットで何も見えない。既に一度行ったところが多いので、「まっ、いいか」とも思うが、よく考えたら以前来たときも霧で何も見えなかったな。道東には死ぬまでにもう一度くらいは来るだろうからその時は晴れてほしい。
@=
(2020-07-25) 北海道ロカビリー道中18日目。曇り。ドライブ観光。野付半島、ポー川自然公園。まぁ、大したことないですな。やっぱり山に登らないと感動できる景色はない。羅臼の道の駅が漁協の直売店になっていていろいろ安い。夜は貝づくしの網焼きである。ホタテ、牡蠣、ホッキ貝、ツブ貝。巨大貝だけでお腹が一杯になるのは贅沢であるが、流石に濃厚すぎてしつこい。口に残る後味が歯を磨いても残るのは良くない。
@=
(2020-07-26) 北海道ロカビリー道中19日目。曇のち晴。霧雨の中、テントを撤収。テントは濡れたままだが仕方がない。知床峠までは濃霧。なんにも見えない。羅臼岳どころか20m先が見えないありさま。峠を超えて少し下ればいい天気。知床連山が雲を堰き止めていたようだ。ネイチャーセンターに立ち寄り、知床五湖へと向かう。知床五湖の無料開放エリアは木道散策。高架でさらに電気柵付きという超安全な観光コースで、「これなら、クマが出ても大丈夫」と思っていたら、本当にクマが出た。ヒグマでかいわぁ。ほんの10mの距離だよ。 4日続きの雨であったが、今日は満天の星空。夕日も綺麗であった。
@=
(2020-07-27) 北海道ロカビリー道中20日目。移動日。最後の目標である旭岳に登るために旭川へと向かう。知床からは遠いわ。やっとこさ晴れになったオホーツク側を離れ、大雪山エリアに入ると大雨。時間も遅いしホテルを予約して旭川市街に入ると雨が降った形跡はなし。なんか損した気分だが久しぶりの布団はやはり快適。北海道に着いた初日以外はずっとテン泊だったからなぁ。 SSCCの意外なキャンプ適性に感心。
@=
(2020-07-28) 北海道ロカビリー道中21日目。 10時半までホテルでうだうだ。 3人で6500円と破格のホテルだが、長く寝袋生活をしていた身にはスーパーコンフォタブル。重い腰を上げて明日の大雪山に向けて麓のキャンプ場を根城にする。登山口まで30キロ。車なら1時間とかからない立地。一泊300円にもかかわらず施設充実、整備の行き届いた最上級のキャンプ場。コストパフォーマンスは今までで一番である。明日に備えて早めの就寝。
@=
(2020-07-29) 北海道ロカビリー道中22日目。 5時半、喜び勇んで出発。旭岳登山口は濃霧で視界不良。だめだこりゃ。旭岳は明日にまわして観光に切り替え。こういう場合、車だと自由が効いてありがたい。天人峡と羽衣の滝は小雨。羽衣の滝は見る価値あり。が、完全に過疎っていて廃墟となったホテルが2軒。良いところだと思うけど、上手く宣伝できなかったのかな。美瑛は一度行っているので特に感動は無し。丘に広がる農地であればヨーロッパの方が綺麗。白金の青い池。悪くはないんだけどねぇ。何キロか歩かないと行けない秘境の池であれば凄いんだけど、堰堤で生じた人工池で巨大駐車場付きの一大観光地となれば味わいなし。個人的には天人峡が景観として一番優れていると思うけど、完全にプロモーションに失敗してる。交通も不便。もったいないなぁ。
@=
(2020-07-30) 北海道ロカビリー道中23日目。晴れ。7座目。大雪山旭岳。二度目の旭岳である。 6時半登山開始。旭岳ロープウェイ下駅が起点。ロープウェイを利用すると一気に5合目近くまで上がれる。 500mの高度差を往復して3200円。 SSCCを見送り私は歩く。体力は十分なのでもったいない。ただし、下から歩くのは全くお勧めはできない。景観が優れるのは4合目からである。それまでは背丈ほどもある笹原か樹林帯で展望はなく道がとにかく湿っている。岩道が多く滑りやすいし、そうでなければぬかるみである。二箇所ほど高層湿原があり少し開けているが、高層湿原であれば他にもっといいところがたくさんある。木道も朽ちるに任せたままでうまくバランスを取らないと湿原にハマってしまう。実際登山者の99%以上はロープウェイを使っているはずだ。危険箇所こそないもののあまり人が通らない登山道は整備されておらず荒れた悪路である。さて、1合目。登山より写真をメインにしているらしいおじさんを追い抜く。とりあえず一人ではない。後続の人間がいると思えば幾分安心だ。大雪山はヒグマの産地である。 2合目。下山中の女性とすれ違う。まだ20代であろうか。聞けば2時から登り始めて旭岳登頂後降りてきたとのこと。すごいなぁ。若い女性一人で草木も眠る丑三つ時、ヒグマの寝床を横断しての登頂とは恐れ入る。少なくとも私はやりたくないし、やれと言われても躊躇するだろう。 4合目。ものすごいスピードで外人さんに追い抜かされる。私が7合目に着いたときには下る彼と再度すれ違う。相変わらずトレイルランナーは無茶苦茶な体力だ。標準コースタイムの5倍近いスピードじゃなかろうか。ロープウェイ上駅。電話するとSSCCは7合目くらいにいるようだ。前回は霧で何も見えなかった姿見の池や蒸気沸き立つ噴気孔をのんびり散策してから追いかける。景色もよく気持ちの良い登山。旭岳山頂部こそ雲がかかっているものの、冷ややかな空気は澄み、視界良好、遠くまで見渡すことが出来て大雪山系の広大さを堪能する。 8.5合目付近でSSCCシバじぃに追いつく、一応最後尾を歩くことにしているのでここからはスローペース。パパじぃは先に行ったそうで、後から聞けばこの時点ですでに山頂に着いていたようだ。冷たい霧を抜けて、無事、山頂に到着。「ほっかいどーのてっぺんとったどー」である。山頂から北西側は雲に隠れていたが南東側は時折霧が晴れて御鉢平くらいまでは見渡すことができた。これにてノルマ達成である。SSCCが登りたいと言っていた山はコンプリート。個人的には、カムエク、ニペソツ、斜里岳、十勝岳、羅臼岳、アポイ岳が北海道で登りたい山として残っている。大雪山の他の山、トムラウシ、忠別岳、富良野岳、美瑛岳、化雲岳あたりも登ってみたい。北海道、後、何度かは来なあかんな。
@=
(2020-07-31) 北海道ロカビリー道中24日目。目標をコンプリートし、疲労がたまり、キャンプにも飽きてきた。明日、北海道を去り大阪に戻ることにする。特に訪れたい観光地もないので旭山動物園に行く。展示に工夫を凝らしたいい動物園だけど1000円は少し高いかな。
@=
(2020-08-01) 北海道ロカビリー道中25日目。一路小樽港へ。山に登らないなら行きたい観光地もない。北海道は歴史が浅いからなぁ。名所旧跡の類となると極端に少なくなってしまう。あまりに早く小樽港に着いてもやることがないので、石狩川河口のはまなす公園に寄道。無料だから、まぁ、悪くないと言ったところ。 2時間ほど散策し時間を潰すも小樽で7時間の乗船待ち。運河を見に行く。もう何度目だろう。相変わらずしょうもないなぁ。古い倉庫が並んでるだけだし(しかもテナントはびっくりドンキーとか)、運河の水も汚い。ガラス細工の街も今やどこにでもある。そして、寿司屋は高い。唯一、北海道鉄道開闢の地である廃線跡だけが僅かながら趣があった。
@=
(2020-08-02) 北海道ロカビリー道中26日目。船に乗っているだけの一日。船上何もする気が起こらず寝るか風呂に入るだけ、我々だけではなく乗客全員がそんな感じ。行きの船では計画を立てたり、やりたいことを整理したり、船上散策したりと、それなりにアクティブにもなるが、帰りとなれば皆が疲れ切っている感じ。無事に全員、事故、怪我、病気なく帰れてまずは良かった。これにてSSCCと行く北海道ロカビリー道中は終わり。ジジィ連には冥土へのいい土産になったろう。キャンパーレベルも上がったのでもうどこへでもSSCCだけで行けるはずだ。足を痛めて行けなかったおかんも初の独身暮らしとなりいい夏休みとなったろう。しかし、大阪は暑い。北海道ではセーターまで着込んで寝袋にくるまり、それでも寒くて眠れない毎日だっただけに体の適応に時間がかかりそうだ。
@=
知床五湖にて遭遇したクマの動画。安全な木道の上だから見ていられるけど、登山中に出会ってしまうと恐怖だな。羅臼岳に登りたい。これさえなければ安心して単独で登れるのに、、、。
@=
大昔、「暑い!30度超えてる!」今、30度はむしろ涼しいとさえ感じる。昔、「35度とか異常!」今、35度を超えるほうが普通となった。我慢できるし、風吹く木陰だと心地よささえ感じる。
@=
午後二時、室温37.6度。流石に体温超えは我慢できない。もはやセミすら鳴かない。
@=
(2020-08-27) 岐阜県は平湯キャンプ場に避暑に行く。大阪は連日の35度越え。予報ではこの後も37度、38度と絶望的である。そんな中標高1300mの平湯キャンプ場の朝は15度らしい。乾燥気温低減率から考えると日中でも25度位だろうか。 7:20難波発、高山で乗り換えて、14時半に平湯バスターミナルに到着。うん。本当に涼しい。都市部と違って天国である。令和2年8月17日-8月23日の熱中症による救急搬送人数は速報値で12,799人である。滞在するだけで体力を失う環境は正にデスゾーンと言ってよいだろう。キャンプ場にて上野のI氏と待ち合わせ。。平日は空いたものだ。管理棟裏の水場、トイレともに一番近い最高立地にてテント設営。少し休憩した後、平湯温泉散策。こじんまりとした温泉街は1時間もあれば一通り回れるコンパクトさ。程よく汗を書いたところで入浴施設へ。露天風呂が豪華。600円は大変お得感がある。
@=
(2020-08-28) 寝るのが早いので起きるのも早い。 6時半には食事(面倒だったので袋麺)も終えて、 7時前キャンプ場脇のスキーゲレンデから高みを目指す。先を行くI氏の足取りは早い。、、、が、体力がない。この半年間ステイホームを律儀に墨守していたらしく色々衰えたらしい。 40分300mほど登ったところでI氏撤退。以降、あまり踏まれていない登山道を独り進むことにする。天気上々、花咲き蝶が舞う草原の道は気持ち良いものである。 500m登った1800m地点にてリフトの頂上駅(平湯テラス)に出る。さらにここから200m程度進むと乗鞍岳登山口が待っている。大阪近郊の山であれば、すでに「さぁ、山頂」と言った気分だが、ここは北アルプス、やっと登山道のスタート地点に立ったに過ぎない。西穂であろうか、遠く岩稜の尾根も見ることが出来て、テンションは急上昇。しかし、楽しいのはここまで。この後はひたすらに修行であった。まず天気が良くない。青空が消えて雲が広がり、いつ雨が来てもおかしくない状況。ところどころ背丈ほどはある笹薮をかき分けて進まなければならずズボンは朝露に濡れてびしょ濡れである。ぬかるんだ土道はグリップが効かず、濡れた岩道はなおさら滑りやすい状態だ。そして一番のダメージは尾根道にかかわらず景色が良くないのである。樹林帯は視界が開けずずっとジメジメしている。当初は2000mを超えればハイマツ帯、2200mくらいからは岩稜帯だと期待していたのだが、行けども行けども深い森である。 2400mの乗鞍大権現を越えて一旦100m下降。風の通り道になっているのかこのあたりだけハイマツ帯で遠望が効くが、見上げた硫黄岳は再び樹林帯の模様。 10時15分。目標としていた折返し時刻の11時までには硫黄岳までは行けそうだが心が折れた。厚い雲もかかっているしおそらく展望もないだろう。撤退、撤退。「やーめた!」である。しかしあまり知られないコースなのか、行きも帰りも誰独りすれ違うことがなかった。平尾尾根。この時期の北アルプスでこの状態ははっきり言って不人気なコースと言ってよいだろう。収穫は朝早く出発すれば十分に乗鞍岳までは行けそう(ただし往復は私の体力では無理)とわかったこと。天気さえ良ければ樹林帯歩きも楽しいはずだし、硫黄岳の向こうは乗鞍スカイラインで絶景のはず(想像)。来年また挑戦するかな。
@=
(2020-08-29) I氏は本日帰京。予報では午後から雨で私も帰る気だったのだが、午前の煌めく太陽を見て、翌日の予報を調べれば雨から曇りに変わっていることから延泊に心変わり。 8時半、I氏をバス停まで送りに出れば、9時発の上高地行きのバスがあったことから即決で独り上高地へ。いやぁ、人気だねぇ。すごい人出だよ。有名な河童橋。初めて来ました。 1500mの広々とした山間部の平野には美しい沢が流れ、青々とした広葉樹が涼しい風に揺れている。人気があるにはワケがある。昨日の平尾尾根とはエラい違いだ。まずは観光案内所に駆け込む。見どころは河童橋から明神橋までの湿原地帯。また、9時半と遅い出発になったが、岳沢小屋までであれば2時間で登れるらしい。 2時間かぁ。じゃ、空荷だし私なら1時間ちょいで行けるだろ(己が体力を過信)と思えば、かかった時間は1時間40分。後から標準コースタイムを調べれば2時間半のコース。こんなとこまで来て山登りする人は体力があって当たり前だから、観光案内所のアドバイスも健脚仕様になっていたようだ。岳沢は大小様々な岩が広がるガレた谷。適当な岩の上に立って見下ろせば穏やかな梓川、見上げれば急峻な穂高連峰が迎えてくれる。小屋までの大半は樹林帯だが、整備されており苔なんかもいい感じに生しているが空気は冷涼で乾いている。昨日とは打って変わって楽しい森林浴である。岳沢小屋から望む上高地もなかなか良かったが、穂高に登れば最高なんだろうなぁ。残り標高差900m、コースタイムは3時間。急げば行けないこともないと思うが時間に追われる山行となるだろう。雲行きも怪しくなってきて、2500m以上は雲で見えない状態だ。ここは涙をのんで下山。上高地も巡ったことがないので湿原観光に切り替える。再び、人気があるにはワケがある。上高地いいとこですわぁ。透き通る清流は青く碧く、立ち枯れの樹皮が水面に白く揺れている。うん、美しい。こりゃあ、すぐ上流の徳沢キャンプ場や横尾キャンプ場にもそのうち行かんとあかんなぁ。 14時、ポツポツと雨が来た。帰路を急ぐ。が、間に合わず。もう5分、いや走れば2分というところで大雨。河童橋近くの大樹の陰で雨宿り。一向に止まないのでずぶ濡れ覚悟でバス停まで走る。あんまりにもいいところなんでゆっくりしすぎたわい。キャンプ場に戻れば干していた洗濯物も絞り直し。やれやれ。
@=
(2020-08-30) 五時半起床。手持ちの食料が米一合と朴葉味噌のみ。ティーパックのお茶があるので朝食は朴葉味噌茶漬けとする。一口、まぁイケるかな。二口、お茶と味噌は合わんなぁ。三口、いや、むしろまずいよなぁ。四口以降、作ってしまったものは仕方がない、とにかく胃袋まで流し込んでしまえ。昨晩の朴葉味噌焼き鳥丼が思いの外美味しかったので、米と味噌なら何やっても食えるやろと思ったが間違いであった。さて、明日からは連日の雨予報。幸い朝は晴れているので濡れたテントを乾かしてキャンプ場を後にする。 2時間ほど時間があるので高山観光。古い町並みは結構な観光客でごった返していた。高山には大昔、中学の修学旅行で来たことがあるのだが、何一つ覚えていない。赤いさるぼぼの造形だけはわずかに記憶に残っているが、町並み、観光名所など全て初見であるかの印象である。思えば遠足なんかも含めて過去の記憶が殆ど無いので(概ね5年経つとほぼ忘れる)、相当記憶力が悪いのであろう。なんとなくは覚えているという感覚すらなくて、イベントそのものが完全に欠落している状態になる。結構色んな所を旅行してるけど、よほどのインパクトがない限りすぐに忘れるからホンマは行く価値ないですなぁ。さて、外界は熱い暑い。帰路の高速バスは焦熱地獄へとひた走る。関のSAでは熱風にクラクラする。早くも高原に帰りたくなる残暑厳しい夏である。
@=
(2020-09-21) 秋晴れ。暑すぎた夏。その後のぐずぐずした天気。すっかりインドア仕様でなまった身体を鍛えるため六甲ロングコースへ。岡本駅からいつものコースで七兵衛山。ここからの選択肢は広いのだが、住吉道から最短で六甲最高峰を目指すことにする。午前の山は人も少なくて快適。何度も通った道。本庄橋を過ぎ、迷う訳がないと地図を確認することもなく進んで行くがなんだか様子が違う。おかしい。これは蛇谷から石宝殿へと向かう道である。少し引き返すと大きく通行禁止の看板と侵入止めのロープがある。まさか、六甲登山の大幹線、高尾で言うなら一号路が通行止めとは露とも思わず、通り過ぎてしまったようだ。困ったなぁ。石宝殿は遠回りな上に笹の藪漕ぎがあって気が乗らない。何十回と歩いた路だし危険は対処可能であると判断して、あえてロープをくぐる。本当に危険であれば引返せばいいだろう。進んでみるとそれなりに人も歩いている。岳人。基本は皆さんマナーがいいんですけどね。キケンに対する警戒は相当甘いようですな。問題の崩落地だけど、50cmくらいの路肩が残っており、注意して歩けば何でもない。六甲の一般道でこれより危ない所は沢山あると言うレベル。まぁ、大幹線だけに通行量が多いため大事を取ったと言うことなんかな。山頂は結構な人。何度も来てるのですぐさま有馬方面へ。魚屋路から炭屋道経由で紅葉谷に降りてから登り返し。休日の六甲でも、メインロードを外れると登山者も少なく、秋風鳴る深い森は喧騒なるも人の声は遙かに遠くて怖いくらいの空間である。登り返した山頂は昼過ぎという事もあり大混雑。ついでに道路も大渋滞。極楽茶屋から一軒茶屋まで全く動かない車列が続いていた。一体、始まりと終わりは何処なんだろう。秋晴れの休日に車で六甲なんて行ってはだめですな。さて、通行止めの登山道にもかかわらず、この人出がどこから湧くのかと思っていたのだが、どうやら住吉川の沢筋から一軒茶屋に続く新道があるようである。新道は魅力的だが、人混みは嫌である。それに混雑する登山道よりかは通行止めの道のほうが安全そうである。崩落地だけ少しばかり注意するだけで良い。結論。再び、キケンロープをくぐる。崩落地帯も早々に通過。本来の幹線だからね。少ないとはいえヒト歩いてます。途中すれ違う人全員(5組くらい)から声がかかる。「この先通れますか?」うー、どう答えるべきなんだぁ。私が登山道の管理人なら、「危ないですよ。引き返して下さい。」と言うんだろうけど、そもそも警告を無視した一登山者だし、主観的に危ないと思う部分は全くない。登攀技術は要らないし、用具はロープすら要らない。素直にそう答える。「いやぁ、安心しました。」なんて言われるも、いいのであろうか。あくまでも主観ですからね。自己責任でお願いします。まだ少し足が残っているので東おたふく山に寄り道してから風吹岩経由岡本駅へ。下山間際、課外授業らしい10名程度の少年少女と出会う。「こんにちは」と通り過ぎようとすると、「山のおじさん。僕は中学生です。」と唐突な挨拶。これまた対応に困るなぁ。引率の先生も苦笑い。思わず、「山の少年よ。僕は無職です。」と答えそうになるも、これでは相手が返答に困ることになろう。無難に「山のおじさん、今日は二回も山頂に登ったよ。」と答える。「わー、すごーい。」とこれまた無難な反応。これでいいのである。大人は子供の手本にならなければいけない。大人って嘘つきですね。いや、嘘ではないか。本当のことを言わないだけですね。
@=
(2020-09-27) 曇後晴時々雨。有馬往復。鍛錬である。温泉には当然入らない。前回は魚屋路から西へ炭屋路を選択したので今回は東の筆屋路である。遠回りした上で復路は有馬三山にも登ることにする。これがハードなのである。登って降りての繰り返し。最後は六甲そのものにも登る必要があるから都合四度登らないといけない。鍛錬である。 6時半登山開始。早朝の山には誰もいない。風が強くて不気味であった。明るい広葉樹林が広がる六甲で妖気を感じるのは珍しいことで、せせらぎから妖怪小豆洗いでも顔を出しそうな雰囲気である。二時間ちょっとで最高峰に到着。まずまずのペース。筆屋路は初めてであったが、可もなく不可もなくありふれた登山道である。筆屋路入口となる瑞宝寺公園はモミジの名所のようだ。秋に来ればそれなりの景観を楽しめそうである。有馬は思ったよりも賑わっていて温泉街としていい感じであった。観光客が多過ぎても風情がないしこのくらいがちょうどいいように思う。猿回しの一座が来ていたようで、小太鼓がポンポコと囃子たてているのも宜しい。さてここまで足は余裕。問題は有馬三山。とにかくキツイ坂、嫌になる。しかもとっても急。更に加えて展望なし。普段であれば避けるコースであるが今回は敢えての選択。鍛錬々々。六甲山地に登り返したところで本降りの雨。再度、六甲最高峰、、、には行く気がせず、西おたふく山から住吉川へ下山。途中、結構な崩落地があって中々の迫力であった。落ちたら間違いなく重体以上だ。住吉川も雨で増水していて渡渉しにくい。西おたふく山で小さな子供連れの家族に、この道が御影に続いているか聞かれたので、 YESと答えたものの、崩落地に増水では大変だったかもしれない。ゴメンね。知らなかったんだよう。7月の大雨で登山道は至るところ荒れているようだ。さて、帰り。一本見送って乗った特急が人身事故を起こしてしまった。踏切での飛び込みか、遮断器無視の横断か? 二時間足止め。皆さん、余程のことがない限り命は大事にしましょう。
@=
(2020-10-02) 六甲縦走。雲一つない秋晴れ。 7時、鵯越駅を出発。菊水山、鍋蓋山、摩耶山の三連登であるが、体がまだ慣れていない最初の菊水山300mの登りが一番キツイ。早朝にもかかわらず下山のお年寄り何人かとすれ違う。菊水山は町から近く手頃な高さのため、地元の有志は毎日登っているのであろう。摩耶山への登りは稲妻坂、天狗道と言う名が示す通りの急坂であるが、ここまで来る頃には体も出来上がっているので、比較的楽である。摩耶山、10時半。六甲最高峰13時。大体予定通り。鵯越からの六甲縦走もかれこれ5、6回はやっている。 15年前、初めての時は余りの疲労に三日間歩けなくなったものだが、随分強くなったものだ。最高峰から宝塚は消化試合。ダラダラとした下りで一向に標高が下がらず、距離だけは長い。 16時前、やっと宝塚到着。30kmちょい、9時間弱。もう少し歩けそうである。
@=
(2020-10-07) ロックガーデン周遊。本当は金剛葛城縦走の予定であったが、午後から天気が崩れるらしいので短距離コース。一週間以上間が空くと次がしんどくなる。今晩からしばらくは雨のようなので午前で勝負である。よく歩く道なので書くことの程はなし。
@=
(2020-10-13) 金剛、葛城、二上山。曇。体力の試金石。このコースが完走できると衰えていないと言える。あまりの夏の暑さに運動不足であったが、先々週、六甲縦走が出来るまでに回復したので、今回は金剛、次は和泉山地である。修行向き三コースである。紀見峠を発して、金剛までの12kmは比較的楽なもの。ここからの葛城山、岩橋山、二上山の登り返しがとにかくキツイ。二上山などせいぜい500mのお手軽ハイキングとしての山なのだが、 30km近く歩いた後では200mの坂が、果てしなく思えてくる。「もう、やめてぇー。」20m登るのでさえ息絶え絶えなのに、、、。「終わらない上り坂はない。」私が辛い上りで自分に言い聞かせてきたセリフである。どんなに辛い上り坂でも必ず終わりがある。そして登りきったならば素晴らしい展望が開けるものだ。それは、人生も同じだ。、、、と今まではそう考えてきた。でも、登りきれば次は下りで、下ってしまえばまた登らなければならない。上って下っての繰り返し。結局、上り坂に(下り坂にも)終わりはないのである。「人の一生は重荷を負ひて遠き道をゆくが如し」なのだ。人様には「お前の荷物は軽い!」と怒られそうですけど。
@=
(2020-10-21) 六甲横断。晴れ。同行は上野のI氏。岡本から魚屋道で有馬に抜ける最も安全なコース。高所恐怖症のI氏でも安心。、、、なはずであったが、、、。魚屋道の最後の上り、七曲りが「崩落キケン」で通行止のため、代替ルートを初めて登ってみたが、通行止のルートより10倍は危険な道であった。今まで通行止を無視して七曲りを通っていたが、崩れているのはほんの一箇所、長さ5mほどで足場も幅50cmは残っている。それに反して代替ルート中盤はほぼ全域に渡って崩落しているようなものだ。落ちて死ぬほどではないが、崩落の急峻さ、足場の脆さ、道幅の狭さ全てで代替ルートのほうが危険である。登山客の多くなる週末だとすれ違いも大変だろうし、メインルートを通行止にしたせいで怪我や軽い事故は何倍も増えているように思う。 I氏も相当に怖かったようである。うーむ。安全な道がほんの僅かに崩落しただけで通行止になり、遥かに危険なマイナーコースが代替ルートになっているのは正直訳がわかりませんな。
@=
(2020-10-26) 和泉縦走。快晴。大阪三大修行コース。最後に残った和泉縦走である。距離は30キロ弱と一番短いが、14:30までに下山必須と時間制限がある。 6:40、紀見峠駅出発。岩湧山を越えて9時過ぎに滝畑到着。さて、しんどいのはここから。滝畑までの10キロは前座みたいなものである。前座とは言え岩湧山の茅は今が一番の見頃。正直このコースで景色がいいのは岩湧山くらいなもの。滝畑から後の20キロは特段見どころもなく、そのくせキツイ登り返しと登山としてはあまり価値がない。ただし、古来、修験者がそれこそ本当に修行してきた山道なのだ。進まねばなるまい。誰が私を止めることができよう。ゆっくり歩いていると間に合わないので、比較的平坦で安全そうな道は小走り程度に駆けてゆく。休憩は2時間に1度、5分だけ。食事も歩きながらのオニギリである。「はぁ、しんどいわぁ。なんで俺こんなことしてんだろ。」急坂が続く猿子城山を超えると修験道らしく道端に石仏が散在するようになる。地蔵であろうか?彫りの摩耗が激しいことから結構な年季を感じるが、そのせいかとても穏やかに見え、しんどい中にも癒しを与えてくれる。急いだ甲斐があって三国山で11時。心拍数190超えと50前のオッサンが出しちゃいけない数値が出ているが、ここから鍋谷峠までの4キロは舗装路、かつ、緩い下りなので頑張って走る。鍋谷峠から和泉葛城山までは尾根コースと巻き道コースがある。尾根コースは当然上り下りの連続、道も悪く、更に展望がないと言うマゾルートであるが、良いこともある。修行には向いていること。「Punish me!」一声叫んで尾根コースへ。進んですぐに後悔は、、、しない。巻き道を進むようであれば鹿之助先生に怒られる。和泉葛城山12時過ぎ。5時間半で来てしまった。新記録である。後は帰るだけ。牛滝温泉に進路を取ると、「危険通行止め」のロープ。土砂崩れだとか書いてある。他の道は全て10キロ以上の遠回りになってしまう。無視して進むと、再び、ロープで通行止め。しつこいなぁ、無視。すでに25キロ歩いて疲れた体にマイナールートで遠回りとか余計に危ないわい。道は、、、昨年と変わらずどこが危ないのかわからないくらいであった。蜘蛛の巣の状況や道の踏まれ方からして相当数の登山者が無視して登ってるようだ。 28キロ、6時間40分。13時半に牛滝温泉到着。道中急いだ分、温泉にはゆっくりと入って帰宅。
@=
(2020-11-08) 晴れ。有馬往復。昨晩は雨。濡れた森は新鮮。何度も通った道であるが、見覚えのない景色に「こんな道やったっけ?」てな感覚である。デジャブ(既視感)の反対。木々が放つ湿気に陽光が煌めき、なぜか甘い香りが漂っていた。七曲り直前で引き返してきたカップルに会う。「この先通行止めですよ。」とな。「あー、全然大丈夫。危険ロープくぐったらいいですよ。」と答えて私は迂回ルートの方へ。後ろから、「行けるんやぁ。山の人は優しいなぁ。でも、なんで知ってるんやろ。」との声が聞こえる。もちろん、迂回ルートがあることも教えましたよ。でも、私が迂回ルートを選んだのは、ヤセ尾根で危険度が高く面白いから。帰りは安全な危険通行止めの道を通る予定。カップルは素直にロープをくぐったようだ。ヤセ尾根に入った所、迂回ルート中盤でご老体から声がかかる。「通行止めやったんでこっちに来たけど山頂までいけますか?」「行けますよ。でも、こっちの方が険しいですから気をつけてくださいね。」追い越して進むと、なぜかお爺さんの連れの小学生らしい子供が付いてくる。「お祖父ちゃん、おいていってええんか?」「あいつ、遅いねん!」生意気ではあるがこういうのは嫌いじゃない。「危ないから気をつけろよ。」「落ちたら死ぬなぁ。」死にはしないだろうけど怪我はするだろう。しばらく私の後を追っていたようだが、心配になったのか、「あいつ、ホンマに遅いなぁ。」とふてくされながら引き返していった。根は優しい少年なんだろうね。さて、行楽シーズンの六甲山頂は人だかり。さっさと退散。一軒茶屋の向かい、長らく工事中であったトイレが完成していた。ものすごく綺麗でヒーターまで付いている。スッキリしたらしいオバちゃんから「感動的なトイレやなぁ。」との歓声。でも、大丈夫かなぁ。シンプルだけど清潔というのがいいと思うんだけどなぁ。あまりに綺麗で高機能なトイレだと山では維持管理が難しいのではないかと心配になる。さっさと有馬に抜けて有馬三山で引き返そうと思っていたのだが、先月行った瑞宝寺がモミジの名所であったことを思い出し、筆屋道から瑞宝寺公園に寄り道。大正解。ちょうど見頃。素晴らしい色づきである。真紅の紅葉は太陽を透かしてみるのが美しい。ただし、観光客が多すぎる。周辺の駐車場はどこも満車で空き待ちの車列が連なる。中心部の温泉街は避けることにしてロープウェイ駅近くから灰形山へ。いつ登ってもここは急。足が上がらん。やけにしんどくて最短経路でとっとと帰ろうと決意する。登りきったところでまたカップルから声がかかる。「こっちの道は大変ですか?」「どちらから登りました?」「紅葉谷からです。」「紅葉谷よりかは大変ですけど、まだ1時半ですし行けると思いますよ。」まだ、若そうだけど、相当な急坂だからね。楽観的に言ったけど、下山前に日が暮れてしまわないか気にはなる。彼女の方に体力がなかったら「ごめん!」ってところだけど、その時は彼氏の方に男らしさを見せつけるチャンスだと思ってもらうことにしよう。登ってしまえば何故か体力回復。最高峰をもう一度踏んでからメインロード(危険通行止めの安全路)で下山。到着は四時。やはり疲れていたのか、いつもより大分と遅い時間になっていた。
@=
(2020-11-14) 六甲紅葉谷。先週行った瑞宝寺公園のモミジが見事だったので再び北六甲へ。目的は紅葉谷。瑞宝寺谷は有馬の東、そして紅葉谷は有馬の西である。山頂までの表六甲はただの通り道。常緑樹多めでこの時期はあまり見るべき物がない。やはり秋は裏六甲である。ただ、紅葉谷経由での往復なら体力的には余裕なので東おたふく山にも寄り道しておく。二時間ちょい、早々に六甲最高峰を通りすぎて有馬へ下山。途中、大きな秋田犬を連れた孫(と言っても成人した女性であったが)と登山中のおジィさんから声がかかる。「西おたふく山に三角点はありますか?」うーん、知らんなぁ。話好きのおジィさんで、なんでも六甲には100回以上登ってるそうだが、西おたふく山だけ残っているそうだ。「いやぁ、もう81ですわ。」おぉー、すげー。パッと見は70歳前に見えましたよ。「ラッセルの相棒だったんやけどねぇ。」秋田犬は雪山登山で交代で雪かきするための言わば山岳犬だったそうな。「もう、14歳ですっかりおじいちゃんですわ。」あんたもなー。「最近はマラソンの練習に一緒に行ってもすぐバテよる。」ジジィ、マラソンまでやるんかい。「ハーフやけどね。」いや、20キロ走れる81歳はなかなかいないと思うよ。小柄な人であったが(孫のほうが大きかったような)、えらく元気なものである。さて、有馬手前で魚屋路から紅葉谷へと降りる。谷底からの登り返し。なお、有馬から直接紅葉谷へ抜ける道は、土砂崩れのため長らく通行止めであったが、ようやく復旧したようだ。ちょうどモミジの時期なので結構な登山者がいた。紅葉谷では、おぉ、山が燃えている。北六甲は落葉樹が多くてよろしい。色とりどり、特にオレンジに染まった木々は炎のようだ。歩いていて一番気持ちのいい季節である。とは言え、モミジの見事さでは先週行った瑞宝寺公園に軍配が上がる。自然林だと一面のモミジというわけにはいかないしね。ところどころ、ハッとする見事なモミジもあるにはあるが、やはり、綺麗に整備された公園のほうが色づきといい壮観さといい映えますわ。紅葉谷が終われば後は消化試合。そう言えば、西おたふく山は私も山頂まで行ったことがなかったので寄ってみた。行く価値ないです。踏み跡のみで、道はわかりにくいし、山頂にはなんにも(標識も景色も)ない。六甲最高峰に戻って、一軒茶屋からいつものように危険ロープをくぐったのだが、崩落地点に迂回路が出来ていた。先週はなかった結構立派な木組みの階段が設えられている。迂回路作ったなら危険看板とロープを外せばいいのに、、、。しかし、岡本駅起点だと前座と消化試合が長いなぁ。紅葉を楽しむなら有馬を起点に紅葉谷で登って、魚屋路から筆屋路を下って有馬に戻るのが一番オススメ。
@=
(2020-11-16) 摩耶回遊。曇後晴。食欲の秋である。そして、私は健啖家である。好きなだけ食べたいので、その分だけ運動しておく。世には様々なダイエット法があるようだが、思うにすべからくまやかしであろう。体重なんてのは単にINとOUTの差でしかない。摂取したカロリーが消費したカロリーより多ければ太り、逆であれば痩せる。それだけのことでる。運動嫌いで食べたいけど太りたくないのであれば、古代ローマ人のように消化される前に入口からお帰りいただくか、下剤を飲んで未消化のままさっさと出口に向かってもらうしかあるまい。あれっ、なんか汚い話になってる。好きに暴食するための健全な山行が本旨であった。この時期、裏六甲が思いのほか綺麗なので、本日は三宮から摩耶山の北側を目指す。早足で市ケ原まで1時間。布引渓谷のモミジは真紅にはまだ少しばかり早いと言った感じ。生田川を北に遡る。市ケ原から先はトゥエンティクロスと呼ばれるハイキングコースだが、大雨による崩落があったらしく2年以上も通行禁止が続いている。解除される見込みなしと思われるので無視してしまうことにする。なんか最近、通行止めを無視してばかりだが、自己責任は当然として安全には最大限の注意を払っている。まずは道を観察。良く踏まれている。実際には多数のハイカーが通っているのだろう。湿った土には真新しい靴跡。おそらくは昨日、もしかすると今朝方早くに付けられたものである。よし。おそらくは問題ない。本当に危なければ引き返せば良い。、、、で、着いた崩落現場は、、、「そんだけ?」、、、。多くは語るまい。生田川上流はプチ上高地みたいな風情であった。清流に枯れ木立は、梓川のそれである。なんと河童橋まであった。いや、やっぱ、プチ上高地は言い過ぎだな。「TTK」(TinyちっぽけでTrivialつまらないKamikochi上高地)と命名する。悪くはないんだけどね。上高地が良すぎるから流石に比較はできんわ。「TTK」なんて言ってみたけど、谷幅は広く落葉樹林が続く六甲では屈指の良コースであった。惜しむらくは時期を過ぎていたこと。せめてあと一週間早ければ素晴らしかったのではないかと思う。摩耶山に北側から登るコースは3つある。桜谷道、徳川道、シェール道である。とりあえず一番遠回りのシェール道を選択。遠回りと言っても距離が長い分、傾斜は緩いわけで楽な道とも言える。最盛期は過ぎてしまったが、裏六甲の風情はやはり優れている。落ち葉を踏みしめる道は気持ちがいいし、所々、色づいた木々がまだまだ残る場所もある。摩耶山に着いてしまったら後は帰るだけ。なんだかもったいない気がして、徳川道を下ることにした。そんでもって桜谷道で登り直し。摩耶北側の道はどこも落ち葉の絨毯が広がりそれぞれに良い道であった。いずれ歩いて損はないコースであるが、体力に不安があるなら徳川道がいいだろう。距離と傾斜のバランスがとれている。本日、二度目の摩耶山。さぁ、岡本駅までは長い長い帰り道である。
@=
(2020-11-18) Operation MWA - 摩耶波状攻撃作戦、始動。天狗道を登り、地蔵谷を下る。黒岩尾根で登り返し、桜谷道で下る。さらに、徳川道を登って、最後にシェール道を下る。実に男らしいコース設定である。山頂を目前にして引き返しては別ルートで登り直す。正に益荒男振りを見せつけていると言って良いだろう。、、、が、実は大したことはない。 300m前後の登りが3回で獲得標高は1000mと言った所か。実際には六甲縦走の方がしんどいはずである。しかし、大事なのはそこではない。折角登ったのにわざわざ下ってまた登ると言う、ある種「アホらしい」行為を繰り返せる姿勢が大事なのだ。田中陽希(100名山一筆書)の偉業の本質もそこにある。登山自体は誰でも出来るし、むしろ望んでしたい人の方が多いくらいだろう。だが、普通の人は登山口までは交通機関を使う。家から登山口まで歩くなんて「アホらしくて」しないのである。彼はそれをしている。家から登山口も、登山口から次の登山口へも全て歩く(走る)のである。本当は誰でも出来る。でも、アホらしくてやらない。それをやり切ることはやはり偉業である。番組でも山登りのシーンでは特に感銘を受けないが(カメラマンの方が大変やろと思う)、写っていない部分で地道にロードを走り続けている様を思うとやはり凄いと言わざるを得ない。、、、と、無意味な自己満足を十分に正当化したところで、MWAである。 7時神戸三宮駅、8時市ケ原、トレッキングシューズに履き替えて作戦開始。まずは、稲妻坂・天狗道を登る。六甲縦走路の一部であり、摩耶登山のメインロード。しかもハイシーズン。平日にもかかわらず早朝から結構な人数が歩いている。縦走中であれば菊水山・鍋蓋山を越えてからの急登となるため辛い所であるが、今回は最初の登りであり体力十分、1時間かからずに高度600mを越える。山頂までは残り100mもない。、、、が、ここで勇気ある撤退。エベレストを目の前にしながらも悪天候に道を阻まれ、涙を飲んで下山する登山家の気持ちを味わう(注、本日晴天)。摩耶山腹の迂回路から地蔵谷に入る。道標などでは地蔵谷(難路)との表示があるが、SSCCによれば大したことはないとの話であった。如何程のものかいざ下らん。特に危ない箇所はないですな。清流沿いの落葉絨毯がカラフルな道であった。時折零れる朝の陽光にひらひらと枯れ葉が舞うのは幻想的ですらある。マイナー道で誰も通らないけど、この時期であれば間違いなく天狗道より美しい。みんなこっちを通ればいいのにもったいないなぁ。程なく300m下って、お次は黒岩尾根である。ここの取り付きは急である。下りは思いのほか筋力を使うので登り返しは足が重い。一気に300mを登り切ると名もないピークがあり、そこからは爽やかな尾根歩きである。途中、ベンチがあり、振り返ると菊水山や高取山まで見渡せる。摩耶山に行くには少し遠回りになるけど、稲妻坂よりこっちを登るほうがいいんじゃないかなと思う。そして、いつしか標高は680m。摩耶山頂は702m、展望台のある掬星台で690m。あと、ほんの僅か、、、というところで名誉ある撤退。南極点まで後少しでありながら、怪我をした仲間の命を救うため、歯を食いしばって引き返す冒険家の気持ちを味わう(注、本日単独行)。さて、下りは一昨日も歩いた桜谷道。裏摩耶の谷は何れ劣らず素晴らしいの一言。この道はやはり人気らしく何名かの登山者とすれ違う。 250m下って、徳川道で登り直し、流石に少々疲れてきた。徳川道も沢道です。素晴らしい。ハイ終わり。流石に書くことがもうないですな。 150m登れば穂高湖到着。後はシェール道を下るだけなのだが、湖周道でシェール槍なる看板を見つけ寄り道。 50m登るだけ、穂高湖のついでに行けるので、機会があれば行く価値あります。シェールガスやシェールオイルとかよく聞くけど、ここでのシェールも頁岩のことかなぁ。ちょっとした岩登り、アスレチックを楽しめる上、山頂からは新穂高や石楠花山といった摩耶北の山塊を望むことが出来る。さて、やっと終わりだ。シェール道に入る。生田川の本流となる沢道だ。裏摩耶の谷は素晴らし、、、以下略。徳川道まで戻ればMWA終了であるが、体力も残っているので、石楠花山まで寄り道してみた。展望台がある割にはさほど視界が開けない山ではあるが、秋の裏摩耶はどの道を歩いても損はしないコースである。寄り道しすぎて時間が押してきた。市ケ原に帰り着けばすでに15時半。山は夕暮れの風情であった。これにて、Maya Wavy Attack、作戦完遂である。今回は摩耶山頂を目前にしながら、敢えて下ると言う趣向でやってみた。地図と行路を眺め直す。大好きだったマヤちゃん。良い所までアプローチしながらも、告白できずに引き返してしまう。そして最後は、「幸せになれよ」と心の中で祝福しながら友人のもとに見送る結末。そんな切なくも優しい男の悲哀が行程記録からは感じられよう。
@=
(2020-11-21) 西六甲。曇後晴。再度山大龍寺の表参道である大師道から入山。渓流沿いの風流な道。寺伝に和気清麻呂や空海が出てくるあたり相当歴史は古い。空海はどこにでも出てくるけど、清麻呂は珍しいんじゃないかな。ほとんど舗装されていて山歩きとしては面白くないけど、道中、茶屋も多く文化の香りが漂うのは良い。「急ぐとも 心静かに 手を添えて 外に漏らすな 松茸の露」途中立ち寄ったトイレの張り紙である。使用後は水を流すのも忘れずに。六甲縦走路はハイカーが多いので、早々に北へと続く寂れた道に入る。休日でも人気のないコースは誰もいないのはいいのだが、人気がないだけに見どころも少ない。西六甲の残念なところは開発が進みすぎて車道が多いこと。北進できるのは森林公園まで。西に向かって再度公園は風光悪くはないが結構な人手であろう。東に向かって六甲牧場は長い車道歩きが待っている。どちらも気が乗らないので修行に切り替える。先日は登らなかった摩耶山へ。何度も登ってるので特に書くことはなし。
@=
(2020-12-11) 3週間ぶりの山。晴天。12月にかかわらず暖かで穏やかな気候。冬は葉が落ちて森が明るいのが良い。枯れ木の枝ぶりも味わい深し。ルートはいつもの大回りコース。改めて書くことは特にない。冬の平日となれば登山道はガラ空き。誰もいない山中は陽光に溢れて快適だ。
@=
(2020-12-13) 摩耶修行。曇。年末年始を前に予め脂肪を消費しておく。冬眠前に脂肪を貯め込むクマとは逆である。修行ルートは「愛しの摩耶さん三度のアプローチ」である。先月もやったが摩耶山三往復は訓練に丁度良い感じ。本日、曇天。太陽は見えず、風は冷たく寒い。休日の天狗道は混むので早い時間に通過。それ以外はマイナールート、or、通行止めだったりするので空いている。それでも、休日なので何組かとはすれ違う。前回は意地でも摩耶山には登らなかったが、今回は変な制約はつけてないので、普通に掬星台にも寄ってみる。結構な人手である。ロープウェイにもそれなりのお客さんがいるようだ。修行なので特に書くこともない。紅葉も終わってしまい森は寂しい状況。足早にコースを消化する。シェール道での帰り道、通行禁止と書かれた舗装路の方を少し探検してみた。どうやら六甲牧場の北側に抜けることが出来るようだ。しかし、道路にしろ建物にしろ打ち捨てられた人工物は不気味である。登山道でもないただの廃道であるため人はほとんど通らないのであろう。帰り着けば8時間25キロの道のりであった。
@=
芦辺拓『紅楼夢の殺人』4/5点。今までにない探偵像であった。主人公が属する貴族社会においては、上級の人間による殺人は罪に問われない。主人が使用人を殺したとしても、それは使用人の不始末であり、不始末でさえない快楽殺人であったとしても権力で握りつぶせる。よって殺人者が犯行を隠蔽する必要はないのでトリックも無用である。この舞台設定は秀逸で、トリックがあるならばそれは犯人ではなく探偵が計画したものであり、トリックによって犯人に利する(共犯?)状況を探偵自身が提供せざるをえない。ところが、犯人にとってはトリックも共犯も大きなお世話であるがゆえに、逆に犯人を追い込んでいくという見事な構図になっている。なんとも寂しい結末は必然だろう。
@=
今村昌弘『屍人荘の殺人』3/5点。こちらも特殊な舞台設定。題名通り「屍人」に囲まれた中で起こる連続殺人事件。映画化もされた2018年の話題作。ラノベテイストで読みやすい。エンターテイメントとして楽しく最後まで一気に読めた。屍人、まぁ、もう、ゾンビって書いちゃうけど、素晴らしいガジェットだよなぁ。ゾンビさえ出せば、ホラーは当たり前として、コメディ、恋愛、ロカビリー、社会問題、アクション、ハードボイルド、、、なんでも描けてしまう。本書はミステリーだから、クローズド・サークルを構成する要素としてのほか、凶器や共犯者(直接の実行犯)としてもゾンビが大活躍している。なお、怖くはない。美少女探偵だったり、青春小説っぽい展開があったり贅沢な一品です。
@=
(2020-12-26) 六甲中周りコース。曇後晴。 6時半目覚まし。寒い。布団から出られず。寝直す。暖かくなってきた時間に活動開始。家を出たのが11時。岡本駅12時。時間も遅いし荒地山の方を散歩しようかと考えていたのだが、気が変わる。 SSCC+1が、8時に同じく岡本駅を出発し、石切道経由で凌雲台(山頂)に行くと言っていたので、位置情報共有アプリ(自作の野良アプリ)で確認すると、未だ凌雲台に着いていない。遅っ!「これ、追いかけたら間に合うんじゃないか?」 SSCCが後1時間で上り切るとして、下山に2時間で15時。昼食がまだであれば山頂で1時間は休憩するだろうから16時。 3時間、ないしは、4時間で1000mを登り降りできれば追いつくな。相手は70越えたジジィ連だ。ペースも遅いし休憩も多い。急げば山頂で出会うかもしれない。急遽、コース変更。SSCCを4時間遅れで追いかけてみることにする。八幡谷から入って打越山、12時40分。昼時とあって20名近いハイカーがいた。休日とは言えこの人数には驚き。打越山って不人気な山だと勝手に思い込んでいたけど、単に私がいつも早すぎた(大抵は8時とか)だけだったようだ。住吉川に下って13時。石切道は何度か登ったことがある。休憩しなければ1時間ちょいだろう。途中、アプリで確認するとSSCCは頂上で昼食にしているようだ。動いていない。これは間に合ったな。比高600mを70分で登りきって14時10分に凌雲台。無事、休憩中のSSCCと合流。下山路まで追いかける必要がなくなったので、彼らとは別行動にして六甲最高峰にも行ってみる。 15時着、流石に遅い時間のためか誰もいない。ここから有馬なら1時間だが、神戸側へは2時間かかる。日の落ちるのが早い季節、暗くなる前に下山したい。走りはしないものの早足で岡本駅を目指す。急いだ甲斐あって16時には風吹岩。やっぱり誰もいない。沢山いるはずの猫もいない。エサをくれる登山客が帰ったら、猫たちも巣に帰るのだろう。ここまで来れば安心。何十回と通った道。とは言え、夕暮れ時の山中っていかにも妖怪が出そうな雰囲気である。真っ暗でヘッドライトとは違い、視界が広いだけに森に誘われるようだ。なんとか暗くなる前に下山。岡本駅に着けば17時。
@=
(2020-12-29) 六甲小周り散歩。八幡谷から黒五谷経由荒地山。普段はメインルートの岩梯子の方に下りるのだが、地図にはない高座谷に下りる道があるみたいなので今回はそちらを選択。初めて通ったが登山道は整備されており、むしろこっちのコースの方が岩場が少ない分安全であった。途中、奥高座の滝とキャッスルウォールの分岐があり、再び初めての奥高座の滝ルートを選択する。、、、が、こちらは急坂。坂と言うより崖。岩に固定のハーケンが打ってある。ロープがいるほどではないが、落ちたら大怪我以上は必定だ。慎重に三点支持で下降する。登り返して八幡谷に戻る尾根道を漫然と歩いていると道に迷う。何回か歩いた道は地図を確認しないし、分岐への注意も疎かになるので、気がつくと「あれっ」となっていることが、所謂「まれによくある」のである。「明らかに道じゃない」ものの、落ち葉がめくれていたり、土が荒れていたりと人が通った痕跡はある。おそらく先人が迷いながらも突っ切ったのであろう。こういうときスマホは便利だ。GPSと地図で確認すると300mほど尾根を進むと登山道に出会うようだ。尾根の左右の谷は相当な急斜面で下りるには危ない。道は谷筋なのだが八幡谷は崖が多いことも知っている。下手に焦って登山道に近い谷に入ると滑落しかねない。尾根のほうが安全だ。とは言え、尾根も結構急。落ち葉と腐葉土で土は柔らかく、歩くと言うよりは斜面を削りながら滑ると言ったほうが正しい。先人も至る所で滑ったらしく斜面に落ち葉の剥げた後が散在している。たった200メートル進むのに10分くらいかかってしまった。本日、行程は10キロと体力は使わなかったが、神経をすり減らす山行であった。
@=
(2021-01-02) 六甲 with SSCC+2。本年初登りも六甲から。爺s+弟と帰省した甥を連れて荒地山へ。六甲でちょっとしたボルダリングを楽しめる岩梯子から七衛門嵓コース。本当はロープワークが必要なほどではないのだが、ザイル+ハーネス+カラビナでお遊びクライミング。小学生には(大人も)メチャクチャ面白いアトラクションである。遊んだ後は奥高座の滝上部から横池を経由して八幡谷から帰る。 10キロ7時間のお気軽楽チンハイキングとして最適なコースであった。
@=
(2021-01-14) 六甲最高峰往復。晴、ただし、霞。次はロックガーデン周辺の地図未記載の道を調査しようと思っていたのだが、心境の変化から軽く修行したくなったので最高峰往復に切り替える。六甲には所々雪が残っており、場所によっては泥と混じり合ったぬかるみで大変歩きにくい。頂上部の方は寒い分、雪が締まっているのでまだましではあるが、トレランシューズは間違いであった。防水のトレッキングシューズにしておけばよかったと後悔。しかし、それにしても今日はしんどい。靴のせいを差し引いてもしんどい。いつもなら二時間強で登りきれる六甲に三時間弱もかかってしまう。体力が落ちたのだろうか?いや、そんなことはあるまい。おそらく心の問題である。心が乱れれば、技が鈍り。技が鈍れば余計な体力を使う。そして体力を失えば心は焦るのである。結局、心技体は同じものだ。どれかが欠けると全てが崩れる。常に最良のパフォーマンスを発揮することは兎にも角にも難しいものである。
@=
(2021-01-25) ロックガーデン周遊。雨上がりの小春日和、ハイキングに絶好である。本日はロックガーデン周辺の地図未記載の道の調査だ。岡本からまずは荒地山を目指す。山は最良の有酸素運動の場である。自然の中でリラックスできて健康によく筋力まで付く。おまけに登山路は全て哲学の道と言っても過言ではない。山中だけあり、考える時間だけは山ほどある。思索に耽りながらの散策は人生を豊かにすることが出来る、、、とまで言うのは言い過ぎである。そもそも、人間考えていることの99%以上はしょうもない事である。「お腹空いたなぁ」とか「宝くじ当たったらどうしよう」とか、深い意味のないことや妄想が大半である。それでも、たまーに、ふとした拍子に何か人生がわかったような気になるから、やはり山は良いと思うのだが、別に家で寝ていてもそれくらいの瞬間はあるようにも思う。、、、などと本当にどうでも良いことを考えながら歩いていると、ほどなく荒地山に着く。山頂から少し進んだ南東尾根から岩梯子までは巨岩地帯で何度歩いても面白い。さて、地図にない路はここからだ。南を続く道を外れて西へ、方向的にはブラックフェースと呼ばれる岩壁に向かって下っていく。踏み跡はしっかりしているので、特に迷うこともなくブラックフェースに到着。初めて見たがデカい岩である。キャッスルウォールより大きそうだ。岩壁には固定のハーケンがたくさん打ち付けられている。休日ともなれば大勢のクライマーたちが集まるのであろう。一応、足がかりのある割れ目があるので、フリークライミングでも登れると思うが、落ちると重体以上が確定なのでもちろん登らない。単独行でそんな危険なことは出来ません!ブラックフェースから高座谷に向かっても一応道はある。いや、これ道だよね。シダに覆われて足元は見えないし、濡れた岩は滑りやすくて大変危ない。ゆっくり慎重に下山する。大した距離ではないはずだが、昨夜の雨に濡れたシダをかき分け、時間だけはかかって高座谷に到着。広い道に出会いホッとする。場所は奥高座の滝の少し上流のようだ。さて、高座谷を登り返す。このあたりも歩いたことはないが地図に道は載っている。 15分ばかり歩くと見知った場所に出た。そして見知った「進入禁止」の看板である。この看板は無視して良い。横池の方に抜けられるのは知っている。しばらく進むと「右、宝寿水」と書かれた小さな木片が枝に吊り下がっている。よし、こちらに行ってみよう。歩くこと10分。「宝寿水」発見。だが、枯れていた。昨日まで雨であったにもかかわらず枯れているとは何事であろうか?まぁ、人通りも殆ど無い超マイナールートなので管理がされていないのであろう。戻りたくないので、先へと続く道のようなそうでないような踏み跡をたどると、荒地山西麓の水場に出た。あら、こんなところにつながっていたのね。まだ、時間が早いので風吹岩から万物相に行ってみる。昔、歩いたことがあるはずだが10年以上前のことである。うん、ここはやっぱ良いなぁ。風化した花崗岩が林立する奇景である。屏風折となった岩が続く自然の迷路。そして、お約束として道に迷う。とりあえず地獄谷の方に向かえば良いはずなのだが迷い込んだ谷は気がつけばゴルジュ。小さな滝もあり、結構危ない。三点支持で慎重に降りる。到着した地獄谷も、「こんなに急だったっけ?」と思う結構な難コース。落ちたら骨くらいは普通に折るぞ、これ。神経を擦り減らせば体力は輪をかけて消耗する。一時間近くかかってやっと下山すれば14時半。まだ時間があるので中央尾根を登り返すが、想像以上に疲労が蓄積しており、息絶え絶えであった。風吹岩に戻って八幡谷から岡本へ帰還。
@=
今村昌弘『魔眼の匣の殺人』3/5点。屍人荘に引き続きの美少女探偵二冊目。なんか最近ミステリの世界にこのタイプが増えてきたな。読みやすい文体で相変わらず色んな要素てんこ盛りの贅沢な作品。預言者と予見者が「死」を示唆する中で起こる殺人の動機は別段驚くほどではない。超常現象を信じるものもいれば、信じない者、信じないふりをする者もいる。信じたくはないが信じざるを得ない状況に追い込まれていく中で、預言や予見を(事後に)利用して殺人やそのトリックを構築したことは面白いと思うが、もっと踏み込んで、犯人が積極的に預言や予見を(事前に)制御してたらもっと面白かったと思う。例えば、何らかの時限殺人装置を考案し、殺人直前に予見させ、その時のアリバイは確保するとかは考えられそうだ。超能力物はあまり好きではないのだが嫌いでもないので、もっと予知という特殊なガジェットを使い倒す頭のいい犯人が欲しかった所。最終章、殺人とは関係はないが、事の真相は大変面白かった。
@=
(2021-02-06) 六甲、もはや、個人的冬の庭。小春日和の晴天。暖かい日差しにこれは出かけねばならんと遅まきながら10時半に芦屋川駅。荒地山からロックガーデン探訪の二回目をやろうかと思っていたのだが、荒地山山頂で心変わりして最高峰を目指す。魚屋路から七曲りの定番コース。いい天気の休日とあり13時半の山頂はそれなりの人手。ポカポカ陽気はいいのだが大気は春霞状態。月並みな表現だが冬の冷たい凛とした空気の方が遠景までハッキリ見えるので良い。普段は山頂から引き返すのだが、再び心変わりして有馬に抜けることにする。有馬は二ヶ月ぶりくらい。どうなってるかなと行ってみるとそこそこ賑わっていた。インバウンドでごった返していた時ほどではないが、温泉街はこのくらいが風情があって丁度いいように思う。 15:10にバス停に付けばバスは16:00発。これがあるから普段は阪急側に引き返すんだよなぁ。しばし温泉街散策。とは言え何度も来てるので見るところもない。念仏寺の前にいい言葉。「したいことは あきらめず やるべきことは あせらずに できることは くらべずに」人生哲学として汎用性が有りそう。でも、こういう言葉は全幅の信頼が出来ないのも事実。生き方の指針として採用しながらも、例外となる状況を意識しておく必要があるんだよなぁ。
@=
(2021-02-11) 穏やかな日差しの休日。冬の庭へ。最高峰かロックガーデン周遊かで迷ったが後者に。晴天ではあるが暖かいがゆえに、上まで登っても水蒸気で景色は霞んでるだろうとの読み。さて、最近運動不足なので兎にも角にも体力維持である。遊びも仕事も体力は二番目に大事である。知識なんぞは三番目以下だ。なお、一番大事なのはある種のいい加減さというか鈍感力なのであるが、これは性格的なものが大きいから鍛えようがない。私も結構ええ加減な人間ではあるが、真面目で神経質な面もある。まぁ、人間ですからね。相反する二つの性格が同居するのは当然なのだが、必要に応じて鈍感になれるための訓練ってどうしたらいいのであろうか?スタートはいつものように八幡谷から七兵衛山。天気に恵まれてハイカー多し。一度、黒五谷に降りる。森の奥でガサガサと音がなるのでイノシシかなと思えばキジであった。初めて見たよ。続いて荒地山へ。昼時とあり景色のいいめぼしい場所は先客がいる。高座谷に降りるマイナー道を選択、こちらにも一箇所だけ展望抜群の岩があるのでここで休憩。地獄谷から登り返し。中級コースで先日下ったときは大変に思ったが登る分には楽勝であった。私の前を行くのは親子連れである。まぁ、小学生でも登れるわな、、、と思っていたのだが、この小学生、かなりの猛者であった。あえて難しいコース、巻き道を選択せず滝があれば直登するという具合である。親が登れない懸垂岩をスイスイ登っていく。これ斜度70度はあるよなぁ。私登れません。怖いです。両親も登れないようです。下で見守るだけです。ハーケンの打たれた大岩をフリークライミングで登っていく。落ちたら間違いなく大怪我以上だ。うーむ。時々いる天才小学生というやつですね。万物相では再び道迷い。気がつけば中央尾根に出てしまったので引き返す。みんなが思い思いの場所を歩くから踏み跡だらけで正しいコースがまるでわからない。やっとついた風吹岩から保久良神社はピクニックコース。手をつないだ幼児もたくさん歩いている。「だっこー!」「ダメ、だっこは危ないから。」ピクニックコースとは言え山だからね。こうして子供は強くなるのだ。保久良神社梅林は1分咲き。満開までは後2、3週間ってところかな。
@=
(2021-02-14) 大春日和。世間の恋人たちの熱気か?チョコレートも溶けちゃいそうな陽気である。岡本駅を発して、保久良神社上の展望台から眺めればうっすらと四国まで見えている。比較的空気が綺麗なようなので最高峰を目指す。鍛錬々々。ファミリーで賑わう風吹岩から東おたふく山経由最高峰である。最高峰からすぐに戻るのも味気ないので、一旦西おたふく山まで移動してから下山することにする。まぁ、有馬まで降りてから登り返すのが一番ハードなのだが、そこまですると修行になってしまう。今日は鍛錬である。西おたふく山に着くが、なんせノドが渇いている。 2月にもかかわらず20度越え、汗が吹き出て久しぶりにシャツが濡れている。自販機を求めて下山前に極楽茶屋跡まで往復。あー、ジュースうめぇ。こんなに暑いとは思わなかったよ。住吉川から七兵衛山に寄り道して、15時半岡本駅。今日は早めの帰宅。
@=
二週間ぶりに山へ。六甲最高峰往復。目標は毎週だけど、冬はなかなか億劫だったりして行けない。山行なんて遊びのはずなんだけど、私の場合遊びのほうがよっぽどしんどい。旅にしろ山にしろ、常に決断が求められるし体力的にもクタクタになる。仕事で辛かったことなんてたった二回しかない。まぁ、仕事なんて真剣にしてないとも言えるけど、遊びの方が何倍もしんどい生活である。登り始めてわかる、今日は体調がすこぶる良い。よし、いっちょ最高峰まで行ってみよう。東おたふく山に寄り道して、いつものちょっと危ないハードコースで最高峰へ。登山道には霜が降りており、強風とあいまってかなり肌寒い。昨日、大阪では雨だったが、山では雪だったようだ。頂上部では風が吹くたびに樹上の雪氷が落ちてくる。山頂に近づくにつれサイレンの音が聞こえる。消防に救急車にパトカーが大集合、空にはヘリも飛んでいる。聞けば、捻挫で動けなくなった人が救助要請を出したらしい。ヘリは紅葉谷の方を周回している。地上部隊も10人位の消防隊員が救助に向かっていた。おそらく、七曲滝か百聞滝かのベテランコースに入り込んで挫いちゃったのかな。結構雪が積もっている。今日は寒いからか休日の昼時にもかかわらず最高峰に人影はまばらである。魚屋道で引き返すもなんだかあんまり疲れていない。荒地山に登ることにする。下山途中の展望のいい岩の上で休憩しながら地図を確認すると、親父殿が荒地山南麓のブラックフェース(巨岩)近くにいるようだ。折角だからと下山路をそっち方面へと取るが、私のほうが一足早かったようだ。会うことはなかった。風吹岩に登り返して見頃の保久良神社梅林を見学してから帰路につく。
@=
(2021-03-07) 散歩。緊急事態が明けたからか、暖かくなってきたからか六甲も人が多い。緊急事態宣言中も日中の街中は人が多かったし、山の人気はおそらく季節的な影響が大きいのだろう。家に籠もってるより、健康的で何倍もいいように思う。 4時間ばかりの軽い散歩。いつものように荒地山でボルダーを楽しみ、高座茶屋まで下って地獄谷から再登坂。たった10キロなので楽勝。久しぶりに修行がしたくなってきた。
@=
(2021-03-14) 岡本有馬最短コース。昨日、一昨日とまとまった雨が降ったため、チリや花粉も流れ落ちて空もキレかろうと最高峰を目指す。暖かな日差しの休日とあれば魚屋道は大人気。東京の高尾山稲荷山コースほどではないが何人も抜きながら歩くのはちょいと面倒。 2時間半で登頂。最短コースであれば私にとっては標準的なタイム。有馬までなら急げば3時間もあれば着ける。距離も12キロちょいしかない。山頂からの景色は、、、可もなく不可もなく。暖かいとやはり水蒸気が出てモヤっとしてしまいますな。バスの時間を調べようとするも山頂で電波が入らず。困った。中途半端な時間に下山してしまうとバスがない。遠回りして紅葉谷で降りようと思っていたのだが、最短の魚屋道を継続する。結果的には14時のバスにギリギリ間に合ったのでよかった。この次は16時である。 SUICAに残金がなかったので、スマホからクレジットカードでチャージ。しかし、昨今のネットの進歩はすごいなぁ。何でもかんでもスマホで出来る。最近は現金どころかカードすら使わなくなってきた。スマホ落としたらこりゃ大変だな。
@=
(2021-04-10) 六甲最高峰往復。快晴。一ヶ月ぶりの山行である。忙しかったり雨だったりで間が空いてしまった。春。抜群の天気。休養十分で体調もすこぶる良い。往復15キロでは簡単すぎるので、往路は七兵衛山、東おたふく山と寄り道。朝の八幡谷はハイカーも少なく静かな森歩きで良い、、、部分もあるのだが、暖かくなったせいか鳥の喧騒が凄かったりする。七兵衛山、独り。あー、上から見下ろすと人間世界はちっちゃいなぁ。黒五谷から魚屋道へ。こちらは渋滞。本道から離脱。東おたふく山から人気のないコースで山頂を目指す。 2時間半で最高峰。空気は比較的澄んでおり雲ひとつない青空。金剛の向こうには大峰が、和泉の向こうには高野が春霞を越えて見渡せる。さて、帰路であるが全然疲れていないので荒地山に行く。が、ボケ〜と歩いていると分岐を通り過ぎてしまう。ありゃ〜、引き返すのが嫌なので適当な踏み跡を探して荒地山の方へと進路変更。途中迷いながらも無事荒地山山頂に到着。軽いボルダリングが楽しめる岩梯子を通って高座谷へ。やっと疲れてきた。風吹岩に登り返して岡本駅へ。
@=
(2021-04-18) 荒地山から地獄谷。晴時々雨。午後から雨との予報がある中、「多分大丈夫やろ」と軽い気持ちで出発。山に暗雲が垂れ込めている。少々不安。パラパラと小雨も降り出す。最高峰までは行かずに荒地山から地獄谷へのコースとする。そもそも、風吹岩は人混みだし、魚屋道も鈴なりのハイカーとあらば最高峰まで行く気もしない。高座谷の方へ降りていく。踏み跡だらけの迷いエリアだが、何度も行ってやっと覚えてきた。最短コースで一本松の岩へ。昼食のおにぎりとコーンスープ。風が強くて少し寒い。荒地山山頂から岩梯子。鎖場で20名近い集団が渋滞。引率者に率いられた初心者たちのようだ。「ええっ!ここ下るんですか?すごいですね!」「まぁ、いつも通ってるので、、、」うーん、まぁ、初心者のオバちゃんにとっては怖いかもしれないけど、そんなに大したことないしなぁ。しばらく下ると今度は小さい男の子と女の子の兄弟。おおっ、こいつは凄い。岩梯子登ってきたんだ。私「何年生?」兄「3年生。」妹「2年生。」私「すごいなぁ。頑張るなぁ。」大人とは身長が全然違うからなぁ。いや、これは本当に凄いよ。しかも嬉々として楽しそうに体全体を使って自分より大きい岩を登っていく。兄「この前行った雪山より大変やなぁ」妹「兄ちゃん遅い!はよ行って!」引率のお父さん「急がんでいいいからゆっくり!」多分、子供は急いでないんだろうけどね。落ちたら大怪我必至なだけにお父さんのほうが気が気でないだろうな。奥高座の滝まで降りたところで結構な雨。雨具を着る。結局汗で濡れるからできるだけ雨具は着たくないのだが本降りとあれば仕方がない。高座茶屋まで降りて地獄谷を登り返す予定だが、雨の具合によってはそのまま帰ってしまうことにする。で、雨はというと少し回復して小雨。また、これか。雨がやんだらもう一度登るし、本降りのままなら帰るのに、一番判断しづらい小雨。うーむ。登り返して雨がひどくなると嫌だし、帰ってしまって雨がやんだら悔しいなぁ。「小雨が中途半端だって?逆に考えるんだ!雨が降っているから登山道はすいているじゃないか。しかも雨は止むかもしれない!」ありがとう、ジョースター卿。行くしかないね!小雨の中、地獄谷へ。登ってるやつはいないが、下ってくる人は多い。多分すで途中まで下っていて雨にやられたんだろう。普段はなんともない沢登りなのだが、雨後とあれば結構な水量でなかなかの迫力である。オバちゃん二人が滝を下るのを待っていたら、あと少しというところでオバちゃん足を滑らす。オバちゃん派手に滝壺へ。ほとんど降りてたので怪我するような高さではなかったんだけど気が抜けたんだろうね。「もー、恥ずかしい所見られたわぁ。」って言われても、返事に困ります。ヌレヌレ美女ならともかくオバちゃん(おばあちゃん?)やし。気を取り直して、「大丈夫ですか?気をつけてくださいね。雨で岩が滑りますよ。」と社交辞令。万物相に着く頃には再び本降り。天気の神様はチャレンジャーをあざ笑う。午後は降ったり止んだりであった。本降りと思っていたら、すぐに回復して太陽が出る。が、すぐにまた雨。横池経由で八幡谷から帰還する。そして山を降りると青空。いつものことである。
@=
(2021-04-24) 六甲訓練。曇後晴。半袖で登れる季節である。今日は6月並みの気温だそうだ。曇りで良かったと思うくらいの暑さである。しばらく大阪を離れるので最高峰に行くことにする。魚屋道はハイカーで溢れている。最短コースで2時間半、到着。最高峰の賑わいを写真に収めようとしたらバッテリー切れ。しばらくカメラの充電を忘れていた。今日は写真なし。久しぶりに訓練でもしようかと思い有馬側へと下る。とは言え、有馬は混んでるだろうから手前で引き返す。400mの登り返し。この2ヶ月15キロ程度の楽チンな山行しかしていなかったので結構堪える。季節も良くなったし鍛え直さないと駄目だな。帰りは静かな住吉道。誰も歩いていない。うんうん、この寂静が単独行の醍醐味やね。午後は晴れてくるが下りなので暑さは問題ない。せせらぎの音を聞きながら帰還。
@=
(2021-05-01) 陣馬高尾ミニ縦走。晴後曇。久しぶりの関東。手始めは高尾山から。陣馬山からの18キロコース。傾斜もゆるいし楽勝である。バス停の人手はそこそこ。GWと言うことを考慮すればガラ空きと言っていい状況である。緊急事態で人は少ないが、GW向けの臨時バスはたくさん出ているので立ち客が出ることもない。高尾発のバスで座れたことなんて初めてかもしれない。陣馬高原下バス停着。臨時バス二台構成だが、ハイカーはいつもより少ない。 500mちょいの登りなんてあっという間。本日晴れで360度の展望。陣馬山は高尾山系では一番景色がいい。、、、が、霞んでいて富士山は見えない。春風吹く長閑な草原である。こんなに良い所だったのかと再確認。この季節普段ならハイカーだらけですからね。縦走路も静かなもの。陽光が新緑を透かして降り注ぐ。ここは本当に高尾かと不思議になるくらい閑散としている。景信山の茶屋で名物ナメコうどんを食べる。600円。うぅ、高いなぁ。前は500円だったのに値上がりしたようだ。流石にワンコインを超えると今後は考えるな。しかしながらGWでこの客足では今日の売上はしれているだろう。向かう高尾山には見るところはない。山頂は行かずに稲荷山コースでただちに下山。 4時間半の行程、12時半には高尾山口駅へ。この時間に帰れると1日が2日分ある様でなんだか嬉しい。朝が超早いから結局パッパと寝ることになって、実はそれほど変わらないんだけどさ。
@=
(2021-05-02) 丹沢表尾根から大倉尾根、丹沢山往復付。晴。関東二度目はやはり丹沢である。同行は三ノ輪のA氏。 A氏とはチベットで一緒に山登りをした仲である。 28歳、若いぜ!自転車で日本一周した後、2年かけて世界一周しただけあり体力がある。普段の登山では抜かすことはあっても抜かされることはほぼないのだが(トレラン愛好者を除く)、さすがのA氏はエラいペースで登っていく。うむ、追いつけない。先に行って待っててくれと頼む。「ペースの遅い人間の気持ちが少しわかる。」表尾根はやはり良い。1200m-1500mくらいの割には高木がなく2000m越えの風景が広がる。塔ノ岳から望むユーシン渓谷には人工物がなく、ここは北海道かと見まごうばかりだ。なお、10時半過ぎには山頂についてしまった。はや!あまりのペースについていくのが精一杯(それでも遅れていたけど)で写真を取る余裕もなかったよ。このまま下山では13時にもならない。居酒屋すら開いていないということで、丹沢山を往復。塔ノ岳以北は芽吹いたばかりの明るい灌木帯でこれがまた最高なのである。丹沢があるから東京暮らしも悪くないと思えるくらいの引っ越しの大きな原動力となっている。時間調整。丹沢山(100名山だけど丹沢山系では最もしょぼい)で時間を潰して塔ノ岳に引き返し大倉尾根にて下山。町に帰り着けば16時。二時間ばかり軽めに飲んで帰宅。
@=
(2021-05-04) 丹沢表尾根から大倉尾根。快晴。一日おいて再び丹沢へ。同行は海老名のH氏、京都のS氏とF氏。ぶっちゃけ、弟と次男とその連れである。転居一週間で早くも二回目の丹沢であるが、それだけ良い所なのである。関東近郊での山登りであれば、まずは連れて行きたくなる場所なのである。 GW真只中とあり一昨日とは打って変わって超満員。バス停は長蛇の列。臨時便が多数出ているがそれでも乗り込むまでに30分近く待たされる。それと細い林道は入れ違いが難しいので対向車のたびに止まるため結構な時間がかかる。 H氏は近頃体重が増加気味、ゆっくりとしたペースで登る。若い二人は体力が余っている。「先に行って待っといて。」てな感じで、休憩多め4時間位かけて山頂へ。休みながらのスロウハイクもまた充実している。本日は暑いくらいの陽気。前回半袖が少し寒かったので長袖にしたのだが選択ミスであった。それと、登山道は当然渋滞しており、抜かしながら歩くのは困難。鎖場では30分くらいの待ち行列。最高の季節、最高の天気とあれば、残念ながら最高の人出である。山頂からは富士山、遠くには未だ冠雪の南アルプスまでが見渡せた。人工物が何もないユーシン計渓谷を挟んだ蛭ヶ岳も間近に見える。ここはいつ来ても良い。しかも今日は珍しく風も穏やかであった。下山中、電話を落とす。わーお、やっちゃった!電子マネー。銀行口座、クレジット情報、証券口座となんでも入ってるだけに焦る。 H氏に電話を借りて自分の電話にかける。良かった繋がった。親切な人に拾われたようで下山後のバス停で受け取ることが出来た。明るい間に駅で軽く飲んでから帰宅。
@=
(2021-05-08) 丹沢主稜縦走(檜洞丸-蛭ヶ岳-丹沢山-塔ノ岳)。晴後曇。同行は再び三ノ輪のA氏。二日前にLINE着。「山、行きます?」「じゃ、西丹沢で!」 4時起きで5時半の電車に乗り、新松田駅から更にバスで一時間かけて登山口、9時。遠い。しかし遠いだけあって西丹沢は関東の秘境、登山者は圧倒的に少ない。ゴーラ沢までは足慣らし、すでに朝食から4時間以上経っているので、おにぎりを食べてから、檜洞丸への急登に取り掛かる。 A氏はやはり早い。「先に行って適当なところで待っといて」と伝えて自分のペースで登る。私も結構早いはずなんだけどなぁ。で、登れど登れどA氏がいない。途中、展望所があったりベンチがあったりするのだがいない。結局彼が待っていたのは檜洞丸の山頂。おいおい、こっちは1時間半全く休憩が出来なかったよ。山頂で11時。元々は北に向かい犬越路から下山するか体力が残るようなら大室山に行こうと思っていた。、、、が、気が変わる。ここは蛭ヶ岳に行ってしまおう。丹沢のメインルートで唯一残していたのが檜洞丸から蛭ヶ岳までの4.6キロである。丹沢の盟主、蛭ヶ岳は丹沢山系の最深部。どこから登っても10キロ以上ある。行ってしまえばエスケープは利かない。捻挫一つで帰れなくなる。また、危険箇所があるとのことで単独行は控えていた。しかし、今日は私より体力があるA氏がいる。よし、今日こそ行くべき。主稜縦走は5年前からいつかやりたいと思いながら、実現できなかった。時期的にも5月の陽の長さはありがたい。A氏に異論はなく主稜縦走決定。うん、来てよかった。蛭ヶ岳周辺は何処も素晴らしい。ただし、檜洞丸からは結構下る必要がある。下ってしまえば目の前の蛭ヶ岳はまさにそびえ立つかのようである。 A氏はラクラクと登りきったようだが、私としては相当苦しかった。とにかく止まらないようにと遅くてもいいから足を動かす。ふくらはぎと大腿四頭筋が悲鳴を上げている。蛭ヶ岳の西からの登りはめちゃくちゃ急。危険箇所は大したことはないし、鎖場も簡単なものであったがとにかく急でしんどい。盟主蛭ヶ岳からの展望は素晴らしい360度なのだが、少し曇ってきたのと水蒸気で遠望が利かなかった。ちょっと残念。ここから丹沢山までの3キロは丹沢の核心部。地の果てを行くかのような景色は、北海道と比べても引けを取らない。 14時過ぎに丹沢山に到着。ここまでくれば何度も通った道。塔ノ岳から大倉尾根へ。2日、4日、8日とこの一週間で塔ノ岳へは3回も登ってしまった。長い長い消化試合をこなして大倉バス停で5時。8時間で丹沢主稜縦走完遂。やってみれば23キロと距離的には大したことはなかった。ただし、登って降りての累積標高2000mと相当にハード。ただ、六甲縦走でもこのくらいはある(距離はもっとある)ので想像していたよりはイージーであった。
@=
(2020-05-15) 高尾ミニ縦走。晴時々曇。同行は山の相棒三ノ輪のA氏と、その友人小田原のM氏。 M氏は5年かけて世界一周をしたそうで日課のランニングを20キロもしているというツワモノ。ちょっとちょっとー、A氏と一緒だとなんだか自分が一番遅いって感じになる。とは言え、まぁ、最近自分に甘い気がしていたのでいい訓練である。さて、こんなツワモノ共と高尾だなんて腑の抜けたことだが、今回の趣旨はランチを豪華にである。庶民なんで豪華と言っても発想がしれている。思いつくのは肉であり、そうなると焼き肉ということになる。藤野駅集合、バスで陣馬山登山口。A氏には持参した2リットルのペットボトルを持ってもらう。実際にはこんなにいらないのだが、多めの水分は心の余裕。そして、A氏へのハンデである、、、はずだったのだが、うぉー、ペースはえぇ。 2時間20分のコースタイムがほぼ半分の1時間ちょいで陣馬山到着。いつもながら着いていくのが精一杯。山頂の清水茶屋でなめこ汁をすすって、縦走開始。、、、が、このメンバーであれば高尾山系の尾根ごとき平地の舗装路と変わらない。苦もなくランチポイントである景信山に到着。テロ活動を開始。コンロは三台あるので飯炊き、カレーパック温め、そして本題の焼き肉である。いやぁ、肉の焼ける素晴らしい匂い。晴れた日の山頂で食べる焼き肉は最高ですな。周囲が湯を沸かしてカップ麺などを作っている中、我々は焼き肉である。肉汁の匂いは相当広い範囲に拡散し、不意を突かれたハイカーに「うまそう!」と思わせる破壊力は抜群だ。まさにテロ行為と言っても良いだろう。飯テロである。M氏などは早々にビールを飲み終えてワイン瓶まで開けている。今この瞬間、世界で最高に贅沢な昼飯を食べているのは自分たちのような気になる。たっぷり二時間の昼食を取った後は完全に消化試合の後半戦。普段なら高尾山は巻いてしまうのだが、A氏は初めてM氏も10年ぶりとのことなので敢えて1号路を選択。薬王院の修験道文化に触れながら下山すれば時間は16時といい塩梅。帰りの電車では爆睡。
@=
(2021-05-29) 雲取山。晴。雲取山は遠い。交通の便が悪すぎる。 4時に起きて食事後、6時発の電車で出発、8時30に秩父からバス。三峯神社10時。登山口に着いた時点ですでに起きてから6時間である。登る前からお腹が空いているのでおにぎり。バスは満員でギュウギュウ詰めであった。一時間半揺れるバスで立ちっぱなしであるのもきつかった。こんなに不便なのに人気なのは雲取山が特別な山だから。東京都の最高峰2017mである。同行は三ノ輪のA氏。同行と行っても登山開始が同じなだけで、速いA氏には先に行ってもらう。ついて行けんわい。スタートから一時間、茶屋のある霧藻ヶ峰に着く。待っているならここだろうと思っていたが居ない。「ああ、こりゃ山頂の雲取山まで先に行ってるな。」開き直って自分のペースで休憩も入れながら進むことにする。雲取山は東京から見れば最高峰であるが山梨から見ればなんでも無い低い山。尾根から西を望めば2000m超えの稜線が見渡せる。遠く霞んでいるが八ヶ岳や北アルプスも見えているようだ。 3時間40分かかって雲取山頂。奥秩父縦走路でつながる飛竜山までの尾根がよく見えた。飛竜山、名前がかっこいいね。なお、飛竜山の次は竜喰山でこちらも名前がかっこいい。さらに甲武信ヶ岳、金峰山、瑞牆山まで続く縦走路は70キロ。いつかやりたいけど出来るかなぁ。雲取山から下る石尾根は景色もいいものの鴨沢に入れば完全に消化試合。ダラダラと長いばかりで面白みがない。下山後バスの時間調整のためラーメンを食べて帰り着けば21時。雲取山、遠いわ。
@=
(2021-06-05) 南高雄。曇。予報では降水確率30%。雨が降ってもエスケープしやすい高尾にする。人の少ない南高尾へ。首都圏自然歩道No.1湖のみちを選択。このコースはなんと言っても眺望が悪い。基本森林浴向けであるが天気が悪いのでちょうどよろしい。高尾山口駅からさくっと草戸山へ。山頂から漂う美味そうな匂い。3人組が焼き肉やってやがる。飯テロだ。さっさと通過。さしたる展望もない。ここから南高尾の大洞山まではゆるいアップダウン。長くて単調。トレラン組と多数すれ違うが、鍛錬目的なら北高尾の方がハードでいいと思う。大洞山から大垂水峠まで下って城山に登り返すも150m下りて200m登るだけ。楽勝である。久しぶりに城山茶屋のなめこ汁を食べると、後は帰るだけ。高尾山はマスク圧が高いのでもちろん巻く。 4時間半、15キロの行程で高尾山口駅に戻る。
@=
(2021-06-12) 西丹沢、大室山-加入道山-畦ヶ丸。同行はA氏。西丹沢に行くことは決めていて、「行ったことない山がいい」とのリクエストを受けて大室山へ。大室山は私も3年以上前に一度登ったことがあるのみ。この季節は初めてなので新鮮である。バスの終点まで乗って8時半。登山口の用木沢までの林道が崩壊しているらしく本当は通行止めなのだが、行ってみると歩行者用の仮設橋がかかっていた。たとえ仮設橋がなくとも通行は可能。なんで歩行者まで通行禁止なのだろう。通行止めのロープはくぐる。他の登山者も含めてみんな通行禁止の看板なんて無視している。ハイカーは基本マナーがいいんだけどね。こと「キケン、通行止」だけは守らない。さて、しばらくは渓流沿いの気持ち良い谷筋。尾根に至る最後の500mだけは急登。峠である犬越路からは南に景色が広がる。南下すれば檜洞丸だが、今回は北上して大室山へ。道中ブナの森は新緑が萌え上がるようであった。これはこれで悪くないが、初冬で葉が全て落ちていた前回のほうが趣はあったように思う。大室山はどっしりとした山容に丹沢山系3位となる1588mであるが樹林に覆われ展望はない。緑の映える明るい広葉樹の森であるので気持ちは良い。続く加入道山までも丹沢特有のブナの森。緑の隙間に時折黒い富士が顔を出す。前回は白石峠から下ったが、今回は時間が早いので畦ヶ丸まで足を伸ばす。ただ、加入道山以降は標高も低くなり余り特徴のない尾根歩きとなって面白みは少ない。特に畦ヶ丸からの下りは単調。ただし西沢に入ると雰囲気は良くなる。ファミリーも多く、木橋で何度も沢を横切り、岩を越えて歩くのは子どもたちにとってはさぞかし楽しかろう。もちろん、大人だって楽しい。バスの時間ギリギリとなり最後少しだけ小走り。15時40分のバスに間に合う。山行が6時間半。往復の交通時間が同じくらい。ほんとに遠い西丹沢。
@=
(2021-06-26) 菰釣山、甲相国境尾根。曇。以前からやってみようと思っていた丹沢から山中湖へと抜ける甲相国境尾根コースである。同行は三ノ輪のA氏から引越しした三鷹のA氏。結構なロングコースであるがA氏がいれば安心である。大滝橋バス停を出発してまずは800mの高度上昇。緩やかな谷筋コースなのでそれほどしんどいわけではない。川沿いは常に湿度が高いのか、広葉の緑に路も苔に覆われて緑と視界全てがグリーンワールドである。二時間弱でモロクボ沢ノ頭、標準コースタイムの半分。まぁ、このくらいでないと山中湖まではいけない。ここからの甲相国境尾根が本日のメインデッシュ。天気は曇りであるがピーカンで暑すぎるよりは良いと思う。途中、霧に巻かれての天然ミスト。涼しいのはいいのだが景色は全く見えない。まぁ、そもそも樹林に覆われたコースなので晴れていたとしても展望はしれているだろう。路は悪くないがヤセ尾根が多く、冬であればそれなりに危険かもしれない。全体的に険しくはないのだが地味にアップダウンの連続なので体力は少しづつ削られる、道のりが長いだけに後半はそれなりに辛い。中間地点の菰釣山が本日の最高峰、1379m。ここまでくれば富士山も間近だからね。雄大な富士が眼の前に、、、は見えない。まぁ、曇りである。梅雨の晴れ間だ。雨が振らなかっただけで良しとする。贅沢は言えない。気分はもう消化試合。富士岬平まで歩いてやっと山中湖が見えた。富士は裾野の裾しか見えないが仕方がない。神奈川から山梨まで歩けたことだけで満足だ。温泉を目指す。汗だくでシャツもパンツもびしょ濡れだ。15時前に石割りの湯に到着。距離は20キロ。思っていたよりは楽であった。のんびり湯に浸かって、高速バスで新宿へ。これほんとにもう小旅行だよ。富士五湖まで歩いて行って全く観光せずに帰る。実に男らしい小旅行である。
@=
(2021-07-06) 曇時々小雨。高尾-城山。毎日々々呪われたように雨である。梅雨なので当たり前とは言えるのだが、近年、地球温暖化か日本の南国化か、梅雨でも普段は晴れていて夕方頃ゲリラ豪雨というパターンが多かったのだが、今年は昔ながらのしとしとジメジメな梅雨の再来である。折角の平日の休みが台無し。二週間も三週間も晴れがないとか嫌がらせであろうか。雨天上等で高尾に行く。10日も引きこもっていられないし高尾ならどこからでもエスケープできる。高尾山口9時半。稲荷山から高尾山。小雨が降ってきたのかパラパラと音はするが、木々に囲まれた山中まで雨は届かないので特に問題はない。しかしながら、超絶不快である。暑い上に湿度100%とくれば、汗はまとわりつくようである。そして高尾は道が悪い。いや、登山道はこの上なく整備されているのだが、歩く(走る)人が多いだけに雨や雪の後は踏み返されて泥濘となるのだ。なお、夏の低山でレインウェアは意味がない。汗で濡れるよりは雨に濡れたほうがまだマシというものである。天気が悪いし平日だしということで、普段は巻いてしまう高尾山頂にも行ってみる。流石に人が少ない。また、小雨ながら雲は高いのか富士が見えた。城山まで行ってギブアップ。不快すぎる。二時間も歩けば運動としては十分だろう。汗も普段より何倍もかいた。まぁ、今日は体力維持ですな。こんな天気で出かけても楽しくない。家にいるのが嫌だと言うだけで来てしまったが、夏の風物詩、アジサイが綺麗でそこだけは良かった。東海自然歩道を歩いて相模湖から帰還。10キロ3時間は物足りないが、天気悪いし不快すぎるわい。
@=
(2021-07-10) 塔ノ岳、定番コース。雲時々晴。朝から曇天。降水確率20%とあれば山では雨が降るかもしれない。雲で景色は見えないだろうし、雨が降ればロングトレイルは厳しいので定番の東丹沢塔ノ岳へ。バスは空いていて座ることが出来た。今日の最高気温は予報では33度。暑いし天気も良いわけではないのでハイカーも引きこもってんでしょうな。さて、ヤビツ峠の時点で雲の中。日差しがないのはむしろありがたいくらいなのだが、湿度は非常に高い。 1000m程度の低山では気温低減効果もしれている。暑い暑いムシムシする。二ノ塔で息絶え絶え、三ノ塔に着く頃には、雨でも振りましたかと問われかねないくらいの汗だくである。大学生だろうか?4人組の声が聞こえる。「なんで山登るんかな。」「登ってるときはしんどいし、下りは早く着かないかなって思うし。」「楽しいとかほんのちょっとしかないものね。」ふむふむ、なるほど。若人よ答えてあげよう。(山に登る理由。それは君たちが馬鹿だからだよ。)と心の中でそっと思う。自ら不快な目に合いに来ているのだからもしくはマゾだからかもしれない。吹き出る汗を何度も拭い、塔ノ岳に着く頃、雲に晴れ間が覗くようになる。太陽が背中にジリジリと照りつける。いつもは強風が多くて寒いくらいの山頂だが、こういう日に限って無風である。本日、1.5Lの飲み物を持ってきたのだが、全く足りなかった。涼しい日であれば500mLで十分なのだが、山頂で飲み尽くしてしまったので水場まで往復する。 300m、標高差100mの下り上り。山腹に湧く清水は冷蔵庫から取り出したかのような冷たさ。うまい。ペットボトルいっぱいに汲んでこれで帰りも安心。塔ノ岳に戻れば後は帰るだけ。何度も下った大倉尾根。展望もないし今更見どころもない。パッパと下山して駅前でソバを食べて帰宅。
@=
(2021-07-22) 陣馬山。晴。明日、塔ノ岳に行くので軽めの山行。高尾は混むので一駅ずらして相模湖駅から出発。与瀬神社から栃谷尾根は、昔、逆コースで行ったことがある。高尾山系も高尾山と縦走路を除けば空いている。杉の植林帯が多く、暗くて展望も開けないが、今日の暑さを考えればむしろ好都合かもしれない。吹き出る汗を拭いつつ、2時間で陣馬山、855m。木陰で休憩する分には涼しい風が吹いて心地よい。都会の無茶苦茶な熱波に比べれば何倍もマシである、が、山頂にたどり着くまでは何倍も暑いししんどい。塩分補給に茶屋でなめこ汁を飲んで下山。 10分ほど歩いたところで、大汗かいた小太り兄ちゃんから声がかかる。「もうすぐですか?」「えぇ、もうすぐですよ。後ちょっとで山頂です。」ハイカーの言う「後少し」は信じてはいけませんよ。腕時計の高度計を見ながら、「ここが720mですから、100mちょいですね。」と客観的なデータも示してあげると、「まだまだですね。がんばります。」とのこと。うーん、100mくらいすぐなんだけどなぁ。普段運動不足だとそうでもないのかな。栃谷尾根を下れば途中に陣馬温泉がある。寄るべきかどうか悩んだが見送る。駅まではまだ4キロある。今日の暑さじゃ、帰るまでに再び汗だくとなろう。栃谷集落からは面白みのない車道歩き。太陽とアスファルから立ち上る熱気にクラクラしながら昼過ぎには駅到着。
@=
(2021-07-23) 塔ノ岳。曇。同行は練馬のR氏。何度も登った塔ノ岳だけど、近郊で登りやすさの割には満足度の高い風景が広がる。よって、初めて登る相手とは丹沢に行くことが多い。山行、好きになってほしいからね。しかしながら、生憎の曇り空。この季節、カンカン照りでも困るんだけど、曇りと言うより雲の中なので景色が全く見えないのは残念。天然ミストで照りつける暑さはないものの、湿度は高いので汗は結構かく。 R氏。最近運動不足で山登りは不安とか言っていたはずだが、さすがは21歳。基礎体力が違う。むしろ私がついていけません。うーん、衰えてるんかなぁ。自分では結構体力ある方だと思っていたのに、本当に若い人と一緒だと登りでついていけない。時間があれば丹沢山までピストンする予定だったけど、景色がないのでヤメにする。よって、休憩多め。それでも昼前には塔ノ岳山頂についてしまった。 1時間以上山頂でのんびりして、必要ないのに水汲みに行ったり、定番の花笠茶屋で麺を食べたりして時間調整。 4時半といい具合に下山したものの駅前の居酒屋は全て休み。緊急事態宣言恐るべし。小田原にも近いし美味しい海産物を食べる予定だったのに肩透かし。仕方がないので新宿まで戻って海鮮居酒屋に寄ってから帰宅。
@=
(2021-07-25) 18きっぷで袋田の滝へ。同行は鉄道マニアでもある上野のI氏。滝って大概がつまらないし期待していなかったけど、思っていた以上に良かった。嬉しい誤算。入場料300円も良心的。観光地なのに鮎の塩焼き400円などと物価も安心。帰りに水戸駅で途中下車すれば駅コンコースで見かけた利き酒セットに釣られて茨城の地酒を味わう。程よく酔いも回って駅前に出れば、地酒フェスティバルみたいなのをやっていて再びお尻に根が生える。地元のミュージシャン(玉石混交)のライブを聞きながら贅沢な時間を過ごす。本来、往復6000円かかることを考えればものすごくリーゾナブルな旅であった。、、、が、交通費以上に地酒にお金を落とした旅であった。
@=
(2021-08-01) 大岳山。晴。同行は先週に引き続き練馬のR氏。日曜(明日仕事)のため、軽めにということでケーブルカー利用。 831mまで上がってくれるので、実質的な上りは300mちょっとと非常に楽な山。大岳山は奥多摩三山の中では一番低いが、山容が独特で遠くから眺めてもわかりやすく、登ってみれば景色もいいため結構好きな山の一つ。ケーブルカー駅から歩いてすぐに御岳山。山頂は御嶽神社で門前町があるため、山という感じはしないが、林間の社殿には趣がある。由緒は古くヤマトタケル伝説が残るほか、眷属のおいぬ様が有名になったためか、愛犬連れの参詣者も多くいる。ここから、大岳山はピストンなのだが、同じ道では面白くないので、行きは少し下ってロックガーデン経由とする。暑くさえなければ沢筋の気持ちのいい道。汗は吹き出るが直射日光が照らない分、ジリジリと焼け付くという感じはない。また、夏だからこそ岩も木々も全てが苔に覆われている。視界全てがモスグリーンである。大岳山は最後の100mこそ急登だが比較的なだらかで歩きやすい。山頂は11時ということもあり登山客はそれなりにいた。天気はいいんだけど、春から夏は水蒸気多めなのでどこか靄がかかっているのは仕方がない所。御岳山に戻れば12時過ぎの丁度いい時間。門前町で昼食にそばを食べてから日の出山へ。ここも気楽に来れる割には関東一円を展望できる。コストパフォーマンスの高い山。秋になれば焼肉セットをもってまた来たいと思う。今回のコースは高低差があまりないのでそれほど疲れた感じはしないが、それでもなんだかんやで15キロ。大量に書いた汗を温泉で流して帰宅。
@=
(2021-08-21) 高尾縦走。曇、時々、雨、時々、晴。本日、天気予報は曇、降水確率30%。明日は曇時々晴、降水確率30%。わずかばかり明日のほうが良さそうだが、似たりよったりだし、そもそも夏の低山は太陽が出てるほうが嫌。ということで本日を選択。雨が降るかもしれないので高尾。奥高尾縦走路はハイキングどころかウォーキング並み。超絶イージーだが、湿度は高く蒸し暑い。草木も生い茂っていて景観も登山道の状況もいとわろし。体力維持のためだけに来たようなものですな。特筆すべきことはなし。
@=
(2021-08-29) 大菩薩嶺。曇。同行は練馬のR氏。大菩薩嶺は景色が大変良い稜線歩きが楽しめるのだが、晴天とはいかず。時折陽が指すものの概ね雲の多い天気。登山口の時点で1600mあるので登るのは400m程度と気楽な割に満足度の高い山とありハイカーも多い人気の山。日曜登山のため、丸川峠経由で甲府側に降りる。下山路がとかく長いのだが展望はないものの気持ちのいい森林浴コースである。 1500m以上となると暑さも酷くはなくなる.。雷岩で30分ばかり休憩しても総工程は4時間程度。遠いだけに短いコースはもったいなく感じるものの翌日仕事とあらば仕方がない。やっぱ、無職が最強だなぁ。
@=
(2021-09-11) 塔ノ岳。曇後雨後晴。降水確率30%では山では雨が降る見込み高し。盆休み週末ととかく天気が崩れる。嫌がらせのようだ。テレワークで毎日家にこもっているのに、週末まで出かけないとなると精神的にも体力的にも良くないので丹沢へ。高尾と丹沢なら雨でもどうにでもなる。で、やっぱり雨。それなりに本降りとなったため、久しぶりに傘をさしての山行。レインウェアも持参してるが夏は着る気になれない。雨だし何も見えないしで山頂をスルー。時間が早いせいもありハイカー少なし。まぁ、文字通りみじみずしい森もたまには悪くない。下山を始めると晴れてくるのはいつものこと。
@=
(2021-09-19) 檜洞丸から犬越路。晴天。久しぶりの晴天。台風一過で空気も大変澄んでいる。行くしかないなこれは。遠いけど満足度の高い西丹沢へ。同行はマイブラザー。檜洞丸への定番、つつじ新道から犬越路を周遊するコース。 9月も後半になり、これまでの暑さが嘘のような涼しさである。湿度も高くないし適度な風が吹いて気持ちの良い尾根道。標高差800mの急な登りも気候が良いとそれほど疲れないものである。行楽のシーズンとなり今日は混んでいるのではと心配していたが、西丹沢は交通の不便さからかこの時期でもハイカーは少なく全くの杞憂であった。昨日の台風による大雨のおかげで空がとても綺麗。水蒸気も出ていないので遠くまでくっきりと見渡せる最高の天気である。そして、檜洞丸から犬越路は丹沢でも最も美しい風景が広がる稜線の一つ。それなりに危険な箇所もあるのだが、左を向けば常に雄大な富士が眼に入るので歩いていても楽しい。今回のコースにはマイブラザーも喜んでくれたようだ。のんびり歩きすぎたか、下山すれば16時過ぎであった。麓はキャンプ場になっているのだが、朝通ったときとは違い「難民キャンプか!」と思えるほどのテント村になっていた。帰り道、信玄の隠し湯に寄るが、ここも入場制限で20分待ち。パス。行楽のシーズン、キャンプ場は大盛況のようです。
@=
(2021-09-23) 鍋割山から塔ノ岳。晴天。家でやりたいことがある。しかし、いい天気とあれば家にいるのは惜しい。仕方がない4時起床だ。午前中に山登り。午後は家で趣味のプログラミングだ。さて、行き先だが本日は鍋割山にする。大倉なら6時台にバスがあるし、鍋割山はしばらくぶりだ。登山口まで1時間ばかりの長い林道歩きが続くが、まぁ、良いウォーミングアップである。 9月の大倉尾根は人混みだが、一本谷を挟んだこちらは静かなもの。広葉樹林が広がる森を見上げれば、晴天の陽光を受けて緑の葉がさざ波を打っている。いいなぁ、天高い秋。一番いい季節が始まった。本日、東京は暑かったようだけど山は涼しいものである。とはいえ、それは止まって休憩すればの話で、急坂が延々と続くので道中は汗だくである。何回か通った道なのだがいつもは下りに利用するため登るのは今回が初めて。林道歩きが長いだけに後半一気に高度を上げることになるのは結構ハードである。さて、山頂の鍋割山荘は鍋焼きうどんが超有名で非常に美味しいのだが、到着が9時半。山荘開店前。残念。晴天で雲ひとつない山頂からは相模湾が見渡せる。伊豆大島の方も見えると思うが、少し水蒸気が出ており靄がかかっている。富士も大変近くて迫力なのだが、先週の台風一過後の澄んだ檜洞丸からの風景に比べれば一段落ちるだろうか。帰りは定番の大倉尾根まで稜線伝いに歩く。この道は北を向けば盟主蛭ヶ岳と副将檜洞丸を結ぶ丹沢主稜が見え、南を向けば江ノ島から伊豆半島まで相模湾が見渡せるちょっと贅沢な道である。金冷やし(大倉尾根との分岐)まで来れば塔ノ岳もすぐなのでついでに立ち寄る。山頂のハイカーは100人くらいだろうか。少なくはないがこの季節にしては控えめな人数である。まだ、11時にもなっていないし、体力的にはまだまだ歩けるが、今日はここまで。下山は消化試合。12時過ぎには大倉バス停へ。さて、家に返ってシャワーを浴びれば休日第二ラウンドである。
@=
(2021-09-25) 大岳山から馬頭刈尾根。雨。予報は曇で降水確率は30%。同行は三鷹のA氏。午後に向けて回復傾向だし、遅目の8時集合にしたしで、多分雨は降らないだろうと出発。が、駅に着いたら雨。駅から歩いて登るつもりだったが、雨やし、、、と言うことで、バスとケーブルカーを使う。まずは御嶽神社に参詣。雨がやまないことから、門前の定食屋へ。食事は10時からとのことで、飲み物で10時まで粘ってからソバを注文。雨宿りのつもりだったが全く止む気配なし。やむを得ない。傘をさしての登山とする。なお、山中靄がかかっているし、景色は全く見えない。大岳山山頂はケーブルカーを使えば小一時間で着くが、ただの白いだけの世界。長居しても仕方がないので、今日は修行と割り切って、秋川温泉を楽しみに歩くことにする。さて、大岳山から温泉目指して馬頭刈尾根に下りたつもりが、気がつけば引き返していた。「あー、こっちの道も険しいなぁ。」「あの道を塞ぐあの倒木巨大やなぁ」などと話しながら下山を始めて15分。分岐点まで戻ってやっと道間違いに気づく。明らかに登って来た道と反対側に下ったはずだし、特徴的な岩道であるにもかかわらず、同じ道を帰っていることに二人して全く気づいておらず、なんだか化かされたような気分になる。私としては二ヶ月前にも来ているし、合計すれば10回は通った道だ。雨の霧中であったとは言え不思議である。少し遠回りとなったが気を取り直して温泉へ。景色はなんにも見えないし、山中しゃべくり道中で3時間、目的地に到着。ほぼ何も良いことがなかった修行を終え、湯に浸かれば気分は極楽。まぁ、こんな日があってもいいだろう。なお、A氏とは3ヶ月ぶりとなる山登り。しゃべり続けてGPSログを取るのすら忘れていたためコースマップはなし。
@=
(2021-10-02) 霧ヶ峰、八島湿原から車山周遊。晴れ。同行は大森のW氏。木曜日にW氏から電話で霧ヶ峰に行こうとのお誘い。車も出してくれるとのこと。断る理由は何もない。即決でオーケー。なお、八島湿原には15年ほど前に行ったことがあり、詳細は覚えていないものの良かったとの記憶はある。前日の夜9時半に自宅を出発し、大森駅10時半にW氏の車に乗り込む。深夜の高速を経て八島駐車場に午前2時半。既に数台の車が停まっている(泊っている)ようだ。漆黒の闇に満天の星空。前日の台風による大雨がむしろ嬉しい。空気が澄んでいるのだろう。齢25日の月が眩しい。車中仮眠。眠いので間もなくまどろみの世界へ。、、、が、寒くて5時に目が覚める。まだ、真っ暗。30分程度車中で時間を潰し、明るくなってきた頃朝食をとって6時前には行動開始。夜明け前の八島湿原にはアマチュアカメラマンが多数待機していた。日の出とともに訪れるシャッターチャンスを狙っているのであろう。シルエットの湿原に池塘は赤紫色の空を映しこんで幻想的である。湿原を右回りで霧ヶ峰最高峰の車山を目指す。折角なのでできるだけ大回りの遠回りで楽しむことにする。 W氏はこの一年で相当体力が落ちたそうだ。コロナでのテレワークは確実に健康を阻害しているように感じる。リハビリを兼ねてのハイキングであるが、車山は1900m越えながら駐車場の段階で1600mはあるのでそれほどしんどいわけではない。朝の高層湿原は鮮やかで美しい。青い空に緑の草原と色づき始めた赤い葉でRBGの全てが揃っている。どの方向を向いてもそこには美が存在する。人の一生とはこの美といかに触れるかで充実度が計られるように思う。強すぎず弱すぎず風が耳元を掠め、色めく草木が朝露で光り、清涼で張り詰めた空気に肺も喜ぶ完璧な朝だが、足元だけはずぶ濡れで気持ち悪い。まっ、仕方ないね。煌めく朝露と湿る靴下は不可分だ。時間はたっぷりとあるので、贅沢に時間を使いゆっくりと進む。時間とともに雲は上昇霧散し、北八ヶ岳の柔らかく穏やかな山肌が眼の前にひろがる。そして、車山に登れば、結構な人だかり。白樺湖からはリフトもあるし、車山駐車場からは1時間もあれば往復できるとあり、景色もいいので車山は大人気のようだ。昼食に車山駐車場のレストランでカレーを食べて、帰りもできるだけ遠回り。午後の陽気は暑いくらい。雲もほぼ消え晴天と言って良い状況で、湿原にはビビッドな風景が広がるが、やはりなんと言うか味消しである。山はやはり朝が良い。なんとなく幽玄な雰囲気が残っているのが良いのだ。午後2時半に駐車場に帰還。理想的な下山時刻である。
@=
(2021-10-03) 景信山、陣馬山。快晴。この所週末のたびに天気が崩れて憤懣やるせなしであったが、久しぶりの連日の晴れ。目覚まし5時。、、、が、寝不足続きで起きれず、6時半起床。溜まった洗濯をすれば7時半。この時間からだと高尾しかありませんな。どこでも良いのでバスルーレットにする。バス停に最初に来たバスに乗るので行き先は運次第。 9時過ぎに高尾駅に付けばバス停は長蛇の列であった。いやぁ、緊急事態宣言はそれなりに有効だったのね。正直、9時はハイカーにとっては遅い時間だけど、この人数に驚くとともに臨時の増便が出ていることに安心する。そりゃ、そうだ。これだけのハイカーは通常便だけではさばききれないでしょうな。最初に来たのは小仏行。増便付で二台同時発車。小仏かぁ。じゃ、景信山だな。さくっと、登頂。400mくらいの高度なら息すら上がらない。高尾山方面に進むと混雑が予想されるため陣場山へ。縦走路は一昨日の雨で所々ぬかるんでいた。健脚者にとって高尾縦走路なんて平坦路みたいなもの。あっさり、陣馬山へ。お腹が空いたので清水茶屋にて「陣馬うどん」を食べる。山の食事だからね。山で食べられることに意味がある。味は、、、おおー、期待以上だ。山菜にナルトにハンペンにタケノコいり、値上げしたとは言えこれで700円は町中の蕎麦屋に匹敵するコスパに思う。時間は13時。帰りは相模湖駅へ。日曜なので軽めで帰宅。
@=
(2021-10-09) 丹沢主稜縦走。曇。同行は練馬のR氏。若いし私より体力があるので難度の高いコースを選択。春に行ったときもキツくて死にそうだったが季節も変わったところで再度挑戦である。新松田7:15発のバスで西丹沢ビジターセンターへ。R氏は始発で来たもののギリギリであったようだ。遠い遠い西丹沢、8時半スタートであるが私だって4時起床だし、登山開始時には既にお腹が空いている。檜洞丸までは1000mの登り2時間ちょい。一座目から急登でしんどいのだが、このコースの核心はやはり檜洞丸から蛭ヶ岳の4.6キロ。まずは300m以上下らされる。最終的には1250mくらいまで下りるので蛭ヶ岳へは400m以上の登り返しとなる。しかもアップダウンの連続で平坦部が非常に少ないため歩きながら休憩と言うか疲れを取ることが出来ない。そして蛭ヶ岳直前は一気に300mの登りで鎖場ありの急坂である。これにはさすがのR氏もしんどかったようだ。私はと言えば息も絶え絶えである。このあたりから雲が多くなり山頂霧中となって景色は全く見えなかった。残念。距離的には1/3と言ったところだが、蛭ヶ岳は丹沢の盟主1673m。塔ノ岳までは稜線上でアップダウンが続くとは言え斜度はぐんと緩くなり全体的には下り傾向。疲労が蓄積しているため辛いことに変わりはないが、帰りの算段がつくようになるため気分的には楽である。塔ノ岳からは長い長い消化試合。結構急いで折りたため二時間弱で下山。ものすごい汗で、服を着ているだけで不快なため体を拭いて着替える。駅前で軽く飲んでから帰宅。最後に、今回、丹沢では最も山奥と言える臼ヶ岳で裸足の登山者と遭遇。奥多摩や高尾で裸足の登山者は時々見かけるが、まさか、こんな岩だらけの丹沢の最深部にまでいるとは思わなかった。平丸から蛭ヶ岳を登ってきたんだとさ。思わず好奇心から足の裏を見せてもらったのだが結構綺麗でびっくりした。こちとら登山靴をはいていても膝ガクガクなんだけど、きっと足運びがうまいんだろうなぁ。
@=
(2021-10-16) 宮ヶ瀬湖から丹沢山経由大倉。曇後雨。予報は曇り、夜から雨。なんとか大丈夫やろとの判断で宮ヶ瀬湖から大倉に抜けるコースを選択。同行は三鷹のA氏。本厚木駅で下車、雨。おいおい、いきなり雨かぁ。流石に出発から雨だと萎える。結構な雨量だが、雨雲レーダーで確認すると山の方は逆に降っていないようだ。とりあえず宮ケ瀬行のバスに乗り込むことにする。バスに揺られて50分。宮ヶ瀬湖では雨が降っていなかった。良かった。登山道に入ってすぐに、ヤマビルよけの塩水スプレーがおいてあったので、念のために足元に噴射。東丹沢はヤマビルが多いとの情報があるが、表尾根や大倉尾根を歩いている限り出会ったことがない。今までホンマにおるんかいなと思っていたのだが、いた。普通にたくさんいるぞ。ザックをおろしてちょっと休憩したすきにA氏のザックにヤマビルが一匹。更には靴にも一匹。ちょっとこれは危ないな。じっとしていると奴らはニオイを嗅ぎつけて寄ってくるようだ。 A氏はなかなか実験心が豊富。ヒルを自分の腕に吸い付かせてどうなるかの実験を始めた。数分経過。結構吸い付く力は強いようで、ちょっとやそっとでは剥がれない。つまんで強く引っ張らないとだめなようだ。特に吸血痕もなし。ヒルと言えど流石に数分では皮膚を食い破って血を吸うまでは出来ないようだ。 20分も30分も実験してるわけにはいかないので(てか、その間にも足元に寄ってくる)、実験はここまで。先を急ぐことにする。早足であまり休憩をせずに進んでいる分にはヒルにはやられないようだ。つまり、いつもの山行スタイル(ハイペースで休憩なし)では自然とヒルを避けていたことになる。今回、宮ヶ瀬湖からの道は初めて歩いたのだが、岩場あり鎖あり、ブナの自然林が広がる明るい森で大変いいコースである。ただし、そもそも曇で程なく霧中、昼前には雨になってしまったので、このコースの良さを半分も知ることは出来なかったであろう。寒い時期の好天を捉えてもう一度歩いてみたいと思う。丹沢山に着いてしまえば後は長い長い消化試合。風のキツイ雨の中、傘をさして下山する。塔ノ岳を越え、大倉尾根をひたすら下降する。下山後のバス停にある靴洗い場では、大勢が靴に着いたヒルを落としていた。「うわー、塔ノ岳、トラウマやわー。」てな声も聞こえてくるので、やはりヒルってたくさんいたんだね。今まで全然気づかなかったよ。雨の日に誰かと行くことはほとんどないし、一人のときは足早に行動しているので今までヒルと出会うことがなかったようだ。ただ、いることが分かって気をつけてみると、バス停近辺にもヤツがぬめぬめ動いているのが観察できる。今日はほとんど雨で辛いことが多かったが、血を吸われることなく下山できたのは良かったとしよう。駅前で軽く飲んで帰宅。
@=
(2021-10-23) 大菩薩嶺から牛ノ寝通り。晴。同行は三鷹のA氏。奥多摩で一番美しい紅葉が見れるという牛ノ寝通りへ。奥多摩の本気が見れるとのことで3年前に訪れたことがあるのだが、その時は見事な紅葉を期待していたのだが肩透かしを食ってしまった。すでに11月(2018-11-11)になっており、本気を出した後なのか大半の葉が落ちた枯れ木の森であった。というわけで、再チャレンジ。前回は小菅村からの往復であったが、今回は大菩薩嶺から縦走での牛ノ寝通りである。昨日は雨。空気中のチリが洗い流されて空気がたいへん澄んでいる。見事な青空。、、、が、紅葉には少し早かったようだ。大菩薩嶺は1600m付近までバスで行けるのだが、全然色づいていない。さくっと大菩薩嶺(雷岩)へ。登山口から400m登るだけなのですぐに着く。しかも富士に甲府盆地、南アルプスまで見渡せる絶景である。大菩薩嶺はこの手軽なコストパフォーマンスが魅力、、、なのだが魅力的すぎて大変登山者が多い。いや、いつもはここまで多くないんだけどなぁ。緊急事態宣言が明けた行楽シーズンとあり一気に皆が外出した結果だろうか。先週、丹沢では雨にやられたが、富士では雪が降っていたようだ。今シーズン初の冠雪した富士山を望みながら気持ちの良い尾根歩き。ただ、今回、大菩薩嶺はおまけ。目的は大菩薩峠、石丸峠を越えた先の牛ノ寝通りである。奥多摩の本気を是非見てみたい。、、、が今回はどうやら本気を出す前のウォーミングアップ中であったようだ。木々はところどころ赤くなっているものの、それも1500m以上の高所だけ。 1400mでは黄色っぽいくらいで、1200mではまだまだ青々としたモミジの森が広がっていた。残念。これは日を変えてもう一度こないといけませんな。しかし、この牛ノ寝通り。何分交通の便が大変に悪いことから人は極めて少ない。静かな森林浴コースとしてもなかなかおすすめできる路である。誰もいない道中、妖怪に出会う。いきなり頭上から「きゅいー」と不気味で得体のしれない音が鳴り響く。しかも複数回である。同行のA氏と二人で一瞬ギョッとする。「なんだ。なんだ。」おそらくは風のいたずらによる木々の摩擦音だと思われるが、科学進歩のない江戸時代までの人々にとって、こういった自然現象はすべて妖怪の仕業であったろうし、それらが写実化され記録に残り現在の妖怪たちが生まれたのだろう。 14時過ぎに下山口となる小菅の湯に到着。冬の到来を思わせる木枯らしで冷えた体を温泉で温め、奥多摩で餃子を食べて帰宅。
@=
(2021-10-30) 乾徳山。快晴。同行は三鷹のA氏。前日は仕事の飲み会。金曜夜の予定は断ることが多いのだが、三年ぶりの旧知となればこれはむしろ行きたい。飲みは軽めを意識して帰宅したら23時過ぎ。イカン、何の計画も立てていないのでA氏を頼る。「明日、どこ行くの」「乾徳山」「俺も行きたい」で、眠い目をこすって4時半起き。塩山駅からバスで乾徳山登山口下車、9:15行動開始。遠い、遠すぎる。すでに小旅行だ。 30分ばかりの林道歩きで登山口からしばらくは杉の植林地帯。感じは丹沢の大倉に似ている。ただ、こちらのほうが階段がないだけまし。緩くはない登りが続くが急坂はなく程よい斜度なので順調に高度を上げていける。バス停が800mで1200mを過ぎたあたりから明るい広葉樹林帯に変わり黄色い葉が目立ち始める。国師ヶ原(1500m)を超えると紅葉は見頃。赤も所々あるがこの辺では黄色が特に美しい。目指す山頂もすぐそこに見えて(まだ500mくらいは登るのだが)気持ちは高まる。高原ヒュッテ(無料の休憩所)に寄り道してから少し登ると役小角の石像があった。空海に次いで何処にでもいる人第二位である。なお、大きく引き離されて第三位は坂上田村麻呂とヤマトタケルノミコトが追う感じだろうか。見上げれば青地に赤と黄色の万華鏡な世界が続く。15分位で到着する扇平は輝くすすきヶ原で振り返ればやはりアイツ。大きな存在感の富士である。ここから山頂までは急な上り坂。陽光を透かした色づく木々があまりに綺麗で写真ばかり取っていたので、余り疲れはしない。休み(撮影)の合間に登っているようなものだ。最後の200mが乾徳山の核心。岩道に鎖場が続く。落ちたら重体以上が確定の絶壁もあるが、登山道自体はそれほど危険ではない。最後の鳳岩もある程度の腕力があれば、テクニック無しで登れるし、落ちても死ぬほどじゃないかな。垂直に近い20mの一枚岩とか書かれている例もあるけど、実際に見れば斜度は45度くらい。のっぺりした岩で足場はあまりないけど鎖がしっかりしているので腕力だけで登れてしまいますね。秋晴れの山頂からの景色は抜群。1点360度。空は青く、山は赤く、麓は緑で白い雲。富士と甲府盆地を望む南はもちろんとして、奥秩父や奥多摩を遠望できる北西や東も非常に良い。往復11キロでこの景色はコスパがいいですな。今回、写真ばっか取っててものすごくゆっくり歩いたけど15時には下山。山行は5時間半程度。往復の交通時間が7時間とかだから、そういう意味ではコスパは悪い。塩山駅でソバを食べて帰宅。なお、A氏は甲府に泊まって明日は北岳だとか。体力あるなぁ。
@=
(2021-11-03) 鷹ノ巣山。晴。同行は三鷹のA氏。 3年前の秋に登って紅葉が綺麗だった稲村岩尾根へ。事前にネットで地図を確認すれば通行止めになっている。台風で道が崩れたらしい。同じくネットの情報によれば行けるらしいので、とりあえず行ってみてダメならコースを変えることにする。 3度にわたる通行止めの看板を無視して入山。アウトドアは自己責任です。真似しないでくださいね。稲村岩尾根に取り付くまでの沢筋は確かに豪快に崩れている。岩を越え、倒木をくぐりながら進む。幸い先人が残した小さなケルンが要所要所に存在しているので迷うことはない。それなりの人が通っているのだろう。それとなく道のようなものが出来つつあるようだ。先人の道標に感謝しながら、私達も小石を積み上げる。尾根上に登ると5分のピストンで稲村岩にも行けるのだが、滑落事故があったらしく稲村岩への道標は消されていた。まぁ、断崖絶壁の道やからね。私は行く気もしないので、高所耐性抜群のA氏を見送って休憩することにする。さて、稲村岩尾根は奥多摩三大急登の一つ。1100m登りっぱなしで少々しんどい。ただ、たしかに急ではあるのだが、なんと言っても今は紅葉のベストシーズン。煌めくオレンジの森は疲れを忘れさせてくれる。通行止めのおかげで人は誰もいないのでこの美しさは我々の独占である。手近な森も良い、そして、見渡す山々も黄色と赤の絨毯模様、いや、午前の陽を受けて輝くさまは絨毯と言うより宝石と言っていいだろう。二人して感動しながら標高を上げていく。ヒルメシクイのタワ(午後飯喰のタワ)で、折角だからとおにぎりを食べる。ここらへん(1500m)まで来ると紅葉には少し遅い感じで枯れ木が多くなるのだが、青い空が広がるのでこれはこれで良い。程なく鷹ノ巣山山頂へ。石尾根から伸びる複数の枝尾根もオレンジ色で綺麗なものだが、流石に紅葉もお腹いっぱい気味。石尾根は奥多摩駅から雲取山まで続く20kmで、鷹ノ巣山はそのほぼ中央にあたり南方面への展望が開ける。奥多摩では人気の山とあり10人位が昼食を取っていた。下りは石尾根を東へ奥多摩駅まで歩く。こちらも良かったんだけどね。普通に綺麗な紅葉だけど気分はやはり消化試合。 15時前には下山。奥多摩は遠いよ。家に帰り着いたら18時前。
@=
(2021-11-06) 大菩薩嶺から牛ノ寝通り。晴後曇。同行は三鷹のA氏。二週間前のリベンジマッチ。奥多摩がいい感じに色づいているので再チャレンジである。コースは前回と全く同じであるが、たった二週間で山の色合いは全く違っている。大菩薩嶺から富士を望んだ際に眼下に広がる樹海は深緑から黄橙へと変わった。正に山吹色である。この短期間でここまで変わるとは驚きである。さぁ、今度こそ奥多摩の本気を見せてもらおう。期待に胸が踊る。先々週はほとんど登山者もいない道であったが、今日はそれなりの人手、、、というより混雑気味である。みんな事前情報を集めて、時期を狙って来てるんだね。肝心の牛ノ寝尾根は、、、良い、それは間違いないのだが感動できるまでじゃない。ここの所立て続けに見事な紅葉と黄葉を満喫していたため、目が肥えてしまったようだ。また、本日は曇り空であり、牛ノ寝通りも本領を発揮できていなかった事情もあろう。やはり、木々の美しさは光線の具合によるところも大きい。今秋の中では一番赤み成分多めで悪くはないんだけど、それこそ真紅のアーチをくぐり抜けたかったのが希望。少し期待値が高すぎたようだ。写真では綺麗に写っていると思うし、部分部分はいいんだけどねぇ。基本下りで体力がなくても縦走できるコースなのでハイキングとしては特上なのかもしれないが、ガッツリ登山で易易とは行けないところも含めるなら、これよりいいところは沢山あるかなという印象。とはいえ、5キロ近くにわたってずっと紅葉通りなのは見ごたえはあった。さて、ハイカーが多ければ交通機関は当然混む。バスは満員の上に一時間立ちっぱなしで駅に着く頃にはヘトヘト。今回の山行で一番疲れたのは急登でも長距離でもなく、帰りのバスであった。
@=
(2021-11-13) 三ツドッケ-蕎麦粒山-川苔山-本仁田山。晴天。奥多摩で歩いたことのなかった長沢背稜(東京埼玉都県境)へ。長沢背稜はとにかくアクセスが悪い。行ってみたいと思いながらずっと尻込みしていた。核心は酉谷山・長沢山となろうが、日の短いこの季節、下山出来なくなりそうなので、まずは前衛と言える三ツドッケに登ることにする。奥多摩駅からバスで30分480円、東日原バス停へ。おそらく東京で一番の秘境であろう。都県境目指して北上する。しばらくはつまらない杉の植林地帯が続く。 1000mを越えた頃から広葉樹林帯となるが、紅葉には時すでに遅しで冬枯れの明るい尾根筋となる。奥多摩の谷は本当に深い。眼が眩みそうな斜度なので慎重に歩を進める。切れ落ちたヨコスズ尾根東側は見事なブナ林のようだ。二週間前であればさぞかし素晴らしい色づきであったと思われる。春の桜もそうだけど満開の時期が短すぎる。もったいない限りである。本日は秋晴れ、最高の天気で空気も大変澄んでいる。空の青さがこの半月ほどで一番綺麗だ。枯れ木の白い樹皮も青空を背景にすると美しいものである。しかも、アクセスが悪いだけあり登山者がとても少ない。混んでいるのも嫌だがあまりに少ないのも少し不安。二時間弱で一杯水避難小屋へ。最近抜かされることも多くなり体力の衰えを感じるのだが、コースタイムの7割くらいでは歩けているようだ。避難小屋から20分、三ツドッケ山頂からの景色は素晴らしいものであった。南を向けば奥多摩駅から雲取山まで続く石尾根の全貌を見渡すことが出来る。先週登った鷹ノ巣山の向こうには冠雪の富士山も鎮座している。北を向けば上越の山であろうかやはり冠雪の山嶺である。東は関東平野の向こうに筑波山まで見えているようだ。うーむ。関東平野広いな。眼が良ければスカイツリーなんかも見えるんじゃないかな。今度双眼鏡を買おう。さて、山頂でしばし休憩して未だ10時半少し前。ピストンするのも嫌なので奥多摩駅まで尾根伝いに歩くことにする。蕎麦粒山や本仁田山は登ったことがないのでこの機会に制覇する。都県境はブナの森のようだが葉は落ちているので明るい登山道となり気持ちが良い。まぁ、天気さえ良ければいつだって山は最高だ。 1時間半で蕎麦粒山。狭い山頂。特段目立つ特徴はないが、南東方面への視界は広がり、川苔山がすぐ近くに見える。ここからの下りはものすごく急。岩場はなく広い尾根で危ないことはないのだが、滑りそうにはなる。広い尾根は防火帯となっているようで伐採されているため開放感がある。このあたりも紅葉のシーズンであれば素晴らしいように思う。さて、眼の前の川苔山であるが意外と遠い。地図を見てもらえばわかるが、谷が入り組んだ非常に複雑な地形をしている。大きく回り込んで山頂へ。川乗山は人気の山。20人くらいはいたであろうか。結構な人出である。ヨコスズ尾根から長沢背稜と歩いてきた尾根が一望できて感慨深い。長かったなぁ。さて、最後の目標本仁田山である。が、川苔山-本仁田山間の鋸尾根が辛かった。本仁田山はすぐそこに見えており比高も200m程度と一時間かからずに着けるだろうと踏んでいたのだが、なかなかどうして危険な道である。岩場で急。いや、これ慎重に降りなければ命に関わる。下りなのに上り以上に時間がかかる。加えて最近は鳴りを潜めていた膝痛である。恐怖心もありかなり無理をした足運びだったのだろう。息絶え絶えで本仁田山。展望大したことなし。次来ることはないだろう。ここから700mの下りは辛かった。奥多摩三大急登の一つ大休場尾根を痛い膝を抱えての下山である。 50分のコースタイムに一時間かかってしまうが、なんとか林道にたどり着き安心する。いつもならつまらない林道歩きであるが、アスファルトの道のなんと歩きやすいことか。やっぱり文明は偉大だ。奥多摩駅に帰り着けば16時。8時間20kmに渡るロングトレイルであった。
@=
(2021-11-20) 三頭山。晴。三鷹のA氏から一泊二日での八ヶ岳登山のお誘い。私には初冬の横岳をチェーンスパイクで行けるとは思えない(夏でも怖かったよ)のでこれはお断り。じゃ、何処に行こうかと考えて久しぶりの三頭山へ。奥多摩湖の浮橋からヌカザス尾根コース。イヨ山までとヌカザス山手前がとにかく急登。こんなに急やったっけ。しんどい。3年前と比べて体力が落ちてるような気がする。低地の植林地帯を抜けるとブナの広葉樹林だが、葉はすでにほとんど散っているため明るい冬枯れの森となる。葉が落ち遠見が効く分、雲取山から続く石尾根や御前山からからの馬頭刈尾根、ここ三頭山から続く浅間尾根が見渡せたりする。 2時間半と少しで登頂。名前の通り三頭山には三つの頂きがあり、一般的に山頂扱いされているのは開けた西峰なのだが実際には一番低い。中央峰が一番高くて次いで東峰。ただ、この2つは狭いしあまり眺望もない。下山は笹尾根へ。日が短い季節なので数馬峠までにして数馬の湯へ。笹尾根やその枝尾根ももう少し早ければ素晴らしい紅葉が見れたであろう。落ち葉がすごくて道がわからないのが少し危ないくらいのふかふか絨毯であった。
@=
(2021-11-23) 御前山。晴、山中は霧。同行は三鷹のA氏。昨日のLINEにて、(A)「明日、山行きます?」(私)「御前山、7時25分のバス。」(A)「行きます。」てなやり取り。元気やなぁ。LINEの前日、前々日にこの寒い中、八ヶ岳をテン泊で縦走してきたばかりというのに恐れ入る。火曜休日なので翌日の仕事を考慮して軽めのハイキング。奥多摩三山で唯一登っていなかった御前山へ。三山の三頭山と大岳山は何回も登っているのだが、標高・距離ともに中途半端に感じて御前山だけ登っていなかった。奥多摩湖でバス下車。朝の湖は雲も低くて荘厳な雰囲気が漂う。昨日の雨のおかげで空は澄み渡っている。遠く湖の向こうの山の木々までがくっきり見える透明度は素晴らしい。これだから雨上がりは良い。空気の匂いも瑞々しい。濡れた落ち葉が太陽を反射してキラキラと明滅しているのもいとおかし。奥多摩はやはり秋がいいね。全て散った後で残念。登り始めて一時間でサス沢山に到着。ここには展望台があって奥多摩湖を挟んで奥秩父の山々が見渡せる。透徹した秋の空、群青の湖、遥か広がる山嶺。素晴らしいの一言である。絶景にしばらく足に根が生えてしまった。少し長めの大ブナ尾根を登り、惣岳山を越えれば、すぐに御前山。山頂からは石尾根を中心に飛竜山の方まで見えるが、程なく雲が出てきて眺望は失われてしまった。下山は鋸山経由で奥多摩駅まで歩くがずっと霧の中であった。これはこれで幽玄な雰囲気で悪くはないが、風も出てきてチト肌寒い。天然ミストは夏だけで良い。 13時半には奥多摩駅に。列車待ちの時間をビジターセンターで過ごして早めの帰宅。
@=
(2021-11-27) 鍋割山から塔ノ岳。晴。同行は海老名のマイ・ブラザー。丹沢で何処か行こうとのこと。おそらく運動不足が見込まれるブラザーを考慮して鍋割山とする。ブラザーは鍋割山には登っていないはず。二時間の登りなので運動不足でもなんとかなるレベル。塔ノ岳には何回か登っているはずであるが、周回コースで近くまでは行くことになるのでこちらはおまけ。朝イチのバスで渋谷駅から大倉へ。7時過ぎには到着。鍋割山へは長い林道を歩くことになるが、舗装されているわけではないので歩くのがつまらないと言うほどでもない。奥多摩では完全に終了した紅葉であるが、丹沢の麓の方ではまだ残っているようだ。途中三台の車に抜かれる。今日は多くのハイカーが見込めるため頂上の鍋割山荘への補給部隊であろう。大倉尾根と比べて普段は人の少ない鍋割山コースであるが、行楽のシーズンとあり人目が途切れないくらいには賑わっている。さて、ここを登るハイカーのおよそ8割は山荘名物「鍋焼うどん」が目的であろう。山荘開店が10時で私達もほぼ10時に山頂についたのだが、既に50人位が並んでいた。私も3年ぶりに食す。うん、うまい。濃厚な醤油系の出汁が疲れた体に染み渡る。空気は突き刺すような冷たさだが、幸い風はなく陽があたっている分には暖かい。寒冷な分水蒸気は出ておらず、輝く海原の向こうに伊豆大島が見える。名前通りであるが鍋割山からだと本当に大きく見える。ここからはあまり高低差のない尾根歩き。塔ノ岳に向けて東進すれば、北に丹沢山塊、南に相模湾、振り返れば富士という抜群の景色が広がる。相変わらず塔ノ岳は大人気。まぁ、お手軽で絶景ですからね。でも、何度も来てるので今更言うことは何もない。長い長い大倉への消化試合をこなして下山すれば15時半。ブラザーが奢ってくれると言うので海老名で途中下車して食事。たいへん旨い店であった。
@=
(2021-12-04) 権現山から扇山。快晴。同行は練馬のR氏。 R氏から週末山に行けるとの連絡。何処に行こうかと考えて北都留三山(権現山・扇山・百蔵山)にする。三鷹のA氏にも連絡しようかと思った所、金土が連休になったらしく小屋泊で長沢背稜に行くらしい。まだ山の記録を取ってなかった5年くらい前に権現山には登った記憶がある。当時は東側の用竹の方から登った(もしくは下った)記憶があるので、今回は西の杉平からの入山とする。登山口で500m、最高峰の権現山で1300m、前衛の三ッ森北峰が1250mなので、比較的楽そうかなと思っていたのだが、いきなりの急坂でなかなかにハード。しかも道標にある鋸尾根という名前にも嫌な予感がする。大体、鋸と名前がつくところはヤセ尾根、岩の上り下りと相場が決まっている。ギザギザの刃のごとく急峻な尾根筋が続くことが多い。最初の三ッ森北峰は好展望、巨大な富士が間近に拝める。冬枯れの明るい広葉樹林で歩いていて楽しい。所々、急斜面のトラバースもあるなと言うくらいで危険はなかったが、ここから麻生山のほんの500mが結構大変であった。特に前半の300mが正に鋸で、登って降りての繰り返し。たかが、300mの距離にコースタイムが30分などとなっているので、何かの間違いかと思うくらいだったが、いや、その位かかりますわ。危ないのでしっかりと三点支持で進む。権現山でお昼。麻生山以降はよく踏まれたハイキングコースなので危険はない。危険はないのだが、、、A氏もそうだがR氏も20代で体力があるので歩くのが早い早い。ついて行くのが大変。扇山へは権現山から500m下って300mの登り返しなのだが、登りでおいていかれる。扇山に14時過ぎ着、冬は日が短いし、そもそも相当足に来てるので、百蔵山は残念ながらパス。なんか体力落ちたなぁ。もう少し鍛えないといけないかもしれない。扇山から鳥沢駅にエスケープ。駅前で食事して帰宅。
@=
(2021-12-11) 陣馬山から北高尾。寒い、起きれない、ということで近場の高尾へ。冬は葉が落ちて森が明るいし、比較的暖かい低山がお手軽。高尾であればまだ紅葉も残っているだろうとの予測もできる。さて、藤野駅からバス。超満員。まぁ、みんな考えることは同じなんだなぁ。 8時過ぎと遅めだが始発のバスである。歩き始めれば先頭に立てるので静かな森の散歩と言った感じ。奥高尾縦走は何度もしているし、ハッキリ言って大した高低差もない。山登りと言うより散策だ。 1時間ちょっとで山頂。雲ひとつないいい天気。うーん。もう少し遠出すべきだったかなぁ。これだけの快晴だと近場であることが少しもったいなくも感じる。陣馬ソバを食べて縦走路へ入る。エラい人混み。あ~、この喧騒は耐えられない。コースを変えてこのまま下山してしまおうかとも考える。しかし、流石に疲れていない。堂所山から北高尾縦走路に向かう。高尾切っての不人気コース。植林で展望のない尾根が続き、しかもアップダウンが激しい。楽しい要素がほぼないコースである。以前は曇天の修行用としており、天気のいい日に登る価値は無しなのだが、こうも人手が多いとあればやむを得ない。で、こちらはと言うと、恐ろしいくらいの静けさである。誰も歩いていないし暗くて深い森は怖いくらいであった。関場峠を超えてやっと何人かとすれ違うようになったが、奥高尾縦走路であれば数百人と行き交うだろうから高尾と比べて人気指数は1%以下であろう。帰りはついでなので八王子城山経由にする。山頂近くには八王子神社がある。祭神は誰なんだろうと思って調べてみるとスサノオの8人の王子(王女もいるけど)を祀っているらしい。ナルホドそれで八王子っていうのか。ひとつ賢くなりました。
@=
(2021-12-18) 景信山。快晴。同行は上野のI氏。寒いので低山の近場。ノンビリハイキングということで運動不足のI氏を誘う。景信山程度ならと思ったけれど臨時の増便が出てバスは三台構成。まぁ、それでも高尾に比べたら断然マシだけど早朝にしては結構な人混みである。小仏バス停からなら1時間かからずに山頂。昨夜の雨と強風で空気は最高に澄んでいる。山の端の空との境界も、陽を受けての山肌の陰影もくっきりとしていてシャープだ。茶屋にて私は鍋焼きうどん、I氏は天ぷらを注文。うまー。思う存分ノンビリして小仏峠から甲州街道で小原宿へ。郷土資料館があったので立ち寄る。訪れる人も少なく最高に暇だったのだろう。受付の人が丁寧に色々と説明してくれた。多謝。駅まで車道歩きはつまらないので、弁天橋の方から帰れば良いと教えてくれたので助言に従う。なんだかんだで帰り付けば12キロ。まぁ、楽ではあったけど距離はそれなりにあったようだ。遅めの昼食を相模湖駅前で食べて帰宅。、、、はせずに川崎での飲み会へ。
@=
(2022-01-08) 塔ノ岳。曇時々晴。同行は三鷹のA氏。 2022年、始まりの山はやはり丹沢、塔ノ岳。雪に期待が膨らむ。一昨日は東京でも5cmの積雪。さぞかしいい感じの雪山になっているはずだ。 A氏はこの所2500mを超える本格的な冬山を志向しているようだが、流石に私には無理。 12月に入ってからは寒くて布団から出れない日々のため近場の1000m前後の山が多かったのだが、少し気合を入れて塔ノ岳1500mで折り合う。平地より10度は寒いから、本音はちょっとやだなぁって思っていた。さて、普段ならヤビツ峠までのバスも降雪があれば麓の蓑毛までしか走らないため標高300mからスタート。うん?思っていたより雪が少ない。東京より少ない。南の方では余り降らなかったのかしらん。雪もなく登りやすい登山道。A氏とはなんだかんだで二ヶ月ぶりくらいなので話も弾む。一時間弱でヤビツ峠に到着。標高は700mでこの辺まで来るとやっと雪が多くなってくる。シャリシャリと雪を踏む感覚が気持ちいい。林間は風もないため思っていたほどは寒くない。ただし、表尾根には何箇所か風の通り道と言える場所があってそこは、、、、寒い。天気はほどほど。朝、電車からは綺麗な富士が見えていたが、基本曇天で時折陽が差すという感じであった。表尾根全体としては雪道が楽しめるが、南斜面は融けているのでもう少し積もっていたほうがより良かったかな。二月に向けてさらなる降雪を期待する。塔ノ岳到着は12時半、そして強風。まぁ、山頂は十中八九風なので致し方ない。気温はゼロ度を少し下回るくらい。風に煽られて耳が千切れそうになる。慌てて耳あてを装着。あと、手袋も。折角だからユーシン渓谷を広く見渡そうということで、丹沢山との中間地点である日高(ひっだか)まで足を伸ばす。ただし、こちらの尾根も強風。渓谷から吹き上げる冷たい風が頬を殴りつけてくる。痛いよ。たまらず退散。下山の大倉尾根はいつもの消化試合。雪もほぼない。恒例の花立小屋で温かい麺を食べる。この瞬間はいつも幸福だ。 16時に下山。渋沢駅前で新年会?をやってから帰宅。
@=
(2022-01-15) 鍋割山から塔ノ岳。晴。同行は三鷹のA氏。寒いので気楽に行こうとのことでいつもの丹沢へ。二週連続。 4時半起床、新松田駅で駅ソバを食べてからバスで寄へ。ちょっと趣向を変えて今回は寄から登ることにする。登りやすい整備された道であるが人通りは少なく快適。所々展望所や伐採された小さなピークもありなかなかに景色は良い。塔や鍋割へ向かうのに大倉が飽きたら寄からもいいと思う。静かな山歩きが楽しめる。鍋割山に着けばそれなりの人手で登山者の8割は名物鍋焼きうどんを食べている。オフシーズンの冬でも休日は200食くらいは出ているんじゃないかな。一杯1500円なので売上は30万円。俗な計算が頭をよぎる。そんな中、我々はスーパーで買ったアルミカップの鍋焼きうどんを食べる。おにぎりやカップ麺ではなく、敢えて鍋焼きうどんを作って食べるのはチャレンジングな試みである。もちろん、名物は色々と具が入っていて美味しいんだけどね。水を加えてコンロで温めるだけのスーパー売アルミ鍋焼きうどんも負けてない。卵や肉なんかを持っていって加えたら名物にも勝てるかもしれない。さて、下りはやっぱり大倉尾根。先週も歩いて代わり映えしないので本当は小丸尾根での下山を考えていたのだが、少し進むと融けた雪が土と混じり泥濘となっていたため引き返す。難路ならぬ悪路とあれば辛いだけなので仕方がない。大倉尾根は面白くはないが歩きやすくはある。そうなれば、ついでに塔ノ岳も登ってしまう。本日は道中とにかくのんびりしたので帰りのバス停に着けば16時。
@=
(2022-01-22) 陣馬山。快晴。 8時になってノコノコ出発。早起きできないし、寒くて高いところに行く気がしない。ハイキング感覚の陣馬山だけど、午前中の北側斜面はそれでも十分に寒い。冷気が服の上から突き刺さるという感じで、どこが寒いかと言うと骨が寒いと言う感覚である。なお、風が吹いてさらに寒いと「痛い」と感じられる。山手線車両のテレビ広告の雑談コーナーで、本日もまたひとつ教養をいただいたのだが、「冷たい(つめたい)」の語源は「爪痛い(つめいたい)」であるらしい。強烈な寒さ冷たさは痛さに通じるようだ。さて、さっくりと登った陣馬山の茶屋でうどんを食べてどうしようかと思案する。雲一つない晴天だが、渋滞が予想される縦走路には向かう気がしない。とっとと一ノ尾根で下山することにする。何度も通った道であるが下山に利用するのは初めてだ。 3時間10キロのお気軽ハイキング。帰りのバスを1時間待つのが嫌で最後の3キロは車道歩きとなったが里谷の風景もいいものである。
@=
(2022-01-29) 倉岳山、高畑山。曇。高いところは寒い。でも、高尾は混んでて嫌という場合に手頃なのが上野原から大月にかけての山梨東部の山。特に秋山山稜は駅から直接登れるのでお手軽である。梁川駅から月屋根沢で立野峠へ。梁川駅で降りたのは3人。他の人がどこに向かったのかはわからないが、月屋根沢ではずっと一人であった。静かでよろしい。昨年クマが出たとの注意箇所で、いきなりガサゴソ音がして飛び出してきたのは、、、ネコ。驚かすのではない!クマなんて滅多に出会うものではないと思ってはいるけど、注意情報のすぐ近くだと流石にびっくりするわい。寒い中、汗をかくのが嫌なのでいつも以上にゆっくりと歩く。沢沿いはその昔明治天皇が下賜したと言う恩賜林らしいが結構荒れていた。立野峠からは尾根道で風はないものの曇っており空気は冷たい。1000m弱とは言え平地より5度は下がるだろう。道自体は歩きやすいハイキングコースで数組のハイカーと行き違う。直前のみ急坂だが、ほどなく倉岳山山頂。倉岳山は高畑山と並んで秀麗富嶽十二景の第九番である。選定が大月市なので正直大したことはないのだが、それでもこんな素晴らしい景色も拝めるようだ。ちなみに本日は曇で富士は見えず。まぁ、以前登ったときに見てるからいいだろう。一旦、穴路峠まで下って、続いて高畑山。こちらも直下だけは急坂。秀麗らしい富士はやっぱり雲の中。さて、11時。時間も早いし足は十分に残っているので、第十番の九鬼山にも行こうかと思ったのだが寒いのでヤメ。曇りだしどのみち秀麗な富士は見れまい。穴路峠まで戻って小篠沢から下山することにする。高畑山から直接小篠沢中部に出る道もあるのだがこちらは以前通ったことがあるので少しピストンで戻ることにした。小篠沢最上部は苔に覆われた岩が広がる緑な世界。沢の透明度は非常に高く、キラキラと反射明滅する水面を通して底の砂粒までがくっきりと見える。うん、穴路峠まで戻る選択は正解であった。ここは夏に来ても気持ち良さそうである。所詮低山なので下山はあっという間。13時には烏沢駅に到着。電車の連絡が悪いので駅近くの食堂で昼食。今日は寒くて余り汗をかくこともなかったので飲み物は全く消費せず。食べたのもおにぎり一つ。お腹は空いていたのでガッツリとんかつ定食である。最後に梁川駅も烏沢駅も無人駅であった。東京から一歩出たらド田舎ですな。
@=
(2022-02-05) 高尾縦走。晴後曇。同行は練馬のR氏。体力ある若人R氏にお手軽高尾山系だと悪い気もするが、寒いので冬の定番高尾縦走路へ。藤野駅8:10集合で陣馬山登山口から縦走開始。いつもと同じく1時間ちょいで山頂。午前は快晴で360度の展望。北から半時計回りに大岳山、大菩薩嶺、権現山、扇山、丹沢とR氏と一緒に登った山が全て見渡せる。清水茶屋にてR氏はけんちん汁、私は陣馬うどんを食べる。ここのけんちん汁は具たくさんでおすすめである。縦走路は快調に飛ばす。あんまりゆっくり歩いているとむしろ寒くて辛いくらいである。人気のハイキングコースなので混んでいたら相模湖駅にエスケープしようと考えていたが、流石に2月の寒さのせいか思ったよりは空いていたので無事高尾山までの縦走を完遂。いつもなら高尾山は巻いて稲荷山登山道で下山だが、 R氏はしばらく高尾山には来ていないとのことだったので舗装された1号路で薬王院などを見学しながら下山。結構、食事したりおやつしたりののんびり行程ではあったが、14時には高尾山口駅到着。小腹は空いていたので新宿でラーメンを食べてから帰宅。
@=
(2022-02-11) 鍋割山から塔ノ岳。曇、うえ、晴。都心部にて結構な降雪があったものの、気温は下がりきらなかったのかすぐに融けてしまったが、山はさぞ積もっているはずだ。てなわけで、5時半起床の7時出発。だいぶと遅めだが東丹沢の表側ならこのくらいの時間からでも十分間に合う。渋沢駅から9時前のバスで大倉へ。ガラ空き。人気の丹沢でもこのくらいの時間になれば座れて快適なものだ。大倉バス停は300m。雪はない。平野部では積もらなかったようだ。 500mを越えたあたりから雪景色となるが、天気は悪く曇り空である。雪は降っていないのだが、風を受けた木々から常に雪が落ちてくるので帽子やザックに積もる。 800mで完全に雲の中となり、霧中、地も空も白となった。青空に映える雪景色を見れないのは残念だけど、雪を踏みしめて歩くのは楽しいものなので、今日は雪遊びだなと考えていた。が、1000mを超えると空が明るくなってくる。これは、、、もしや、雲の上に出てしまうのか。空が暗いので厚い雲かと思っていたけど案外薄かったようだ。そうなると、逆に雲海が見れることになるので期待が膨らむ。歩きつつ、霧は晴れつつ、空は水色に、そして青くなる。枯れ木の向こうにヤツが見え始める。標高を上げるにつれ雲海の潮は引き、近隣の小さな頂は浅瀬に浮かぶ小島のようである。凄い。完璧だ。雪中雲上、遠見富士。低気圧一過の大雪とあり空気は澄み渡っている。 2月の太陽は思いの外燦々として塵のない新雪は眩しいばかりである。サングラスを持ってきてよかった。なけりゃ眼を開けてられないわ。今日のベストは鍋割山山頂手前のちょっとした見晴らし台。ここが雲海も近く一番迫力があったかな。塔ノ岳への道も悪くはなかったけど少しづつ雲が上がってきており南側の展望はなし。北側は主稜がよく見えた。帰りのバカ尾根は泥混じりの雪となりてわろし。沢山の人が往来するから仕方がないんだけど、いつもどおりの消化試合である。
@=
(2022-02-26) 日ノ出山。晴。カゼで二週間引き篭もっていた。病み上がりで万全ではないが、これ以上お外に出ないと別の病気になりそうである。昨日、三鷹のA氏から連絡があって、二俣尾からさくっと日ノ出山に登ろうとのこと。 1000mもない低山なのだが、まだ、咳が止まらないので登りはちとキツイ。山頂での合流を約束して御嶽からケーブルカーで上がってしまう。ここからなら二時間程度の下りハイキングコース。超軟弱だが体調が戻っていないので仕方がない。天気良し、ただし、登山者は多くない。間もなく3月とありすでに雪は少ないが、日陰では何度も溶けて凍った雪がアイスバーンになっているので念の為チェーンスパイクを履く。 1時間かからずに日ノ出山。A氏と合流。氏は道中カモシカを見たそうである。こんな低い山で出会うこともあるのだなと驚き。山頂からは東側の展望がよく関東平野を見渡すことが出来る。今日は14度だとか。風もなく非常に温かい。ただ、そうなると晴天ではあるが春霞と言うかモヤっとしているのは残念。簡単な食事を取った後は下るだけの早くも消化試合だが、まぁ、今日は仕方がない。午前中にはつるつる温泉到着。風呂の後、食堂で昼食を取って帰宅。なお、今回のカゼであるが、最初の2、3日は微熱と関節痛。次の2、3日が喉の痛み。最後の2、3日が咳であった。なんか種類の違うウィルスに複数連続してやられたのであろうか?特に喉の痛みがひどくて水を飲んでも激痛。ツバさえ飲み込めないという有様で、当然飯も食えずでちょっと痩せてしまったわい。
@=
(2022-03-12) ジダンゴ山、檜岳、雨山、鍋割山。快晴。 4時半起床。寒くない。天気予報で確認すると最高気温19度、最低気温9度とか4月下旬並みである。今日は西丹沢の表側で行ってなかった所を攻めてみようと思い、寄のバス停から大きく円を描くように一旦西進してから、北上、そこから東進して鍋割山を目指す。鍋割山西の尾根は危険標識が多く今まで敬遠していたのだが、まぁ、丹沢の危険なんて大したことはないだろう。最初の西進部分は以前に歩いたことがある。ジダンゴ山山頂付近以外は杉の植林でほとんど展望もない。山頂付近のみ低木林で相模湾を見渡せるが、水蒸気が多く遠望が効かない。暖かくなるのは大歓迎なんだけど、空はやっぱり冬が綺麗だ。水蒸気に花粉、まだ少し早いが黄砂なんかも混じっているかも知れない。春霞という言葉があるくらいで空気は白くモヤがかかっている。西丹沢と言えば富士のすぐ近くなのだが、その富士さえ見えないので相当なものである。北上するあたりで鍋割山から南西に続く稜線に入る。未踏破のエリア。しばらく雨がなかったせいか土は乾いておりホコリっぽい。1000mを超えると残雪があり、登山道は逆にぬかるみ状態。時期を間違えたかなぁ。快晴にもかかわらず景色は見えないしあんまり楽しくない。しかもアップダウンが激しい。雨山以降はヤセ尾根の連続で危ないと言うほどではないが、緊張を強いられて余計に体力を使う。鍋割山へと続く最後の300mの上りは大腿四頭筋が攣りそうになった。長らく本格的に登っていなかったので筋力も落ちているようだ。本日の感想としては(時期が良くなかったのかもしれないが)、労多く大したことのない景色であった。数年を経て思い出したときに来ることはあるかもしれないが、定番には出来ないコースである。
@=
九尾の狐、逃げ出す。日本史上最凶の妖怪王大復活。 900年の時を経て殺生石として封じられた九尾の狐が岩を割って世に解き放たれた。、、、てなわけもなく、実見して、ただの割れた岩でした。まぁ、元々ただの岩だったので当たり前だけど、せっかくの伝承があるのだから、割れるならもう少し曰くが欲しかったなぁ。時をおかずして政界に玉藻前現るとか、、、はないか。
@=
(2022-03-19) 南高尾。曇時々晴。 4時半起床。昨晩は雨、そして今日も午後は雨予報。勝負は午前一杯。先週の疲れも残っているのでここは手軽な高尾だろう。 6時前の電車で出発。高尾山口駅に着けば霧が低い。雲の高さが20mとかだろうか。高尾の低い尾根筋すら見えない。まぁ、南鷹尾は木立の道で展望があるわけでもないので、これはこれで雰囲気があって良い。もとより本道に比べ北と南はハイカー少なめなのだが、天気が不安定とあり山中はほぼ独り歩き。快適である。陽が昇るにつれ霧は晴れ、尾根に棚引く雲がいい感じである。昨日の雨のおかげで空気もかなり澄んでいるようだ。僅かな時間であるが晴れ間も覗き、木々の切れ間から富士もくっきりと見えていた。南高尾の最高所は大洞山。なかなか着かないなと思っていたら通り過ぎていた。おいおい、嘘でしょ。こじんまりした山頂とは言え、ベンチとテーブルがあり大きな看板もある。さすがに気付かないとはウッカリにも程があるが、思考に雑念がなく集中していたと思うことにしよう。山歩きは思索の時間でもある。常に様々なことを考えながら歩いている。なお、内容は大抵がしょうもないことなので覚えていない。昨晩見た夢の自己解釈であったり、薬を飲むことはあっても食べることがないのはなぜなのかとか、そんなようなことだ。大垂水峠に下って城山に登り返し、景信山まで来たところで12時。特筆することもないですな。とっとと下山して13時には高尾駅へ。
@=
(2022-03-21) 4時半起床。18きっぷで大津港へ。水戸駅で途中下車して朝食。時間調整のため千波湖を散策。ついでに駅近辺の水戸黄門神社を見学。絵馬が何故か美少女化した黄門様一行。大津漁港で昼飯。生しらすイクラ丼とアン肝+アンコウ友酢。うめぇ〜。満腹で苦しい中、腹ごなしに海岸沿いに適当に歩く。どうやら大津港は岡倉天心と縁があるようで立派な美術館もあるようだ。何もない岬の林間にやけに立派な歩道付きの道路もある。市財政が潤っているのだろうか。なかなか良き漁労町であった。また、来てもいいかなとも思えるがいかんせん遠いからなぁ。
@=
(2022-03-27) 丹沢表尾根。霧中小雨。起床。空が明るい。では、行くか。定番の丹沢。定番の表尾根である。この時期、奥多摩は花粉が酷いことになっているので、避けるがよろし。西丹沢まで行けばより花粉は少ないのだが遠すぎるので敬遠。東京は悪くない天気かなと思っていたのだが、秦野駅に着く頃には町中でもちょっとした霧。雲が相当に低い。バスに揺られてヤビツ峠に着く頃には完全に雲の中。濡れると言うほどではないが時折小雨もちらつく。ただ、雨よりも木々の枝から滴る大粒の水玉の方が厄介ですな。それと昨夜の雨で道がぬかるむ。靴はドロドロだし、鎖場も滑りやすい。まぁ、お天気は仕方がないね。体力維持が目的の半分だし、歩きながらの思考は捗るというものだ。何も見えない白い世界を進む。到着した塔ノ岳では視界10mというところか。さっさと下山。本日は最初から最後までなんにも見えんかった。ハイカーが少ないのだけは良かった。
@=
(2022-04-02) 大山。快晴。 15時から横浜で用事。さくっと登って横浜に出れるということで大山へ。大山は簡単すぎてつまんないんだけど、久しぶりだしということで選択。ロープウェイは使わない。最初の男坂はしんどいけど、阿夫利神社に着いてしまえば後は楽なもの。昨日の雨は山では雪だった模様。1000m以上は雪とドロでぬかるみ。ハイカーの多い道は踏み返されてこうなるので困る。山頂に着けば整備中だそうで新しいベンチやテーブルの工事をしていた。大山からだと江ノ島が近い。近いんだけど霞んではっきりとは見えない。うーん。いい季節で遠望も利くのが最高だけど、そんなの秋の台風一過後くらいしかない。人気の大山周遊コースは3時間程度で終わったので蓑毛まで歩くことにする。結果的に表参道で登って裏参道で下ることになった。12時半下山。横浜に出るには余裕を見た時間。
@=
(2022-04-17) 陣馬山。曇。同行は上野のA氏。日曜なので軽めに、、、さて、どこに行こうかなと考えていたのだが、 A氏が高尾山系なら行くとのことだったので、おなじみの陣馬山へ。天気は午後から崩れるらしいので8:08の始発バスで行って早めに下山する予定。一ノ尾尾根は樹林帯を抜ける幅広の歩きやすい道。少し肌寒いくらいで登りでも汗をかかない完璧な気候。ただし、モヤがあるのは春の気の毒。約一時間で山頂着、茶屋でソバ。曇とは言え日も高くなると暖かく、尻に根が生える。一時間近く休憩してようやく出発。縦走路を明王峠まで歩いて相模湖駅に向けて下山。何度も歩いた道なので特筆することはなし。 A氏とぺちゃくちゃ喋りながら気がつけば駅についていたという感じ。13時前の下山なので本日は休日二回戦である。
@=
(2022-04-23) 丹沢主脈縦走。晴曇半々。最近、寒いだの花粉が嫌だので軟弱な山行が続いていたので、一発気合を入れ直すために丹沢主脈縦走。 23キロちょい。二日間4万円のツアーが組まれたりするみたいだけど、ちょっと頑張れば日帰りで行けます。主脈縦走は3度目だが、前回は2018年と随分と前になる。以来、体力は落ちて体重は増えているので大丈夫かと少し不安。 3時起床。食事と身の回りの用意をして4:38の始発で出発。電車混んでるぜぇ。なんで?橋本駅6:20のバス。混んでるぜぇ。流石は行楽時期なだけはある。三ケ木でバスの乗り換え。超混みすし詰め。普段主脈縦走する人なんてほとんどいませんよ。登山道一人ぼっちで「なにかあったら」と怖くなるくらいなのに、今日は心強いが過ぎるくらいだ。気温は朝から相当に高い。Tシャツでも何ら問題がない。なお、すでにヒルが出ているようである。私はタイツに長靴下で下半身に露出部がないため気が付かなかったが、半ズボンで登っている人によると結構やられたらしい。このコースでしんどいのは焼山までと蛭ヶ岳の最後の登り。それ以外は比較的平坦で蛭ヶ岳へのルートとしては一番易しいと思う。それでも距離(11km)と比高(1400m)はそれなりに手強いのである程度の脚力は必要になる。、、、が、このコースに挑む人は基本みんな健脚のようだ。何人もに抜かされてちょっと悲しい。やっぱ、体力落ちてるなぁ。姫次から蛭ヶ岳は荒れた原生林と言った風情で私好みのエリア。ただ、原生林で言うなら大峰のほうが良い。まっ、所詮丹沢だしね。昼前に蛭ヶ岳着。珍しいくらいの人出。嬉しいことに山頂では晴れていて、近くて巨大な富士も霞んでいながらも見えた。さて、丹沢奥地の稜線は素晴らしいのだが、残念ながら厚い雲に覆われ始める。塔ノ岳に着く頃には完全に霧中となった。まっ、蛭ヶ岳に登ってしまえば後は消化試合なんで別によろしい。丹沢山に着く頃には「あー帰るの面倒だな」くらいの気持ちしかない。出発から8時間かけて大倉着。季節が良いからであろうか、主脈縦走は予想よりは楽であった。
@=
(2022-05-03/2022-05-06) 5泊4日の九州旅行。船旅でのんびり。ただし、現地は歩いて自転車でとハードな旅路。福岡は町中を歩いていても寺社仏閣が多く歴史を感じる。食べ物も美味しいし、なかなかに住んでみたいと思える都市。太宰府天満宮を始めたくさんの神社に寄ってみたので気になる絵馬を集めてみた。
@=
(2022-05-08) 陣馬山。晴時々曇。 GW、寝不足、疲れてる。本当は動きたくないのだが、食べ過ぎ飲み過ぎの毎日だったので軽めのハイキング。 8時半の高尾バス停は超満員。とりあえず最初に来たバスに乗る。引いたのは陣馬高原下であった。臨時バスも出ていて座れるのはありがたい。新緑の登山道、茶色かった山々も今ではすっかり若緑に覆われている。下山は明王峠から藤野駅の方に抜ける。この道は一度しか通ったことがないが以前は何百何千の蝶が舞い踊る不思議な道であった。残念ながら季節が違うので今日は蝶の乱舞はなし。 12時過ぎに駅着。何度も来てる高尾山系なので特に言うことなし写真もなし。
@=
(2022-05-15) 高尾、大洞山、城山。曇。昨日は雨。今日も空模様は怪しいのでエスケープしやすい高尾へ。はっきりしない天気だとはいえ、春の行楽地は大賑わい。高尾山には近づかない。南高尾から城山に回り込んで日陰沢に降りる。アップダウンもあまりない15キロのハイキングコース。明日は平日だし、体力維持としてはこんなものでいいだろう。リモートワークで体力を全く使わないので、週末くらいは運動しないとカロリーの収支が合わない。何度も来てるし写真を取ることもなく歩いていたのだが、最後の城山を超えて日陰沢に降りる道を少し下ったところでカモシカに出会う。ええっ!ここ高尾だよ。猿は時々見かけるがシカすら出ないのにカモシカを見るとは珍しい。慌ててカメラを取りだすが木陰に隠れてしまった。残念。日陰沢からは林道を歩こうかと思っていたのだが、ちょうどバスの時間だったので乗車。今日の歩きは4時間まで。
@=
(2022-05-28) 笹尾根。晴。同行は三鷹のA氏。先週、藤野駅で集合したものの雨。駅から出もせずに引き返したので今日はリベンジ。薫風香る五月の空はやや雲が多めではあるが爽やかな淡い青。昨日は雨であったので空気もキレイだ。終点の和田までバスで行き、北上、最短経路で笹尾根に取り付く。笹尾根は概ね1000m前後の20kmに及ぶ長い尾根。高尾縦走路と比べて100分の1も人はいないが、道幅は広く十分すぎるほどに整備されている。静かに低山を歩きたい時には断然おすすめの道である。笹尾根と言う名ほど笹は多くなく、多くは広葉樹の森で新緑の葉に陽光が透けて木々が本当に美しい。それなりにアップダウンはあるもののなだらかなエリアも多く体力を回復しながら歩けるのもいいところ。途中、ギンリョウソウの群生地を通る。真っ白なモヤシ状の植物で先端に一輪の花を持つ。とにかく奇っ怪不思議な植物である。葉はなく葉緑素も無さそうで光合成をしているとは思えない。さりとて花を咲かせることから明らかに被子植物で菌類ではない。A氏がネットで調べてくれる。腐生植物というキノコに寄生するツツジの仲間らしい。普通はキノコが植物に寄生するのに逆転した関係もあるんだと生物界の多様性に驚く。本日はとにかく風が気持ちの良い一日であった。14時半に数馬に下山して温泉に入ってから帰宅。
@=
(2022-06-04) 石棚山から檜洞丸。曇。同行は三鷹のA氏。久しぶりの西丹沢。そして西丹沢の盟主檜洞丸。石棚山経由は初めての道である。 3時半起床、5時前出発。小田急で1時間半。バスが1時間10分。8時半登山開始。とにかく遠い西丹沢であるが人手の入ってないブナの自然林はとにかく美しく充実感は高い。箒沢公園橋バス停から石棚山西尾根コースに入る。バスは臨時便が出るほどの盛況であったが、このコースを選んだのは7人8人と言ったところ。静かでよろしい。しばらくは沢沿いの緩やかな道だが、尾根に入るあたりから急になる。いや、半端なく急。ものごっつしんどい。さすが檜洞丸、どこから登っても急登だ。バス停から5キロとか楽勝じゃんと思うくらいの距離なのだが、檜洞丸は急斜面が多く神経を使う場面もあったりして行程以上のしんどさを感じる。名前の通り石が棚状に積層した登山道は楽しくもあるのだが、危険を感じる切れ落ちた谷も多い。石棚山を越えたあたりから道は緩やかになり一息つける状況になる。そして、この道がまたグリーンワールドで大変素晴らしい。土に苔、岩に苔、木々に苔、道を示す杭にも張ったロープにも苔である。昨日の雨で森は瑞々しさにあふれている。葉を透かす光が映すのは魔法使いオズの住むエメラルドの都。やはり広葉樹林は良い。檜洞丸はもはやおまけ。山頂は霧に包まれて何も見えなかったけど、道中が良かったので気にならない。気分はすでに消化試合。とっとと下山して西丹沢ビジターセンターに14時。
@=
(2022-06-10) 高尾半縦走。曇時々雨。同行は上野のI氏。金曜休暇を取っての三連休。にもかかわらずスッキリとしない空模様。梅雨入りして悲しい限り。なんとか天気は持ちそうであるが、雨に備えて近場が良いかと思っていたところ、I氏が高尾に行くとのことであったので同行。「ヤマノススメ」なるアニメ作品のスタンプラリーをやっているそうなので私も参加することにする。「女の子だけの"ゆるふわ"、だけど本格的な登山アニメ」だと。こんなものがあったのか。う〜む、知らんかったわい。よくわからん萌系アニメのようだが、登山者の裾野が広がるのはいいことだね。ギアなんかがたくさん売れると値段も下がるわけだし。さて、全10個のスタンプを押していく。京王高尾山口駅前、ケーブルカー清滝駅、びわ滝、ケーブルカー高尾山駅、薬王院、高尾ビジターセンターとスタンプ集めを順調に消化。 1時間もかからずに半数以上をゲット。最低5個集めれば抽選に応募できるのでとりあえずノルマは達成。ここからは城山、景信山、陣馬山とスタンプ集めはちょっと遠くなる。今回は景信山まで。今日は平日なので高尾山以外の茶屋は閉まっている。そうなるとそもそもスタンプがなかったりして押せない。下山途中に雨に振られたものの5時間10キロのノンビリハイク。高尾駅にて応募BOXにスタンプ帳を提出。景品はビアマウント招待券とヤマノススメポーチ。当たれば良いなぁ。
@=
(2022-06-18) 武川岳から武甲山。曇。行ったことのない山に行こうと思い、武甲山をターゲットにする。 200名山の一つであり、関東のハイキングガイドでは必ず載っているメジャーな山であるが、林道歩きが長いことから敬遠していた。武甲山は山全体が神社であり、一般的には表参道コースから裏参道コースに抜けるのがメジャーなようだが、どちらの参道も林道が長いのである。ターゲットは決めたものの出来れば2つも林道は歩きたくない。地図を眺める。奥武蔵全山縦走コースなんてものがあるらしい。よし、武甲山を縦走コースとつなげてみよう。今回はソロだし夏に向けて自分のペースで修行したいとも思っていたところだ。芦ヶ久保駅から武川岳に登り、ここから縦走コースで武甲山を目指すことにする。天気は雲、夕方から雨らしいので無理のないペースで飛ばすことにする。駅で降りたのは30名くらいいたが、今回武川岳への進路を取ったのは5名ほどのようだ。駅からすぐ登山できるのが奥武蔵の良いところ。しばらく沢沿いの道で苔むす岩がいい感じだがかなりの急坂。最初の二子山まで2.5キロの距離で600mの上りだからそりゃ急だ。二子山雌岳への最後の100mは本当に急。今日は約20キロの長丁場なのだがのっけから体力を奪われる。一旦下って二子山雄岳。息は絶え絶え。すぐ近くに武甲山が見えているのだが、大きく回り込む必要があるのでそれなりに遠い道のり。二子山さえ超えれば武川岳まで急登はないので、少し落ち着けるものの、奥武蔵は平坦な場所が殆どなく安易には楽させてくれない道である。武川岳までの2時間は誰一人会わなかった。展望があるわけではなく樹林帯の道なので不人気なのであろう。静かでよろしい。今日は天気も悪いので展望がないのもそれほど恨めしいわけでもない。 6月ともなれば暑くて滝のような汗だが、瑞々しい森林は苔にも覆われておりやはり綺麗である。焼山、蔦岩山を超えて武川岳で昼食。と言ってもおにぎりを一つのみ。夏になると出るのが虫。なんかハエが多くて落ちつなないので早々に縦走再開。ここからはメジャーなコースなのでハイカーが多くなる。多いと言っても10分に一人すれ違う程度でちょうどよい。大持山、子持山周辺はちょっとスリリングなので誰にも会わないとむしろ不安になる。しかしこのコースしんどいわぁ。武川岳から200m下って、大持山への400mの登り返し、子持山までは両側急谷の神経を使う尾根を上り下り。子持山からはまた200m下って、武甲山へ200mの登り返し。丹沢縦走に比べれば楽だけど、それでも十分しんどい。何より梅雨の季節は湿度が高くて汗だく。到着した武甲山は人気の山とあって100人くらいのハイカーがいた。本当は秩父盆地が見渡せる絶景のはずなんだけど、雲に覆われて何も見えず。さっさと退散。秩父鉄道を二駅だけ乗って西武に乗り換え、、、はすぐにはせずに秩父駅で温泉。流石に汗を流さないと落ち着けません。
@=
(2022-06-19) 高尾半縦走。晴。予報では昨日曇時々晴、今日曇時々雨。ところが、昨日は曇後雨で今日の予報は晴に変わる。今日雨と思い頑張って昨日秩父くんだりまで行ったのに、、、。というわけで「なんか悔しい」というだけの理由で高尾へ。昨日20キロ歩いたので正直まだ疲れているのだが、晴が恨めしいだけの意地である。が、高尾は良くなかった。雨後はヒルが嫌なので丹沢はやめたのだが、高尾は高尾で道がドロドロだ。たくさんのハイカーが歩くから掘り返されてぬた場のごとくである。高尾にはイノシシもシカもいないのになぁ。歩きにくいし登山靴泥まみれで嫌になる。あと、やはり疲労が取れていない。一歩踏み出す足が重い。景信山から陣馬山までの10キロでおしまい。特に書くこともない。晴れが悔しいから行っただけである。
@=
(2022-06-25) 不老山、三国山。曇。同行は三鷹のA氏。ちょっと遠目のロングトレイルということで、相駿国境尾根で静岡側から山越えで山中湖を目指す。 3時起き始発に乗って駿河小山駅7時過ぎ着。まぁ、遠いが駅から直接登れるのでバス要らずで良い。本日東京は晴れ、気温は35度の予報だが、山は曇りがち。気温は暑さを感じるが高度が上がれば涼しくなるだろう。市街地を30分ほど歩いて登山口。沢沿いは倒木多めでワイルドな趣。おっ、リスが横切る。野生動物も多そうね。急な坂道を登っていると、、、、A氏が「あっ、ヒルがいる。」「ホントだ!」と答える私の靴にもヒルが3匹。西丹沢にもこんなにいるんだ〜などと思いながら引っ剥がしているそばから次のやつがやってくる。こりゃイカンとペースを早めてヒル地帯を突っ切ろうとするが、ここからの一時間は悪夢のような山行であった。 3秒も足を止めると靴に5匹くらいたかられる。よく見ると登山道にうじゃうじゃいる。 10cm四方に小さいのも含めると10匹くらいはいる(見えていないだけでもっといるかもしれない)。完全に飽和していると言っていいだろう。立ち止まらずハイペースで登るが、それでもすぐに靴はヒルだらけだ。下ばかり見てヒルを払い落としながら進む。登り始めたばかりなのにムチャクチャ疲れた。大量のアリが大きな獲物を倒すというのがあるが、このヒルの大群もちょっとしたホラーである。標高が700mを超えるあたりでヒルは突然いなくなった。やっと落ち着いたので立ち止まって靴の中を調べるが、一疋でっかいやつが入ってましたよ。小さいのも2、3疋いる。幸い靴下は食い破れないようで流血の惨事にはならずに済んでよかった。不老山から明神山までは晴れていれば樹林帯としてそれなりのコースであろうが残念ながら霧で何も見えず。風が強く涼しいのはいいのだが、幾分トラウマになったのか靴に小枝や小石が入る度にヒルではと疑心暗鬼になってしまう。明神峠に向けてブナと杉の混合林が続く。虫の音、鳥のさえずりがいい感じ、、、なのだが、富士スピードウェイが近いため大爆音のエンジン音も流れる。興ざめ。目的地の三国山は樹海同様水はけの良い黒い土壌に苔むした広葉樹が広がり、霧に包まれて幻想的である。ここから下山しても良かったのだが折角なので籠坂峠まで歩くことにする。いつもの下山は消化試合という感じだが今日は緑溢れる樹海っぽい雰囲気で苦にならない。着いた籠坂峠は晴れ。天気が悪くても下山すれば晴れるもの。顔と手を洗う。これだけでだいぶとスッキリする。今日も汗だくだ。バスのタイミングが悪かったので山中湖まで歩く。湖水に手を付けて本日の山行は完了。巨大な富士も見れて最高だ。始まりは苦痛であったが、終わってみれば大満足の一日である。
@=
(2022-07-02) 鍋割山、塔ノ岳。晴。一週間連続の猛暑日。平日は冷房の部屋に引きこもっていた。やっと迎えた週末の今日も猛暑日予報。正直、こうも暑いと出かけたくないのだが、週に一度は体を使わないと衰える。今年の夏は暑いらしいし、今のうちに暑さへの耐性をつけておかないと熱中症の危険性も高まる。何事も事前の対策が大事なのだ。予防に勝る治療なしである。でも、あまり遠くまで行きたくない。だって、暑いし。カッコつけて言っておきながらこの体たらくである。とは言え、最低1000mは超えないと灼熱地獄である。という訳で丹沢へ。表尾根ならばバスで行けるヤビツ峠登山口で700mあるのだが、見晴らしの良い開けた尾根筋は強烈な太陽光が予想される。これはこれで死ぬな。よって、あえて展望のない樹林帯にする。大倉スタートなら早起きすれば7時には登山開始できる。、、、が、やっぱ暑いですわぁ。シャツは絞れるくらいの汗だし、その汗がズボンに垂れて下半身も膝上くらいまでびしょ濡れだ。飲んだ水分の量からして2L以上汗をかいたはずだ。じっとしていれば500mでも木陰では涼しい。下りであれば1000mくらいでも涼は感じられる。しかし、登りは駄目ですな。 1200mを超えて風が強ければなんとか、、、というところだが、本日はほぼ無風。日本全体が高気圧に覆われているので仕方がない。普段はいつも強風の塔ノ岳山頂も穏やかなもの。こういう天気は春や秋のために取っておいてほしいものである。いつものようにバカ尾根で下山。とてもでないがバスに乗れない。下山口の水道で上半身裸になり水浴び。服を着替えて幾分さっぱりする。コース自体は何度も通っているので特に言うことなし。緑は鮮やかであった。
@=
(2022-07-09) 塔ノ岳。曇時々霧。天気が思わしくないので近場の丹沢。20回くらいは行っている表尾根。都心は今日も32度とかの予報だが、猛暑日でなければ山は1000mを越えると結構涼しい。曇りで景色はまるで駄目だが、夏場は強烈な日差しよりはむしろありがたい。 1300mを越える大日岳のあたりからは完全な霧の中で視界は20mもない状態であった。そして、天然ミストとなれば肌寒いくらいである。何度も行ってるので特に書くこともなし。普段の散歩みたいなものである。
@=
(2022-07-18) 生藤山から陣馬山。曇後晴。せっかくの三連休なのにすっきりしない天気。近場の奥高尾へ。近いけど奥。生藤山周辺はアクセスが良い割にハイカーはぐっと少なくなる。鎌沢バス停で降りて、林道を辿り登里集落へ。舗装されているものの本当に車が走れるのかと思うほどの急勾配である。正直、この集落までが一番しんどい。さすがは登里という名だけはある。登山道に入ってからのほうが緩やかで楽になると言うのもおかしなものだ。桜のプロムナードと呼ばれる登山道はハイカーで賑わうらしいが、それは春の話。この時期は誰も歩いていない。そりゃ暑いからね。今日も2L近い汗をかいたはずだ。一応、いいことも書いておくとまだまだ紫陽花がキレイに咲いておりました。まずはどこにでもある三国山、武甲模の県境。ベンチがあるので一休み。ここから東進すると生藤山、茅丸、連行峰、醍醐丸と小さなピークが連続する。巻道はあるのだが、今回は陣馬山までのショートトレイルなので全て登ることにする。、、、が、いかんせん展望はない。この道は樹林のハイキングを楽しむコースなのだが夏は駄目ですな。緑で蒸せ上がっている。小ピークも繰り返されると流石に疲れる。大汗をかいて着いた陣馬山の茶屋で冷たい蕎麦を食べる。うめぇ〜。濃いだしが良い。少々の塩分など気にもならない。失ったナトリウムのほうが多いはずだ。最後は汗を流すために温泉へ。流石にこの濡れた衣服では電車に乗る気がしない。帰りの電車は爆睡。
@=
(2022-07-23) 三ツ峠山。晴時々曇。低山は暑い。登山口で1000mくらいの標高がほしい。、、、と、言うことで富士北部の三ツ峠山にする。少々の遠出でもこの時期であれば18切符が使えるので安心。王道の三つ峠駅からの出発。登山口までの1時間は舗装路。8時前の太陽だがすでに熱線である。日陰であればそれほどでもないが、山に入るまでは木々がないところも多いのが難点。駅から300m登って登山口に到着。距離的には3分の2を消化。残りの標高800m。と、言うことは、そう、急である。植生は植林された杉と広葉樹の混成林で雲取山などの奥多摩と似た雰囲気。急登ではあるが葉が陽を透かして綺麗なのと、いい具合にビューポイントあるのであまり疲れない。そう、ここは富士山のすぐ近くなので視界が開ければ広大な山裾から天を衝く日本の最高峰を拝むことができる。加えて古くからの信仰の道でもあるようで、道中、「達磨石」「愛染明王塔」「不二石」「空胎上人墓」「八十八躰供養塔」など見どころ多数である。 1600mを超えると屏風岩のトラバースとなり平坦に近い道となる。絶壁の屏風岩のすぐ下を通る道は山水画のような趣で白い岸壁が快晴の空によく映える。屏風岩を登るロッククライマーも多数いて、安全な登山道と合わせて老若男女、初心者から上級者まで楽しめるいい山である。程なく山頂に到着。三つ峠は富士山を眺めるための山でもある。南側一面の展望が得られる山頂は東は丹沢から西は南アルプスまで見渡すことができ真正面に巨大な富士山が望める素晴らしいものである。ただ、残念なことに本日は午後に向けて天候が崩れる予定。実際に雲が多くなってきて富士山頂は隠れてしまった。三つ峠は屏風岩こそ急峻であるが全体的には非常になだらかの山である。山頂近くの山小屋までジープが入れるほどであるし、山頂には電波塔など多数の建造物もある。山小屋には電気も通じており自販機があったりする。そしてなんと言っても涼しい。下界と比べて10度は気温も低いはず。気持ちがいいので長居してしまった。さて、下りは道を変えて河口湖の方へ降りることにする。が、こちらは退屈。ザ、変哲のない道という感じで高尾あたりと変わらない。涼しいのはありがたいが面白みがないし木々に覆われ景色が変わらない。大倉バカ尾根と同じで超安全ではあるが逆に言うとスリルがなく単調である。 14時前に河口湖駅到着。かいた汗は1Lくらいかな。やはり夏はある程度標高が高いほうが良い。
@=
(2022-07-30) 谷川岳。晴後曇。同行は上野のI氏。なんせ遠い、そして、交通費が高いという理由で登りたいと思ってはいても敬遠していた谷川岳であるが、18切符が交通費に関しては解決してくれる。片道3000円のJR運賃が鈍行乗り放題で2410円である。ただし、電車だけで片道3時間半はかかるので往復で7時間。圧倒的に山行時間より電車の方が長い旅である。水上駅からバスとロープウェイで天神平へ。登山開始は9時半であった。3時半起床で4時半出発。4時48分の電車に乗ったので、移動だけで片道5時間くらいかかった計算である。天神平で1300mくらいはあるので山頂までの比高は700mしかない。距離も片道で3.5km、往復で7kmしかないので楽勝コースである。普通に歩けば3時間ちょっとくらいであろうか。初心者向きの100名山として人気のある谷川岳であるが、流石は有名所とあって結構な人出であった。夏の富士山に近い状態で鈴なりの前の人のおしりを見て進むという感じである。天神平からしばらくは樹林帯であるが30分ほどで急な岩場となる。ただ、道幅は広く断崖というわけではないので、滑っても尻餅をつくくらいで大怪我になるということはないだろう。実際、80歳くらいのお婆さんや、未就学児も登っている。ただ、危険ということはないが、滑りやすい岩もあるので慎重に歩む必要はあるだろう。谷は結構深いので冬であれば危なそうではある。1800mを超えると高山植物のお花畑が広がる。急な道が続くが色とりどりの花が咲いており疲れを感じない。万太郎山につながる稜線、そしてそこから沈み込む急峻な谷川に映される陽光の陰影も圧巻である。人気の山にはやはり訳がありますね。いい山ですわ、谷川岳。肩ノ小屋に着いてしまえばトマノ耳はあとわずか。写真では絶壁に見える耳も西側は緩やかなので、一般道を歩いている限り恐怖を感じるところは皆無である。実際に何百人と登っているので渋滞の方が気になるくらいだ。さて、山頂。人だかり。写真だけ撮って退散。ついでなのでオキノ耳まで行く。この両耳の間の道は特に良い。花も多く咲いており、西に広がる万太郎谷が雄大である。オキノ耳で11時半。少し進んで30分ほど休憩アンド食事。オキノ耳の先まで行く人は少ないので静かだし涼しいし最高である。午後からは天気が崩れるようなので急ぎ下山する。、、、が、人が多すぎて抜かすこともできない。結構時間がかかる。13時半に天神平に帰着。ロープウェイで下山。
@=
(2022-07-31) 韮崎散歩。
@=
(2022-08-06) 陣馬山。曇。同行は大森のW氏。大菩薩嶺に行く予定だったのだが天気が優れないので陣馬山に変更。夏に低山は地獄なのだが、天気が悪いことから予報では最高気温29度。これなら高尾山系でも大丈夫であろう。なお、終始曇で山頂付近は霧。展望はまったくない。これはわかっていたことなので特に落胆なし。今日のテーマはなんちゃって登山に茶屋ビール。 8時半に登山口を出て2時間、10時半に山頂。そこから13時まで茶屋でうどん食べたりソーセージ焼いたり、W氏は1Lもビールを飲んだりとダラダラと過ごす。 1時間半かけて下山して14時半から温泉。山に行ったというよりおしゃべりしに散歩に行ったという感覚である。まぁ、何度も行った陣馬山なので山行自体に言うことはない。霧の中でなんにも見えなかったし写真もない。手術明けで自称満身創痍のW氏であったがいいリハビリになったのではないだろうか。
@=
(2022-08-07) 栃木でダンジョン探索。大谷資料館。
@=



 (2017-09-09) 阿弥陀岳から望む赤岳と横岳。
(2017-09-09) 阿弥陀岳から望む赤岳と横岳。
 (2017-09-10) 硫黄岳から横岳と赤岳。
(2017-09-10) 硫黄岳から横岳と赤岳。
 (2017-09-15) 毛越寺 in 奥の細道歩き旅。
(2017-09-15) 毛越寺 in 奥の細道歩き旅。
 (2017-09-16) 鳴子への道中 in 奥の細道歩き旅。
(2017-09-16) 鳴子への道中 in 奥の細道歩き旅。
 (2017-10-01) 御前山から見た富士。
(2017-10-01) 御前山から見た富士。
 (2017-11-04) 檜洞丸から大室山への風景。
(2017-11-04) 檜洞丸から大室山への風景。
 (2017-11-05) 大菩薩嶺から見る富士。
(2017-11-05) 大菩薩嶺から見る富士。
 (2017-11-11) ユーシンブルー。
(2017-11-11) ユーシンブルー。
 (2017-11-19) Kさん、Kさん、Mさん、Sさん。 in 陣馬山。
(2017-11-19) Kさん、Kさん、Mさん、Sさん。 in 陣馬山。
 (2017-11-25) 振り返って蛭ヶ岳。遠くに見えるは南アルプス。
(2017-11-25) 振り返って蛭ヶ岳。遠くに見えるは南アルプス。
 (2017-12-02) ものすごい所を登っているように見える一枚。実際にはたいしたことはない。同行のKさん、Mさん、Nさん。 in 丹沢表尾根。
(2017-12-02) ものすごい所を登っているように見える一枚。実際にはたいしたことはない。同行のKさん、Mさん、Nさん。 in 丹沢表尾根。
 (2018-03-18) 南房総へ。富山と鋸山。写真は日本寺の石窟。
(2018-03-18) 南房総へ。富山と鋸山。写真は日本寺の石窟。
 (2018-03-21) 大谷資料館はダンジョン。
(2018-03-21) 大谷資料館はダンジョン。
 (2018-03-24) 行ったことなかった偕楽園へ。梅は散り気味。弘道館が良かった。大日本史は紀伝体であった。
(2018-03-24) 行ったことなかった偕楽園へ。梅は散り気味。弘道館が良かった。大日本史は紀伝体であった。
 (2018-03-25) 檜洞丸から大室山を臨む。何度も見た風景。三日前の雪のため犬越路では怖いめにあった。
(2018-03-25) 檜洞丸から大室山を臨む。何度も見た風景。三日前の雪のため犬越路では怖いめにあった。
 (2018-04-01) 奥多摩から五日市に抜けると桜はまだ満開であった。
(2018-04-01) 奥多摩から五日市に抜けると桜はまだ満開であった。
 晴れ。汗ばむ陽気。 13時過ぎ、自宅を出発。
晴れ。汗ばむ陽気。 13時過ぎ、自宅を出発。
 14:23発。新大阪行きのぞみ。遅めの昼飯に駅弁+お茶。合計1151円。
14:23発。新大阪行きのぞみ。遅めの昼飯に駅弁+お茶。合計1151円。
 昨日行った勝連城址。火災の痕跡がなく、落城を経験したとは思えないため、なぜ廃墟となったのか謎とのこと。潮風が通り過ぎる。
昨日行った勝連城址。火災の痕跡がなく、落城を経験したとは思えないため、なぜ廃墟となったのか謎とのこと。潮風が通り過ぎる。
 摩文仁の丘。三度目だがいつ来ても良い。晴天はいいのだが、汗だくになる熱気。
摩文仁の丘。三度目だがいつ来ても良い。晴天はいいのだが、汗だくになる熱気。
 立ち並ぶメコンビューのペンション(タイ側)。
立ち並ぶメコンビューのペンション(タイ側)。
 対岸の風景(ラオス側)。
対岸の風景(ラオス側)。
 このGHにはネット環境ないのかなと思っていましたがありました。今やWIFIのない宿ってないな。ムアン・シンなんて相当山奥の何もないとこなのに。写真は部屋のドアを開けたら広がる風景。
このGHにはネット環境ないのかなと思っていましたがありました。今やWIFIのない宿ってないな。ムアン・シンなんて相当山奥の何もないとこなのに。写真は部屋のドアを開けたら広がる風景。
 この夕焼け空の下。コンパスは人知れず眠る。相棒よ。私の不注意ですまない。いい年したおっさんがしばし悔悟の念。そんなムアン・シンの二度目の夕暮れ。
この夕焼け空の下。コンパスは人知れず眠る。相棒よ。私の不注意ですまない。いい年したおっさんがしばし悔悟の念。そんなムアン・シンの二度目の夕暮れ。
 雨の後の市場前。ムアン・シンで一番の繁華街。
雨の後の市場前。ムアン・シンで一番の繁華街。
 バス停だってこの通り。アスファルト?なにそれって感じですわ。
バス停だってこの通り。アスファルト?なにそれって感じですわ。
 濁流の中、漁をしているご婦人。カメラを向けて「写真取っていい?」って日本語で聞いたらポーズを取ってくれました。
濁流の中、漁をしているご婦人。カメラを向けて「写真取っていい?」って日本語で聞いたらポーズを取ってくれました。
 雨季が始まり田植えのシーズン。
雨季が始まり田植えのシーズン。
 と、思いきや、実るほど頭を垂れる稲穂かな。
と、思いきや、実るほど頭を垂れる稲穂かな。
 手前は田植え前、奥は収穫間近。う〜む。二期作?多期作?一年中いつ植えても実るのだろうか。
手前は田植え前、奥は収穫間近。う〜む。二期作?多期作?一年中いつ植えても実るのだろうか。
 脱穀しているのに。
脱穀しているのに。
 種籾を発芽させている?
種籾を発芽させている?
 この石だらけのひどい道をママチャリで3km。滝を目指す。
この石だらけのひどい道をママチャリで3km。滝を目指す。
 更に歩いてジャングルの先に、、、、
更に歩いてジャングルの先に、、、、
 滝が出現。うん、なんだ?
滝が出現。うん、なんだ?
 滝壺では南国美女がヌレヌレになって遊んでました。
滝壺では南国美女がヌレヌレになって遊んでました。
 もう少し下流では子どもたちが遊んでいました。このあと、バク宙回転飛び込みを披露してくれました。うーん。市民の憩いの場なのね。とんでもない道の先にあるのに。
もう少し下流では子どもたちが遊んでいました。このあと、バク宙回転飛び込みを披露してくれました。うーん。市民の憩いの場なのね。とんでもない道の先にあるのに。
 川沿いの遊歩道は七色に変色するライトアップが施され、摩天楼地区もいくつもあります。壁面には細工が施されゴミひとつない綺麗な遊歩道は数キロに渡って続きます。
川沿いの遊歩道は七色に変色するライトアップが施され、摩天楼地区もいくつもあります。壁面には細工が施されゴミひとつない綺麗な遊歩道は数キロに渡って続きます。
 中国側に入れば高速道路。上下で別の高架になっていて、片側二車線、合計四車線。高架とトンネルが連続する景色もいい道です。
中国側に入れば高速道路。上下で別の高架になっていて、片側二車線、合計四車線。高架とトンネルが連続する景色もいい道です。
 そして着いた景洪は、雰囲気のいい都会。幼稚園前には迎えのお父さんお母さんがバイクで集結。
そして着いた景洪は、雰囲気のいい都会。幼稚園前には迎えのお父さんお母さんがバイクで集結。
 幼稚園。みなさん、結構英才教育してるみたい。ちなみにここに住むのはルー族であって漢族は少数派。
幼稚園。みなさん、結構英才教育してるみたい。ちなみにここに住むのはルー族であって漢族は少数派。
 ちなみにラオスの子供はこうだった。田んぼがプールだい。とても幸せそうではあります。
ちなみにラオスの子供はこうだった。田んぼがプールだい。とても幸せそうではあります。
 散策路は綺麗に整備されています。夜になると七色にライトアップされます。(ネオンは個人的には趣味じゃないけどなぁ。)
散策路は綺麗に整備されています。夜になると七色にライトアップされます。(ネオンは個人的には趣味じゃないけどなぁ。)
 河岸の休憩所で楽団(アマチュアの趣味?)が練習してました。
河岸の休憩所で楽団(アマチュアの趣味?)が練習してました。
 ちゃんとゴミ箱もある。しかもリサイクルの可否で分別。ベンチも適度な間隔で設置されてます。
ちゃんとゴミ箱もある。しかもリサイクルの可否で分別。ベンチも適度な間隔で設置されてます。
 水は透明度があり下流域のように赤く濁っていません。
水は透明度があり下流域のように赤く濁っていません。
 昔ながらの漁船も発見。
昔ながらの漁船も発見。
 散策路はいつしか木道になりました。
散策路はいつしか木道になりました。
 川岸にはホテルとマンションが林立しています。
川岸にはホテルとマンションが林立しています。
 街にはこういった自転車ステーションがちらほらあります。好きなところで乗って好きなところに乗り捨てていいみたい。日本のプリペイド式乗車券のようなものをタッチして利用するみたいです。
街にはこういった自転車ステーションがちらほらあります。好きなところで乗って好きなところに乗り捨てていいみたい。日本のプリペイド式乗車券のようなものをタッチして利用するみたいです。
 中国名物路上将棋。その他、路上麻雀、路上トランプも至るところで見かけます。
中国名物路上将棋。その他、路上麻雀、路上トランプも至るところで見かけます。
 街にゴミはなくとても綺麗です。掃除のおばちゃんをよく見かけますが、ちりとりには枯れ葉くらいしかありません。日本の方が道端の植込みなどを覗くと結構なゴミが放置されていたりして汚いかもしれません。
街にゴミはなくとても綺麗です。掃除のおばちゃんをよく見かけますが、ちりとりには枯れ葉くらいしかありません。日本の方が道端の植込みなどを覗くと結構なゴミが放置されていたりして汚いかもしれません。
 朝ゴハンに肉まん。肉包1.5元(30円ほど)と書かれていたので、2個頼んだら10個くらい入れてくれました。食いきれんて、、、。販売の単位がよくわからない。
朝ゴハンに肉まん。肉包1.5元(30円ほど)と書かれていたので、2個頼んだら10個くらい入れてくれました。食いきれんて、、、。販売の単位がよくわからない。
 建設ラッシュ。至るところでクレーンを見る。巨峰って書いてあるけど、ブドウではないですわな。高層ビルのことかしらん。
建設ラッシュ。至るところでクレーンを見る。巨峰って書いてあるけど、ブドウではないですわな。高層ビルのことかしらん。
 おしゃれな店もいっぱい。靴屋さん。
おしゃれな店もいっぱい。靴屋さん。
 汗だく。五時間ほどで散策を切り上げ。ここほんとに地方都市ですか?大広場と巨大商業施設。只今内装工事中で営業はまだしていない模様。
汗だく。五時間ほどで散策を切り上げ。ここほんとに地方都市ですか?大広場と巨大商業施設。只今内装工事中で営業はまだしていない模様。
 自動販売機があるのは、泥棒があまりいない証。
自動販売機があるのは、泥棒があまりいない証。
 こちらは飲み屋街。ワールドカップ開催中なのでどこもスポーツバー状態。ネオンの趣味の悪さだけは昔ながらの中国といったところやね。
こちらは飲み屋街。ワールドカップ開催中なのでどこもスポーツバー状態。ネオンの趣味の悪さだけは昔ながらの中国といったところやね。
 孔明先生。悪弊と瘴疫の地であった南蛮はエライことになっています!
孔明先生。悪弊と瘴疫の地であった南蛮はエライことになっています!
 さて、景洪はこれでおしまい。最後に、、、。この街に一週間は滞在したい気になった最大の理由、それは宿の子が優しくて可愛かったからだぁ!
さて、景洪はこれでおしまい。最後に、、、。この街に一週間は滞在したい気になった最大の理由、それは宿の子が優しくて可愛かったからだぁ!
 地下鉄の自動券売機。タッチパネルで英語対応しています。
地下鉄の自動券売機。タッチパネルで英語対応しています。
 昆明駅。左下の青いポリスボックスは昆鉄特警。
昆明駅。左下の青いポリスボックスは昆鉄特警。
 裏道に入れば薄汚れた庶民街も色濃く残る。ただし、ゴミは落ちてない。タンを吐く人もいない。
裏道に入れば薄汚れた庶民街も色濃く残る。ただし、ゴミは落ちてない。タンを吐く人もいない。
 6車線側道付きで御堂筋に似ていると感じた北京路。
6車線側道付きで御堂筋に似ていると感じた北京路。
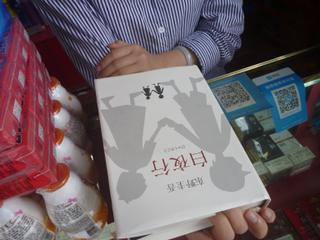 売店の小姐が東野圭吾の白夜行を読んでました。当然中国語訳。読んでいる姿を写そうとしたら、「やめてぇ」とのことだったので自粛。東野圭吾は私も大好き。
売店の小姐が東野圭吾の白夜行を読んでました。当然中国語訳。読んでいる姿を写そうとしたら、「やめてぇ」とのことだったので自粛。東野圭吾は私も大好き。
 再び地下鉄で翠湖公園へ。今日は土曜日。どこに行っても人がいっぱい。
再び地下鉄で翠湖公園へ。今日は土曜日。どこに行っても人がいっぱい。
 青山か表参道あたりに似ていると思った翠湖南路。
青山か表参道あたりに似ていると思った翠湖南路。
 翠湖公園も人がいっぱい。いい公園ですよ。いかにも中国風という感じである。
翠湖公園も人がいっぱい。いい公園ですよ。いかにも中国風という感じである。
 やたらと色んな所でみんなが踊っている。
やたらと色んな所でみんなが踊っている。
 あっちでも。
あっちでも。
 こっちでも。
こっちでも。
 見事な蓮の池。花も咲いている。
見事な蓮の池。花も咲いている。
 そして見事なカメラ。そのレンズ高そう!アマチュアカメラマンが集まっているみたいで、中には1m近いレンズのカメラを抱えたおばちゃんもいた。
そして見事なカメラ。そのレンズ高そう!アマチュアカメラマンが集まっているみたいで、中には1m近いレンズのカメラを抱えたおばちゃんもいた。
 みんな楽しそう。でも、公園には公安もたくさんいます。
みんな楽しそう。でも、公園には公安もたくさんいます。
 そして繁華街へ。
そして繁華街へ。
 広い。綺麗。人だかり。もう、銀座や心斎橋あたりと変わりない。
広い。綺麗。人だかり。もう、銀座や心斎橋あたりと変わりない。
 列車は軒並み遅れる。始発駅なのになんで?新幹線はほぼ定刻通りに走っている。
列車は軒並み遅れる。始発駅なのになんで?新幹線はほぼ定刻通りに走っている。
 昆明駅の食事処。ハンバーガーのセットが119元(約2000円)。結構流行ってます。もしかして、日本人より金持ち?
昆明駅の食事処。ハンバーガーのセットが119元(約2000円)。結構流行ってます。もしかして、日本人より金持ち?
 楽山は普通の地方都市。昔ながらの中国のままでした。建物も古く、町の住人も野暮ったい衣装です。
楽山は普通の地方都市。昔ながらの中国のままでした。建物も古く、町の住人も野暮ったい衣装です。
 河川は完全に濁流。渦巻いてます。雨もやの向こうは大仏(があるはず)。
河川は完全に濁流。渦巻いてます。雨もやの向こうは大仏(があるはず)。
 乗船できません。ある意味見ものでした。
乗船できません。ある意味見ものでした。
 激流とV時谷。
激流とV時谷。
 今晩の寝床は8人部屋。
今晩の寝床は8人部屋。
 伊達女もかっこいい。
伊達女もかっこいい。
 街に至る川沿いの遊歩道はきれいに整備されています。相変わらず清掃員いっぱいだし、整備されすぎて逆に趣がない。
街に至る川沿いの遊歩道はきれいに整備されています。相変わらず清掃員いっぱいだし、整備されすぎて逆に趣がない。
 街は急峻な谷筋にある。農地もなければ産業なんてあるはずがない。宿と食堂と商店しかない街である。ここは民族の十字路。交易で成り立っているのであろう。
街は急峻な谷筋にある。農地もなければ産業なんてあるはずがない。宿と食堂と商店しかない街である。ここは民族の十字路。交易で成り立っているのであろう。
 ゴンパ(寺)は大したことない。まぁ、チベットエリアに来た感じはする。
ゴンパ(寺)は大したことない。まぁ、チベットエリアに来た感じはする。
 もう一つのゴンパも大したことはないが、山の中腹にあり景色は良い。
もう一つのゴンパも大したことはないが、山の中腹にあり景色は良い。
 朝の白塔寺。手前に五体投地をしている人がいる。ゴンパ前の白い平屋部分が祈願所らしく、そこでは何人ものチベット人が五体投地をしていた。残念ながらこの日は時折小雨の降る曇り空。
朝の白塔寺。手前に五体投地をしている人がいる。ゴンパ前の白い平屋部分が祈願所らしく、そこでは何人ものチベット人が五体投地をしていた。残念ながらこの日は時折小雨の降る曇り空。
 タルチョーの丘から街を眺める。高峰に囲まれて、ちょこんと街があります。街の周囲は全て牧草地でヤクがのんびりと草を食んでいる。
タルチョーの丘から街を眺める。高峰に囲まれて、ちょこんと街があります。街の周囲は全て牧草地でヤクがのんびりと草を食んでいる。
 多分これが鳥葬台。今日は日曜日で、月水金に鳥葬が行われる。明日、この前で遺体が解体され、ハゲワシによって天へと運ばれる。
多分これが鳥葬台。今日は日曜日で、月水金に鳥葬が行われる。明日、この前で遺体が解体され、ハゲワシによって天へと運ばれる。
 老街は狭い道が曲がりくねり完全に迷路です。なお、チベットエリアではゴミが結構落ちています。伊達男はかっこいいんだけど、ツバやタンを吐くやつも結構います(多いわけではない)。
老街は狭い道が曲がりくねり完全に迷路です。なお、チベットエリアではゴミが結構落ちています。伊達男はかっこいいんだけど、ツバやタンを吐くやつも結構います(多いわけではない)。
 ガンゼは山に囲まれた小さな町です。
ガンゼは山に囲まれた小さな町です。
 町外れのゴンパの境内では結婚式が行われていました。かけられたカタ(スカーフみたいな布)の数だけ幸せになれるのかな?
町外れのゴンパの境内では結婚式が行われていました。かけられたカタ(スカーフみたいな布)の数だけ幸せになれるのかな?
 さて、写真に取るとどうしても迫力がないのですが、大草原。以下、バスの車窓から汚れた窓越しなのでうまくピントが合わない。
さて、写真に取るとどうしても迫力がないのですが、大草原。以下、バスの車窓から汚れた窓越しなのでうまくピントが合わない。
 高原はこれ全て牧草地。
高原はこれ全て牧草地。
 湿原はお花畑。
湿原はお花畑。
 休憩中に高山植物。
休憩中に高山植物。
 牛とヤクは道路の王様。完全に片側一車線を塞いでいることもあり。車も避けて走ります。
牛とヤクは道路の王様。完全に片側一車線を塞いでいることもあり。車も避けて走ります。
 菜の花畑は人間の産物。
菜の花畑は人間の産物。
 こんな大自然の村で生活してたら、誰でも(牛ですら)哲学者になりそうな気がする。
こんな大自然の村で生活してたら、誰でも(牛ですら)哲学者になりそうな気がする。
 標高4300mの峠は草もまばらな荒野。以上、本日の車窓からシリーズ終わり。
標高4300mの峠は草もまばらな荒野。以上、本日の車窓からシリーズ終わり。
 こんなところ攻め込めません。蜀の政権って引きこもりが多いのもわかります。
こんなところ攻め込めません。蜀の政権って引きこもりが多いのもわかります。
 松藩の松州古城。ほぼすべての観光客はここで写真を取るだろう。
松藩の松州古城。ほぼすべての観光客はここで写真を取るだろう。
 松藩も所詮中華テーマパークです。いい古い町並みが残ってたんだろうけどなぁ。中国人は好きだね、こうやって本物を壊して偽物でテーマパークを作ってしまう。
松藩も所詮中華テーマパークです。いい古い町並みが残ってたんだろうけどなぁ。中国人は好きだね、こうやって本物を壊して偽物でテーマパークを作ってしまう。
 映月橋。風雅な名前だね。たぶん夜は七色に光ります。屋根の周囲に電飾が施されている。まぁ、わざわざ夜に見に行くことはない。
映月橋。風雅な名前だね。たぶん夜は七色に光ります。屋根の周囲に電飾が施されている。まぁ、わざわざ夜に見に行くことはない。
 巨大なきゅうり。直径が、、、20cmは超えている。
巨大なきゅうり。直径が、、、20cmは超えている。
 町並みは中華っぽいけど、、、。
町並みは中華っぽいけど、、、。
 テナントは洋服屋さん。
テナントは洋服屋さん。
 スーツ屋さん。男のマネキンにはズボンを履かせたほうがいいと思います。
スーツ屋さん。男のマネキンにはズボンを履かせたほうがいいと思います。
 ウィグル人が多数いて少し驚きました。松藩は、少しおかしな民族のるつぼであり、少しおかしな中華テーマパークです。
ウィグル人が多数いて少し驚きました。松藩は、少しおかしな民族のるつぼであり、少しおかしな中華テーマパークです。
 裏通りに入れば古い家屋も多々残っています。こういうのが街の個性が出ていていいと思います。
裏通りに入れば古い家屋も多々残っています。こういうのが街の個性が出ていていいと思います。
 路上果物屋さん街。そんなに売れないだろうなぁ。隣近所商売敵ばかりで揉めないのかな。
路上果物屋さん街。そんなに売れないだろうなぁ。隣近所商売敵ばかりで揉めないのかな。
 と、思えば、やっぱり暇なんでしょう。おばちゃん達、仲良く麻雀をやってました。
と、思えば、やっぱり暇なんでしょう。おばちゃん達、仲良く麻雀をやってました。
 ゾルゲには1時間ほど滞在しただけ。草原のど真ん中に新しく作られた行政のための計画都市という感じ。歴史を感じないためあまり興味は惹かれない。
ゾルゲには1時間ほど滞在しただけ。草原のど真ん中に新しく作られた行政のための計画都市という感じ。歴史を感じないためあまり興味は惹かれない。
 この草原の広さはどうかしている。 3000m超えてる高地なんだけど地平線が見える。
この草原の広さはどうかしている。 3000m超えてる高地なんだけど地平線が見える。
 道路をヤクが横断中。チベットでは歩行者より車優先。ヤク最優先。
道路をヤクが横断中。チベットでは歩行者より車優先。ヤク最優先。
 頻繁に一車線通行規制。 30分は待たされる。おかげで景色は堪能できる。
頻繁に一車線通行規制。 30分は待たされる。おかげで景色は堪能できる。
 色とりどりの高原植物が咲いており、待っている時間も気にならない。チベット人はピクニック感覚。
色とりどりの高原植物が咲いており、待っている時間も気にならない。チベット人はピクニック感覚。
 わかりにくいけど紫はラベンダー。緑、白、黄色、ピンク、紫の絨毯です。
わかりにくいけど紫はラベンダー。緑、白、黄色、ピンク、紫の絨毯です。
 車は全く動きません。もう、なんか、着かなくってもいいやって気分になります。
車は全く動きません。もう、なんか、着かなくってもいいやって気分になります。
 パワフルなロシア人。化学エンジニア。 64歳にして、一ヶ月の個人旅行。純粋にそのエネルギーを尊敬します。
パワフルなロシア人。化学エンジニア。 64歳にして、一ヶ月の個人旅行。純粋にそのエネルギーを尊敬します。
 チベット僧二人。車は長蛇の列。結局、信号のまったくない80キロの道のりを3時間かかりました。時速100キロ以上で馬鹿みたいに飛ばすけど全く意味がありません。
チベット僧二人。車は長蛇の列。結局、信号のまったくない80キロの道のりを3時間かかりました。時速100キロ以上で馬鹿みたいに飛ばすけど全く意味がありません。
 あの先の山に登りたい。
あの先の山に登りたい。
 この辺までは風景地区。観光客も多い。大したことはない。
この辺までは風景地区。観光客も多い。大したことはない。
 渓谷の入り口。
渓谷の入り口。
 ここから引き馬。もちろん乗らない。
ここから引き馬。もちろん乗らない。
 道中は完全に沢登り。朗木寺は標高3400m。水は冷たい。凍えそうだ。
道中は完全に沢登り。朗木寺は標高3400m。水は冷たい。凍えそうだ。
 山間の小さな草原。引き馬サービスはここまで。ここも相当に気持ちのいい場所である。ここで谷は2つに別れる。
山間の小さな草原。引き馬サービスはここまで。ここも相当に気持ちのいい場所である。ここで谷は2つに別れる。
 まずは左の谷を進む。
まずは左の谷を進む。
 両側絶壁。ただし、道は比較的しっかりしているので先には進めそうだ。誰にも会わない。不安ではあるが、風景独り占めで最高の気分だ。
両側絶壁。ただし、道は比較的しっかりしているので先には進めそうだ。誰にも会わない。不安ではあるが、風景独り占めで最高の気分だ。
 一面のお花畑。カルスト地形ながら比較的なだらかで登れそうだ。
一面のお花畑。カルスト地形ながら比較的なだらかで登れそうだ。
 が、やはり険しい。とにかく行けるところまで行く。
が、やはり険しい。とにかく行けるところまで行く。
 流石に道が怪しくなり進むのを断念。万が一、捻挫でもしようものなら助けすら呼べない。そもそも誰もいない、誰も通らない山中だ。
流石に道が怪しくなり進むのを断念。万が一、捻挫でもしようものなら助けすら呼べない。そもそも誰もいない、誰も通らない山中だ。
 振り返れば、絶景。うん。結構登ったよな。
振り返れば、絶景。うん。結構登ったよな。
 横を向けばこんな感じ。山は逃げないしね。またの機会があるさ。
横を向けばこんな感じ。山は逃げないしね。またの機会があるさ。
 一度戻り、右の谷を進む。
一度戻り、右の谷を進む。
 もうずっと沢登り。濡れるのは気にしない。景色がいいので気にならない。
もうずっと沢登り。濡れるのは気にしない。景色がいいので気にならない。
 着いたのはチベットの隠し谷。誰もいないし。非常に気持ちがいい。観光地はどこも人が多すぎる。求めていたのはこの風景だ。
着いたのはチベットの隠し谷。誰もいないし。非常に気持ちがいい。観光地はどこも人が多すぎる。求めていたのはこの風景だ。
 息を切らしてようやく到着。この村、とんでもない所にあるな。
息を切らしてようやく到着。この村、とんでもない所にあるな。
 旅は道連れ世は情け。二人いればとりあえず安心だ。 Aはビーチサンダルで登っていく。すごいな、おい。
旅は道連れ世は情け。二人いればとりあえず安心だ。 Aはビーチサンダルで登っていく。すごいな、おい。
 振り返ればテント村も小さくなっていた。
振り返ればテント村も小さくなっていた。
 ヤクを発見。遊牧地であるということは人がいるはずだ。空気が薄く半端ない疲れ方であるが、心強く感じる。
ヤクを発見。遊牧地であるということは人がいるはずだ。空気が薄く半端ない疲れ方であるが、心強く感じる。
 正面の岩の上に二人の人影を発見。ゴールは決まった。
正面の岩の上に二人の人影を発見。ゴールは決まった。
 到着。心臓が破裂しそう。標高は4100mとちょっとだそうだ。しばし、チベットのヤク飼いと歓談(言葉はわからないけど、、、)する。谷は広く深く遠い。遠近感がよくわからなくなる。
到着。心臓が破裂しそう。標高は4100mとちょっとだそうだ。しばし、チベットのヤク飼いと歓談(言葉はわからないけど、、、)する。谷は広く深く遠い。遠近感がよくわからなくなる。
 私は流石に疲れ切ってましたけど。 Aは元気なもので更に先の岩の上まで行ってました。元気だなぁ。
私は流石に疲れ切ってましたけど。 Aは元気なもので更に先の岩の上まで行ってました。元気だなぁ。
 帰りは楽なもの。結局、8時間の山行となりました。
帰りは楽なもの。結局、8時間の山行となりました。
 黄色いジャケット。背中に「文明交通対導員」と書いてある。
黄色いジャケット。背中に「文明交通対導員」と書いてある。
 水井巷。商店街は人でいっぱい。ソフトクリーム2元(40円)は安すぎる。買い食いしまくり。
水井巷。商店街は人でいっぱい。ソフトクリーム2元(40円)は安すぎる。買い食いしまくり。
 今日一日で食べたヨーグルト(何の乳か不明)は3個。黄色い脂肪分が浮いています。あまり発酵は進んでおらず乳清が多いです。
今日一日で食べたヨーグルト(何の乳か不明)は3個。黄色い脂肪分が浮いています。あまり発酵は進んでおらず乳清が多いです。
 トルファンといえばぶどう棚。街の中心部は漢人が多く、ウィグル人は少ない。
トルファンといえばぶどう棚。街の中心部は漢人が多く、ウィグル人は少ない。
 壁画のモスク部分が剥がされている。(政府の命令で自発的に剥がしたのかもしれない。)町中は異様に警察が多い。 100人に1人くらいは治安維持要員。市バスはドライバーと荷物チェック者の二名体制。
壁画のモスク部分が剥がされている。(政府の命令で自発的に剥がしたのかもしれない。)町中は異様に警察が多い。 100人に1人くらいは治安維持要員。市バスはドライバーと荷物チェック者の二名体制。
 ゲストハウスですら入り口には金属探知機。全ての宿泊施設(高級ホテルでも)の入り口はこれである。
ゲストハウスですら入り口には金属探知機。全ての宿泊施設(高級ホテルでも)の入り口はこれである。
 公園もこの通り。入り口で身体検査と荷物検査。もはや、市民の憩いの場ではないように思う。
公園もこの通り。入り口で身体検査と荷物検査。もはや、市民の憩いの場ではないように思う。
 夜明け前の伊寧駅。不相応に立派の駅舎です。国境都市だから政府が力を入れているのでしょう。
夜明け前の伊寧駅。不相応に立派の駅舎です。国境都市だから政府が力を入れているのでしょう。
 緑豊かな中央アジアの高原都市。火州(トルファン)は強烈に暑かったけど、ウルムチでぐっと楽になり、ここ伊寧(グルジャ)では朝は寒いくらい。
緑豊かな中央アジアの高原都市。火州(トルファン)は強烈に暑かったけど、ウルムチでぐっと楽になり、ここ伊寧(グルジャ)では朝は寒いくらい。
 百貨店前では朝の朝礼(発声練習?)。在りし日からは考えられないくらい中国のサービスは良くなっています。日本以上に能力主義・資本主義ですし。
百貨店前では朝の朝礼(発声練習?)。在りし日からは考えられないくらい中国のサービスは良くなっています。日本以上に能力主義・資本主義ですし。
 バス停は交番とセット。公安、警察、武警(武装警察)、特警(特別警察)。武警は自動小銃を携行。人口の1%くらいは治安維持要員ではなかろうか?
バス停は交番とセット。公安、警察、武警(武装警察)、特警(特別警察)。武警は自動小銃を携行。人口の1%くらいは治安維持要員ではなかろうか?
 イリ河の堤防上は整備された遊歩道。綺麗なんだけどあまり活気を感じない。ウィグルは徹底的に管理されている。同じ国境都市でも景洪のほうがまだしも自由を感じる。
イリ河の堤防上は整備された遊歩道。綺麗なんだけどあまり活気を感じない。ウィグルは徹底的に管理されている。同じ国境都市でも景洪のほうがまだしも自由を感じる。
 イリ河大橋。それなりの観光地らしいけど大したことないです。河原では大人が子供と一緒になって水遊びに興じていました。ウィグル人が楽しそうにしていたのがなんだか嬉しい。
イリ河大橋。それなりの観光地らしいけど大したことないです。河原では大人が子供と一緒になって水遊びに興じていました。ウィグル人が楽しそうにしていたのがなんだか嬉しい。
 コルガスは雨。このミニバンで300km。アルマティに向かう。およそ3時間で到着。何もない原野の道を時速100キロ超で疾走する。写真はカザフのイミグレを通過した直後の場所であるが既に何もない。
コルガスは雨。このミニバンで300km。アルマティに向かう。およそ3時間で到着。何もない原野の道を時速100キロ超で疾走する。写真はカザフのイミグレを通過した直後の場所であるが既に何もない。
 乾燥地帯。道路脇はずっと原野です。建物は見当たりませんが草原地帯では時々牛がいます。
乾燥地帯。道路脇はずっと原野です。建物は見当たりませんが草原地帯では時々牛がいます。
 アルマティのバザール。おおっ、清潔。ハエがいない。自由で活気がある。この街は好きになりそうだ。果物が豊富で干アンズ(みたいなもの)を試食させてもらったが美味しかったです。
アルマティのバザール。おおっ、清潔。ハエがいない。自由で活気がある。この街は好きになりそうだ。果物が豊富で干アンズ(みたいなもの)を試食させてもらったが美味しかったです。
 街も緑が多くて小奇麗です。道中見かけた山脈の山頂付近は冠雪していた。結構高いのだろうか?こりゃ登れないな。
街も緑が多くて小奇麗です。道中見かけた山脈の山頂付近は冠雪していた。結構高いのだろうか?こりゃ登れないな。
 町中の噴水。美女がキャーキャー言いながらヌレヌレになって遊んでいる。ついでに美男もワーワー言いながらヌレヌレで遊んでいるが、体のラインがわかってもこちらは嬉しくない。
町中の噴水。美女がキャーキャー言いながらヌレヌレになって遊んでいる。ついでに美男もワーワー言いながらヌレヌレで遊んでいるが、体のラインがわかってもこちらは嬉しくない。
 建物はこんな感じでロシアという雰囲気が漂う。今まで山ほどいた中国人がいなくなったのも異なった文化圏に来たことを強く感じさせる。
建物はこんな感じでロシアという雰囲気が漂う。今まで山ほどいた中国人がいなくなったのも異なった文化圏に来たことを強く感じさせる。
 夕暮れ時の目利き通りは人でいっぱい。路上ミュージックや路上パフォーマンスで歩いていても楽しい。
夕暮れ時の目利き通りは人でいっぱい。路上ミュージックや路上パフォーマンスで歩いていても楽しい。
 昇仙峡。同行は上野のI氏。台風一過で空が非常が澄んでいた。緑も深い。残暑が厳しいが、渓谷沿いは天然ミストで比較的涼しい。散策後は甲府市内に戻ってワイナリーを見学。
昇仙峡。同行は上野のI氏。台風一過で空が非常が澄んでいた。緑も深い。残暑が厳しいが、渓谷沿いは天然ミストで比較的涼しい。散策後は甲府市内に戻ってワイナリーを見学。
 八王子城跡。北条氏照の居城だとか。名前は聞いたことあるが、何をした人かは知らない。
八王子城跡。北条氏照の居城だとか。名前は聞いたことあるが、何をした人かは知らない。
 詰の城。相当な山奥。ここまで攻められたら確かに詰んでいる。
詰の城。相当な山奥。ここまで攻められたら確かに詰んでいる。
 高尾山1号路。比較的空いている男坂。薬王院の前とかは亀の歩み。
高尾山1号路。比較的空いている男坂。薬王院の前とかは亀の歩み。
 鉄五郎新道の起点、金比羅神社に控える不動明王。左は崖。道中の安全を祈る。
鉄五郎新道の起点、金比羅神社に控える不動明王。左は崖。道中の安全を祈る。
 全く食欲を感じさせないピンクのきのこ。結構色んな所に生えていました。
全く食欲を感じさせないピンクのきのこ。結構色んな所に生えていました。
 なんだか語りかけてきそうな気がした老木。手前に伸びる太い根が、森の世界に誘うかのようだ。
なんだか語りかけてきそうな気がした老木。手前に伸びる太い根が、森の世界に誘うかのようだ。
 日の出山からの景色は相変わらず良い。よく整備されているしハイキングコースとして人気なのも当然。
日の出山からの景色は相変わらず良い。よく整備されているしハイキングコースとして人気なのも当然。
 鴨沢バス停。奥多摩6時5分発のバスは立ち客が出るほど。
鴨沢バス停。奥多摩6時5分発のバスは立ち客が出るほど。
 可愛い登山口標識。本当かどうかはわからないけど登山道には将門伝説の標識が多数ありました。地名の由来はほぼ将門。こんなとこまで落ち延びて来たことになってるけど、本当かいな。
可愛い登山口標識。本当かどうかはわからないけど登山道には将門伝説の標識が多数ありました。地名の由来はほぼ将門。こんなとこまで落ち延びて来たことになってるけど、本当かいな。
 木立と倒木のいい道。一瞬、晴れそう!って期待を抱かせてくれたんだけどね。この後はずっと曇りとガスだった
木立と倒木のいい道。一瞬、晴れそう!って期待を抱かせてくれたんだけどね。この後はずっと曇りとガスだった
 写真を撮る気にもなれない。撮ってもこんなのばっかり。気持ちのいい尾根道、、、のはず。
写真を撮る気にもなれない。撮ってもこんなのばっかり。気持ちのいい尾根道、、、のはず。
 雲取山山頂。完全にガス(雲)の中。雲は取り放題。
雲取山山頂。完全にガス(雲)の中。雲は取り放題。
 下山中、少しづつ霧が晴れてきた。あの雲の向こうに雲取山があります。
下山中、少しづつ霧が晴れてきた。あの雲の向こうに雲取山があります。
 名栗湖からスタート。ツーリングのメッカなのか、格好いいバイクが集まっている。ハーレーもあった。ちなみに、カメラを新調した。折角だから綺麗に丁寧に使っていこうと思う。
名栗湖からスタート。ツーリングのメッカなのか、格好いいバイクが集まっている。ハーレーもあった。ちなみに、カメラを新調した。折角だから綺麗に丁寧に使っていこうと思う。
 気持ちのいい沢沿いの道。整備された登山道です。前行く年少児連れの家族も見ていて安心。軽装の若い女性も多い。
気持ちのいい沢沿いの道。整備された登山道です。前行く年少児連れの家族も見ていて安心。軽装の若い女性も多い。
 安全な道は最初だけであった。先週の台風で沢に架かっていたはずの橋は全て流されている。流木や落ち枝で登山道も大変荒れている。
安全な道は最初だけであった。先週の台風で沢に架かっていたはずの橋は全て流されている。流木や落ち枝で登山道も大変荒れている。
 そして、これが道である。沢の中に入れということか?
そして、これが道である。沢の中に入れということか?
 ゴルジュ(岩壁の狭った峡谷)の中にロープと鎖が続く。濡れないように歩くのは相当に危い。そもそも、歩幅の短い子供では無理だろう。
ゴルジュ(岩壁の狭った峡谷)の中にロープと鎖が続く。濡れないように歩くのは相当に危い。そもそも、歩幅の短い子供では無理だろう。
 急登。かなりハードな道が続く。手は泥だらけ、新調したカメラも泥だらけ、ついでに汗まみれ。折角だから汚しまくってでもとことん酷使しようと思う。
急登。かなりハードな道が続く。手は泥だらけ、新調したカメラも泥だらけ、ついでに汗まみれ。折角だから汚しまくってでもとことん酷使しようと思う。
 危険。通行止め。当然無視。というよりみんな無視している。道が完全に崩れ落ちてますな。子供や軽装の人たち大丈夫かなぁ。
危険。通行止め。当然無視。というよりみんな無視している。道が完全に崩れ落ちてますな。子供や軽装の人たち大丈夫かなぁ。
 山頂は大人気。木々も色づき始めている。
山頂は大人気。木々も色づき始めている。
 南下して御嶽駅を目指す。途端に岳人も少なくなり、静かな山歩きを楽しめる。思ったよりアップダウンもあり遠かった。
南下して御嶽駅を目指す。途端に岳人も少なくなり、静かな山歩きを楽しめる。思ったよりアップダウンもあり遠かった。
 雨で心が折れた中で、最短の下山コースに向かうと、「崩れあり通行困難」。心は複雑骨折。実際にはさほど大変なことはありませんでした。
雨で心が折れた中で、最短の下山コースに向かうと、「崩れあり通行困難」。心は複雑骨折。実際にはさほど大変なことはありませんでした。
 登山道は荒れている。道に沿って進めない。
登山道は荒れている。道に沿って進めない。
 「植生保護のため経路内を通行してください」って無理でしょ。
「植生保護のため経路内を通行してください」って無理でしょ。
 こんな大木も折れている。
こんな大木も折れている。
 もはや道がどこだかさっぱりわからない。先々週の台風はやっぱりすごかったんだなぁ。
もはや道がどこだかさっぱりわからない。先々週の台風はやっぱりすごかったんだなぁ。
 丹沢はいつ来ても綺麗です。
丹沢はいつ来ても綺麗です。
 1500m付近では紅葉が始まっていました。
1500m付近では紅葉が始まっていました。
 関西国際空港の夜明け。期待と不安で胸が膨らむ。
関西国際空港の夜明け。期待と不安で胸が膨らむ。
 海外最初の食事はマーケット前の露天で。
海外最初の食事はマーケット前の露天で。
 まずくはないがうまくもない。てか、辛いってば。辛いのを食べるとお腹を壊すので嫌なんだけどなぁ。
まずくはないがうまくもない。てか、辛いってば。辛いのを食べるとお腹を壊すので嫌なんだけどなぁ。
 ウィークエンド・マーケットは人がいっぱい。騒々しいなぁ。バンコクは嫌いなんだけど空の玄関口なんで経由しないと仕方がない。
ウィークエンド・マーケットは人がいっぱい。騒々しいなぁ。バンコクは嫌いなんだけど空の玄関口なんで経由しないと仕方がない。
 夜行で国境の町メーソートに来る。朝4時なんだけど、結構な人がいる。
夜行で国境の町メーソートに来る。朝4時なんだけど、結構な人がいる。
 夜明け前の道を国境へと歩く。如何にもな感じのうら寂しい道。治安は心配してないけど(て言うか誰もいないし)、野犬に囲まれるのが怖い。
夜明け前の道を国境へと歩く。如何にもな感じのうら寂しい道。治安は心配してないけど(て言うか誰もいないし)、野犬に囲まれるのが怖い。
 イミグレは出稼ぎ地元民の長蛇の列。
イミグレは出稼ぎ地元民の長蛇の列。
 暁前の橋の上で国境通過。左岸がタイで右岸がミャンマー。
暁前の橋の上で国境通過。左岸がタイで右岸がミャンマー。
 ミャンマー初フード。マメ入りチャーハン。納豆を炒めてご飯と絡ませたような味。やはり、まずくはないが、うまくもない。
ミャンマー初フード。マメ入りチャーハン。納豆を炒めてご飯と絡ませたような味。やはり、まずくはないが、うまくもない。
 ミャワディーの朝市。活気があって、色とりどりの傘が美しい。カラフルだけどボロボロ。
ミャワディーの朝市。活気があって、色とりどりの傘が美しい。カラフルだけどボロボロ。
 こちらはガラクタ屋さん。
こちらはガラクタ屋さん。
 扱う商品はSonyやHITACHI、Panasonicなど。潰れたものを買い取って修理して売るそうな。店主は中央のグレーのシャツの渋い親父さん。ミャンマーは親日だなぁ。
扱う商品はSonyやHITACHI、Panasonicなど。潰れたものを買い取って修理して売るそうな。店主は中央のグレーのシャツの渋い親父さん。ミャンマーは親日だなぁ。
 ヤンゴンに向かうマイクロバス。先程のガラクタ屋さんで冷蔵庫を二台積み込み済み。
ヤンゴンに向かうマイクロバス。先程のガラクタ屋さんで冷蔵庫を二台積み込み済み。
 ドライバーは裸足で運転。なお、スピードメーターを始め計器類は全て動かない。私は助手席。だから、怖いんだよ〜。スピード出すなよ〜。
ドライバーは裸足で運転。なお、スピードメーターを始め計器類は全て動かない。私は助手席。だから、怖いんだよ〜。スピード出すなよ〜。
 ミャンマーは何もない。いいところだなぁ〜。幹線以外は全て土道。幹線も穴ボコだらけ。ラオスとどっこいな感じ。以上、ヤンゴンに着くまでの写真から。
ミャンマーは何もない。いいところだなぁ〜。幹線以外は全て土道。幹線も穴ボコだらけ。ラオスとどっこいな感じ。以上、ヤンゴンに着くまでの写真から。
 列車も古めかしい。ペイントはミャンマビールの宣伝。なお、列車が走らない間の線路は庶民の通行路。
列車も古めかしい。ペイントはミャンマビールの宣伝。なお、列車が走らない間の線路は庶民の通行路。
 一応、ちゃんとビルもあります。公園の池の木道からの一枚。
一応、ちゃんとビルもあります。公園の池の木道からの一枚。
 すごく綺麗なショッピングセンターもあります。日本の化粧品会社がプロモーションをしていました。
すごく綺麗なショッピングセンターもあります。日本の化粧品会社がプロモーションをしていました。
 シュエダゴン・パゴダは思ったより良かった。
シュエダゴン・パゴダは思ったより良かった。
 課外授業なのかな。小さな学生たちが引率されてお祈りに来ていた。
課外授業なのかな。小さな学生たちが引率されてお祈りに来ていた。
 アジアの人たちは金ピカ・カラフルが大好き。
アジアの人たちは金ピカ・カラフルが大好き。
 パゴダは丘の上にあり、日陰に入ると涼しい風が吹くので、ゆっくりと昼寝するのも気持ちよさそうです。
パゴダは丘の上にあり、日陰に入ると涼しい風が吹くので、ゆっくりと昼寝するのも気持ちよさそうです。
 バガンは広いエリアに大小の遺跡が点在している。
バガンは広いエリアに大小の遺跡が点在している。
 馬車での観光も趣がある。年配の方の利用が多いようであった。
馬車での観光も趣がある。年配の方の利用が多いようであった。
 登れる遺跡も多い。高いと遠くまで見渡せてよい。
登れる遺跡も多い。高いと遠くまで見渡せてよい。
 広い原野である。こりゃ遺跡巡りも大変やわ。
広い原野である。こりゃ遺跡巡りも大変やわ。
 こちらは結構大物の遺跡。
こちらは結構大物の遺跡。
 木陰のお土産物屋さん。観光客の服も鮮やか。現地(タイ人かなぁ?)っぽい人が多い感じ。
木陰のお土産物屋さん。観光客の服も鮮やか。現地(タイ人かなぁ?)っぽい人が多い感じ。
 バガンの市場。露店の並ぶ狭い道を人とバイクが行き交う。
バガンの市場。露店の並ぶ狭い道を人とバイクが行き交う。
 夕日ポイントは人がいっぱい。結論。みんなが行くところには行ってはいけない。
夕日ポイントは人がいっぱい。結論。みんなが行くところには行ってはいけない。
 一応、夕日の写真も取っておく。以上、14日の写真。
一応、夕日の写真も取っておく。以上、14日の写真。
 本日の相棒(オンボロ電動バイク)と遺跡群。バガンの遺跡は5キロ四方くらいに渡って存在する。相当広いよ。
本日の相棒(オンボロ電動バイク)と遺跡群。バガンの遺跡は5キロ四方くらいに渡って存在する。相当広いよ。
 遺跡も飽きてきた頃。長閑な村を見つけた。こういう風景の散歩が好きである。
遺跡も飽きてきた頃。長閑な村を見つけた。こういう風景の散歩が好きである。
 平和だなぁ。
平和だなぁ。
 The Inaka.
The Inaka.
 やっぱり観光客は地元っぽい人が多い感じ。
やっぱり観光客は地元っぽい人が多い感じ。
 皆さん真剣にお祈りしています。
皆さん真剣にお祈りしています。
 有名所(大物遺跡)には土産物屋街があります。あんまり売れてなさそうだけど。
有名所(大物遺跡)には土産物屋街があります。あんまり売れてなさそうだけど。
 牛車が通る。自動車も通る。馬車も通るし、電動バイク(私)も通る。
牛車が通る。自動車も通る。馬車も通るし、電動バイク(私)も通る。
 そして観光客のほとんど居ない郊外へ。本日はイラワジ川に沈む夕日。
そして観光客のほとんど居ない郊外へ。本日はイラワジ川に沈む夕日。
 小坊主たちが土手で遊んでいました。以上15日の写真。
小坊主たちが土手で遊んでいました。以上15日の写真。
 朝日を拝んで一日が始まる。
朝日を拝んで一日が始まる。
 シュエズィーゴン・パゴダ。なんか似たようなものをたくさん見てる気がする。
シュエズィーゴン・パゴダ。なんか似たようなものをたくさん見てる気がする。
 参道は結構立派な商店街。
参道は結構立派な商店街。
 ティローミィンロー寺院。大きいけどあまり特徴はない。
ティローミィンロー寺院。大きいけどあまり特徴はない。
 壁画もほとんど残っていない。
壁画もほとんど残っていない。
 アーナンダ寺院。多聞第一、阿難(アーナンダ)。流石に舎利弗(シャーリプトラ)と摩訶迦葉(マハーカーシャパ)とあわせて三人トリオは知っている。十大弟子?他の七人は知らん。
アーナンダ寺院。多聞第一、阿難(アーナンダ)。流石に舎利弗(シャーリプトラ)と摩訶迦葉(マハーカーシャパ)とあわせて三人トリオは知っている。十大弟子?他の七人は知らん。
 多分こちらがアーナンダさん。
多分こちらがアーナンダさん。
 タビニュ寺院。うーん。大したことない。
タビニュ寺院。うーん。大したことない。
 名もなき寺院。比較的レリーフが綺麗に残っている。
名もなき寺院。比較的レリーフが綺麗に残っている。
 内部の壁画も一番綺麗だった。楽人と踊子。
内部の壁画も一番綺麗だった。楽人と踊子。
 見離されたかのようなエリア。荒れるがままに草が生えている。境内にも壁にも屋根にも、、、。寂れた門からは打ち捨てられた仏像の視線を感じる。
見離されたかのようなエリア。荒れるがままに草が生えている。境内にも壁にも屋根にも、、、。寂れた門からは打ち捨てられた仏像の視線を感じる。
 夕日を拝んで一日が終わる。
夕日を拝んで一日が終わる。
 倒壊間近。こういうのは無管理で登り放題なんでテラスで朝寝、、、と思っていた。
倒壊間近。こういうのは無管理で登り放題なんでテラスで朝寝、、、と思っていた。
 なんともいい村を発見。なんかやってる。なんか大音響が聞こえる。
なんともいい村を発見。なんかやってる。なんか大音響が聞こえる。
 稚児行列、、、とでも言うのだろうか?
稚児行列、、、とでも言うのだろうか?
 先頭は年頃の少女たち。おしゃれな傘。でも、主役じゃない。
先頭は年頃の少女たち。おしゃれな傘。でも、主役じゃない。
 続いて馬に乗った少年たち。多分一番の主役。
続いて馬に乗った少年たち。多分一番の主役。
 白塗り化粧で女の子みたい。
白塗り化粧で女の子みたい。
 最後列は牛車に乗った女児。
最後列は牛車に乗った女児。
 本当の最後尾は爆音スピーカー車と手押し車の発電機。
本当の最後尾は爆音スピーカー車と手押し車の発電機。
 本日の夕日は渡船場から。橋がないので川は流通の要。
本日の夕日は渡船場から。橋がないので川は流通の要。
 宿の目の前をパレードが通る。
宿の目の前をパレードが通る。
 牛車も大行列。
牛車も大行列。
 なんと象まで出てきた。
なんと象まで出てきた。
 動物園じゃないからね。ちょっとよろけてコケようものなら(象がコケても私がコケても)、押しつぶされて死にますな。
動物園じゃないからね。ちょっとよろけてコケようものなら(象がコケても私がコケても)、押しつぶされて死にますな。
 オカマも出てきた。
オカマも出てきた。
 なんか、変なん出てきた。
なんか、変なん出てきた。
 もっと変なん出てきた。中の人、暑いだろうなぁ。
もっと変なん出てきた。中の人、暑いだろうなぁ。
 おばちゃん、これは歌ってて気持ちいいだろう。
おばちゃん、これは歌ってて気持ちいいだろう。
 王宮。しょうもないなぁ。
王宮。しょうもないなぁ。
 有名所のパゴダを何件か回る。
有名所のパゴダを何件か回る。
 うーん。どれも大したことない。
うーん。どれも大したことない。
 あんたは喪黒福造か。金ピカだけど。
あんたは喪黒福造か。金ピカだけど。
 マンダレーヒルからの景色はなかなかだが、むしろ乾季はだめだな。雨が降らないから空気が濁っていて遠望は霞んでいる。
マンダレーヒルからの景色はなかなかだが、むしろ乾季はだめだな。雨が降らないから空気が濁っていて遠望は霞んでいる。
 ニャウンシェはいい雰囲気の街だ。
ニャウンシェはいい雰囲気の街だ。
 野良犬が多い。でも、吠えない。皆温厚。
野良犬が多い。でも、吠えない。皆温厚。
 何やら人が集まっている。何らかのステージがあるのだろうか。
何やら人が集まっている。何らかのステージがあるのだろうか。
 黄昏時の波止場。明日の予定はボートトリップ。
黄昏時の波止場。明日の予定はボートトリップ。
 西山の端に炎の落つ見えて
西山の端に炎の落つ見えて
 かへり見すれば月立ち出づる(柿本偽麻呂)
かへり見すれば月立ち出づる(柿本偽麻呂)
 夜になればさらなる人だかり。一向に始まらないから見ずに帰ってしまった。
夜になればさらなる人だかり。一向に始まらないから見ずに帰ってしまった。
 新しい朝が来た。
新しい朝が来た。
 さぁ、ボートに乗って。インレー湖へ。本日の相棒。船長のミューミュー。
さぁ、ボートに乗って。インレー湖へ。本日の相棒。船長のミューミュー。
 こちらは水上農場。トマトを作っているとか。おおっ、最先端。水耕栽培ってやつですね。だって、ここ浮草の上ですよ。
こちらは水上農場。トマトを作っているとか。おおっ、最先端。水耕栽培ってやつですね。だって、ここ浮草の上ですよ。
 湖上の村。今は乾季だけど、雨季になると2mほど水位が上がるそうな。
湖上の村。今は乾季だけど、雨季になると2mほど水位が上がるそうな。
 湖西のインデイン村へと続く水路。なお、湖東にあるのはライデイン村(嘘)。さらに、湖南にあるのはミナデイン村(大嘘)。
湖西のインデイン村へと続く水路。なお、湖東にあるのはライデイン村(嘘)。さらに、湖南にあるのはミナデイン村(大嘘)。
 インデイン村では水の色がコバルトである。何らかの金属イオンが豊富に含まれているのだろうか。
インデイン村では水の色がコバルトである。何らかの金属イオンが豊富に含まれているのだろうか。
 あっ、首長族(カレン族)の子供だ。文化って難しいなぁ。纏足もそうだけど、虐待と習慣なんて同じもの。
あっ、首長族(カレン族)の子供だ。文化って難しいなぁ。纏足もそうだけど、虐待と習慣なんて同じもの。
 インデイン村にて3つの丘を攻める。いやぁ、インレー湖は素晴らしい山に囲まれています。次来たときは是非ともトレッキングをやらねば。
インデイン村にて3つの丘を攻める。いやぁ、インレー湖は素晴らしい山に囲まれています。次来たときは是非ともトレッキングをやらねば。
 水上パゴダにて。猫が一番いい席を占領している。しかも寝てる。インレー湖の街はニャウンシェ。バガンの街はニャウンウー。船長はミューミュー。なんか猫みたいな名前が多いな。
水上パゴダにて。猫が一番いい席を占領している。しかも寝てる。インレー湖の街はニャウンシェ。バガンの街はニャウンウー。船長はミューミュー。なんか猫みたいな名前が多いな。
 人間が猫に遠慮してお祈りしています。パゴダでの序列。如来、菩薩、猫、人間。
人間が猫に遠慮してお祈りしています。パゴダでの序列。如来、菩薩、猫、人間。
 街に戻って1時間歩いて夕日の丘へ。帰りが暗くなって怖かった。いや、だから人は優しいけど犬が怖いんだよ。昼間は温厚な犬もなぜか夜は凶暴です。
街に戻って1時間歩いて夕日の丘へ。帰りが暗くなって怖かった。いや、だから人は優しいけど犬が怖いんだよ。昼間は温厚な犬もなぜか夜は凶暴です。
 ヤンゴン国際空港はあまりに綺麗で驚きました。
ヤンゴン国際空港はあまりに綺麗で驚きました。
 うまかった。機内食は都合3食でたけど全て美味しかったです。
うまかった。機内食は都合3食でたけど全て美味しかったです。
 大変綺麗な機体。液晶下のリモコンはゲームのコントローラーにもなっている。液晶の操作はタッチパネルでメニューは日本語にも対応していました。
大変綺麗な機体。液晶下のリモコンはゲームのコントローラーにもなっている。液晶の操作はタッチパネルでメニューは日本語にも対応していました。
 あさやけい(朝焼+夜景)。パリの上空にて機中から。期待と不安で胸が膨らむ。
あさやけい(朝焼+夜景)。パリの上空にて機中から。期待と不安で胸が膨らむ。
 パリ市庁舎。いちいち格好良い建物ばかり。
パリ市庁舎。いちいち格好良い建物ばかり。
 ノートルダム大聖堂のステンドグラス。外観も内装も素晴らしかった。
ノートルダム大聖堂のステンドグラス。外観も内装も素晴らしかった。
 セーヌ川。建物が歴史掛かっているが、普通に町中にこんなのばっか。
セーヌ川。建物が歴史掛かっているが、普通に町中にこんなのばっか。
 チョー有名なオブジェ。ルーブル美術館ですね。
チョー有名なオブジェ。ルーブル美術館ですね。
 オー、シャンゼリゼー。オー、シャンゼリゼー。
オー、シャンゼリゼー。オー、シャンゼリゼー。
 凱旋門。でかいよ。
凱旋門。でかいよ。
 適当に歩いてたら、ムーラン・ルージュを見つけた。うーん、コレは大したことない建物でしたな。
適当に歩いてたら、ムーラン・ルージュを見つけた。うーん、コレは大したことない建物でしたな。
 モンマルトルの丘。パリは晴天。空が綺麗だ。
モンマルトルの丘。パリは晴天。空が綺麗だ。
 丘ですからね。パリ市街が一望できます。
丘ですからね。パリ市街が一望できます。
 最後にもう一度ノートルダム大聖堂に寄って本日は終わり。気がつけば四万五千歩。
最後にもう一度ノートルダム大聖堂に寄って本日は終わり。気がつけば四万五千歩。
 ブローニュの森。こんないい森が市内にあるとかちょっと羨ましい。
ブローニュの森。こんないい森が市内にあるとかちょっと羨ましい。
 ミニチュア細工みたいな街。
ミニチュア細工みたいな街。
 そして、ミニチュア細工みたいな風景。
そして、ミニチュア細工みたいな風景。
 あいにくの曇り空だけど景色は本当に綺麗。
あいにくの曇り空だけど景色は本当に綺麗。
 地の果てを行くかのよう。
地の果てを行くかのよう。
 山には雪も残っていた。一部、道が雪に埋もれていて滑りそうで怖かったよ。
山には雪も残っていた。一部、道が雪に埋もれていて滑りそうで怖かったよ。
 Roncesvallesの教会。どの教会も歴史と趣きがありステンドグラスが美しい。
Roncesvallesの教会。どの教会も歴史と趣きがありステンドグラスが美しい。
 昨夜の宿。 7時30分、一日の始まり。なお、ヨーロッパは夏時間であるため。実質は6時30分。7時15分くらいからようやく明るくなってくる。
昨夜の宿。 7時30分、一日の始まり。なお、ヨーロッパは夏時間であるため。実質は6時30分。7時15分くらいからようやく明るくなってくる。
 早朝の牧場。標高は1000m。肌寒いです。
早朝の牧場。標高は1000m。肌寒いです。
 遠くピレネーを望む。風景が絵に書いたようなヨーロッパ。
遠くピレネーを望む。風景が絵に書いたようなヨーロッパ。
 ヨーロッパ猫歩き。さてどこにいるでしょう。
ヨーロッパ猫歩き。さてどこにいるでしょう。
 多分養蜂農家。写真の左手はお花畑。
多分養蜂農家。写真の左手はお花畑。
 朝もやの中出発。
朝もやの中出発。
 街中、ブドウ棚かなぁ。
街中、ブドウ棚かなぁ。
 高台のお城から。
高台のお城から。
 パンプローナの街。
パンプローナの街。
 こんな道ならいくら歩いても疲れないよね。
こんな道ならいくら歩いても疲れないよね。
 お花畑の向こうに来し方を振り返る。
お花畑の向こうに来し方を振り返る。
 水場で休憩。
水場で休憩。
 風車街道。
風車街道。
 ヨーロッパ猫歩き。本日はこの街まで。
ヨーロッパ猫歩き。本日はこの街まで。
 日の出前に出発。まぁ、毎日のこと。
日の出前に出発。まぁ、毎日のこと。
 私より10キロ以上は重い肉を担いでるな。毎日500グラムは痩せていくから巡礼が終わる頃にはグラマラスになっていることでしょう。
私より10キロ以上は重い肉を担いでるな。毎日500グラムは痩せていくから巡礼が終わる頃にはグラマラスになっていることでしょう。
 サンチアゴまで676キロ。こんな看板いらない。気が遠くなるし、実感がまるでわかない。
サンチアゴまで676キロ。こんな看板いらない。気が遠くなるし、実感がまるでわかない。
 Estellaの教会。はるかローマ時代に建てられたとか書いてあった。
Estellaの教会。はるかローマ時代に建てられたとか書いてあった。
 さぁ、最後の上り。あの山に登れば今日のゴールだと思っていたら、街は山の裏側中腹にありました。気合が空回り。
さぁ、最後の上り。あの山に登れば今日のゴールだと思っていたら、街は山の裏側中腹にありました。気合が空回り。
 今にも降りそう。雨が降ったら逃げ場がない。
今にも降りそう。雨が降ったら逃げ場がない。
 Los Arcosを通過。ここから雨。
Los Arcosを通過。ここから雨。
 午後からは晴れてきた。誰もいない平原を一人目的地を目指す。
午後からは晴れてきた。誰もいない平原を一人目的地を目指す。
 雨上がりの遊歩道。午前は雨のため全く写真を撮っていない。
雨上がりの遊歩道。午前は雨のため全く写真を撮っていない。
 午後から晴れ。この町に泊まろうと思ってたんだけどなぁ。ここから行く先々の街でアルベルゲ満室攻撃。
午後から晴れ。この町に泊まろうと思ってたんだけどなぁ。ここから行く先々の街でアルベルゲ満室攻撃。
 野宿を決意。教会の庭には先客がいた。アルベルゲでテントを借りたらしい。どう見ても一人用の小型テント。
野宿を決意。教会の庭には先客がいた。アルベルゲでテントを借りたらしい。どう見ても一人用の小型テント。
 Ventosaの教会。うん、玄関になにかあるぞ。
Ventosaの教会。うん、玄関になにかあるぞ。
 あー、なんだ、私の寝床か。教会のゴミ捨て場に落ちていたクロス付きのテーブルの天板を拝借。石の上に直接は底冷えするからね。コレがあっただけでずいぶんと快適になりました。
あー、なんだ、私の寝床か。教会のゴミ捨て場に落ちていたクロス付きのテーブルの天板を拝借。石の上に直接は底冷えするからね。コレがあっただけでずいぶんと快適になりました。
 ありがとう。教会。あなたのお影で眠ることができました。
ありがとう。教会。あなたのお影で眠ることができました。
 月下銀嶺。山には雪が残る。今朝は寒かったよ。
月下銀嶺。山には雪が残る。今朝は寒かったよ。
 Najeraの街。大急ぎで通過。
Najeraの街。大急ぎで通過。
 いい天気。ハイキングがてらの地元民カミーノもたくさん。
いい天気。ハイキングがてらの地元民カミーノもたくさん。
 北海道と似たような景色。しかしながら風景を楽しむ心の余裕がなかった。とにかく急がねば。
北海道と似たような景色。しかしながら風景を楽しむ心の余裕がなかった。とにかく急がねば。
 So Domingoに着く。無事宿も確保できて一安心。街はお祭り、イースター。
So Domingoに着く。無事宿も確保できて一安心。街はお祭り、イースター。
 Beloradeの街。街の教会。今日は曇と雨でしかも寒い。
Beloradeの街。街の教会。今日は曇と雨でしかも寒い。
 スペイン中の街への道標。
スペイン中の街への道標。
 牧場の中を街は続く。
牧場の中を街は続く。
 近くで見ると牛は巨大なモンスター。こんなのと戦う闘牛士が尊敬されるのはよくわかる。
近くで見ると牛は巨大なモンスター。こんなのと戦う闘牛士が尊敬されるのはよくわかる。
 出発から30分歩いて峠の最上部へ。峠と言ってもなだらかな丘のようなもの。山登り自体は全く楽勝。
出発から30分歩いて峠の最上部へ。峠と言ってもなだらかな丘のようなもの。山登り自体は全く楽勝。
 夜明け前、薄もやの中にメセタが広がる。ちょっと感動した。広い!
夜明け前、薄もやの中にメセタが広がる。ちょっと感動した。広い!
 ブルゴスの大聖堂はとても立派。これも世界遺産。見る価値あり。残念ながら内部は写真撮影禁止。
ブルゴスの大聖堂はとても立派。これも世界遺産。見る価値あり。残念ながら内部は写真撮影禁止。
 出発から2キロほど進んだところで夜明け。おっ、天気予報ハズレんじゃない。と思ってたんだけど朝焼けすれば雨ですね。
出発から2キロほど進んだところで夜明け。おっ、天気予報ハズレんじゃない。と思ってたんだけど朝焼けすれば雨ですね。
 目的地に着く頃、ようやく雨が上がる。凍える手で写真を取る。指が動かないので腕ごと動かしてシャッターを切る。
目的地に着く頃、ようやく雨が上がる。凍える手で写真を取る。指が動かないので腕ごと動かしてシャッターを切る。
 おおっ、広い。遥か遠くまで続く道。このあと猛吹雪にやられました。
おおっ、広い。遥か遠くまで続く道。このあと猛吹雪にやられました。
 教会で休憩。暖かいコーヒーで生き返る。
教会で休憩。暖かいコーヒーで生き返る。
 晴れてきた。前ゆくは韓国人のキムさん。日本に8年いたそうで日本語が大変流暢。
晴れてきた。前ゆくは韓国人のキムさん。日本に8年いたそうで日本語が大変流暢。
 晴れたら本当に綺麗な風景。遠くに見える風車(風力発電)は高速回転。
晴れたら本当に綺麗な風景。遠くに見える風車(風力発電)は高速回転。
 雲が高速で流れていく。晴れていたかと思えばアラレ。猛烈な風とともに降るだけ降るとまた太陽が出る。わけがわからん天気だ。
雲が高速で流れていく。晴れていたかと思えばアラレ。猛烈な風とともに降るだけ降るとまた太陽が出る。わけがわからん天気だ。
 メセタを潤す運河。
メセタを潤す運河。
 遊覧船もあるみたい。
遊覧船もあるみたい。
 宿でのんびりしてたらいきなりの雨。干した洗濯物を慌てて取り込みしばらくすると綺麗な虹が出た。
宿でのんびりしてたらいきなりの雨。干した洗濯物を慌てて取り込みしばらくすると綺麗な虹が出た。
 夜明け前。晴天である。
夜明け前。晴天である。
 うわー、広い、綺麗だなぁ。、、、と思うのは最初だけ。どこまで歩いてもおんなじ景色。
うわー、広い、綺麗だなぁ。、、、と思うのは最初だけ。どこまで歩いてもおんなじ景色。
 町も似たようなもの。
町も似たようなもの。
 全ての道はローマに通ず。看板にはローマの道と書かれていた。
全ての道はローマに通ず。看板にはローマの道と書かれていた。
 1時間歩いてこれ。地平線に吸い込まれた道は、近づけば近づいただけ遠くなる。
1時間歩いてこれ。地平線に吸い込まれた道は、近づけば近づいただけ遠くなる。
 こちらは牧場。だだっ広い高原に小麦畑か牧場しかありません。
こちらは牧場。だだっ広い高原に小麦畑か牧場しかありません。
 今日も朝から晴天。風もなくなったため、絶好のハイキング日和。しかしながら見飽きた風景に心は弾まない。変化がほしい。
今日も朝から晴天。風もなくなったため、絶好のハイキング日和。しかしながら見飽きた風景に心は弾まない。変化がほしい。
 道中の教会。 360度、小麦畑ばかりで写すものがありませんわ。
道中の教会。 360度、小麦畑ばかりで写すものがありませんわ。
 レオンの町が見えた。やっとメセタを抜けた。遠くに見える山嶺も数日後には越えるはずである。
レオンの町が見えた。やっとメセタを抜けた。遠くに見える山嶺も数日後には越えるはずである。
 レオンもパリと同じく全ての建物が芸術と言った感じ。
レオンもパリと同じく全ての建物が芸術と言った感じ。
 レオン大聖堂。今日は日曜のため午後は閉館。明日再訪する予定。
レオン大聖堂。今日は日曜のため午後は閉館。明日再訪する予定。
 こちらはガウディ作とか。
こちらはガウディ作とか。
 レオン大聖堂。圧巻のステンドグラス。
レオン大聖堂。圧巻のステンドグラス。
 こちらは巨大なパイプオルガン。もはや砲台。
こちらは巨大なパイプオルガン。もはや砲台。
 ホビットみたいな家。住んでる人も小太りで背が低く本当にホビットのようであった。
ホビットみたいな家。住んでる人も小太りで背が低く本当にホビットのようであった。
 メセタを抜けた。景色が変わって嬉しい。
メセタを抜けた。景色が変わって嬉しい。
 水場で休憩。休憩すると体力は回復するが、痛みも回復する。 1分くらいはビッコを引きずるが3分も経てば痛みは麻痺して普通に歩ける。
水場で休憩。休憩すると体力は回復するが、痛みも回復する。 1分くらいはビッコを引きずるが3分も経てば痛みは麻痺して普通に歩ける。
 今日も晴。無風。多分暑くなるだろう。メセタが帰ってきた。退屈。早く山を超えねば。
今日も晴。無風。多分暑くなるだろう。メセタが帰ってきた。退屈。早く山を超えねば。
 北海道にもありそうな秘境駅。誰が乗るのか?
北海道にもありそうな秘境駅。誰が乗るのか?
 15キロ歩いて町。この橋が有名だとか。
15キロ歩いて町。この橋が有名だとか。
 丘の上からメセタ最後の町アストルガを望む。明日こそ山を超えてやる。
丘の上からメセタ最後の町アストルガを望む。明日こそ山を超えてやる。
 Murias de Rechivaldoの教会。田舎の教会はどこも鳥の巣。
Murias de Rechivaldoの教会。田舎の教会はどこも鳥の巣。
 本日は早起きして明るくなる前に出発。振り返ると町の灯に月。
本日は早起きして明るくなる前に出発。振り返ると町の灯に月。
 朝日に染まる平原。
朝日に染まる平原。
 今日も良い天気。青空に山が映える。
今日も良い天気。青空に山が映える。
 ラベンダーの向こうに冠雪の山脈。自転車の巡礼者は車道をゆく。20人に1人くらいは自転車かな。
ラベンダーの向こうに冠雪の山脈。自転車の巡礼者は車道をゆく。20人に1人くらいは自転車かな。
 巡礼路は花の道。
巡礼路は花の道。
 ここが(多分)巡礼路の最標高地点。車で来てる人も含めて観光客でいっぱい。
ここが(多分)巡礼路の最標高地点。車で来てる人も含めて観光客でいっぱい。
 丘陵全体が赤紫色。自生のラベンダー。これは流石に日本では見れないような気がする。
丘陵全体が赤紫色。自生のラベンダー。これは流石に日本では見れないような気がする。
 黄色はなんの花であろうか?その他、白や青紫の花も咲いていた。
黄色はなんの花であろうか?その他、白や青紫の花も咲いていた。
 痛めた足指が疼いて動けない。少し下ったEl Aceboにて少し早いが一泊。遠くにはPonferradaの街も見えている。
痛めた足指が疼いて動けない。少し下ったEl Aceboにて少し早いが一泊。遠くにはPonferradaの街も見えている。
 山の西側なので夜明けが遅い。 8時前になってやっと日がさしてきた。
山の西側なので夜明けが遅い。 8時前になってやっと日がさしてきた。
 山麓の街その1。 9時くらいまではまだ店も空いていない。
山麓の街その1。 9時くらいまではまだ店も空いていない。
 山麓の街その2。どの町も教会を中心に形作られている。
山麓の街その2。どの町も教会を中心に形作られている。
 やっと着いたPoferrada。が、アルベルゲが開いていない。足は痛いが進むことにする。
やっと着いたPoferrada。が、アルベルゲが開いていない。足は痛いが進むことにする。
 ああー、遠かった。 Ponferradaからの8キロは本当に気が滅入った。あの町で今日はゴールだ。
ああー、遠かった。 Ponferradaからの8キロは本当に気が滅入った。あの町で今日はゴールだ。
 足痛いよう。と、思いながら盆地を横断する。明日はまた山。
足痛いよう。と、思いながら盆地を横断する。明日はまた山。
 Cacaberosの教会はアルベルゲでもあるようだ。
Cacaberosの教会はアルベルゲでもあるようだ。
 ぶどう畑を超えてゆく。水とワインで値段が変わらないのはどういうことか。ただし、カミーノ・フランスの道では水を買う必要はない。水道水がそのまま飲める。しかもおいしい。まぁ、ずっと高原ですしね。
ぶどう畑を超えてゆく。水とワインで値段が変わらないのはどういうことか。ただし、カミーノ・フランスの道では水を買う必要はない。水道水がそのまま飲める。しかもおいしい。まぁ、ずっと高原ですしね。
 本日は山へと続く丘陵地帯を沢に沿って進むと言った感じ。
本日は山へと続く丘陵地帯を沢に沿って進むと言った感じ。
 体調は万全。山は美しい。山というほどでもないか。高原ハイキングです。
体調は万全。山は美しい。山というほどでもないか。高原ハイキングです。
 道はこんな感じ。これじゃ、二つの意味で疲れないわ。傾斜はゆるいし、景色に見とれて疲れに意識が向かわない。
道はこんな感じ。これじゃ、二つの意味で疲れないわ。傾斜はゆるいし、景色に見とれて疲れに意識が向かわない。
 州境。中央のオッサン。こういうなんでお前はそんなとこから出てくるの、、、と思う人たちはスッキリしたあとの人たち。
州境。中央のオッサン。こういうなんでお前はそんなとこから出てくるの、、、と思う人たちはスッキリしたあとの人たち。
 尾根上の村で休憩するのも楽しい。
尾根上の村で休憩するのも楽しい。
 この地方に多い建築様式。まんまるの家にきのこ屋根。
この地方に多い建築様式。まんまるの家にきのこ屋根。
 来し方を振り返りながらコーヒーを飲む。最高ですね。私はコーヒー飲めませんので水ですけど。
来し方を振り返りながらコーヒーを飲む。最高ですね。私はコーヒー飲めませんので水ですけど。
 アルベルゲって基本こういう感じのドミトリー。奥の毛布を敷いてある部分が私の寝床。いいベットは早いもの勝ち。
アルベルゲって基本こういう感じのドミトリー。奥の毛布を敷いてある部分が私の寝床。いいベットは早いもの勝ち。
 薄暗い中出発。
薄暗い中出発。
 あー、はいはい。雲海ね。綺麗だけど。日本のほうが凄いさ。
あー、はいはい。雲海ね。綺麗だけど。日本のほうが凄いさ。
 うわぁ、すげぇ。右の高原から溢れた雲が左の斜面へと流れ落ちていく。
うわぁ、すげぇ。右の高原から溢れた雲が左の斜面へと流れ落ちていく。
 雲の瀑布を眺めながらモルゲンロードを行く。
雲の瀑布を眺めながらモルゲンロードを行く。
 雲の大洪水が麓の村へと押し寄せる。
雲の大洪水が麓の村へと押し寄せる。
 こちらは支流。
こちらは支流。
 山は終わったけど、ガリシア地方の風景は美しい。
山は終わったけど、ガリシア地方の風景は美しい。
 本当に歩いていて楽しい道が続く。
本当に歩いていて楽しい道が続く。
 残り100キロ地点。7時ちょうどに通過。順調に行けば3日。ゴールが見えてくれば嬉しくもあり寂しくもある。
残り100キロ地点。7時ちょうどに通過。順調に行けば3日。ゴールが見えてくれば嬉しくもあり寂しくもある。
 Portmarinの橋。久しぶりの大きな河川に期待していたが霧で何も見えず。
Portmarinの橋。久しぶりの大きな河川に期待していたが霧で何も見えず。
 なんだこの鈴なりの行列は?
なんだこの鈴なりの行列は?
 ロード歩きが多くてつまらない一日でした。ロード以外もありふれた木立の道。
ロード歩きが多くてつまらない一日でした。ロード以外もありふれた木立の道。
 景色は悪くはないけどね。ハイライトは終わっているし、未飽きた感でお腹いっぱい。
景色は悪くはないけどね。ハイライトは終わっているし、未飽きた感でお腹いっぱい。
 今日もやっぱり人だかり。最後の100キロだけ歩いて巡礼者だなんてもったいない。せめて300キロは歩かないと美味しいところを食べ残している感じ。
今日もやっぱり人だかり。最後の100キロだけ歩いて巡礼者だなんてもったいない。せめて300キロは歩かないと美味しいところを食べ残している感じ。
 雲が黒い。そして土砂降り。
雲が黒い。そして土砂降り。
 降るだけ降れば青空も覗く。サンチアゴ大聖堂は圧巻の迫力です。
降るだけ降れば青空も覗く。サンチアゴ大聖堂は圧巻の迫力です。
 Fisterraまで行かす気まんまんですな。キリスト教もアコギですな。バスで行けば10ユーロなのにさ。カミーノ、儲かりますよ。巡礼証明書も収納の筒付きで5ユーロ取られたし。
Fisterraまで行かす気まんまんですな。キリスト教もアコギですな。バスで行けば10ユーロなのにさ。カミーノ、儲かりますよ。巡礼証明書も収納の筒付きで5ユーロ取られたし。
 朝もやの丘を行く。今日は晴れの予報。
朝もやの丘を行く。今日は晴れの予報。
 花咲く丘陵地帯で久しぶりに歩いていて楽しい。こういうときは気がつけば2時間10キロを歩いていたりする。
花咲く丘陵地帯で久しぶりに歩いていて楽しい。こういうときは気がつけば2時間10キロを歩いていたりする。
 海が見えた。遠くに見えるはCeeの町。
海が見えた。遠くに見えるはCeeの町。
 そして旅の最終目的地Fisterraである。夏になると海水浴客で賑わいそうだ。左の丘にゴールの灯台がある。
そして旅の最終目的地Fisterraである。夏になると海水浴客で賑わいそうだ。左の丘にゴールの灯台がある。
 穏やかで美しい海。
穏やかで美しい海。
 さぁ、岬の灯台へ。
さぁ、岬の灯台へ。
 0km地点。巡礼のおじいさんが靴と自分の足を写していた。碑だけ撮っても仕方がないのでそのままモデルになってもらう。
0km地点。巡礼のおじいさんが靴と自分の足を写していた。碑だけ撮っても仕方がないのでそのままモデルになってもらう。
 遂に着いたFisterraの灯台。世界の終わり。
遂に着いたFisterraの灯台。世界の終わり。
 素晴らしい大西洋。
素晴らしい大西洋。
 大海原には何もない。
大海原には何もない。
 降りれそうだなぁ。怖そうだなぁ。
降りれそうだなぁ。怖そうだなぁ。
 降りてみた。地元の漁師がいた。「ここは危ないよ。」ってそりゃそうだろう。
降りてみた。地元の漁師がいた。「ここは危ないよ。」ってそりゃそうだろう。
 磯は迫力満点。大西洋にタッチ。本当に世界の終わり。
磯は迫力満点。大西洋にタッチ。本当に世界の終わり。
 見えげればこれ。どうやって降りてきたんだ俺?
見えげればこれ。どうやって降りてきたんだ俺?
 私のあとから一人降りてきたおじいさん。 0km地点で足の写真を取ってた人だったよ。
私のあとから一人降りてきたおじいさん。 0km地点で足の写真を取ってた人だったよ。
 帰り道すがら一枚。よく降りてまた登ってるもんだ。
帰り道すがら一枚。よく降りてまた登ってるもんだ。
 安全な高台から海を見下ろす観光客。一人勝者の気分。おめでたい奴らだぜ。
安全な高台から海を見下ろす観光客。一人勝者の気分。おめでたい奴らだぜ。
 丘も綺麗であった。ほとんど誰も来ないのが良い。灯台だけ見て帰るなんてみんなもったいないなぁ。
丘も綺麗であった。ほとんど誰も来ないのが良い。灯台だけ見て帰るなんてみんなもったいないなぁ。
 夕日の時間にもう一度灯台へ(往復6km)。しかし日没が9時半とかやめてほしい。いつもなら寝てる時間だよ。今回の旅で初めて見る夕日となりました。
夕日の時間にもう一度灯台へ(往復6km)。しかし日没が9時半とかやめてほしい。いつもなら寝てる時間だよ。今回の旅で初めて見る夕日となりました。
 旅を終えた巡礼者が眺めるものは、、、。
旅を終えた巡礼者が眺めるものは、、、。
 もちろんサンチアゴ大聖堂。今日は晴天。日差しが強くて暑いくらい。
もちろんサンチアゴ大聖堂。今日は晴天。日差しが強くて暑いくらい。
 ノートルダム大聖堂。無残なり。
ノートルダム大聖堂。無残なり。
 次々と荷台に押し込まれるヤギ。ヤギは抵抗しまくり。
次々と荷台に押し込まれるヤギ。ヤギは抵抗しまくり。
 入らなくなったヤギは天井へ。
入らなくなったヤギは天井へ。
 カメラを向ければみんないい顔。一仕事終えた男たちの充実の笑顔である。ヤギはビビりまくり。
カメラを向ければみんないい顔。一仕事終えた男たちの充実の笑顔である。ヤギはビビりまくり。
 あぁ、ラオスである。やっと、ラオスである。
あぁ、ラオスである。やっと、ラオスである。
 ジャングルを切り開いた水田。あぁ、ラオスである。
ジャングルを切り開いた水田。あぁ、ラオスである。
 そして水牛。あぁ、ラオスである。
そして水牛。あぁ、ラオスである。
 あぁ、ラオスである。何もないセポンの街の夕暮れ。
あぁ、ラオスである。何もないセポンの街の夕暮れ。
 ラオスの国境ゲート。ゲートを覗いて向こうに見えるのはベトナムの国境ゲート。
ラオスの国境ゲート。ゲートを覗いて向こうに見えるのはベトナムの国境ゲート。
 国境からわずかにラオス側。なんにもない山岳地帯である。
国境からわずかにラオス側。なんにもない山岳地帯である。
 国境の町の大仏はトボケた顔である。ありがたい、、、のかなぁ。
国境の町の大仏はトボケた顔である。ありがたい、、、のかなぁ。
